暗き影 その1
『イニストラードを覆う影』のプレビュー特集も終わり、カード個別のデザインの話をする時期がやってきた。このセットについて語ることがあるので、今回は二部作となる。前ふりはもう充分だ、さっそく本題に入るとしよう。


私はプレビュー記事の中で、両面カードを再録することをどれだけ早く決めたかという話をした。デザイン・チームの複数のメンバーが持っていたアイデアの1つが、旧『イニストラード』ブロックのある両面カードを通して語られた物語の続きを描きたいというものだった。すべての選択肢を検討したが、選ぶべきものは明らかだった。我々が続きを語るべきは、《秘密を掘り下げる者》である。
気づいていない諸君のために説明すると、私は《秘密を掘り下げる者》を作るにあたって、映画「ザ・フライ」にヒントを得ていた。この映画では、ある科学者が扱うべきでなかった技術を弄び、そして最終的には肉体が蝿と融合して怪物になってしまうのだ。マジックはファンタジーのゲームなので、科学者は魔法使いに、技術は魔法に置き換えられた。
《秘密を掘り下げる者》は最初は1/1の人間・魔術師で、変身すると飛行を持つ3/2の人間・昆虫になる。彼は扱うべきでない力を弄び、そして半分人間で半分昆虫の何かになってしまったのだ。『イニストラードを覆う影』でもこの人間・昆虫に再び触れることにしたが、状況はまったく改善していないのだ。
今や《逸脱した研究者》となったこのカードの第1面は、(《秘密を掘り下げる者》の第2面である)《昆虫の逸脱者》と全く同じサイズ、能力、クリーチャー・タイプを持つ。この魔術師は希望を捨てずに解決策を求めていたのだ。しかし、残念ながら、彼にとって状況は改善しておらず、彼の実験はさらに状況を悪化させていた。彼は人間・昆虫から、《完成態》という昆虫・ホラーへと変化し、人間部分を完全に失って彼の研究室を飛び出してしまったのだった。


魔女はホラーで一定の役割を担っている。お約束の1つが、魔女を殺すと呪われる、というものだ。『イニストラード』ではこのお約束を、死亡するとライブラリーから呪い・カードを探し、対戦相手にエンチャントする、という《苦心の魔女》で描いていた。
イニストラードを再訪するにあたって、我々はこのお約束を新しいカードにすることにした。魔女と呪いが密接に関わっているとしたらどうなるか。両面カードの片面を魔女にし、そして、その魔女が死亡した結果の呪いをもう1面にするのだ。それを踏まえて、次にすることはこの2つの面をメカニズム的に関連させることだった。我々が見つけた答えは、その魔女を対象とする呪文のコストを{1}下げることで魔女を死にやすくするというものだった。その一方、彼女は死に際して抱えていた呪いを対戦相手に向けて解き放つのだ。対戦相手は、まさに魔女が受けていたのと同じ呪いを受けることになる。
《もう一人の自分》
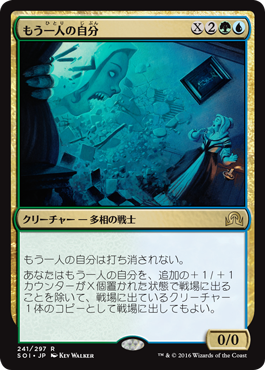
私が《クローン》効果と+1/+1カウンターを愛しているのはよく知られている。非常に残念なことに、私の記憶の限りにおいて、私はこのカードを作っていないのだ。とはいえ、これをプレイするのは楽しかった。コピーしたクリーチャーが本来よりも少し大きいことでどんなクールなことができるか試すのは非常に楽しいのだ。確か、このカードのプレイテスト名は〈科学実験/Science Experiment〉か何かだったと思う。
《苦渋の破棄》

『戦乱のゼンディカー』から、我々はストーリーをカード上で見せるためのさらなる取り組みを始めた。その1つが、物語上の重要な瞬間をカードで描くようにするというものである。《苦渋の破棄》はそのようなカードの一例だ。物語において、アヴァシンが狂気に陥ってイニストラードを害しているということが明らかになった。ジェイスは、アヴァシンが狂気の源で、止めなければならないと判断した。しかし不幸なことに、ジェイスはアヴァシンにはかなわない。その状況を救ってくれたのはソリンだった。ソリンは何百年も前に作った創造物を破棄することになったのだ。
このカードは、物語上の出来事を描くためにトップダウン・デザインされたカードである。デザイン名は〈アヴァシンの破棄/The Unmaking of Avacyn〉だったと思う。このカードを白黒にしたのは、これを唱えるのがソリンであるということを表すためだ。白黒(と、黒緑)は、「パーマネント1つを対象とし、それを取り除く」能力を持つ2色の組み合わせである。土地を破壊できないように調整され、墓地利用への対策になるように追放するようになった。ライフの喪失には、ソリンにとってどれだけ苦渋の決断であったかを表すフレイバー上の意味と、このカードのコストを下げるというデベロップ上の意味がある。
《大天使アヴァシン》/《浄化の天使、アヴァシン》


物語上で重要なところの1つに、かつてイニストラードの救世主だったアヴァシンが狂気に陥り、守ると誓ったその人々を傷つけ始めるというところがある。これが普通のセットなら、我々はおそらく狂気に陥ったアヴァシンを描いて終わりにしていただろう。しかし、今回は両面カードがあるので、変化の前後両方を描くべきなのだ。
物語担当と話し合って最初に決めたのは、最初、アヴァシンは最後に登場した時と同じ白単色のクリーチャーで、その後大きく変化したということを示すため赤のクリーチャーに変身する、ということだった。白の面は元のアヴァシンとよく似た、守護者たらんとするアヴァシン。戦場に出たとき、自陣営の全てのクリーチャーに破壊不能を与えることでそれを表している。さらに(白は第3色だが)瞬速を持たせることで、対戦相手の不意をついて困難から救えるようにした。
しかし、クリーチャー1体でも失えば、狂気がアヴァシンを蝕み始め、《浄化の天使、アヴァシン》へと変身することになる。アヴァシンが守りたいものを傷つけることを描くため、変身の効果として(彼女自身以外の)全てのクリーチャーと全ての対戦相手にダメージを与える。また、アヴァシンのサイズを変身前の4/4よりも少し大きい6/5にすることによって、メカニズム的にも変身を推奨するようにした。とはいえ、この変身は全てが強化されるわけではなく、警戒は失われる。変身によってできることができなくなるというのは面白いと思うし、非常にフレイバー的である。
デザイン中は、このカードの第1面はアヴァシン、第2面はアヴァシンの逆綴りの〈ニカヴァ/Nycava〉と呼ばれていた。


実は、旧『イニストラード』のデザイン中に、我々は人狼のプレインズウォーカー・カードをデザインしていた。このデザインと同じではなかったが、赤緑で、人間と人狼の変身を制御していた。当時は、クリエイティブ・チームはガラクの変身という物語を強調したかったので、両面プレインズウォーカーはそちらで使うべきだと判断したのだ。
興味深いことに、『イニストラードを覆う影』で人狼のプレインズウォーカーを提案してきたのもクリエイティブ・チームだった。デザイン・チームは乗り気で、デザインに盛り込みたい要素がいくつか存在していた。
- 両面カードである ― これは前提だが、ウルフィーのプレインズウォーカーはいらない。
- 変身をプレインズウォーカー自身が制御できる ― 《アーリン・コード》を「狼男」メカニズムとは結びつけないことにした。彼女は主体性を持ち、彼女自身で変身したり戻ったりできるのだ。つまり、両面それぞれの能力の1つは自身を変身させるものになる。
- 狼男デッキで使える ― 彼女はプレインズウォーカーであり、伝説のクリーチャーではないので、彼女は統率者にはなれない。ただし、彼女が狼男デッキでうまく働くようにはしたかった。彼女に[統率者として使用できる]の1文をつけることを検討したかとよく質問されるが、私の答えは、『統率者』以外の商品でその文をつけることはない、というものである。
これらの条件を踏まえて、《アーリン・コード》はデザインされた。狼・トークン部分が追加されたのも気に入っている。こうして、人狼のプレインズウォーカーが生まれたのだ。
《アヴァシン教の宣教師》/《月皇の審問官》


さて、このカードのネタ元になったのは何だと思うかね? ヒントは、映画だ。
予想ができたら以下をクリックしてくれたまえ。
クリックで表示
- 答えは、「ゴーストバスターズ」である。プロトン・パックを装備してゴーストを捕獲するのだ。これは、ゴーストバスターズがクビになる(か、どこかの政治家が市長にゴーストバスターズの貯蔵施設を止めさせる)などでゴーストが解放されるまで続く。興味深いことに、イニストラードは、ネタ元として映画を使ったカード・デザインが一番多い次元だと思われる。


再訪するにあたって決める必要のある重要なものの1つは、前回からどれだけのメカニズム的要素を再録するかである。吸血鬼は今回も黒赤である。黒と赤はマッドネスの色なので、吸血鬼の部族としての役割も変化することになる。前回の『イニストラード』での吸血鬼のあり方を踏まえる形にもしたかったので、この2枚を、旧『イニストラード』でメカニズム的に吸血鬼の主な要素であった「スリス」メカニズム(戦闘ダメージをプレイヤーに与えたら+1/+1カウンターを得る)の名残として入れたのだ。
《月銀の拘束》

このカードは、ブロックにふさわしくなるようにカードを調整するやり方を示す好例である。《平和な心》や《拘引》のような効果はほとんどのセットに存在する効果である。攻撃やブロックを止めるのに加えて、このカードは変身も防いでいる。最後の行は、白に白らしい形でカードを墓地に送る方法が必要だと気づいたデベロップが追加したものである。これによってこのカードは邪魔になっているクリーチャーへと移動させられるようになり、強くなっている。
《往時の主教》

白が調査を行えることについての質問を受けることがある。カードを引くことは白の弱点ではなかったのか、というのだ。その通り。調査がほとんどの場合問題にならないのは、白にキャントリップが認められているのと同じことである。白は呪文を唱えることのカード・ディスアドバンテージを多少減らすことができるが、カードを増やすことはできないのが通例だ。しかし、《往時の主教》は何度も調査が行える。これはルール違反ではないのか。
長年に渡り、我々は「白はカードを引けない」という規則を厳守していたが、これを特定の条件のもとで多少緩和してみることにした。周知の通り、白が効率よくカードを引けない理由は、白があらゆる対策を使える色だからである。あらゆるカードに対策できる唯一の色なのだ。他の色を制圧してしまわないよう、白は容易にカードを手にできないのだ(赤も同じくカードを引く能力は充分ではない)。
しかし、我々は最近、白が白の長所である部分を表すカードに集中した場合にのみ多少カードを引けるようにする、ということを試し始めた。例えば、《往時の主教》を活用するには大量の小型クリーチャーが必要なので、活用できるようにするならデッキに対応策を大量に入れておくことは難しくなるのだ。
これがうまくいくかはわからない。これは実験なのだ。実際のカードにするだけの自信はあるが、白に課せられていた安全弁を取り外すことによって何らかの問題が起こるかどうかを注視していくつもりである。
《血統の呼び出し》

これは面白いマッドネスの相棒である。カードを捨てる必要がある、何度も使用可能な能力を持つ。同時に、それ自身吸血鬼であることが多いマッドネス・カードを使いながら吸血鬼・トークンを出せるので、吸血鬼をテーマとしたマッドネス・デッキを作る助けとなるだろう。
《蟻走感》

このカードでは、自分のライブラリーを削るためのデザイン上のちょっとしたテクニックが使われている。効果としてライブラリーを削るのではなく、ライブラリーを削ることを効果が発生するかどうかを決める乱数として使うのだ。緑が単に自分のライブラリーを削っていたら奇妙に思えるが、トークンを出すために自分のライブラリーを使うのなら、カードを墓地に送りながらも充分に緑らしく見えるものである。
《忍び寄る驚怖》

ゲームデザイナーの多くが望んでもなかなか実行できないのが、他のプレイヤーの行動を読んで考えるゲーム・メカニズムである。ブラフは楽しいものなので、我々はプレイヤーが他のプレイヤーの状況を判断しなければならないようなゲームの局面を作り、プレイヤーがお互いに鑑賞できるようにするのが好きである。周知の通り、これは何度も作られている(あの《呪われた巻物》もそうだ)。このカードの前提にあるのは、マッドネスなどのためにカードを捨てる方法であるということである。しかしそれだけではなく、ブラフ部分のおまけとして3点のライフを失わせることもできるのだ。このカードについてプレイヤーがどう思うのか、私は非常に興味がある。


この2枚の中で、《悪魔の遊び場》のほうが先にできていた。最初はデビル・トークンは6体だったと思うが、それでは少々多すぎたのだ。5体に減らし、さらに4体に減らした。そして、デビル・トークンが気に入った我々は、デビル・トークンを使うカードをもう1枚作ることにし、《悪魔と踊る》が誕生したのだ。



フラッシュバックは非常に面白いメカニズムで、旧『イニストラード』の中核部分だった。問題は、その世界を再訪するにあたって、新しいことをするための場所を開けておく必要があり、フラッシュバックは再録しないという決断を下したのだ。ただし、この新セットも墓地テーマを持つので、自分のライブラリーを削ることと組み合わせて、フラッシュバックと似たようなことをする方法を探すことになった。
そのための1つの方法が、墓地にあるときに本質的にクリーチャー・トークンに変化できる能力をクリーチャーに与えることだった。白ではスピリット、黒ではゾンビが使える。元は、こういったカードはもっと多かった。ほとんど小テーマと言えるほどだったのだ。しかし、このセットに必要なのは少しだけだということに気づいて、3枚まで減らしたのだった。
《石の宣告》

これも、物語上の瞬間を表すためのトップダウンでデザインされたカードである。ナヒリはソリンに激怒していて、ソリンの本拠地であるマルコフ荘園を訪れ、そこにいた吸血鬼たちに恐ろしいことをした。我々がマルコフ荘園を見るのは、ジェイスがイニストラードの謎を解くためにそこにたどり着いたときである。ナヒリがこの邪悪なことをしたこと、そしてそれがジェイスが調査することであることという両方を表すカードが必要だった。白には既に全てのクリーチャーを殺すカードが存在したので、これを全体除去にはできない。結局、我々はクリーチャー1体と、それと同じ名前のクリーチャーすべてを殺すカードにして、クリーチャーのコントローラーが破壊を低減できるようにした。引き換えとして調査を行うようにしたことでフレイバー的にも旨味がでている。
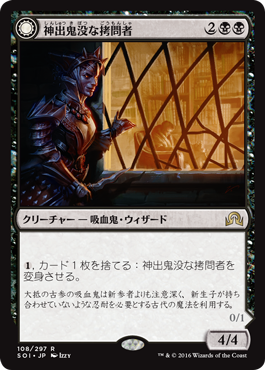

『イニストラード』ブロックで両面カードを扱ったとき、我々は思いつく限り様々な怪物のお約束を書き出していった。その中に、吸血鬼が霧になるとか、吸血鬼がコウモリになるというものがあり、これらはよく知られたお約束だと思われた。そして、これらは旧『イニストラード』で《金切り声のコウモリ》や《忍び寄る吸血鬼》となったわけである。
再訪にあたり、我々は「吸血鬼が霧になる」というお約束を使えると判断した。重要なのは、メカニズム的にどう表現するかである。フレイバー的に吸血鬼は自由に変身したり戻ったりできるものなので、この変身は自主的なものでなければならない。また、フレイバー的に、霧は触れることができないものだということを再現したいと考え、呪禁と破壊不能、「ブロックできない/ブロックされない」を持たせることにした。また、霧状態では何も傷つけることができないので、霧は0/1にした。
その後、吸血鬼が霧になるのには2つの理由があると気がついた。自身を守るためか、防がれないようにするためかである。最初は、変身に必要なのはマナだけだったが、マッドネスを吸血鬼部族に組み込んでいったので、この霧への変身能力でカードを捨てる必要があるようにするのは有用だと判断した。マッドネス呪文を唱えるマナを残せるよう、起動に必要なマナを低く抑えたのだ。そして、《陰湿な霧》に攻撃時の誘発型能力を与え、ブロックされなかったあと、ダメージを与える前に4/4に戻れるようにした。
影が落ちて
今日はここまで。見ての通りまだEまでしかたどり着いていないので、続きは来週になる。いつもの通り、諸君からのこの記事やセットに関する反響を楽しみにしている。メール、各ソーシャルメディア(Twitter、Tumblr、Google+、Instagram)で(英語で)聞かせてくれたまえ。
それではまた次回、その2でお会いしよう。
その日まで、『イニストラードを覆う影』の楽しい探索があなたとともにありますように。
(Tr. YONEMURA "Pao" Kaoru)

