月皇審問
スレイベンの守護者サリアは、屍術師の姉弟ギサとゲラルフが放ったゾンビの包囲からスレイベンを防衛する力となった。最悪の時に彼女はスレイベン大聖堂の中心、獄庫にてリリアナ・ヴェスと対峙した。そしてそのプレインズウォーカーによって指揮下の兵全員の生命を脅かされ、サリアは最終的に恐るべき要求を呑んだ。彼女は獄庫を砕き、その内に封じられていた悪魔全てを解き放った――そして大天使アヴァシンをも。
アヴァシン教会の月皇ミケウスはスレイベン包囲の間に死亡し、その後任もアヴァシンが狂気に堕ちて早くに殺害された。現在は、教会内でも年長の司教らと助言者として指導者級の聖戦士数人から成る新たな月皇評議会が設立されている。スレイベン防衛におけるもう一人の偉大な指導者、オドリックという名の聖戦士は月光評議会の統率において類稀なる戦略を示し、アヴァシンの狂気に対応した。彼は評議会の問題について投票権こそ無いものの、聖戦士の代表として席を得た。
だが天使達の狂気が続き、月皇評議会にまで広がると、聖戦士の指導者二人はアヴァシン教会への忠誠と、教会が象徴するもの全てへの献身との間で舵取りを強いられている。
狩人月の冷たい大気の中、ネファリア州のエルゴード訓練場からスレイベン大聖堂までは馬で数日の道のりだった。指の感覚はなく、だがサリアの頬は今も炎の熱を感じ、その血は今も激怒で沸騰していた。彼女は手綱を右手に持ち替え、頭上をまるで死肉あさりの鴉のように旋回する天使を用心深く一瞥し、がらんとした広間に突入した。
扉を開けて聖域へ向かいながら、慣習から彼女は胸にあるアヴァシンの紋章をなぞった。肩から心臓へ、肩から心臓へ。だがその祝福された紋章がエルゴードにて行った残虐行為を思い、彼女の目はちくりと痛んだ。
この高都市で過ごす時間は貴重で僅かとなっていたが、彼女は今もスレイベンの守護者の名を保持していた。そのため彼女の道を塞ぐ、もしくは要件を尋ねる聖戦士はなく、彼女は勢いよく階段を上り、回廊を下り、月皇の司令官へと評議会が与えた執務室へ入った。彼はそこにいなかった。そのはずだった。
サリアは乗馬用の外套を着たままで肩をすくめ、それを椅子に投げ、広間へと振り返った。「そこのあなた」 彼女は側で緊張とともに監視していた聖戦士を呼びつけた。「あの方を見つけてきて」
彼女はその小さな執務室を行き来しながら、手袋の手を勢いよくこすり合わせて凍えた指先に温かみの火花を灯そうとした。
入口に背を向けた時、そこは無人だった。三歩して振り返ると、彼はそこに立っていた。彼女ははっとした。
「サリア!」 オドリックの声は温かかった。彼は抱擁しようと両腕を広げた。
彼は老けたように見えた。この数年で頭髪は額の漆黒の一房を除いて白くなっていたが、顔は常に若々しかった。今、それは不安に皺を刻んでいた。
「お久しぶりですね、お会いできて嬉しいです」 サリアはそう言って、微笑みを浮かべて一歩進み出た。だが彼を抱擁するのではなく、その銀で飾られた胸当てを拳で殴りつけた。彼女の笑みが消えた。「あそこで何が起こっているか、ご存じなんですか!」
彼は溜息とともに両腕の力を抜いた。「今は最良の時ではないのはわかっている」
「子供です。私達は今、子供を火刑に。罪が蔓延しています、私の――」
「エルゴードでか?」 彼は遮って言った。
「そうです。オドリック、止めねばなりません。ウルマックはやりたい放題です」
「サリア、彼は審問官長だ。ネファリアの教会が関わる限り、彼は管理下にある」
「違います」 彼女はまたも胸当てを叩いた。「月皇評議会は今も教会を支配しているのでしょう? あなたの評議会でしょう?」
オドリックはようやく彼女を振り切ると執務室に入った。「私の評議会ではないよ。だが審問が彼らの援助の下に管理されているのは確かだ」
「止めねばなりません」 サリアは繰り返した。
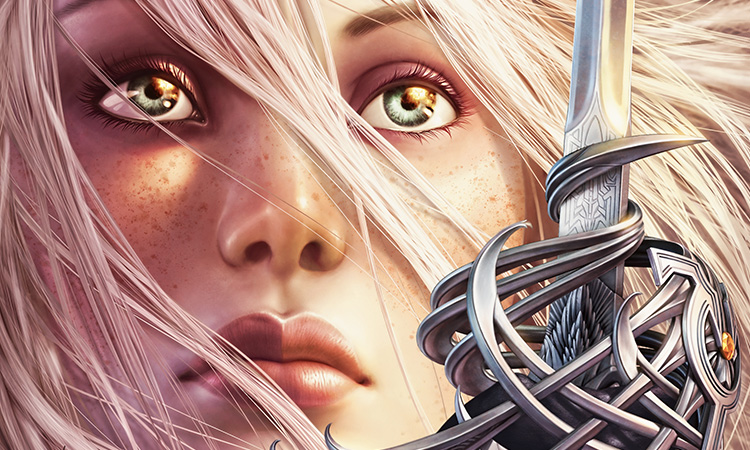
「そしてどうする? いかように天使の怒りの潮流をせき止めるつもりかね?」
「ご自身が何を仰っているかおわかりですか? 天使の怒りは私達が罪人を見逃しているからだとお考えなのですか? オドリック、天使は私達を守って下さる筈でしょう、私達の村を跡形もなく燃やすのではなく。そして私達は子供達を守る筈でしょう、火刑にかけるのではなく! アヴァシン様が私達にそれを望まれていると貴方は本当にお考えなのですか!」
「君も知っての通り、アヴァシン様がこの粛清を導いている。人間の罪がアヴァシン様の憤怒を呼び起こしたのならば、我々の中の罪を絶たねばならない。そうでなければその怒りを受けるだけだ。アヴァシン様は我々に示して下さっている。もしあのお方が悪人の嘆願に心を鬼にしているのならば、我々もそれに倣うだけだ」
「悪人? あの子供達がどんな罪を持っていると仰るのですか!」
「審問官の審判に異議があるのかね?」
「当然です! 子供達の目をまっすぐに見つめて、子供達の心をまっすぐに見つめて、そしてそこに悪を見つけるなどと――あんなひどい死に値する邪悪を?」
「もし、本当に審問官が子供達を死へ向かわせているのならば――」
「向かわせています。私は見ました」
「もしそうならば、そこには正当な根拠があるに違いない。神聖なるアヴァシンは悪を絶ち、罰し、無辜の者達を守る教会へと力を与えて下さる」
「彼らは権力を悪用しております!」
「私に何をしろと言うのかね?」
サリアはオドリックの片手を握った。手袋を通しても、骨まで凍えた彼女の手はそこに温かみを感じた。「議会で発言して下さい。その根拠とやらを見せて下さい」
「知っているだろう、私に投票権はない」
「ですが発言はできます。聖戦士の代表として、彼らはあなたを無視することはできません」
彼はサリアに背を向けた。「だが私は彼らの、アヴァシン様の命令下にある」
「お判りでしょう、その二つは必ずしも同じとは限らないことを」
彼はうつむき、だが返答はなかった。
突然激しい疲労を感じ、サリアは外套を投げた椅子へと座り込んだ。
「オドリック、私は、正しいことをしたのでしょうか?」
彼は振り返り、穏やかな笑みを向けた。二人は以前にも同じやり取りをしていた。だが折に触れて彼女はその答えを聞く必要がある、オドリックはそう知っていた。「君はアヴァシン様を解放した。そしてあの屍術師の手から君の兵を守った」
「そうです、とはいえ私は数えきれない悪魔も解放しました。その何体かは天使の手から逃れています」
「隠れているだけだ」
「ですが戻ってくるでしょう――全て、いつか戻ってくるでしょう。倒すことはできない――だからこそ獄庫が元々存在したのです。そして私はあの女性に、壊させた」

「君はアヴァシン様を解放した」 オドリックは繰り返した。
「もし、それが過ちだったとしたら?」 サリアは言った。オドリックの眉間の皺が深くなったが、彼女は続けた。「獄庫での時間がアヴァシン様を堕落させてしまったとしたら? 今、アヴァシン様は悪魔も同然の存在になってしまったのだとしたら?」
オドリックの表情が硬くなった。「それは私に言うべきではない言葉だ」 その通りだった――そしてサリアも、その考えを他人に向けて声に出そうとしたことはなかった。「私は月皇評議会の一員であり……」
「あなたは善きお方です」
「私はアヴァシン様と教会に仕える。それは君もだ、忘れてはおるまいな、スレイベンの守護者殿」
サリアは再び勢いよく立ち上がった。「私はアヴァシン様が体現する教義に仕えています――体現していた教義に。夜闇の怪物を押し留める柔らかな月光に。私達を引き裂こうとする恐怖を追い払う絆に。熱望してやまない神聖さに。もしアヴァシン様がそれらに背を向けるのであれば、悪魔と何ら変わりません。そして私はもはやアヴァシン様と教会に仕えることはできません」
オドリックの顔が怒りに紅潮し、彼女のすぐ傍に迫った。「神聖なるアヴァシン様と、そのお方が幾多の世紀を戦ってきた悪魔を比較するとは聞き捨てらならぬ。君は友人だ、それゆえスレイベンを去るよう命じる。そしてその口から出る冒涜を一切誰にも聞かせないように。グレーテ?」
赤い髪に縁どられた女性の顔が入口から現れた。サリアは振り返った――オドリックの副官がずっと部屋の外にいたとは思わなかった。彼女は会話を全部聞いていたのだろうか?
「閣下、お呼びですか?」
オドリックは再びサリアへと背を向けた。「サリアを外部城壁の外へ送って行ってくれるか?」
「了解致しました」
サリアはオドリックの背に手を置いた。「オドリック……」
「達者で、サリア」
彼女はぐっと言葉を飲み込んだ。何も言えなかった。
グレーテはサリアが騎乗する馬の手綱を握っていた。オドリックの下を退出してからずっと、彼女はサリアと目を合わせずにいた。だが馬上のサリアへと手綱を渡す時、グレーテはようやくサリアの凝視を受け止めた。
「どうなされるおつもりですか?」 グレーテは小声で尋ねた。
「戦います。私はこの地の人々を、脅威となる怪物から守ると誓いました。それを続けます。もし聖戦士と審問官が怪物と化したならば、彼らから人々を守るでしょう。もし天使が怪物と化したならば……」
「天使そのものとも戦うと?」 グレーテは目を見開いた。
「そうしなければならないのなら」
「自分は正しいと、どうしてそこまで確信なさっているのですか?」

サリア自身もその疑問に悩まされていた。その疑念にこの数週間、眠りを妨げられていた。だが明らかにグレーテも同じ確信を望んでおり、サリアはそれを分け与えられればと願った。
だがその代わりに、彼女は言った。「もし私が間違っているなら、そうですね、自分の良心を裏切るよりは背教者となりましょう」
グレーテは手綱を放し、馬から一歩離れると目をそらした。
「一緒に来ますか?」 サリアは尋ねた。
「いえ」 グレーテは、サリアよりは自身に向けて言っているように見えた。「ですが、どうか……最善を尽くして下さい、サリア様」
「ありがとう」
数週間後、オドリックはそれでもサリアの声を聞き続けていた。数人の熱心すぎる聖戦士が月皇評議会の前に立ち、最近のエルゴードにおける審問の成果を報告する時だった。その若者が「罪が蔓延し」の言葉をゆっくりと言うたびに、彼はサリアのともすると野卑な声を聞いた。そして審問官長についての言及は全て、「ウルマックはやりたい放題です」という彼女の言葉を思い出させた。尋問と拷問と処刑の詳細を聞くことはとても辛く、代わりに彼は評議会の司教達の顔色を観察した。
彼らのうち数人は明らかにオドリック同様に心地悪い様子だった。だが数人は身を乗り出し、目を大きく見開き、口の端に熱望の笑みをひきつらせていた。まるで毒々しい詳細に飢えているかのように。サリアは正しかったのだろうか? 我々は皆怪物と化してしまっているのだろうか? 彼は訝った。

扉が勢いよく開かれ、激しい音が彼を黙考から叩き出した。靴音を石の床に響かせ、サリアが議場へと大股で入ってきた。年若い聖戦士は明らかに彼女の存在に、その両目に燃える憤怒に怖れをなして避けた。
「サリア、何をしている?」 その呆然とした沈黙を破り、オドリックは尋ねた。
ジェレン司教が立ち上がり、腕を組んだ。「月皇評議会を中断することはなりません」
「私はスレイベンの守護者です。そして評議会にて発言する権利があります」 サリアは言い返した。
「サリア、君はもうその地位を保持していない」 オドリックは穏やかに言った。彼はジェレンが微笑むのを見た。「評議会が剥奪した筈だ」
サリアは彼を見た、そこに驚いた様子はなかった。彼女の両眼に燃える憤怒は軽蔑へと変貌した、まるでオドリックが目の前の地面に悶える蛇であるかのように。彼はサリアの信頼を裏切り、評議会へと彼女の背信を伝えていた。彼の胃袋が悶えた。
ジェレンが作り笑いをした。「ですが我々は情け深い気分にあります。評議会にどのようなご用事ですかな?」
サリアはひるませるような凝視をジェレンへと向けた。「司教様、あなたを告発します」
オドリックは椅子に座り直し、喉元を強張らせた。
サリアは続けた。「証拠をお持ちしました。あなたが不敬の皇子と呼ばれる悪魔、オーメンダールと交信しており、あなたは今やスカースダグの長である証拠を」
ジェレンは声をあげて笑った。笑っていた。他の評議会員はそれぞれの主張を叫び始め、だが評議会の名目上の長は、悪魔崇拝教団を率いているという告発にただ笑うだけだった。
「その証拠とやらを見せて頂こうか」 誰かがそう言い、叫びは収まった。
そしてサリアが微笑む番だった。彼女が求めていたのは、事実を示す機会を与えられることだけだった。彼女は顔を上げ、評議会全員へと向けて演説した――だがオドリックとは目を合わせなかった。「三日前の事です。私はウィッタル教区、エストワルドの廃墟近くの森にて聖戦士の小部隊を率いていました。教区の幾つかの村に呪いをもたらした悪名高い魔女の住処を探しておりました。そして柔らかな土に蹄の跡を見つけました」

「我々は君の証拠とやらを待っているのだが」 司教の一人が言った。
オドリックはジェレンを見た。その司教は椅子に深く座し、その指は口の前で組まれ、唇に無意識に浮かぶかすかな笑みを隠しきれていなかった。
「その足跡は魔女が住処にしている陰気な洞窟へと続いていました。洞窟の外ではこの評議会の馬具をまとった馬が、黒くなった草をはんでいました。中に飛び込むと、その魔女が伝令の死体からまだ脈打っている心臓を取り出しているところでした。まるでその生肉を齧ろうとしているかのように」
評議会員の数人が顔をしかめ、サリアから目をそむけた。だが今も彼女を見つめ続けている者達がいることにオドリックは気が付いた。彼らは審問官の報告を聞いていた時と同じ熱心な表情を浮かべていた。
「その魔女を確保しようとしましたが、怒り狂って悪魔のような力を振るってきました。殺す以外に選択肢はありませんでした」
「彼女から証言が引き出せる可能性を都合よく消したのだな」 誰かが言った。
サリアはその横槍を無視した。「死亡した乗り手は大聖堂からの伝令であり、この手紙を携えていました」 彼女は外套の中から羊皮紙を一枚取り出した。血と思しき黒い飛沫と汚れがその表面を損なっていた。「あなたがたご自身でお読みになり、私の告発が真実であると審判して下さい。この手紙にはジェレン司教に他ならない封と印があり、不敬の皇子の名のもとに魔女への指示が書かれています!」
オドリックの手足がかじかみ、心臓が高鳴った。サリアは恐ろしい物語を織り上げた。これが真実などありうるのだろうか?
サリアは評議会の机の端へ歩き、下位の司教の一人クウィリオンへと羊皮紙を差し出した。彼はジェレンへと臆病な視線を投げかけ、そしてサリアの手から羊皮紙を受け取るのを拒否した。サリアは嘲るとそれを隣の司教へと差し出した。評議会が石のような静寂の中に座し続ける中、三人の司教が拒否し、やがてカーリン司教が震える手でそれを受け取った。手紙を読むと彼女の表情は青ざめた。
「ジェレン司教殿、これをいかに?」 少ししてカーリンは言った。
「明らかに偽物です」 クウィリオンは言った、とはいえ彼は羊皮紙を調べてはいなかった。
「その話そのものがありえません」 別の司教が言った。
オドリックは何もかもが信じられなかった。どれほど評議会と意見を異にしようとも、サリアが証拠を捏造するような者ではないと知っていた。そして可能性を考慮するにあたって、正直なところ彼はジェレンを最も神聖なる人物とは呼べないと白状せざるを得なかった。だがスカースダグの指導者が、月皇評議会に席を?
「無論、ありえませんな」 ジェレンが言った。
「私には、この部屋には一人だけ背教者がいるように見えますが」 クウィリオンが言った。彼はその凝視をジェレンへと向けた、まるで年長の司教の賛同を求めているかのように。
評議会員が再び叫び始めると、オドリックは衝撃に言葉を失った。彼らはサリアの処刑を要求していた。サリアの表情は苦々しかった――彼女は落ち着いた表情は次第に蒼白になっていった、ジェレンの脇を固める司教達以上に。確かに彼女は幾らかの抵抗を予想していたのだろうが、これほど大勢とは思っていなかったのだろう。評議会へのジェレンの影響力は彼女の想定以上だったに違いない。サリアの手が剣へと伸ばされた。
それを抜くよりも早く、聖戦士達が現れてサリアの腕を掴むと指示を求めてジェレンを見た。指をごくわずかに動かしただけで司教は彼女を断罪し、聖戦士達はサリアを議場から引きずり出した。
「オドリック!」 彼女は叫んだ。その声は今も叫び続ける司教達の喧騒を貫いて届いた。「私は光に仕えます!」
夜闇の怪物を押し留める柔らかな月光に、私達を引き裂こうとする恐怖を追い払う絆に。彼女はそう言っていた。
そして月皇評議会はここに、恐怖に掴まれ、最も忠実な信者の一人に背を向けた。
サリアの背後で扉が乱暴に閉じられ、そして作り笑い一つとともにジェレンが若き聖戦士へと合図をした。エルゴードにて月皇評議会のために行われた恐怖の報告を続けるようにと。
オドリックは聖堂の地下へと急いでいた。彼はそこでサリアが今も処刑を待っていることを願った。評議会はまだ彼女を大聖堂中庭の木へと連れて行ってはいないだろう。これほど有名な背教者の処刑には儀式的な催しが充てられるはずだった。
「囚人と話すことがある」 オドリックは独房を監視している兵へと言った。その若者は敬礼し、脇に避けて彼を通した。
「声を出すな」 彼はサリアの独房の窓へと囁いた。「一緒にここを離れる」
「え?」
「声を出すなと言った」 オドリックはその兵へと向き直った。「衛兵、独房を開けろ」
彼女は目を見開き、だがその聖戦士はベルトの鍵を手探った。オドリックは同意に頷いた。少なくとも我々の中にはまだ、義務を心得ている者もいるということか。彼は思った。
サリアの独房の扉が軋んで開き、オドリックは手を貸すと汚物がしみ着いた床から彼女を引き上げた。サリアの頬骨にはまだ新しい擦り傷が広がっていた。抵抗したのだろうか? それとも彼女をここに連れてきた衛兵が、規範であるべき者が、アヴァシン大聖堂内でこのような暴力を?
共に階段を上ると、その一番上でグレーテがサリアの細い剣を携えて待っていた。
「馬は?」サリアがベルトに剣を取りつけている間に、オドリックはグレーテに尋ねた。
「馬小屋に着く頃には準備できている筈です」

「よし」
「どこへ向かうんですか?」 サリアが尋ねた。
「君が教えてくれ。ウィッタル教区に別の聖戦士達がいると言っていたな。彼らはまだそこに?」
「はい」
「ならば、そこに加わることは可能か?」
「はい。お伝えすることが沢山あります」
彼らは今や馬小屋のすぐ近くまで辿り着き、月皇評議会とジェレンから、この地を巣食う堕落からの脱出は間近だった。だがそのとき、五人の聖戦士が彼らの前に立ち塞がった。
「止まって下さい、月皇司令官殿」 中央の一人が言った。ドーガンという名だとオドリックは思い出した。数年前にその若者を訓練していた。「ジェレン司教様の命令です」 まるで謝罪のように、彼は付け加えた。
オドリックは歩き続けた。「そこを退いて我々を通せ」彼は言った。グレーテとサリアも彼から離れないように歩いた。
「できません、閣下」 彼の声から謝罪が消え、鋼が取って代わった。「司教様はその裏切りを予測しておいででした。そしてあなたがたを――三人全員を――評議会の議場へ連れてくるようにと」
更に多くの聖戦士が彼らの背後に現れていた――音から察するにもう三人。八対三ということになるだろうか。
オドリックは今や若きドーガンと、サリアとグレーテは彼の両脇を固める聖戦士と対峙していた。
「ドーガン、我々を通せ」 オドリックは繰り返した。
「それはできません」
オドリックは彼を押しのけて通ろうとしたが、背後で鋼を抜く音が全てを変えた。
八対三は難しい戦いだったかもしれない、その三人がアヴァシン教会でも最も熟練の戦士に名を連ねる者達でなかったなら。オドリックの拳が振るわれ、ドーガンの刃が床に音を立てた。かつての生徒が武器を拾おうとする間に、オドリックは振り返って背後からの攻撃を受け流した――マータ、彼が鍛えたもう一人の若き聖戦士だった。突き返しを受け、彼女の肩から血が流れた――訓練でもいつも肩に隙があった――そして後ろによろめいた。
ドーガンは体勢を立て直し、頭上に剣を振り上げて襲いかかった。オドリックはかぶりを振った――もっと良い型を教えていたというのに。彼はそのぎこちない振りを屈んで避け、確認した後にドーガンの腹部を突いた。自分達は木の剣で訓練しているのではないということを彼はほとんど失念していた。
同じくドーガンも失念していたのかもしれない。肋骨の下に手を触れるとその手は赤く汚れ、彼は目を大きく見開いて再び剣を落とした。

三人目の聖戦士が迫った。オドリックはその名を忘れていたが、その不運な身の程知らずはオドリックの刃に自ら突き刺された。マータは肩の傷を押して戦い続けていたが、グレーテの大剣に倒れた。
次にハーラルが対峙した。オドリックとともに不死者と戦ってきた年長の兵。彼はドーガンが誇る以上の経験年数を持ち、もしも彼の意思がもっと強ければこの小部隊を率いていただろう。彼は常にその意志に、情熱に欠けていた。出口を塞ぎながらオドリックと対峙する彼の頬には、涙が伝っていた。
オドリックの剣が彼の兜に音を立て、その聖戦士を背後によろめかせた。だが彼は立ち続け、更にきつく剣を握りしめた。
「私を殺すのか、背教者」 彼はうなった。
オドリックは進み出て鋼の嵐を解き放ち、その容赦ない攻撃にハーラルを後ずさらせた。彼は効果的な反撃を繰り出せなかった――その意志に欠けていた。必然的な隙が生まれ、オドリックはそれを無意識に察し、その男の喉を切り裂いた。
大聖堂の扉は今や目前だった。オドリックが振り返ると、大聖堂の磨かれた床に八人の忠実な聖戦士が血を流し、もしくは死んでいた。アヴァシン教会の神聖なる大聖堂に。「雪花石の天使が導いて下さることを――」 彼は言葉を詰まらせた。今もまだ、天使は人間の魂へと赦しを与えるのだろうか?
「……祝福されし眠りに導かれんことを」 すぐ隣でサリアが言った。彼女の手は胸のアヴァシンの首飾りをなぞった。肩から心臓へ、肩から心臓へ。彼女はオドリックを見上げ、目は涙に濡れながら、そして背を向けて扉へと駆けた。
オドリックの一部も死者とともにそこに横たわり死んだ。だが彼はそれを置いて走った。サリアとグレーテと共に、馬小屋を目指した。副官が約束した通り、三頭の馬が彼らを待っていた。三人は僅かに足を緩めただけで馬に飛び乗り、拍車をかけて飛び出した。大聖堂を出、スレイベンを離れ、そしてこれまでの人生を背後の彼方に残して駆けていった。
「彼らの三分の二が完全にジェレンの手中にあります」 近野の小さな教会。集めた聖戦士の小隊へとサリアは言った。「オーメンダールの影響は評議会を手中にする程広がっていました。私が見くびっていたことは間違いありません」
聖戦士達は取り乱し、かぶりを振った。
「何もご存じなかったのですか?」 彼女はオドリックへと尋ねた。
だがオドリックは何も言わなかった。スレイベンの外部城壁を越えてからというもの、彼は完全に押し黙っていた。瞬きをしているのかすらサリアには定かでなかった――彼はただ座し、見つめていた。
サリアは溜息をつき、彼の肩に手を置いた。「私も、あなたの苦しさはわかると思います」 彼女はその耳へと囁いた。「私達全員が、そうだと思います」
「閣下はきっと大丈夫です」 グレーテが言った。「時間を下さい。休む時間を」
「わかっています。お休み下さい、今はそれが全てです」
「私は何をすれば?」 グレーテが尋ねた。
サリアは微笑んだ。「一緒に来るよう誘ったのを覚えておられますか?」
「応じるべきでした」
「応じて下さらなくて良かったと思っています。あなたの手助けがなければ、私は今頃大聖堂の中庭で吊るされていたでしょうから。そして、あなたは今ここに」
「では、『ここ』には何が? ここで何をするのですか?」
「ようこそ、聖トラフト騎士団へ」 その教会がまるで大宮殿でもあるように、サリアは腕を広げて言った。
「聖トラフト? 聖者の名を掲げて正統を主張するのですか。悪魔殺し、天使に愛されし者、針目の殉教者――これ以上に相応しい後援者を選ぶのは困難でしょうけれど……」
サリアは微笑んで答えた。「選んだのではありません。選ばれたのです」
輝く霧がサリアの背後の宙に凝集し、彼女の髪を流れる黄金色に変え、表情までも光を発して輝くように見えた。一瞬の後、顔は二つとなり、そして離れ、一人の男性がサリアの隣に立っていた。輝きを放ち、だが実体のない聖霊。聖トラフトその人が。
サリアはグレーテの肩に手を置いた。「戦う覚悟はおありですか?」
グレーテは膝をつき、だが両眼はサリアの顔を見据えていた。「御伴致します、何処へでも」

(Tr. Mayuko Wakatsuki / TSV Yohei Mori)

