下僕
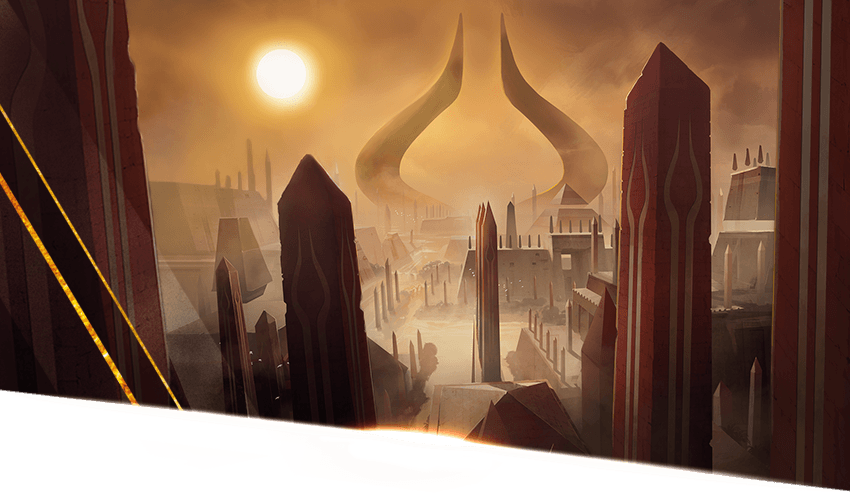
前回の物語:壁の記述
多くの献身的な不死者に仕えられ、かしずかれて過ごすというのはリリアナにとってはまさしく楽園のようなものだった。だがアモンケットで無為に座している余裕はない。彼女は債権者の悪魔の一体を探し出し、殺すためにこの次元へ来たのだから。
砂漠の影の中に、リリアナは何かを思い起こした。
穏やかな気候の中、心地良く涼しい風が存分に吹き付ける場所で過ごすというのは無条件に喜ばしいもの。だが柔らかな影の小島に寛ぎ、周囲の大気の焼け付く熱さを感じながら、動かず太陽に焼かれる木々が触れることのない涼風に撫でられる――率直に言って実に贅沢な気分だった。
物思いとともに彼女はイチジクの実を口にした。隣には、白い布で包まれた不死者の召使が完璧な均衡で果物の皿を頭上に掲げていた。背後ではこの一風変わった奴隷ミイラがもう一体、大きな羽根付き扇子をあおいで心地よい涼風を起こし、今もそれは彼女の髪を梳いていた。他のもう数体のミイラには、何か必要になるまで待っているようにと告げていた。そして彼らは自分の前にじっと動くことなくひざまずいていた。ゾンビの下僕には慣れていたが、これらは滅多にないほど印象的だった――必要を満たすだけでなく、それを予期してくれた。

彼女はこの場所に馴染めていた。
とはいえ。
とはいえ、至る所にニコル・ボーラスの存在感があった、不在の王神とか何とか。更にここの誰もがこの街の贅沢さを楽しむのではなく、神々とその試練と栄光ある来世とやらしか見えていない。更に実際のところ彼女は屍術でこれらのゾンビを操っているのではない。今まで見てきたものとはあまりに異なり、更に、試してみたならどうなるのかもわからない。
更に、何よりも、ラザケシュがいる。
契約によって彼女の魂を所持する悪魔のうち二体は、鎖のヴェールの凄まじい力を用いた不意打ちによって死んだ。そのヴェールとは膨大な力を持つ邪悪な遺物であり、それを手に入れようと彼女を送り込んだコソフェッドは、そのまま持って来させて――そしてその力の前では悪魔でさえ哀れにも死にうると示した。グリセルブランドは遥かに危険だったが、あの悪魔は魔法の銀の牢獄に囚われていた。リリアナは無力な現地人を脅してそれを破壊させ、更には未だ混乱するその悪魔を粉々にした。
ラザケシュが三体目になるのだろう。だが最初の二体とは異なり、ラザケシュに不意打ちができるのかどうかは定かでなかった――この次元のどこにいるのか、もしくは自分の存在に気付いているのかどうかも。
ラザケシュはこの世界のどこかにいる、ニコル・ボーラスの虜の世界に。元々ボーラスこそリリアナへと契約を仲介した者であり、自分が契約破棄に向けて動いていることをそのドラゴンがどう見ているのかはわからなかった。あの古龍に対するゲートウォッチの正面突撃がどうなるのかは知ったことではないが、まず彼らがラザケシュ殺しに手を貸してくれるよう、リリアナは何としても確かにするつもりだった。
「誰かを探さなくて良いのかな?」 背後から、かすかに上品な声がした。
ちょうど彼女が必要としているものだった。鴉の男。過去の幽霊――比喩的にも文字通りにも。彼女が何処にいて、何をしてきたのかを常に把握していた。肉体すら持たないのかもしれない。彼女自身の心に取り憑く苦悩の種、呪いもしくは精神的寄生なのかもしれない。だがこの男は実在した、実在するに違いなかった。どちらにせよ、全く楽しいものではなかった。
正体が何であろうと、この男は自分が若かった頃から断続的に付きまとっていた。そしてここ数年は、露骨なほど饒舌になっていた。
「もっと他にやる事はないの?」 彼女は尋ねた、振り返りはせずに。
リリアナは両脚を暖かな陽光の中にぶらつかせた。鴉の男は影の中を好む、そう知っていた。これなら正面から顔を合わせることはない。だがその男は彼女の隣に現れた。古風な黒い衣装で天幕の柱にもたれかかり、感情のない黄金色の瞳でリリアナを認めた。
「君が心配なのだよ、リリアナ。悪魔の一体は手の届く所にいる、そして時間はない」 彼は最終目的地へさしかかる副陽を示した。「それなのに君はここに座って、果物を食している」
「あなたはよく知ってるんじゃないの、私は無為に過ごしてなんていないって」
不死者の召使が至る所にいてよく維持管理されている中で、彼女が用いる「もぐり」の屍術がどう思われるかをきちんと理解しないうちは、リリアナは自分のゾンビを一体たりともあえて配置しようとは思わなかった。代わりに彼女は数体のシェイド、実体を持たない影と死のアンデッドを召喚していた。そして巨大な碑の隙間の影に送り出し、ラザケシュの気配を探させていた。
そしてどれだけ長い間姿を見せずとも、自分が何をしてきたかを鴉の男は知っているのだろうから。
「ああ、そうだな。自分で辺りを探すよりも下僕を送り出す方が良い。怖れているからではなく、目立たずにいるためだな。それは私もよくわかっている」
「軽蔑は受け取っておくわ。帰って頂戴」
「私はずっと辛抱していたのだよ。君がラヴニカで何か月もゲートウォッチ会館でぶらついて気の向くままにおせっかいを焼いていた間も放っておいた。カラデシュでの小旅行の間も黙って待っていた、それが危険な娯楽と化した後もな。君は、自分が何をしているかをわかっている。そこは私も信頼する所だ。君は愛情の絆を強めて、あの馬鹿者らを命令通りに動かしやすくしている」
「愛情こそ操る技よ。よく効く、そうじゃなくて?」
「誰にだね? 君とジェイスくんは酒を酌み交わして一度ならず旧交を温めていたな。また彼に夢中になりつつあるということかな?」
そう、一度か三度。ゲートウォッチに加わってから、ラヴニカでの彼女の自宅で。後にギデオンがとある戦略会議の場にて、早朝にジェイスの姿がない件について辛辣に言及した。そしてその物事は静かにひっそりと終わっていた。
「そんなことは、あなたの忌々しいお仕事には関係ないでしょう」
「君自身がその愛情に負けないように気をつけるのだな。忠実な馬鹿者らは、君の敵が待つまさに玄関口にいる。それでも君は何もしていない。彼らは考えもなく辺りをつついて回り、そして君はここに座って私達のこれまでの成果を危険にさらしている。弱腰になってしまったのか?」
リリアナの目の前が暗くなった。
「彼らはこれまでのあなたよりもずっと役に立ってくれたわ。あなたみたいな役立たずの幽霊よりもね」
「傷つく言葉だ」 鴉の男が言った、無礼な笑い声とともに。「私がこれまで君を助けてこなかったとでも? イニストラードで君の大切なフードの玩具くんが自分を失っていた時に、君の心を守っていたのが誰だと思っているのだね? 君がここに来た時、鎖のヴェールを操ってあのワームの腹から脱出させてやったのは?」
「何ですって?」
そしてリリアナはこの男を見た。あの胃袋へ落ちていきながら、自分は死んだと思った。どうやって脱出したかの記憶は曖昧だった。鎖のヴェールを操る……本当にそんなことがこの男には可能だったのだろうか? 以前にもあったのだろうか?
「君を助けようとしたのだよ」 鴉の男は微笑んだ。「ラザケシュは君の存在に気付いていないだろう。下僕らを集めて彼を倒すのが早ければ早いほど、君にとっては有利になるはずだ。今こそ便利な馬鹿者らを利用する時だろう」
青い閃光がリリアナの目をとらえた。それは群集の中を彼女へと向かってきた。
「噂をすれば」 彼女は微笑んで言った。「我らが愛しのテレパス君が来るわよ。心を空っぽにされたいかしら?」
「彼と私が会うのが怖いのかね?」
「あの子がやる気を出した時、あなたをどうするかを、よ」
鴉の男の黄金の瞳が睨みつけた。何て愉快な気分。
「君がここにいる目的を忘れないことだ」 彼はそう言って、憤然として姿を消した。
リリアナは椅子にもたれかかり、完全に寛いでジェイスを待つことにした。彼女は丸く紫色をした葡萄の粒を隣の鉢からつまみ上げ、それを半分に齧り、顎に流れ落ちようとした果汁を下唇で止めた。瑞々しくて甘い、とても良質な葡萄だった、
「ここにいたのか」 フードを被ってもなお強い陽光に、目を細めてジェイスが言った。
ジェイスが濃厚で苦いビールに悪戦苦闘していた間に、リリアナは自分の目で街を見ようと借り部屋を出ていた。やがて彼女は川沿いのこの小さな天幕に落ち着き、調査員を送り出し、そして幾らかの食べ物を頼んでいた。
彼女は葡萄を飲み込んだ、種も他のものも全て――吐き出すなんてはしたない。
「ごきげんよう、ジェイス。遅い朝食かしら?」
「もう正午は過ぎてるよ」
「じゃあ遅い昼食ね」
彼は歯を軋ませた。
「あれが……昼食……」
可愛らしいこと。
「好きになさいな。イチジクがあるわよ」
ジェイスは肩をすくめてイチジクの粒へ手を伸ばしたが、皿を持っているものを見て手を引っ込めた。
「死体が食べ物を持ってなければもっといいんだけど」
「ジェイス、あなたには驚きよ。他の皆は嫌がっても、物言わぬ死体の召使いがどれほど便利かってあなたはわかってくれると思っていたのに。見ての通り、この包帯はとっても清潔よ」
「こんな社会は見たことあるのか? 死体が保存されて召使いにされて、ゾンビがあらゆる仕事をしているなんて」
「無いわね、こんなふうなのは。それにこの街の死体は外のそれとは違う、あなたは気付いていないかもしれないけれど」
「確かにこいつらは小奇麗だ。でも、ああ、俺も気付いてた。外の砂漠では、あのワームの一体が自然に蘇った。君は……倒された。周りに他の屍術師がいたなら、気付くべきだった」
その声にあるのは心配だろうか?
「あのゾンビは長いこと、誰かに支配されていたんじゃないのよ。ワームについてあなたが言ってることが本当だとしたら、環境的な屍術か何かによって蘇った可能性があるわ」
「環境的な屍術? そんなものがあるのか?」
彼女は肩をすくめた。
「ここにはあるのかもしれない。良い場所ではないわね」
「ここのゾンビについては?」
「彼らは……奇妙ね」 彼女はそう返答した。事実、この街で働くミイラは不気味だと感じた。「彼らを蘇らせた魔法が何かはともかく、私のとは違う。そして彼らを厳しい管理下に置いている。こんなのは初めて見るわ」
「もっとよく調べれば、ここで何が起こっているかがだいぶ判るかもしれないな」

リリアナはシェイドが近づいてくる馴染みある寒気を感じた。それは碑の影を音もなく動き、傍の木の影から伸びた。
ジェイスは身震いをして周囲の影を見た。賢い男の子ね。
「私のよ」 リリアナのその言葉に彼は力を抜いた、だが完全にではなく。賢い、疑い深い男の子ね。
リリアナがいる日陰にそのまま達することはできず、そのシェイドは少しの距離に留まった。
『キテ』 それは彼女へと囁いた。『ミツケタ』 シェイドは厳密には会話をするわけではない。
「そう」 彼女は声を上げた。「見つかったようね」
彼女は手の一振りで控えていたミイラを去らせ、スカートの裾を整え、ジェイスへと向き直った。
「私を追いかけてきたのよね」
「そうだよ」
「そして、もし、ついて来るなって言っても、どのみちあなたは姿を消して私をつけてくるわよね」
ジェイスは肩をすくめた。「それは考えたよ」
「それなら、最初からついて来るように言ったら?」
「んー……そうするかな?」
「いいわ。それじゃ来て」
彼女はシェイドを追いかけて歩きだした。
ジェイスは溜息をついて彼女を追い、呟いた。「つまり君は俺に来て欲しかった、それとも……?」
彼女は微笑んで、歩き続けた。
二人は日が差す往来に沿って進み、揃いの若者らや不気味なほど熱心に訓練する子供らとすれ違っていった。街では沢山の「修練者」が戦闘訓練で上げる奮闘の叫び声と清い汗の匂いが訓練場から漂っていた。
何て素晴らしい肉体! 彼らが形よく死んで自身に仕える様を、彼女は想像せずには……
あら。
「ジェイス……気が付いた? この街のミイラはどれも身体が欠けているって」
「え? ああ、何体かは。手がないとかそういう。全部なのか、本当に?」
「欠けていなくても、腱が切れていたり骨が折れていたりしてるわ。歩き方でわかるもの。ここの誰もがそんな乱暴な死に方をしているってこと?」
「それとも、そうでない死体は何か違う目的に使われるとか?」
彼女は眉をひそめた。
「この場所は変よ」
「本当に変だ」
「それにギデオンはどうも……」
「……実際ここのを好きになりつつある」 彼は言い終えた。「俺はわかる」
二人は厭わしさに声を漏らした。
「それで、俺達は何を探してるんだ?」
「私が探しているの」 リリアナは微笑んで言った。「ついて来て。どのみち、秘密よ」
「秘密は嫌いだよ」
「秘密を知るのが? それとも知らないのが?」
「どちらにせよ困ったことになる。だけど、まあ、知らない方が良くない。もちろん」
もちろん。彼はまだ時に、とても純粋だ。
彼女は溜息をついた。
「怒らないでくれる?」
「怒らないよ」
「ギデオンには言わないって約束できる?」
「それも約束するよ」
「じゃあ、当ててごらんなさい、外套くん」
彼はリリアナの隣を歩きながら、考えた。
「ニコル・ボーラスを見つけようとしている」
「今すぐには違うわ」
「俺達をニコル・ボーラスに売ろうとしている」
「そそるけど、違うわよ」
「君は……前にここに来た時にやり残した何かを探している」
彼女は微笑んだ。
「んー。面白い推測ね。でも曖昧ね」
ある建物沿いの壁の影の中、シェイドが姿を現して止まった。その壁は碑文に覆われていた。現地の文章、幾つかの表象は読めず――そして幾つかは読めた。
ラザケシュ。
その碑文が目の前で揺らぎ、意識の端に囁き声がした。彼女はよろめき、建物の壁につかまった。暑さ。これは暑さのせい。
ジェイスはそれを支えようと手を伸ばしはせず、彼女がよろめくのを見ていた。
「大丈夫か?」
「私はいつも大丈夫」
彼はリリアナを一瞥した。
「これまでも、そしてこれからもよ」
シェイドは二人を入口へと導いた。砂漠の太陽に長時間さらされ、その身体はほぐれ始めていた。彼女はそれを手の一振りで散らせた。
その場所は公共へと解放されてはいないようだった。鍵はなく、扉すらなかったが、この街ではそれが当たり前のようだった。
二人は石の傾斜路を下り、不連続に掛かる松明に照らされた長い通路へ入った。壁には彫刻があり、修練者らが熱心に戦う様が描かれていた。その幾人かは死して地面に倒れていた。
彼らの背後に引きずる音があり、足音が傾斜路をやって来た。二人は振り返った。隠れ場所はなかった。不法侵入とみなされないことを二人は願った。
両腕一杯にぼろ布を抱えた召使いミイラの空白の顔が視界に入った。ジェイスとリリアナは凹みを見つけてその中に入り、ミイラはそれに気付いた様子は全くなかった。その背後からまた一体、そして別の一体がやって来た。数体は荷を引きずり、あるいは二人組でもっと重い物を運んでいた。
違う。物ではない。
そのミイラ達は戦闘で殺された修練者の死体を運んでいた。それらは血を滴らせ、ぼろ布に包まれていた。幾つかは身体の一部が欠損していた。死臭から判断するに、死んで間もないものだった。最大でも一時間か二時間か。
隣で、ジェイスが口を覆った。
ミイラ達が通過すると、彼女は通路に出た。
「足元に気をつけて。滑るわよ」
「こんな所にいるべきじゃない。何でここに来たんだ? 君は何を探しているんだ?」
「あなたが言ったんでしょう、ミイラについて調べれば、ここで何が起こっているかがわかるかもしれないって」
それは全くの真実だった、表面上は。だがこの何がラザケシュに関係あるのだろうか?
二人はミイラを追って回廊を進んだ。周囲の彫刻は変化し、ミイラが修練者の死体を運ぶ様子を、そしてそれらを石版の上で不朽し、更なるミイラを作る様を描いていた。
大きな、よく照らされた中央広間に入ると、二人はその彫刻の現実を見た。その場所は忙しく活動的で、石板の上に死体が横たえられ、その隣の机には器具や内臓容器が並んでいた。空気はこれまでと異なり、死臭と防腐剤の黴臭い悪臭が入り混じっていた。

ミイラ達は全くの無言で働いていた。それを中断するのは包帯を巻かれた足の摩擦音と死体を整える際の時折の叩く音、削る音、もしくは押し潰す音だった。
何という大規模な作業! かつて読んだことのある他の次元でのミイラ化の過程によく似ていたが、ここまで発達してはいなかった。ミイラは修練者の内臓のほとんどを取り除き、ここでそれらは大きく飾り気のない共用の壺に入れられていた。死体は積み上げられ、織機のように能率的な梱包過程に回されていた。
宗教的な儀式ではなかった。純粋に実用的だった。
ジェイスが心に語りかけてきた。『彼らは死んだ修練者全員をこうしているんだ』 彼女はその侵入をありがたいとは思わなかった。そしてミイラの方は全く生者に興味はないらしく、落ち着いた効率でその不気味な作業を続けていた。
何故こんなにも多くの修練者が訓練で死ぬのだろう?
彼女はジェイスを小突き、部屋の向こう側を指し示した。そこには何らかの精巧な壁画があった。彼は頷き、二人は部屋の隅に沿って静かに進んだ。
梱包が終わらないうちに、ある死体が動き出した。それは四肢を振り回して震え、梱包作業は騒々しく停止した。それは二人がこの場所で初めて見た、能率的でなく秩序立ってもいないものだった。脚を止めて二人は見つめた。彼女以外にそこに屍術師はおらず、つまりは屍術もない――ただ、あらゆる場所から湧き出すらしき死の魔力によるものだった。
梱包過程を監督していたミイラがそのはぐれた屍へと近づき、押さえこむと別の一体が大きな金属板、カルトーシュを手に近づいた。彼らはカルトーシュをその死体の胸に押し付けた。
暴れる屍は静まった。
リリアナとジェイスは顔を見合わせた。不朽のミイラが防腐された死体に次々とカルトーシュを押し付ける中、二人は移動を続けた。数体はカルトーシュをはめられる前から動きだしていた。他は少し後まで動かず横たわっていた。
リリアナとジェイスは壁画の前で立ち止まった。それは黒い石に刻まれ、部屋の一面の壁をすっかり覆っていた。背後で恐ろしい作業がつづく中、二人はその壁画を調べた。
それは来世を描いたものだった。都市のそこかしこで見られる碑文の表現形式は、今や二人にも馴染みあるものになっていた。地平線の角の間に座した副陽、来世への道を塞ぐ(と現地の者らが言う)巨大な門。この壁画では門は開いており、その先の来世がわずかに見え――だが巨大な悪魔に守られていた。
ラザケシュ。
『最後の試練』 銘刻はそう読めた。『栄誉無き者も遂にはここに死す。値せぬ者は選別される』
ラザケシュの両手は血に濡れ、足元には屍の山があった。血は川へと流れていた。
その門の先に、ラザケシュがいた。ラザケシュの先に、楽園があった。
ラザケシュの彫刻はリリアナを不安にさせた。まるで自分を見つめ返しているような。

「君は、例の悪魔の一体を探してここに来たのか?」 ジェイスが囁いた。
「二体は倒した」 リリアナが言った、喉を詰まらせながら。その彫刻は不気味にそびえ立っているように思えた。「次はこいつよ」
「何で言ってくれないんだよ! 手を貸せただろうに!」
「あなたは私の悪魔についてそこまで知っていて」 リリアナは言い返した。「あなたは、戦ってくれるんでしょう。でもあなたに全部言ったとして、ギデオンもそうしてくれるって本当に思ってるの? ニッサは?」
「わからないよ」 ジェイスも言い返した。「君の味方にはなれる。でも今、君が嘘を言ったからには、俺は――」
「何も嘘はついてないわよ」 ひどい頭痛がした。
「本当のことを言わなかっただろ。俺達の信頼を裏切った」
「信頼してなんて頼んだことはないわ」
ジェイスは何かを怒りとともに言い返し、だがその言葉は聞き取れなかった。彼女の耳は鳴って視界は揺らいでいた。ポケットの中で鎖のヴェールが熱を帯び、彼女を守っていた。
ラザケシュの彫刻が……その目を開いた。赤、血の赤。彼女に見えたのはそれだけだった。
背後の音が止み、そして十体程の壊れた喉が囁いた。
「「「「「リリアナ」」」」」
やめて、やめて、やめて、やめて、やめて。
そのミイラ達は作業を中断し、彼女を見つめていた。彼らの努力の産物はその隣に立ちつくし、数体は半ば解けて、カルトーシュが急ぎ取り付けられていた。今や、至る所で彼女の名を呼ぶ声が聞こえた。壁そのものからも。
『君の仕業か?』 ジェイスの声が脳内に響いた。
彼女は無力にかぶりを振った。
「「「「「リリアナ……」」」」」
ミイラ達が突進してきた。彼らは二人を取り囲み、包帯の肉と掴む手がもつれ合った。そしして未だ無言の、全くもって無言の――ただ時折のうめきと絹を梱包する囁きだけの、静かな戦いがあった。ジェイスは彼女の隣で呪文を唱え、幻影の綱でミイラ達を一体ずつ遠ざけていた。だが場所は狭く、数は多すぎた。
リリアナの思考が晴れた。彼女は砂漠でそうしたように呼びかけ、ミイラを支配しようとした。彼らはただの死体、他の何とも変わらない。
何も起こらなかった。
環境的な魔力。瞬時に、彼女はその全てを理解した。この世界にある何かが――自然のものか人為的なものか、それは全く問題ではないが――死者を蘇らせる。あらゆる死者を、都市の中でも外でも。召使ミイラを作り命令する者らは全くもって屍術など必要としておらず、ただ制御の手段があればよい。そしてその制御は直接的で物理的――それに打ち勝つのは、劣った屍術師の気まぐれよりもずっと難しかった。
「操れない。カルトーシュが――」
彼女は近くのミイラを掴み、指をカルトーシュの縁に突き立て、そして力の限りにもぎ取ろうとした。ジェイスはその意図を察し、そのミイラの首を掴んで彼女から引きはがした。
肉の弾ける音とともに、カルトーシュが外れた。
そして小さな爆発音と焦げ音がした。カルトーシュが離れた穴は眩しく白い光に燃え上がり、そのミイラは倒れて崩れた。
ああ、何てこと。
そしてミイラが二人を取り囲んだ、多すぎる数が、四肢と喉へ掴みかかった。彼女は鎖のヴェールへと手を伸ばした。必死にそれを避けてはきたが、もし生き延びるためにこれが必要というなら……
突然ミイラ達は凍りつき、その場に動かなくなった。そして誰かを通すように幾つかが脇に避けた。
「あなたがたは本当に余所者なのですね」
テムメトだった。

自分達へと丁重に住居を提供した、若く尊大な高官。リリアナは出会ってすぐにこの若者が嫌いになっていた。あまりに落ち着き、あまりに自信に溢れている。当初彼女は疑いさえした、この少年は見た目よりも年長なのではないかと――彼女自身のように、ずっと年を経ているのではないかと。だが違った。まだ十代だった。この街のあらゆる住民と同じように、とても若いうちに鋭い刃を研ぎ澄ませていた。そして今、その刃は自分達へ向けられていた。権力の真似事をしている子供と馬鹿にできない十分な力をもって。
「当初は信じられませんでした。誰も聞いたことなどないでしょう」
彼は近寄り、取り調べるように二人を見た。
『話を続けてくれ』 ジェイスが心に告げた。『何か防御魔法の類がかかってる。ちょっと時間がいる』
「ですが知識の碑にて出生記録を確認しました」 テムメトは続けた。「ケフネト神は全てをご存知ですが、高官らはあなたがたを知りませんでした。そして今あなたがたはここに降り、神聖なる不朽の間を詮索している。あなたがたは真に私達の道について無知だ。角ある御方についても何一つ知らない――かの御方が疾く帰還されんことを、そして我等は蓋世の――」
「私達、実際そいつに会ったことあるのよ」 リリアナが言った。
ジェイスとテムメトは同じく驚いた。
「黙りなさい!」
「そして知るがいいわよ、あいつは完璧にただの――」
ミイラの手が彼女の喉を絞め上げ、言葉を遮った。
「嘘を!」顔を紅潮させ、テムメトが叫んだ。
次の瞬間、テムメトの両目が青く輝いてその表情が緩んだ。一瞬おいて、ミイラの手が彼女を放した。
ジェイスが彼女の腕を掴んだ。彼の両目も輝いていた、青い光がその隅から漏れ出て、表情は苦しく歪んでいた。
「逃げるよ」 彼は息切れとともに言った。
「何を――」
「長くは……もたない」
なるほど。ジェイスはテムメトを操り、テムメトはミイラを操っている。それはこの愛しい男の子の心を多大に消耗させているに違いない。全てのミイラが動きを止めたわけではなかった。多すぎるのだろう。ジェイスはかろうじて制御しているに過ぎなかった。
リリアナは近くのミイラを肩で押しのけて走りだした。彫刻の赤い瞳から、防腐室から、そして死と静寂の悪臭から、彼女は逃げた。
外へ。眩しい太陽の下へ。心臓が早鐘を打っていた。
ジェイスの瞳が晴れた。リリアナは背後を一瞥したが、追跡は見えなかった。今のところは。
「あれは……」 ジェイスは喘いで言った。「……冒涜するようなことを言って、あいつの気を散らす作戦だったのか?」
「面白かったでしょ」
しばし、二人はただ息を切らして走り続けた。
「何が……あそこで起こったんだ?」
「ラザケシュ」 彼女は答えた。「悪魔。思うに……あいつはこの『来世』に関わってる。そして……私がここにいることも気付いている。鎖のヴェールがあるから、契約を行使できないってだけ」
「上等じゃないか」
「ところで、あなたはテムメトの心を消したの?」
ジェイスは顔をしかめた。
「いや。俺にできたのは……ミイラを遠ざけておくことだけだった。しばらくして気が付くだろう、ひどい頭痛とともに。だけど覚えているはずだ」
「それなら、皆と合流しないと」
『今こそ便利な馬鹿者らを利用する時だろう』 鴉の男の言葉。
友であろうと便利な馬鹿であろうと、リリアナには彼らが必要だった。彼女は駆けた、悪魔から逃げ、助けを求めて。
(Tr. Mayuko Wakatsuki / TSV Yohei Mori)

