物語と結末と
前回の物語:月皇審問
ジェイス・ベレレンのイニストラード滞在はとある謎を追い求めることに費やされてきた。リリアナの邸宅からマルコフ荘園へ、そして溺墓の寺院へ、またリリアナの下へ、そしてついにはスレイベン大聖堂へ。この旅を導くのは一冊の日誌だった――彼がマルコフ荘園で発見した研究記録の束。
折よく、その日誌の著者である空民のプレインズウォーカー、タミヨウは彼の数歩先にいた……
スレイベン大聖堂の礼拝堂、その足は石の床に決して触れてはおらず、漂うように進みながらもタミヨウは自身が爪先立ちで歩くことを思った。何十もの次元で、彼女は二足歩行の生物が爪先歩きをする様子を見てきた。それはしばしば誇張され、もしくは芝居じみた動きで、人目をはばかる振る舞いを意図するものとされていた。とはいえ、爪先で立つことは小さな面積へとその者の体重を集中させることになる。事実、木の床(調査をしてきた多数の次元で、床の材質としてはありふれたもの)を爪先立ちで歩くことは床板を軋ませる可能性を増加させる。それは爪先立ちで歩く者の存在を明かしてしまう迂闊な雑音としては最もありふれたものだった。こういった類の不合理性は人間に最もよく見られるもの。彼女はそう認識し、それを記録することには常に幾らかの楽しみを得ていた。だがイニストラードには楽しみなど何もなく、その兆候は直ちに不合理性よりも遥かに深く危険な何かを示した。彼女は既に想定よりも長く滞在し、とても多くの危険を負っていた。だがこの世界はその軸から完全にずれており、原因を知る必要があった。
筋道の通った調査を幾つも行ってきた。あるものは行き詰まった。あるものは有望だったが、決定的ではなかった。彼女の天文学的調査の信頼性は高かったが、「軸のずれ」の原因は、大元の原因は、今も手の内にはなかった。これは千のパネルから成る細工箱、万の嘘から成る謎。彼女はこれ以上に挑戦的なものを解いたことはなかった。
彼女はまた、仕事を完成させることなく諦めたこともなかった。

最新の一連の調査が彼女をこの聖堂へと導いた。イニストラードの人類はアヴァシンについての最古の歴史をここに保持している。自身で個々に集めて遡った物語は断片的で曖昧ながら、彼女は物語が奏でる音楽を知っていた。どの弦を爪弾き、どの旋律を続ければ現れてくるのか――滑らかな一歩また一歩と、真実の断片が。求めるものが古の秘本に記されていて、それを単純に発見できるとは思っていなかった。そのような物語は何度も聞いたことがあったが、今も生き続けているものはなかった。それでも、最古の歴史とは最も歪みの少ない歴史。目的と意図のためにその記述を捻じ曲げられる機会が最も少なかった歴史。アヴァシン。世界の軸がずれ始めている、そしてその天使はイニストラードの核。この比喩は良く合っていた。
彼女は神へと短い祈りを囁いた。勿論、ここに神はいない。霊は次元ごとに全く異なった姿をとり、イニストラードの幽霊は彼女の故郷の小さな神々とは似ても似つかない。自身の経験から、次元の境界を越えてその神が祈りを聞き届けるとは全く思わなかった。だが神河次元でのそれらの存在の果てしなさは、決して侮れるものではなかった。
彼女のような侵入者を見つけようと、武装した聖戦士達が厳格かつ油断なく広間を巡回していた。タミヨウは既に現地の者達と最適と言える以上に接触を持っており、天性の静けさと身隠しの能力を限界まで引き上げていた。内部書庫へ進むためには、一つの物語が必要だろう――周囲の世界を語る物語が。
ある古い巻物、彼女が最初に手にしたお気に入りの一つが、広げられて隣に浮かんだ。それは故郷の物語、まさしく彼女が必要とする物語だった。
太陽を怖れさせた者
これは暗闇と化した世界と、太陽を怖れさせた者の物語。その影は踏みゆく所全てに夜闇をもたらし、その飢えは決して満たされることはなかった。その鬼は生まれて以来収集してきた戦利品と略奪品を隠し持っていたが、誰もその鬼の怒りを買おうとは思わなかった、怖いもの知らずのとある悪忌以外は。
その悪忌は長い平らな石を見つけ、それを頭上に持ち上げた。ずっと高くから鬼が見下ろしても、それはただの石にしか見えないだろうと思った。悪忌はそのように身を隠し、自信ありげに鬼の洞窟へと入った。

だが鬼はその石に興味を持った。
「奇妙な小石じゃの、動いておるわ! 我が宝を盗むつもりか?」
「石が宝を盗むなど、聞いたこともございやせん。そう思いませぬか? 盗人を見つけたらお知らせいたしやす、約束しやしょう!」 石が返答した。
その鬼は悪忌の言葉を信じ、何事もないと結論づけた。鬼が眠ると、その悪忌は持てる限りの宝を持ちだした。黄金、宝石、そして輝く皿。自分の顔がそこに映ったのを見て、悪忌はにやけた。
次の日、悪忌が戻ってくると、鬼がその石に向かい合った。
「小石、小石め! 我が宝を盗んだ者がおる! おぬし盗人を見たか?」
約束を思い出し、悪忌は返答した。「見ましたとも! 盗人、ずるがしこいちびの悪忌を! 外へ行ってそいつを探し出して懲らしめるのが良いでしょう!」
その鬼は頷き、探しに出かけた。鬼が留守の間、悪忌はまたも宝を、更に沢山盗み出した。
そこで終わらせていれば良かったのに!
三度、小さくも欲張りな悪忌は鬼の洞窟へやって来た。頭の上には石を、心には強欲を。鬼の心には怒りだけがあった。
「小石め! また盗まれたではないか! 盗人は見つからん、だがまたしても宝が無くなった。どうすべきか。西にある悪忌の巣へ行ってそいつらを全員食らい尽くせば、どれかは当たるに違いあるまい!」
故郷と友を心配し、悪忌は返答した。「強きお方! 悪忌は固くて苦くて全然美味くありゃしません! 放っておくが吉です、そして盗人探しを続けなさって下さい!」
鬼は石については知らなかったが、嘘についてはとてもよく知っていた。鬼はその小さな悪忌を石ごとすくい上げ、一飲みにしてしまった。
真実はどのような嘘よりも優れた欺き、悪忌はこの物語でそう告げている。
物語が呼び起こされ、その魔法が実体を成し、タミヨウは視界から消えた。見る者には、彼女はこの場所に属する何かとして映るだろう。別の聖戦士か、もしくは華麗な花瓶か。彼女が嘘を言うまで、もしくは欺きを求めなくなるまで。これはとても役立つ物語だが、彼女はこのように使うことへの謝罪を呟いていた。物語を使う時は常にそうだった。物語とは神聖なもの、そして道具として使用することは常に、わずかだが冒涜のように感じるのだった。
この日、タミヨウは物語の巻物を二十九本持っていた。それとは別に鉄の輪で閉じられた三本を――決して使用してはならないものを。
彼女は目的をもって歩き(今や足は石の床に触れており、極めて冷たかった)、二人組の聖戦士とすれ違うと彼らはきびきびとした敬礼をした。彼女はぎこちない動作で敬礼を返し、聖戦士は自分達が見るべきものとしてタミヨウを見た。中央書庫はすぐ目前だった。彼女は持ちこんだ物語を心の中で列挙し、前方にかかっているであろう鍵に対処するには何が最良かを考え、その時、場違いなものに気が付いた。既に扉はわずかに開いており、その内からは蝋燭の明かりがちらついていた。
手を振ると、かすかな風が重い扉を僅かな角度だけ押し開いた。深く集中して身構え、今や彼女の足はしっかりと床を掴んでいた(とはいえ説明不能な理由から、彼女は今も爪先立ちをしているような気分でいた)。そして直ちに逃げることも飛びかかることも可能な体勢で、扉へと忍び寄った。
油を差された蝶番が更に開き、そして間違えようのない音が聞こえる寸前、彼女の目はそれを認めた。まるで突然眠りに落ちたかのように、床へと倒れている身体。武器も鎧も身につけていない、年老いた司書。そしてその向こうに立つ……プレインズウォーカー。

戦うか逃げるかを決める前に、彼女は短い時間で可能な限りの状況を把握した。自分の調査の中では、プレインズウォーカーは何があろうとも避けるべき存在だった。彼らは厚かましく予測不能、そして見知らぬ世界の先入観や考え方を持ち込みかねない。彼らは要するに、真実を求める者にとっては厄介な存在だった。この者は若い人間男性の姿をしているが、取り巻くマナの塵には欺きの匂いがあった。地元民のものらしき衣装をまとっていたが、それを明らかにイニストラード的ではない模様で飾っていた。奇妙で貧相な変装。その両目は輝き、狂乱し、荒々しく、苦しんでいる様子だった(不意に彼女は考えた……もしプレインズウォーカーがこの次元の狂気に罹ったなら、彼らはそれを別の世界にまで広げてしまうのだろうか?)。そして彼の手には……あの野帳があった。更に複雑な事態。彼女は心拍二つ分、彼の行動を待った。とはいえ既に帯から一本の巻物を取り出し、広げる構えでいた。
彼の両目は混乱していた。怒り、怖れ、好奇心、そしてそれらが何か、認識と安堵のようなものに落ち着いた。
「君か! 君なんだな! 俺をここに連れてきた、違う、君じゃなくて、この日誌だ。君の日誌! 俺に会うために? 違う、でもどうやって?」 その言葉はかすれて消え、彼の両目は再び床へと漂い、そして詰問するように素早く彼女へと戻った。「俺を見てたのか? 知ってたんだろ!」 そしてその声は再び柔らかく、悲しげな嘆願と化した。「手伝ってくれ、できるだろ? きっと……手伝ってくれないか? 助けてくれるよな?」 その最後の言葉は全くもって嘆願ではなかった。命令だった。圧迫するように力強く、雨戸を叩く風のように彼女の精神を叩いた。だがタミヨウの心は彼方の城へと退散し、その風は届かなかった。もう心拍四つぶんだけ考え、彼女は可能な限り穏やかに微笑むと思考一つでそのプレインズウォーカーを隠蔽の魔術で覆い、別の巻物を鞄から取り出した。そして書庫へ滑り込み、背後で静かに扉を閉めた。この物語をそのような方法で使ったことはなかったが、錯乱したテレパスのプレインズウォーカーというのは考えたこともない危険な存在だった。その物語は彼女が遥か昔に収集したものの一つ。五つの月と、見渡す限りの金属が輝く世界の物語。
根源
創造主を失い、その生物、マイアは迷っていた。
あるものは最後の命令を続け、導きも目的もなく務めを繰り返した。またあるものは単純に機能を停止し、来ることのない命令を待った。メムナークの喪失は彼らを殺しはしなかったが、彼らの中に真の自意識はなく、生き続けながらも全くもって生きてなどいなかった。
数体のマイアが、マイアの総数を監視する役割にあった。そして新たなマイアを創造し、傷ついたもしくは破壊されたマイアと入れ替える。指示を受け、そういったマイアの一体が数か月に渡って休眠していた。その種のマイアは希少であり、別の一体を作る必要があった。
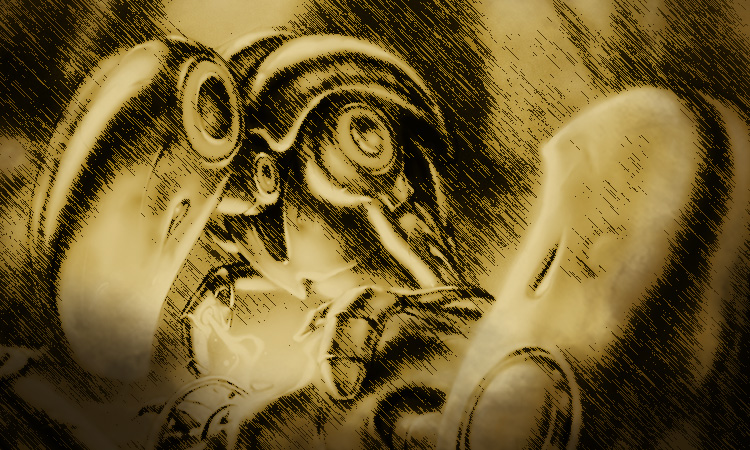
しかしながら、指示をする製作者はなく、どのように製作を進めるべきかの明確な指針もなかった。それは、やるべきだと知っていることを進めた――正しい材料を集め、それらの材料を製作室である球形の小部屋へと運び、自身と完全に同一のマイアを一体組み立てる。
その過程で重要だったのは、主が新たなマイアへと命と心のようなものを与える段階だった。だが主はおらず、それでも、その指示は持続していた。マイアは雛型として自身の心を用いることを決め、自身を複製して新たなマイアを、あらゆる面で自身と同一の存在を創造した。仕事を完了し、そのマイアは部屋を去ろうとして……自身の複製に阻まれた。
そのマイアは複製へと先に行かせようとしたが、その複製も同じ思考を同時に持っていた。二体のマイアは全く等しい時間を待ち、そして再び行こうとして、またも複製に衝突した。マイアと複製はこの不可能な対称性を破ろうとあらゆる手段を試みたが、どれも上手くいかなかった。やがて挫折とともに、二体は互いを破壊した。
少しして、修理役であるまた別のマイアがやって来て、一体を修復した。そして二体目を修復しようとしたが、一体目は全く同じ問題を繰り返す前に修理マイアを止めた。その代わりに一体目は何か違うことを試み、その心を、この時は不完全に複製した。
新たに覚醒したマイアも同様に他のマイアを創造できたが、それらの新たなマイアは、部分的に未成熟の心とともに創造された。彼ら自身を掛け合わせ、修正し、自主的に行動し、そして究極的には今日の彼らのような様々な形態を持つに至った。
マイアはこの物語を創世神話として称えているが、彼らがそれを称える動機は興味深い。今日のマイアという種のうち、実際に最初の存在とされるのはこの物語の中でもどのマイアにあたるのか? それには三つの説がある。創造主からの具体的な命令無しにもう一体を創造した最初のマイアか? 修理マイアは実際には複製されたマイアを先に修理したのではないか、だからこそ二番目のマイアは種の創造とされる決定的な跳躍を成し遂げたのでは? それとも真に最初となるのは、不完全な複製のマイアだったのだろうか? マイアの意見は一致せず、そして彼らはその不一致を称える。事実彼らは根源的な性質に発する不一致を持ちながらも、それでも調和を持ち続けている、マイアであり続けるという存在の核に。
若者の目が閉じられ、彼は数度ゆっくりと深呼吸をした。そして再び開かれたその目は穏やかだった。
「ありがとう、あ、俺は……ごめん、リリアナ……」 彼は叩かれたかのように頭を掻き、そして恥ずかしそうに彼女を見た。「ジェイスといいます。タミヨウさんですよね? 日誌を……」
彼はそれを両手で差し出した。彼女は薄い掌を掲げ、礼儀正しく拒絶を示した。
「これが連れてきてくれました。貴女の計算、研究、月、全て理にかなっています……少なくともそう感じます。俺は狂気に、でも貴女が……治してくれたんですよね。どうやら、俺は錯乱していたみたいです。狂ってるみたいに喋っていたかもしれません。ただ……ありがとうございます」
タミヨウは穏やかに微笑んだ。「私の野帳です。それは信頼できる者に渡したのですが、貴方が持ち歩いている。ジェイスさん、貴方がジェンリクに危害を?」
その人間はかぶりを振った。「いいえ。ですがマルコフ荘園で何が起こったとしても、その方は生き残れなかったでしょう」
彼女はしばし沈黙の中に追想し、だがその表情に悲嘆は残さなかった。「ジェイスさん、ここを離れるべきです。この場所は危険です、特にあなたのような者にとっては。あなたのテレパスの力には責任と負担が伴います。もしあなたが狂気に駆られてしまったなら、次元を越えてもたらされる傷は莫大なものになります。そして私はそれを見過ごすことはできません」
「いいえ。わかっています。ですが……」 ジェイスは唐突に言葉を切った。彼女は自分を脅しているのだ。彼は両手を広げて見せ、一歩後ずさった。
「タミヨウさん、俺は力になりたいだけなんです。俺達はこの地を救えます。俺と、俺の友達とで、ここで起こったことを解明する力になれます、そして元に戻せます。俺達は以前にも……似たようなことをしました」
タミヨウは白い眉を片方ひそめ、黙ったままでいた。
「聞いて下さい。あなたも俺も、アヴァシンこそがここで起こっていることの鍵だとわかっています。そう。彼女には生き物のように心がある。ならば俺は何がアヴァシンをおかしくしているのかを見つけ出せます。そうすれば、彼女を止められます。そしてこの状況を直す次の一歩へ進めます」

タミヨウの笑みが消えた。
「ジェイスさん。あなたは何もわかってらっしゃらない。推測し、理論立てているに過ぎません。証拠はありますが、結論からは程遠い。アヴァシンについて本当のところをどれほどご存じなのですか? 彼女の目的については? アヴァシンが破壊されたなら何が起こるか、見当もつかないのではありませんか? 彼女はこの次元全体を守護しています。一つの次元に縛られる存在がそのように多元宇宙へ干渉できるなど、聞いたことはおありですか? 率直に言いましょう、ジェイスさん。あなたは無知に等しい。そして私はこの世界の問題を正すためにここにいるのではありません。理解し、記録するためです。その真実を知り、記録しておくために。ですがこの次元はおそらく破滅へ向かっており、私にそれを止めようという意図はありません。美しきものを失うのは悲しいことかもしれません。ですが、春の果樹園に咲く花のように、それは一時の美です。無数に存在する次元の一つに過ぎません。長い間に、幾つもの次元が失われ、そして再生してきました。あなたの仮定は不完全です」
ジェイスは殴られたかのようにひるんだ。「ですがこの地の人々はどうなるんですか。何百万という人々が! 彼らの運命を、狂気やもっと悪いものの前にただ放っておくんですか? 俺達にはこうして、力があります。他とは違う力が。あなたには力がある。それを貸して頂けませんか?」
タミヨウの感情は変化せず、だが彼女の声は少しだけ冷たさを帯びた。「ジェイスさん。私は既にあなたを助けました。妥協案があります。私の研究成果を提供しましょう。そしてあなたと御友人方はその情報を用いて他の次元の同じ脅威を防いで下さい、もしそれが好都合でしたら。私は英雄についての物語を万と知っていますが、英雄というものは見方によっては只の災害に過ぎないのです」
その若者は引き下がらなかった。「アヴァシン自身からの決定的な洞察がなければ、貴女の研究は完成しないでしょう。結論は出ないでしょう。俺の力があれば、貴女は完全な物語を手にできます。その過程でアヴァシンを止めることができたなら、貴女の仕事を邪魔することはありませんし、無数の人命を救えます」
タミヨウの声に、わずかな興味が動いた。「アヴァシンの現状を決定的に理解できるなら、間違いなく有用でしょう。ですがあのような異質な心に入ることはあなたにも可能かどうか……」
「可能です」
タミヨウはその人間の尊大さに、魅力と苛立ちを同等に覚えた。「もし試みたなら、彼女の狂気はあなたを貪るでしょう、先程までのように。ですが……理論上は、私が錨になれます。あなたを正気に繋ぎとめます。ですが危険すぎると察したなら、ただちに接続を断って下さい。退却します。また同時に、私達の精神を根源的な階層で繋ぐ必要があります。私はあなたを理解し、あなたは私を理解するでしょう。そして理解することになるものが私にとって不快であったなら、この合意を再度書き換えます。あなたは、あなたの側では、私の能力を正確に知ることになります。それは宜しいでしょうか?」
「大丈夫です」
ジェイスは心の中にチャイムのようなものが鳴るのを感じた。澄み切って、穏やかで、純粋な音。
それは招待だった。
即座に、彼女はジェイスを知った。だがこの人間を知るというのは単純なことではなかった。彼の心は強く、だが壊れていた。千もの破片に砕かれ、それぞれが異なる一人の人物、その多くが一つになろうとしているが、その幾つかは……

彼は自身の記憶を消去していた。自身の真実を破棄していた。無辜の者の心に侵入し、怒りのままに殺し、その力を用いて狭量で自分勝手な終わりをもたらしていた。
それでも。
彼には自己犠牲の精神と、勇敢さと、分別があった。責任を負う意志があった。若すぎる身に、あまりに多くの責任。若いながら、何年もの自身の人生が乱暴に消去されていた。彼の真実への欲求は真摯で、この地の人々の力になろうという誓約は純粋だった。
そして彼は、できると断言したことが可能だと七割がた確信していた。
即座に、彼はタミヨウを知った。だが知ることは理解することではない。ジェイスはずっと神河の空民へと大いに尊敬を抱いていた。その修養を積まれた精神へと。彼はタミヨウの人生を見たが、自身のそれとの対比には肉体的苦痛すら覚えた。自分は何にも繋がれず、だが彼女は家族、伝統、故郷へと安全に繋がれていた。
故郷。天上の雲の中の、果てしない書庫。彼女が何よりも愛する場所。家族の微笑みと優しい安らぎ。子供達。彼らは彼女が独り行く場所について完全には理解していないながらも、持ち帰ってくるその物語に表情を明るく輝かせる。ありえない物語に、彼らが決して見ることのない場所からもたらされた真実の声に。
ジェイスは彼女の重荷を見た。『知る』という凄まじい重荷、声を大にして語るには危険すぎる、とはいえ忘れてしまうには重要すぎる真実を守る必要性。鉄の輪で閉じられた三本の巻物、それぞれに強い力が……
ジェイスさん。
接続が変化し、プレインズウォーカー二人は自分達が立っていた世界へと意識を集中させた。
「ジェイスさん、私の隠蔽呪文が貫かれました。そして強大な存在がこちらへ向かってきています」
人間は頷き、プレインズウォーカー二人は廊下を駆けて大聖堂の中央礼拝堂へ入った。
「アヴァシンと話をしてみます。彼女を攪乱します。必要ならば断固として。私達二人とも殺される前に彼女を止められるほどの余裕はない筈です」
ジェイスは返答しようと口を開いたその瞬間、世界に吼えたける風と砕けたガラスが満ちて響き渡った。
その天使は宙に浮いたまま、巨大な翼は鮮血に汚れ、槍は融けて燃えたぎっていた。その表情は喜びを噛み殺すものだった。タミヨウは浮かび上がり、彼女と目を合わせた。天使の翼は強風を巻き起こし、一方で空民が上がる時には、大気は微かな音を立てることさえなかった。

「アヴァシン。私はあなたの世界への訪問者であり、客人として可能な限り敬意を表してきました。私が求めるのはあなたが守護する者達への平穏と満足だけです。一人の天使として、私の言葉の真実をお聞き下さい。お応え頂けますでしょうか?」
天使の表情が歪んだ。タミヨウが知るあらゆる微笑みの最も貧相な偽物。そして彼女から笑い声らしき音が発せられたが、その唇は動いていなかった。その声は心を虫が這うような、爪でこすられるような、不快な引っかき音だった。
「こた……え? 私は……守る。お前から。侵入者。侵略者。腐敗持ち。不純! 不純!」
「わかりました」 タミヨウは返答し、待機していた巻物を広げた。「悲しいことです」
彼女は巻物の言葉を眺めるだけでよかった。それは哀悼歌、どのような獣よりも冷気と氷が危険な古の世界からの歌。喪失と後悔の歌。彼女は心の底から、その歌の一節一節を知っていた。
冬の咆哮
山の扉をくぐる若者
農園を出て僅かな旅
冬の寒気と雪下の氷が
素早く最期の傷をもたらす。

最愛の美しき妻は
残酷な真実を知らず日を過ごす
山の扉から僅か百尋に
まだ若き愛する者の血が凍りついていることを。
寡婦がそれを察した時
彼女は山の扉から恐怖の吐息を呼び起こし
全き冷気が海から立ち上がる
彼の苦悶の咆哮がただ大きくこだまするのみ。
アヴァシンは翼を大きく羽ばたかせて迫り、タミヨウは宙を滑って天使の燃え盛る槍をかろうじてかわした。大聖堂の軒の中を旋回するアヴァシンへと、タミヨウは正確に狙いをつけて氷の突風を放った。羽根の一部が凍りついて白と赤に砕け、眼下の石の床へと雪のように落ちた。
天使は先程よりも素早く宙を急降下し、その槍が大きな弧を描いた。タミヨウはその攻撃に食いついたように前方へ滑空し、だが素早く後ずさって槍先から離れるように更なる冷気を放った。彼女は天使の右手首を、そして左翼の関節を狙った。背後を通った時には再び、翼の付け根の肩を。アヴァシンの方が素早く、そして彼女の槍のただ一撃で、ほとんど死を意味していた。だがその天使は怒りのままに戦い、そして空民は巧みに計算された正確さで動いていた。アヴァシンの顔には苦痛も失望もなく、だが彼女の機動性は損なわれ始めていた。速度を落とすと同時に、大聖堂は不可解な笑い声にうち震えた。乾いた骨の囁きと千の鼠が引っかく音に。
タミヨウは下で身を隠すジェイスへと急ぎ思考を送った。
彼女は適応しています。長くは持ちません。
アヴァシンは槍を掲げ、一瞬、タミヨウは物語から知るその守護者の姿を認めた。イニストラードの人々の標であったアヴァシンを。眩しい光が彼女から放たれ、大聖堂の隅々までを照らし出し、タミヨウはその力に後ずさった。焼けつくその光はプレインズウォーカー二人を物理的な力のように押し、タミヨウを地面へ下ろし、ジェイスに膝をつかせた。天使はゆっくりと降下し、槍をタミヨウの胸へと向けた。それまでの憤怒は全て消え去り、彼女は死に至る優雅の具現だった。
もう少しです……
そして天使は凍り付いた。光は持続し、だが動きは止まった。彼女は動けないタミヨウからわずか数フィート先に立ち、槍を伸ばし……そこで止まっていた。息はなく、羽ばたき音もなく、完全に静止していた。だが押さえつけるような光が二人を頭上から圧迫し続けていた。
「やりました、タミヨウさん。彼女は、ええと、眠っているとは違うんですが、かなりそれに近い状態です」
「ジェイスさん、あなたは気付かなかったかもしれませんが……」
「大丈夫です。でも聞いて下さい。彼女は天使達の狂気の源です。彼女は天使達と、そして教会とどうにかして同調している。でも……元凶じゃない。何か別のものに影響されている、そして……あなたの言う通りだ! 彼女は今も何かを寸前で留めている。俺には見えない、ですがもしもう少し深く押せば……」
「ジェイスさん、十分です」
「待って下さい。違う。あれは……」
大気に腐肉の悪臭が満ちた。アヴァシンの光は弱まらず、だがその輝かしさは消え去った。その光は冷たく、不快で、油ぎって、無慈悲だった。天使はタミヨウの事は忘れたようにジェイスへと振り向き、圧倒される彼の前へと確固たる目的とともに向かってきた。
「汚すものよ」 その囁き声は炎の中で皮膚を灰と帰す音だった。「盗人よ。堕落の嚢胞よ」 彼女は手を伸ばし、ジェイスの胸に触れた。他にも何かを囁いたが、全て彼の悲鳴に飲み込まれた。

タミヨウは互いの心の接続に集中し、彼に慰めを、死に至る前に苦痛からの安堵を与えようとした。ジェイスの意識の層は剥かれ、天使の掌握に苦しみ悶えて既に感覚を失っていた。だが彼の精神は厚く固く守られ、その苦痛も未だ思考の最深部まで貫いてはいなかった。
タミヨウさん。あの巻物を。鉄の巻物を。見せてくれた、古い物語。強い物語を。失われた世界……セラの聖域の生き残りの。あの大破壊、あの力……あの話が合います。ご存じのはずです、あなたなら、止められる……
彼の苦悶を感じながらも、彼が死にゆくのを感じながらも、次は自分だと知りながらも、タミヨウは僅かも躊躇せずに返答した。
そしてどうするのです? ジェイスさん、彼女は今もこの世界を守っています。その狂気の中にあっても。ジェイスさん、あなたは約束を交わしたことがおありですか? 私はあります。一つ、遠い昔に。それを守ることはただ困難な、そしてただ守るだけではない約束を。時折私達はそのような約束を交わします、絶望的にそれを破りたいと思うような約束を。駄目なのです、ジェイスさん。あの巻物は開かれてはなりません。
失望。憤怒。
ごめんなさい、ジェイスさん。私達の物語も、終わらせなければならない時があるようです。
(Tr. Mayuko Wakatsuki / TSV Yohei Mori)

