アヴァシングル・レディー その2
前回、アヴァシンの帰還における個別のカードやサイクルについての話をしたのだが、Fまでしか行かなかった。そこで、まあ、当然語るべき話はいくらでもある。ゲー。いや、ゲーじゃなくてGだ。それでは始めよう。


このカードは元々は闇の隆盛のためにデザインされたものだ。ホラーの題材を探しているときに、絞首台という話が上がってきたのだ。ホラー世界の絞首台なのだから、怒れる群衆があなたを吊るすものであるのは当然だ。そこでメカニズムを考えたところ、ちょうど良いものが見つかった。3体のクリーチャーを準備して、それらを怒らせるのだ。怒った3体は、クリーチャーを否応なく絞首台に送り――怨みを持った小さな幽霊が生まれることになる。
なぜこれがアヴァシンの帰還に移動したのかははっきりしない。スペースの問題で先送りになったものの、アヴァシンの帰還ではこのすばらしいカードを葬るのは忍びなかったというところだろう。また、人間の団結を物語っているということかもしれない。ホントに自信はないが。私の最大の関心事は、こういったイカしたカードが、そのカードにもっともふさわしいブロックであるイニストラード・ブロックのどこかに入るようにすることだ。

デザイン中に起こることの1つに、セットを貫くテーマを決め始めるということがある。その後でやることと言えば、バリエーションの作成だ。一方は、何をするかが非常によく分かるようになっているカード。その例がこの《連携攻撃》だ。わかるだろうか? 結魂は今回の大メカニズムの1つだ。いろいろなものが組になるのだ。この呪文は明確にそう書いてある。単純に結魂と書いてある以上に、そのテーマを活かすようにすることができる。
《幽体化》は同じような働きをするが、より秘密裏なものだ。組になるクリーチャーというテーマに沿ったものではあるが、結魂とはまったく書いていない。組になっているクリーチャーをブロックできないようにする必要はない。任意のクリーチャー2体を選ぶことができるのだ。では、なぜわざわざ《連携攻撃》のようなカードを作るのだろうか? 可能な限り自由度がある方がいいのではないか?
答えは、第一にこのバリエーションにある。テーマを導入するというのは、プレイヤーの目につくようにするということだ。ベテランのプレイヤーは「なんでプレイヤーにテーマを押しつけるようなことをするんだ」と文句を言うが、その答えは、はっきりと示さなければ気付かないプレイヤーがいるから、なのである。
マジックにはいろいろなプレイヤーがいて、我々はすべてのプレイヤーに必要なカードを提供しなければならない。手取り足取り教えてもらいたいプレイヤーもいれば、そうでないプレイヤーもいる。バリエーションの片方の端は前者を、もう一方の端は後者を相手にしたものなのだ。プレイヤーの層がそうであるように、これはどちらかに寄るという話ではなく、連続的な程度問題なのだ。


さあお立ち会い、2つのテーマが混じり合ったカードだ、が、このカードを取り上げる理由はそれではない。私はアヴァシンの帰還の明滅テーマについては本当に語りたかったので、その代表格としてこのカードに登場してもらったのだ。一歩引いて、明滅とは何なのかについて見ていこう。
前回、ウルザズ・デスティニーの《ちらつき/Flicker》のデザインについて語った。しかし、あれを書いた後、私が一番最初にこの効果をデザインしたのはウルザズ・デスティニーではなく、なんとテンペストのときだったことを思い出した。青のインスタントで、ラテン語で「無地の石版」という意味の〈Tabula Rasa〉というカードだった。このカード名は、人間は空っぽの状態で生まれてきて、教育や訓練を通して何にでもなることができるという説話につながる。青と緑の相違点について知っている諸君のために言うと、これは青側に位置するカードであり、そのため私はこれを青のカードとしてデザインしたのだ(そして、これによってカラー・パイにおいて青がちらつきの2色のうち1つの座を占めることになった)。

《ちらつき/Flicker》がウルザズ・デスティニーで白になったのは、当時私が白の要素を探していたからである。各色に垂直サイクル(単一色のコモン、アンコモン、レアにそれぞれ1枚ずつのカードを有するサイクル)を作ってきて、青には「エンチャントされたら強化されるクリーチャー」というサイクルがすでに存在していた。皮肉なことに、思い返してみればこれは青と言うより白にふさわしい能力だったが。リセットとすべてのものに公正な機会を与えるという理念から言って、白は青以外でちらつきの効果を持ちうる色だったので、私は《ちらつき/Flicker》を白に入れたのだ。
ちらつき効果を作るにあたって、いくつかの決断すべきことがある。
その1:その効果は自分のパーマネントだけに効くのか、誰のパーマネントにでも効くのか。
別の考え方をすれば、「ちらつき系カードは自分のカードを守るためなのか、相手のカードを弱めるためなのか」である。自分のクリーチャーを戦場に戻したいときに自分のクリーチャーをちらつかせたいものだし、相手のクリーチャーをちらつかせるのは、たとえば+1/+1カウンターやオーラがついているなどで、一旦戦場から取り除くのが自分の有利になるときだ。それに、トークンをちらつかせれば殺すこともできる。
相手のパーマネントに打てないようにしたのは、自分のパーマネントに打つのが楽しいからだ。相手のパーマネントに打てなくしたのには理由がないわけではないが、そうしなければ自分を守るより相手を攻撃するのに使うほうが普通だろう。
その2:即座に戻ってくるのか、それともターン終了時に戻ってくるのか。
これによって使い方が違ってくる。即座に戻ってくるなら、攻撃前に事を起こすこともできるのだから、自分のパーマネントに使うほうが巧く働くだろう。ターン終了時に戻ってくるのなら、相手のパーマネントを一時的に追放しておくことができる。ブロック・クリーチャーを除去できるのだ。
その3:カードが戻ってくるのはコントローラーの元か、オーナーの元か。
カードがちらついたとき、それを唱えられたばかりの新しいカードとして扱うか、それとも元あった場所に戻すかという2つのパターンがあり得る。原則として、開発部はこの決定を一貫させたいと思っている。一貫性があれば、プレイヤーはそのメカニズムの働きをある程度予想できるからである。
さて、アヴァシンの帰還の明滅メカニズムでそれぞれどうしたかを見ていこう。
その1: このメカニズムは、戦場に出たときの効果や結魂能力を持つ、善なる者とよく調和するように選ばれた。自分のパーマネントに明滅を使ってもらいたいので、そもそもの選択肢はそれによって決まってくる。このメカニズムを対戦相手にも使えるようにすると、このメカニズムをこのセットに入れた第一の理由が薄れてしまうことになる。
また、結魂のデザインの初期の版では(結魂のデザインの話も近いうちにしよう)、結魂クリーチャーが戦場に出たときにのみ誘発するようになっていた。これはつまり、組になっているクリーチャーをちらつかせると組が解除されるということである。これでは明滅がこのセットの中心的メカニズムの1つである結魂を阻害するものになってしまう。対戦相手のパーマネントに打てなくした理由の1つには、結魂の邪魔をしないようにすることが挙げられる(デベロップ中に、他のクリーチャーが戦場に出たときにも結魂が誘発するようになったので、この問題は根本から否定された)。
その2: 自分のパーマネントだけを対象に取れるようにしたので、即時のちらつきはより魅力的なものになった。これによって、さらなるトリックが可能になったのである。たとえば、結魂クリーチャーをちらつかせれば他のクリーチャーと結魂しなおすこともできる。ちらつきがインスタントであれば、戦闘中にさえ可能なのだ。ちらつきがソーサリーだったとしても、戦闘前に結魂させなおして、新しく組になったクリーチャーが攻撃することもできる(結魂クリーチャーそのものは戦場に出たばかりなので召喚酔いにかかっているため、それでは攻撃できない)。
その3: これが過去との一番の違いだ。アヴァシンの帰還では、明滅したパーマネントは明滅前にコントロールしていたプレイヤーのコントロール下で戦場に戻ってくる。これはデベロップによって決定されたことだ。このデベロップの判断の理由は、おそらく、相手がオーナーであるクリーチャーを自分がコントロールしているとき(クリーチャーを何らかの効果で盗んだ場合などだ)に明滅させたときの処理が間違われやすいからで、この変更によってほとんどのプレイヤーが想像するとおりに働くようになるからだろう。この変更は今後のちらつき系効果にも採用されるに違いない。
ここまで見てきたとおり、ちらつき系効果のようなちょっとしたことにも、水面下では多くのことが支えているのだ。


あるゲームのデザインをこれだけ長きに渡ってやっていると、面白いことに、時代に関係ないものを見始めることができる。プレイヤーやデザイナーの間で瞬き続けている何かに関係して、つねに湧き起こり続けている考え方とは何か。私は、そのメカニズムの背景には心理学的な意味で非常に面白いものがあると言わざるを得ない。そこにある何かが人々を捕えて離さないのだ。
私は、《腐肉化》にそれを感じている。なぜならこのメカニズムはアルファ版の昔から存在しているからだ。
リアニメイトという話ではない。いや、リアニメイトは(年々弱められながらも)ずっと存在するものではあるが、ここで語りたいのはそこではなく、パワーを1だけ弱めるという点だ。これのフレイバーは単純で、ゾンビとして蘇った屍体は完全なものではない、アンデッドであり、生きてはいないということなのだ。従って、脅威さも些少弱まる。《腐肉化》は−1/−0ではなく−1/−1の修整を与えるが、これは今パワーとタフネスの修整を均等にすることでわかりやすくする傾向にあるからである。また、これによって《腐肉化》は小型クリーチャー相手の除去呪文としても働くようになった。
見ての通り、亀の甲より年の功と言うとおり、デザイン歴の長さは一瞬のきらめき以上のものをもたらしてくれる。私は、技術を磨くことは細部を向上させることであり、見落とされがちで重要なことに光を当たることだと強く信じているのだ。
これが、私が《腐肉化》を見て《動く死体》を思い返していた理由である。


ここ数年で大きく伸びたデザイン上の技術は、セットの異なる側面を取り上げ、それを示すデッキを作るメンバーを入れたことだ。こうする理由には、デッキを作ることによってそのテーマが充分に働くかどうかを考察できるようになるということがある。また、狙いと実際の間に差異を感じたなら、その差異を埋めるためのカードをデザインすることもできる。《黄金夜の指揮官》のデザインはまさにそうして行なわれたのだ。
ブライアン・ティンスマン/Brian Tinsman(アヴァシンの帰還のデザイン・リーダー)が、このセットの副テーマを反映したデッキを作るように求めてきたので、私は赤白の人間デッキに志願した。善なるものが勝利するのだから、白と、青赤緑の大半がイニストラードの怪物を一掃するのだ。つまり、青、赤、緑それぞれの善なるものにはそれぞれの個性が必要である。
赤の善なるもののほとんどは人間なので、私は赤と白のシナジーを使って人間・部族カードを入れたデッキを作った。アヴァシンの帰還における善なるものの意味合いの1つに、それらはすべて前向きで、生命を世界に満たすことを使命としているということがあげられる。これを表すために、戦場に出たときの効果をふんだんに盛り込んだ。同様に、クリーチャーが戦場に出たことによってメリットを得られるカード、主にクリーチャーを大量に作ったのだ。
私のデッキは赤白だったので、アグロに寄ることは必須だった。赤と白が共同すれば攻撃に出るものなので、そう組み立てることにした。しかし、実際にデッキを回してみると、まだ不充分だと言うことがわかった。もう少し圧力をかけられなければならない。
《黄金夜の指揮官》が投入されたのは、「他のクリーチャーが1体戦場に出るたび」の誘発型能力を持つクリーチャーを作りたかったからである。攻撃することを是とするクリーチャーが必要で、それは白であるべきだった。《黄金夜の指揮官》は私のデザイン上の望み全てを注ぎ込んだもので、それらをかなえてくれるものだった。
アヴァシンの帰還で赤白をドラフトするなら(個人的に好きなだけで、最強だなどとは言っていない、勘違いしないように――というか、私が好きだから最強だと思うのは私を知らなすぎるだろう)、私はこのカードをピックするだろうね。


メルヴィン度チェックのお時間だ。《墓の入れ替え》を見て、思ったことを言ってくれたまえ。
「お、並行デザイン構造だ」と思った諸君は、メルヴィンだ。
説明しよう。このカードがすることは何なのか? クリーチャー・カードの領域を、墓地と入れ替えるものだ。1つの効果はクリーチャーを墓地に置き、もう1つの効果が墓地からクリーチャー・カードを取り除く。自分の領域変更が有利な方に向いている(墓地から手札に)一方、対戦相手の領域変更は不利な方に向いている(戦場から墓地に)のだ。
さてメルヴィン諸君、このカードの起点はわかるだろうか?
そう、元のデザインは墓地にあるクリーチャー・カードを戦場に戻すもので、完全に対象なものだった。不幸にして、それはあまりにも強すぎるということが分かったため、クリーチャー・カードは戦場ではなく手札に送られることになったのだ。
クリエイティブはこのカードにいいフレイバーを与えたが、このカードのデザインの本質はメルヴィンなのである。


このカードに関して言えば、最大の疑問は、他のあらゆる疑問を蹴散らすものだろう。「なぜこれは7マナではないのか?」 これがなぜ最大の疑問なのか。それは、このカードが芸術学のルールに反するものだからである。
芸術学とは、10年前に私が「Zen and the Art of Cycle Maintenance」という記事(リンク先は英語)の中で触れたものだ。読むのが面倒な諸君のためにまとめるなら、「芸術学とは美の科学である。人々は美を魔力か何かのように思いがちだが、実際は人類の脳がより美しいと感じるものが何なのかは科学的に解明されている」というものだ(もちろんリンク先を読んでもらっても構わない)。
人類の脳が愛するものの1つに、周期性がある。カードの4つの数字が7であれば、カードの7つめの数字も7であって欲しいと強く望むものなのである(実際、7つの数字が全部7であったとしたら、それは特に意識していない人を惑わすことができるだろう)。
《グリセルブランド》は7マナとしてデザインされたと思う。私がデザインしたのであれば、コストは7にしていただろうからだ。デザインされたものと印刷されたものは非常に近いと思う。ブライアンのデベロップ向けのメモに「いじるな」と書かれているほどだ。このカードは我々の内部でのレア評価ナンバーワンだったので、デイブ・ハンフリー/Dave Humpherys(このセットのデベロップ・リーダー)はそのままに残したのだ。
デイブに、このカードのコストを7にすることについて考えたかと尋ねたところ、その問題は生じたがデベロップ・チームが8マナでさえ強いと同意したので、8マナのままにしたと答えた。
もう1つ小ネタを。デベロップのメモを確認している間に、私の残したメモが見つかった。その中に、(デザイン中のもので)「コストは7にすべき」というものがあった。

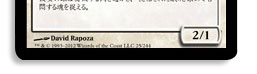
イニストラードと闇の隆盛のデザインにおける大きな部分に、デザインをトップダウンで行なうための部品探しがあった。イニストラードで出てきたアイデアの中に、アンデッドを退散させる僧侶というものがあった。ターン・アンデッドのあるゲームをやったことがない諸君のために言うと、このアイデアは、僧侶は信仰に基づく魔法を使い、ゾンビなどのアンデッドを破壊するものだということから来ている。
イニストラードでそのテーマのカードをデザインしたが、場所がなくてお蔵入りになった。このアイデアを闇の隆盛でも使おうとしたが、人類が逃げ惑うという世界観ではゾンビを追い散らす僧侶というのはふさわしくない。幸いにして、アヴァシンの帰還はこのカードを入れるのに最適な場所だった。人類が怪物のケツを蹴り上げるのだから。
最終的に、我々はこのカードをゾンビ以外にも効くように仕上げた(ゾンビにだけ効くようにすると、ゾンビ・デッキ相手のサイドボードにしかならない。アヴァシンの帰還のリミテッドにはそんなデッキはまず存在しないだろう)が、ゾンビを相手にしたときにこそ真価を発揮できるようにしたのだった。

イニストラードと闇の隆盛は、どちらも部族の副テーマを強く持っていた。我々はアヴァシンの帰還にも何らかの部族要素が必要だと考えたが、問題は5つ中4つの部族が怪物であり、このセットではやられ役だということだった。つまり、必要なのは支配的なクリーチャー1つ――人間に関連したカードだということになる。
そのために、闇の隆盛では人間という部族をさらに弱め、アヴァシンの帰還で復権できるようにした。これにさらに付け加えるために、我々は今まで人間が配置されていなかった色にも人間を散らすことにした。白(とアーティファクト)はもちろんイニストラードの人間・部族の王である。黒は悪なるものの巣なので、わずかな悪人以外は存在しない。
緑は結魂があり、イニストラードでは人間も存在していたので、今回人間を入れるのは第一に赤、そして青にすることに決めた。これによって、赤を白とともに使う動機もできた。人間・部族のデッキは色によって方向性が変わるようになった。赤は攻撃的で、青は防御的に振り分けられたのだ。


デザイン時のプレイテストで赤白の人間デッキを使ったとき、必要だと感じて最初に作ったカードがこれだ。最初、このカードは+2/+0を与えるもので、とても強力だった(デベロップ中に弱体化させられることになった)。これで、赤白デッキは多くの小型クリーチャー、多くの人間が協力して対戦相手をなぎ倒すデッキになると思ったものだ。私はその「我々は団結するぞー!」というイメージが大好きだった。それこそが、善なるものに求められているものだからだ。
- オー、ケイ
さて、Gからはじめた今回の記事は、なんとかKまでたどり着いた。次の「その3」ではもうちょっとペースを上げよう。諸君がこのアヴァシンの帰還ツアーを楽しんでくれたなら幸いである。いつもの通り、ツイッターやTumblr、Google+を使ってのフィードバックを楽しみにしている。
それではまた次回、アルファベットの残り半分の話をする時にお会いしよう。
その日まで、諸君の一つの話題に無数の話がありますように。
(Tr. YONEMURA "Pao" Kaoru)




