最初のプロツアーに関する口伝
1996年の早い時期、マジック:ザ・ギャザリングができてまだ3年しか経っていなかったころに、組織化プレイはよちよち歩きを始めた。数回の世界選手権、アメリカ国内選手権、パワーナインや『レジェンド』のフルセットを懸けた地元のイベントなどが散在していた。『ホームランド』が発売されたばかりで、タイプ2と呼ばれる新しいフォーマットが、《Ancestral Recall》を《Fork》して各種のモックスを食べた巨大《エイトグ》に《Berserk》をかけるようなフォーマットを後方から追いかけていた。
世界全体の姿を知らなくても、私たちは楽しんでいた。デュエリスト誌に、「マジック:ザ・ギャザリング ブラック・ロータス・プロツアー/Magic: the Gathering Black Lotus Pro Tour」と名乗る何かの広告が掲載されるまでは。そのイベントは、それまで誰も手にしたことのない高額賞金を懸けた、プロ・イベントと銘打たれていた。
そのイベントが開催されたのは、今から20年前の2月のことだ。そして、それが今あるトーナメント・マジックのあり方に深い影響をもたらしている。今日、ウィザーズ・オブ・ザ・コーストは。グランプリやプロツアー、プロ・プレイヤーズ・クラブを通して毎年何百万ドルという賞金をマジック最高のプレイヤーたちに支払っている。しかし、当時は、優勝賞金12,000ドルのイベントは空前の規模だった。私は、口伝を残すため、そのイベントに参加していた人たちにインタビューをおこなった。
当時のことを語ってくれたのは、この人たちだ。
- リチャード・ガーフィールド/Richard Garfield - マジック:ザ・ギャザリングの発明者
- スカッフ・エイリアス/Skaff Elias - マジックの最初のプレイテスターの1人にして最初のマジックのブランド・マネージャー。彼がマジックを知的スポーツへと推し進めた。
- マーク・ローズウォーター/Mark Rosewater - 現在のマジック主席デザイナー。このプロツアーでの自身の役割について、ポッドキャストでも語っている(その1、その2:英語)。
- エレイン・チェイス/Elaine Chase - 現在のマジックのグローバル・ブランド戦略とマーケティングに関する上席ディレクター。ウィザーズで長いキャリアを持つ彼女もまだ入社前で、このプロツアーの参加者だった。
- チャーリー・カティノ/Charlie Catino - スカッフ同様、マジックの最初のプレイテスターの1人。開発部ディレクターとして、彼は過去15年間『デュエル・マスターズ』の責任者を務めていた。
- ジョン・フィンケル/Jon Finkel - プロツアー殿堂顕彰者で、プロツアーの20年を通して最高レベルのプレイヤー。
- グラハム・タトマー/Graham Tatomer - 第1回プロツアーのジュニア部門優勝者。現在はサンタバーバラでワイン醸造業を営む。
- マイケル・ロコント/Michael Loconto - 第1回プロツアーの決勝でバートランド・レストレイ/Bertland Lestreeを破った初代プロツアー王者。現在はウースターでソーシャルワーカーをしている。
ブラック・ロータス・プロツアー前
スカッフ
俺がマジックに関わるようになったのは、完全に運だった。リチャード・ガーフィールドはペンシルベニアの数学科の同窓生だったんだ。あいつは俺たちをいつもゲームに誘って、そんなゲームの中にあいつがウィザーズで手がけた「マジック」というものがあったのさ。俺は3番目にそれを手にした人物だと思う。それから、ずっとそれをプレイし続けてるのさ。
グラハム
サンタバーバラは、マジックが世に出たときのマジックの人気スポットだったんですよ。『アルファ版』、『ベータ版』では、普通じゃない量のプレイヤーがいて、カードも大量にありました。私は、自分で自分のデッキを作り、様々な道筋を選べる、ということに本当に惚れ込んでいました。それに、私の好きな競技性もありました。私が惚れ込んだのは、15か16のときで、『アンリミテッド版』の発売前後でしたね。高校卒業間近で、暇でやることがないと感じていました。デッキを作ったり、地元の大会でお互いにプレイしたりする時間はいくらでもありました。
エレイン
第1回プロツアー以前から、私はニューヨークでいくつもの競技マジックに参加していたわ。グレイ・マター・コンベンション/Gray Matter Conventionsはときどき1000ドルのイベントをやっていて、私はそれに参加していたの。ニューヨーク・シティ、ニュージャージー、ニューヨーク州北部のあらゆるコミュニティに顔を出していたのよ。当時、マジックは私の人生の大部分で、週のうち何日かは複数の場所でプレイしていたわ。
チャーリー
僕はリチャード・ガーフィールドのゲームの最初のプレイテスターの1人だった。言ってみれば他の誰よりも早くマジックをプレイしていたんだ。僕は経験豊富で、後のプレイヤーがそうなったように、もちろん僕もマジックに出会った瞬間にその素晴らしさに気付き、そしてプレイして楽しさを知ったのさ。僕はマジックに恋してしまって、信じられないぐらい深く飛び込んでいったわけ。
マイケル
僕たちはマサチューセッツ州のハドソンにある「SMK Collectibles」でプレイしていた。マジックを始めるとき、品不足だった『アンティキティ』のブースターを買ったことを覚えてるよ。誰でも、ショップに走ってパックがあることを祈った思い出はあるんじゃないかな。残念ながら『アンリミテッド版』じゃなかったけどね。僕たちはその店で何度も大会を開いたんだ。ジム・レミア/Jim Lemireと僕がジャッジを務めた。当時、中心はニューヨーク以外ならマサチューセッツ州のハドソンだったんだ。
マーク
私がウィザーズ・オブ・ザ・コーストで職を得たのは1995年の10月だった。それからすぐ、スカッフ・エイリアスがプロツアーの準備をしていることを知ったんだ。それまでにもウィザーズでフリーランスの仕事をしていたので、私はイベントでプレイすることはできなかった。何かできることはないかとスカッフに聞いたら、彼は私を開発部との連絡役につけてくれたのさ。
ジョン
マジックが世に出たとき、俺はイングランドに住んでいて、15歳か16歳だった。ある日、俺は「Fun and Games」という地元のゲームショップに行ったんだ。そこでは人々が『ダンジョンズ・アンド・ドラゴンズ』なんかのゲームに興じていたんだけど、その日は彼らが初めてマジックをプレイする日で、それが面白そうに見えたのさ。それが何なのか質問した俺は、すぐにそれの虜になったのさ。その後、95年の夏にアメリカのニュージャージーに戻って、ゲームショップ通いと地元のイベントでのプレイを始めたんだ。俺は――17歳の少年がみんなそうであるように――強いと思い込んだね。まあ、土地をたくさん出すべきだと知りもしなかったんだけど。
リチャード
マジックは大成功を収めていたけれど、まだ安定した状態とは言えなかった。私は、マジックを真剣にやるようにすればあらゆるレベルでうまく行くようになると強く確信していた。私の脳内にあった例は、バスケットボールだ。NBAが存在するからといって、全てのゲームが超真剣勝負というわけではないし、NBA選手以外がバスケットボールから追い出されるわけでもないのだ。

プロツアーの誕生
スカッフ
俺は当時開発部にいて、どこかの時点でマジックにはブランド・マネージャーが必要だった。だから俺がマジックのブランドとビジネスのマネージャーになったんだ。プロツアーが始まる少し前のことだった。ブランドやマーケティングの計画の中に、マジックを知的スポーツにするというものがあった。マジックの長期的な健全性のために、本当に重要だと感じていたんだ。
リチャード
『アイスエイジ』を発売した直後、セットを分析している投稿があって、このセットには2枚しかいいカードはないと言われていた。何年もかけてこのセットに取り組んできた人たちにとっては、それは信じがたいほどの酷評だった。一言で言うと「これは話にならない」と言われたに等しかった。結局のところ、人々の目を引いたのが2枚だけだったのは、人々が使いたかったのはなじみの強力なカードだったからだ。私たちがただカードを売るだけなら、すぐにカードの種が尽きてしまう。しかし、環境を売ることにすれば、必要に応じて新しい環境を作っていくことができる。プロツアー前夜のマジックはそんな状況だった。
マーク
スカッフと私は、プロツアーというイベントを離陸させるために協力し合っていた。当時は何も参考にできるモデルケースがなかった。未踏の荒野を進むようなものだ。どのイベントを見ても、まったく違う運営がされていたんだ。
スカッフ
お手本に出来る重要な例は、ゴルフとテニスだった。様々なスポーツ・マーケティング会社のいろいろな人に聞き、高額賞金のイベントを開催してかなりの賞金を支払うことで、最上位のプレイヤーの中からスターを作るという方針を決めた。第1回プロツアーからそうならなかったとしても、その方向への第一歩だったわけだ。
マーク
我々はプロツアーに名前をつけようと考え、最初のアイデアの1つが「ブラック・ロータス・プロツアー」だった。それを告知する葉書を送ったが、後に一部の海外市場では蓮はあまり良くない暗示に使われるということがわかった。例えばアジアでは、蓮は薬物密売の目印として使われている。我々は内部で単に「マジック:ザ・ギャザリング・プロツアー」と呼ぶようになり、やがてそれが定着していったのだ。
リチャード
重要なのは、デザイン上多くの問題があったということだ。当時、イベントのあり方をデザインする中で――賞金を受け取るにはあまりにも長い時間プレイしなければならない、とか――これは苦行だったが、それ以上に難しかったのは会議に参加している企業を政治的に同意させることだった。会社の援助や統一した展望がなければ、プロツアーは成立しなかった。
当時の経営会議で、プレイヤーの望むものが何か知る方法について話し合っていた時のことを覚えている。私はプレイヤーを雇うことを提案したが、会議の参加者のほとんどには笑われたのだ。つまり、商品を買う人たちへの敬意がまったくなかったのだ。この政治的問題は解決しなければならなかった。私にとっては、これが最も喫緊の難関だった。
電話回線が開かれた
マーク
我々は史上初のランキングを作り、強いプレイヤーだと思う全員を招待した。上位25人だったか上位50人だったか、そんな感じだった。それでは人数が足りなくて、イベントの枠を埋めなければならなかったが他に強いプレイヤーを選ぶ手段がなかった。そこで、第1回プロツアーに参加する方法は、電話での立候補になったんだ。
グラハム
確か、予選もなく、電話での先着順でした。記憶が正しければ、ほんの数時間で埋まったと思います。ジュニア部門も同じでしたが、こっちは埋まりませんでした。うちの親がサム・ビーヴァー/Sam Beaverに電話をかけて、「もしうちの子をニューヨークに送ったら、その何とか言うのに優勝できますか?」と効いたんです。彼は、充分可能性があると答えてくれて、それで両親は「じゃあ送ります」と言ったんです。この第1回プロツアーは特殊で、それ以降は予選を通過することが必要になりました。
スカッフ
当時、何もかもが適当で、プレイヤーへの連絡網もなかった。第1回プロツアーで、何もかもを始めるのは本当に難しかった。強いプレイヤーの大半の連絡先も知らなかったんだ。枠は決まっていて、立候補で集めることになった。できるだけの連絡はしたんだが、最終的には立候補枠ができてしまったんだ。
エレイン
先着順だったんだけど、私はコンサートのチケットをよくチケットマスターで取っていたから、電話をかけるのが得意だったの。話し中だったらすぐにリダイヤルするのよ。リダイヤルボタンを何度も何度も押して、ようやく繋がったわ。私と、私のフィアンセ(今は夫)の両方が参加したかったんだけど、電話口でそう言ったら、一回電話を切ってもう一度かけ直してくれって言うのよ。運良く、もう1回繋いで参加できたけど。会場はニューヨークシティで、私はニューヨーク州に住んでいたの。これで行かないわけないでしょ。参加できることには本当に興奮したわね。
マーク
マーク・チャリス/Mark Chaliceのように、心から参加したいと思っていたのに繋がらないと言っていた友人のことを思い出す。私に連絡してきたが、ただ何回もかけ直すように答えただけだったな。
マイケル
僕の友達みんなで電話をかけたのを覚えてるよ。僕は1回繋がったけど、向こう側で電話が切れちゃったんだ。それ以降はずっと話し中だった。でも、運良くもう1回繋がったんだ。あとはご存じの通り。第1回は素晴らしいものだったよ。

デッキ構築の新スタンダード
当時、今は「ヴィンテージ」と呼ばれているものを用いたイベントが非常に一般的ではあったが、この第1回プロツアーのフォーマットは調整スタンダード、あるいは当時の呼び名で呼べば「タイプ2」だった。このイベントでは、プレイヤーはそのフォーマットで使用可能な各セット、つまり『第4版』『クロニクル』『アイスエイジ』『フォールンエンパイア』『ホームランド』からそれぞれ少なくとも5枚のカードをデッキに入れて構築することになっていた。
マーク
このプロツアーで重要なのは、これがマーケティングの手段だということだ。憧れの的にしたかったが、同時に最新セットがどのようなものかにも焦点を当てなければならないのだ。今はプロツアーは最新セットの名前で呼ばれている。問題は、第1回プロツアーの時点での最新セットは、『ホームランド』だったのだ……。
エレイン
セットが何々だったかも覚えていないけど、『ホームランド』が入っていたのは覚えてるわ。ホントに苦痛だったの。つまり、『ホームランド』の中から一体どのカードを入れればいいのかってこと。『ホームランド』のカードを入れてデッキを組むのか、それともサイドボードに埋めておくのか。《Autumn Willow》がこのイベントで目立ったのはそのせいよ。私は白ウィニーを組んで、サイドボードに《Aysen Highway》を入れたわ。これは必殺技だったの。他の白ウィニーと当たったら、これを投入して一気に決めるのよ。言ってみれば、まだウィザーズで働くようになる前に「ぷれいんずうぉーかー」を作ろうとしてたのね。
スカッフ
当時考えていたのは、デッキ構築について再考させることだった。デッキを構築し、チームや個人が普通でないことを考えるようにしたかった。これはタイプ2と非常によく似ていたので、さらに技術が必要とされるひねりを加えることでタイプ2を盛り上げたかったのさ。
ジョン
まだ『アライアンス』は出ていなかったはずだ。俺は《Thawing Glaciers》を目にした瞬間に史上最高のカードだと思ったから、絶対使ってるはずだからな。『ホームランド』と『フォールンエンパイア』は本当に難しかった。『フォールンエンパイア』には《Hymn to Tourach》や《Order of the Ebon Hand》、《Order of Leitbur》があった。俺は結局青白《石臼》デッキを使ったんだが、《セラの天使》《またたくスピリット》《Order of Leitbur》2枚を使ったんだ。『ホームランド』からは《鋸刃の矢》と――あとは最低の3色土地があったかな。
チャーリー
僕たちは多様性を推奨し、全てのセットが現れるようにしたかった。環境を面白くて少し違うものにしたかった。プレイヤーがどれかのセットを悪いものだと思うようなことはないようにしたかったんだ。
マイケル
『ホームランド』のカードを入れようとしたことが印象に残ってる。難しかったよ。今振り返ってみると、なぜ皆が僕のデッキを詮索したのかわかるね。当時は、誰もそれが何なのかわかっていなかったんだ。60枚のカードは知っていても、違うものだった。僕は100枚デッキで競技マジックに参加する子供を知っていたんだ。《Hallowed Ground》はそれほど好きじゃないけど入れていたよ。必要だったからね。
マーク
この話を私から聞いたことがある人は知っての通り、『ホームランド』はあらゆる意味で史上最弱のセットだった。デザイン的に特に秀でているわけでもなければ、デベロップ的に特に強力なセットでもなかった。「え?」と言いたくなるセットだったのだ。しかし、『ホームランド』は新製品だったので、そこに注目を集めたかったのだ。我々は『ホームランド』のカードをプレイさせたかったのだ。《鋸刃の矢》がそこかしこにある、だけでない形でプレイさせるにはどうしたらいいかを考え、我々はタイプ2で適正な各セットから5枚のカードを使ってプレイするというフォーマットに行き着いたのだった。
上の階/下の階
初期のプロツアーは、シニアとジュニアの2つの部門に分かれていた。ジュニア部門は、シニア部門が行われていた同じ建物の、別の階で行われた。シニア部門の決勝ラウンドはトップ16人だったが、ジュニア部門はトップ8だった。また、ジュニア部門の賞金は全て大学奨学金の形で支払われていた。
スカッフ
今聞くとおかしなことに思えるだろうが、当時はイベントに賞金を出すことはかなりの論争を呼んだ。他のいろいろな賞品はあったけれど、直接賞金として現金を出すというのは滅多にないことだったんだ。ジュニア部門に賞金を出すと保護者に悪印象を与える可能性があったので、俺たちはそれを避けるために第1回プロツアーのジュニア部門には現金でなく奨学金の形で賞金を出したんだ。ジュニア部門はそれ以降もずっと奨学金だった。マーケティングとして、子供には正しく進んでほしかった。大学に行ってほしかったんだ。
グラハム
私は、ワイン産業で働きたくて経験も積んでいましたので、大学には行かないところでした。1万2千ドルの奨学金のおかげで、ほとんどの授業料と教科書類をまかなえるようになったので、私はサンタ・バーバラの地域短期大学に進学し、その後UCSB(カリフォルニア大学サンタ・バーバラ校)に進みました。予想もしていないことでした。本当にすばらしかったです。
リチャード
そいつはクールだ!
スカッフ
正直、それは嬉しい話だ。それが俺たちの望んでいたそのものだ。オタクな俺たちから見て、反射神経と筋肉に優れた奴らが奨学金を手に入れるのは嬉しくなかった。奨学金と言えばスポーツばっかりだった。俺たちは、それこそ、バスケや野球に打ち込むのと同じように、趣味や知的スポーツに打ち込めるようにしたかった。知的な趣味にもっと敬意を払ってもらえるようにしたかったんだ。
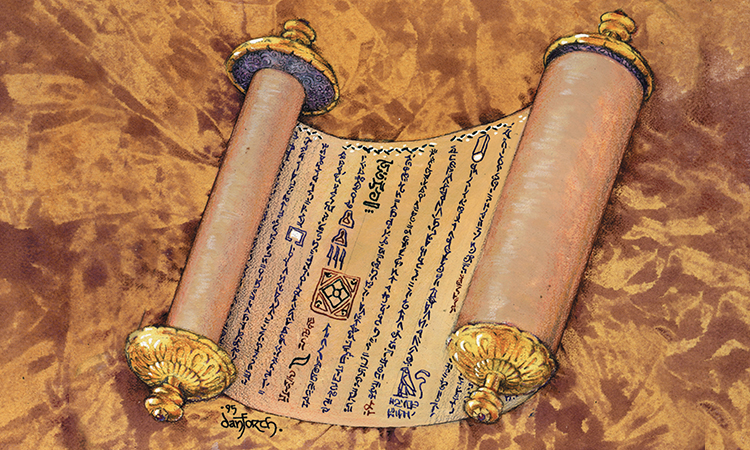
準備完了
グラハム
一般的に言って、強力なカードを選ぶのはそう難しくありません。まったく青を使わないというのは一般的ではありませんが、私が採用したデッキ、《ネクロポーテンス》はほとんど青が入っていませんでした。このデッキの起こりにはある人物――名前は知りません、私たちは彼のことを「フランス人/Frenchy」とだけ呼んでいました――と、デッキビルダーとしての彼にジョエル・アンガー/Joel Ungerが寄せていた絶大な敬意が関わっています。彼は、初めて《ネクロポーテンス》を採用した人物でした。私は、フランス人からこのデッキを受け取ったばかりのジョエルからこのデッキを受け取り、地元のイベントで試したんです。
マイケル
当時、《ネクロポーテンス》デッキなんてどこにもなかった。そんな状況に準備もしていなかったよ――幸いにも何戦かはしのぐことができた。最初のプロツアーの後では、突然そこら中に《ネクロポーテンス》デッキが湧いたけどね。
ジョン
俺はただマジックをプレイしてたな。よく行っていた店がいくつかあって、ノース・プレインフィールドのヒーローズ・アウトポスト/Hero's Outpostが通ってた一番地元の店だった。強いプレイヤーが集まるリンデンのアウター・レルム/Outer Realmsにも行っていた。そこには、第1回プロツアーで活躍したエリック・フィリップ/Eric Phillipps、デビッド・バックマン/David Backman、アンディ・ロンゴ/Andy Longo、アーロン・クライン/Aaron Klineが集まっていたんだ。
エレイン
(私の夫の)キーリン/Kierinがプレイテストのパートナーだったの。グレイ・マターのイベントに行くときと同じように、ほとんどずっと2人でいろいろなデッキを組み、そしてお互いに対戦していたわ。今みたいな大規模なプレイテスト環境はなかったの。「デッキにおかしな制限のかかるイベントがあるらしいけど、どんなデッキが組めるかやってみない?」みたいな感じよ。
スカッフ
この第1回プロツアーは狂気だった。イベントをやって、話題にもならずにそれで終わり、とはしたくないものだ。マジック/コミュニティ全体に興奮を届けたかったのだ。まず最初に価値を活かすための戦略ありきだった。広報するつもりだったので、見た目も良くしたかった。予算には限界があったが、いい場所を取りたかった。マジック・コミュニティの中心であるニューヨークにしたかった。予算は潤沢ではなかったが、本当に見栄え良くできたのだ。出来たばかりのどこのものともわからないゲーム会社が、驚くほどの見栄えにできたのだ。贔屓目かもしれないが、本当に印象的だったのだ。
ジョン
この第1回プロツアーはすごい注目を集めたメディアイベントのようだった。今のプロツアーはオンラインで観戦するようになっているけれど、当時は大規模なお祭りのようなイベントだった。収容人数は多くなかったけれど、会場は綺麗だったよ。
スカッフ
会場に来たプレイヤーに、立派なイベントだと感じてもらいたかった。「すげえ! こいつはクールだ、マジで」と言わせたかったんだ。そのプレイヤーたちはイベントの後で友人に話すだろうからね。これが、マジックのプロツアー・コミュニティの種だった。彼らに、俺たちが活発に続けていくという確信を持ってもらいたかったんだ。
エレイン
第1回プロツアーの面白い話といえば、私は第2回があるなんて思わなかったってことね。ウィザーズはニューヨークで、「ザ・ギャザリング1/The Gathering 1」という名前の大規模な『アイスエイジ』のプレリリースと『ホームランド』のイベントを開催していて、「ザ・ギャザリング2」は開催されなかったの。いろいろなイベントとして、毎回違うことをやっていた感じ。当時の私の感想を言うと、これは新しい今月のマーケティングで、これからも新しいことを試して、また違うことをするんだろうな、と思ったわ。
チャーリー
当時の僕らの考え方を伝えるのは難しいな。マジックへの情熱はすごかったし、アイデアはいくらでもあった。でも、経験はなかった。周りのことすべてからあらゆることを経験し、向上しようとしていたけれど、初めてのことに挑戦するから今では考えられないようなこともたくさんやった。重要なのは、そこから学ぶことなんだ。初期のジャッジ・プログラムを立ち上げやイベント環境の構築に関して、このイベントに向けての決定が元になってるんだ。
スカッフ
登録は難しくは思えないだろうけれど、考えたこともなかったなら大失敗することになる。登録、様々な計算、ラウンド数の計算、イベントの構造。俺たちは既存のあらゆるイベント形式を研究したんだ。それ以前のカジュアル時代は、何も問題にならなかった。でも、金が賭かるとなったら話は別だ。システムのあらゆる可能性を調べて抜け穴が探されることになる。俺たちは、どうやって不正に操作するかを考えなければならなかった。システムの抜け穴を見つけて賞金を手に入れるためにはどうしたかいいかだ。それ以降のイベントは、それ以前のイベントとはまったく違うものになったんだ。
マーク
最初にマジックができたとき、リチャード・ガーフィールドの展望していたのは発見だった。リチャードは、情報を開示せずにマジックのカードを自力で見つけてほしいと思っていた。最初の1年か1年半ぐらいは、何がデッキに入っているか完全に内緒だったのだ。私は1995年に世界選手権を取材しているが、デッキのリストを作ることは許されなかった。私は1つ1つのプレイを記し、手札にどのカードがあるかを書いたが、デッキ全体は伝えなかった。このイベントでは、我々はそれらを伝えただけでなく、記念品としてのデッキのコピーを販売し、プレイできるようにした。それは、それまでのマジックとは全く違うアプローチだったのだ。
リチャード
そのプロツアーを開催するより前に、その考えについては完全に見切りをつけていたよ。それがマジックの重要な部分だったのは1年かそれぐらいだと思うし、雑誌やオンラインで人々が自力で調査した不完全なリストが公開されたときにかなりの満足感を覚えたんだ。私の記憶が定かなら、1年ぐらいで、こうして見つけさせるというアイデアは実現不可能で、正解が求められているということがわかった。そこで、私は自分の過去の構想に見切りをつけたんだ。
最初に私が想定していたマジックの遊び方は、デッキを1つ買って、それで楽しんで、それからまた別のデッキを買い、その後でそれらのデッキを組み合わせるというものだった。4~5デッキ以上も買うなんて想像していなかった。グループの各人が4~5デッキだけ買うとしたら、そこには発見の余地がある。8人ぐらいのプレイグループではすべてのカードを見ることはできないし、そもそも存在しないだろう。しかし非常に早いうちに、これが実態と異なるということが非常に明らかになった。私はその現実を受け入れたんだ。
ジョン
今の、誰もがすべてをいつでも知っているのとは違うな。
スカッフ
スポーツ・マーケティングの人たちは、全部シングル・エリミネーションにしないのは気違い沙汰だと言ってきた。でも俺たちは2つの理由からスイス式を採用することにした。1つ目が、そのほうが技術を示せるということ。プレイの量が多くなる。大雪の中を6時間運転して、1回戦で負けて帰る、というのは誰も望まないだろう。そこで、俺たちはスイス式を採用したんだが、シングル・エリミネーションが必要だという強い圧力もあった。シングル・エリミネーションはわかりやすいんだ。非常に明瞭で、どのゲームもエキサイティングで、先がわからないハラハラ感もある。この2つを組み合わせたかった――ので、組み合わせたんだ。俺たちはこのフォーマットのことを誇りに思っている。そして、これはマジックの標準になったし、今はほかのそこかしこでも見かけられる。
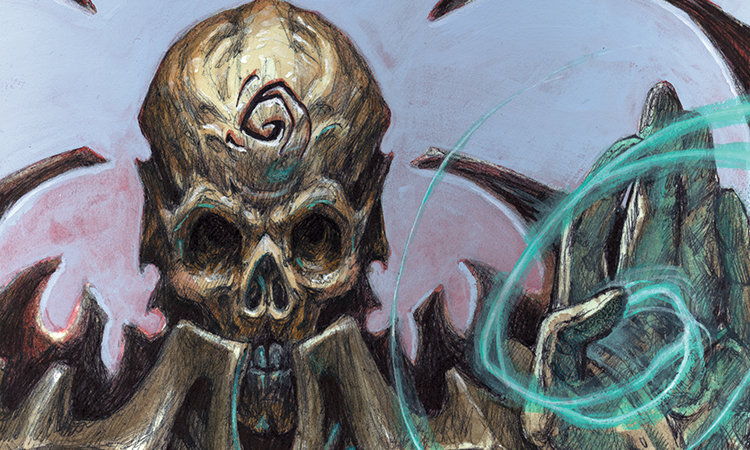
《冠雪の島》
真冬のニューヨーク・シティで大規模なマーケティング・イベントを開催するのはいい考えとは言えない。
マーク
スカッフは、開催地はニューヨーク・シティでなければならないと決めていた。また、プロツアーの開始は2月にしたいと熱望していた。しかし、その両方を満たした2月のニューヨーク・シティでは雪が降るということは考えていなかったようだ。
ジョン
96年は、雪どころか吹雪だった――96年の吹雪のことを忘れられはしない。当時俺はホランド・トンネルのすぐそばに住んでいたので、たぶん車で行ったんだと思う。俺の車は古い三菱ミラージュのハッチバックで、冬のドライブにはどう考えても不向きだった。俺はこの車でそこら中のプロツアー予選や1000ドル・トーナメントに行っていて、まあ事故の確率は2割ぐらいあっただろうけど、なぜか俺はいつもうまくいっていた。ほとんど問題はなかったさ。
エレイン
すでに2回の大吹雪があって、ニューヨークに60センチの雪が積もっていたの。プロツアーが開催されて、3回目の吹雪でさらに25センチの雪が積もったわ。ニューヨーク・シティに行けなくなりそうだったし、車は滑るわ滑るわで大変だった。なんとかたどり着いたけれど、マンハッタンはどこも閉まってた。車もなくて人もいないマンハッタンの写真を撮ろうとしたのが一番おかしなことだったでしょうね。
リチャード
私はマーチン・ルーサー・キング・ジュニア記念日に開催されていたMITのパズル・ハントによく通っていた。その日のことは「一年で一番寒い日」と呼んでいたんだ。ひどい気候の日に大勢を一カ所に集め、屋内でゲームをするという経験はそれまでも何度もあり、ある意味ではどうなるかわかっていたと言える。
マイケル
ひっどい天気だったよ! 正直おびえてた。ジム・アレン/Jim Allenと僕はバンか何かを借りたんだ。ジムが運転して、僕はその横に乗っていた。他の皆は寝てたか気絶してたかで、僕はその中の1人を必死で起こしてた。「死にたくねえよ」ってね。
グラハム
私は南カリフォルニア出身で、ニューヨークは雪に覆われていました。ニューヨーク・シティに行くのが初めての私は、高いビルが雪に覆われているのを見て興奮していました。私はただ流れに任せていたのです。覚えているのは、とにかく寒かったことだけです。
チャーリー
僕がそのことを覚えているのは、冬服を準備していなかったからだ。あまり考えていなかったんだ。ある夜、同じく冬服を持っていなくて薄着だったスカッフ・エイリアスと一緒に、トーナメント会場からホテルに歩いて戻ったことを思い出すよ。雪は狂わんばかりに降ってきてるのに、僕たちはジャケットも着ず、テニスシューズを履いていたんだ。
スカッフ
俺が薄着でパック・ビルディング/Pack Buildingの屋上にいたのは、問題解決のためだった。梱包用ワイヤーで看板や横断幕をつるそうとしていたんだ。控えめに言って大惨事だった。そんな事態について事前に相談していたが、いくつもの理由から会場はニューヨークでなければならなかった。まず第一に、海外からも招待したいと考えていたので、海外からの移動が簡単であること。そしてニューヨークのマジック・コミュニティは非常に強く、多くの人々が車で訪れることができること。第1回プロツアーの舞台にはこれしかないほどふさわしかったんだ。
マイケル
ジム・アレンの運転はひどかった。地獄から舞い出たコウモリのようだった。雪の中で風除け頼りに進むミレニアムファルコン号のようで、僕はいつ道を外れるか本気で心配してた。ジムは狂ったように笑ってた。気が狂ったのか、それとも僕をからかってたのか、今でもわからないよ。
マーク
私は、1日で50センチほども積もらないと雪の日だと言わないような豪雪地帯で育った。ビデオ撮影にあたって、私は建物の外で導入部を撮ろうと考えた。風が強くて雪も降っていたので、8回挑戦して諦めることになった。雪が強かったので、初日の開始は遅れた。9時か10時に始める予定だったのが、午後まで延期することになったのだ。
スカッフ
わからないだろうが……いったんボスの承認を受けたら、次の機会を与えられるためにも完遂しなければならない。選択肢などなかったのだ。天候が問題になり得ることはわかっていて、それによって調整はした。受付を遅らせたり、ラウンド開始を遅らせたりした。人々を招くために可能な限りのことをしたのだ。気が狂いそうで、もしかしたら楽観的すぎたかもしれないが、俺は失敗するなんて考えもしなかった。俺は北東部出身だ。吹雪の中で雑に運転するのも普通のことなので、俺は「来いよ、ぐちぐち言わずに来い。車の横に多少傷ついても構うなよ。ガードレールはそのためにあるんだからよ」と思っていた。
台風の目で
エレイン
前の晩に、参加できる人だけでパーティがあったの。豪華な前夜祭を遠慮した人もいたけれど、皆何も食べるものがなくて飢えていたのよ。実際、たくさんのピザが注文されていて、ほんとにすごかったわ。ピザが届いたら、皆でむさぼり食べたのよ。
マイケル
僕たちが着いた夜、すごいパーティだった。忘れられないよ。当時の有名人のリチャード・ガーフィールドがいて、僕は初めて会ったんだ。僕たちはホテルのホールで練習していたんだけど、僕はちょっと飲み過ぎていたんだ。僕は彼のところに行って、「やあリチャード! 僕はマイケル・ロコント、これから勝って日曜日に挨拶するよ!」と言ったのさ。
言い終わってそこに立っていると、彼は頭を振って、「勝てるとは思わないけどな」と言った。ほんとに楽しい時間だったよ。
マーク
壮観なものにしたかった。前夜祭には、プレイヤー向けに飲み物や食べ物を提供したし、プレイヤー全員が来られるようにしようとしたのだ。私はプレイヤーに電話をかけ、これがマジックのための一大イベントだと伝えたのだ。
エレイン
その夜遅く、私たちはホテルに帰って、「レイト・ショー・ウィズ・デイヴィッド・レターマン/Late Night with David Letterman」を観たの。おかしかったのは、誰もシティから出入りできなかったのに、レターマンは公開収録だったの。カメラマンが観客を写したのだけれど、5人ぐらいしかいなかったわ。それから、待機線を見て、そこには12人ぐらいいたかしら。全員を入れても、客席は最前列も埋まらなかったわ。キーリンと私は顔を見合わせて、「ちぇー! レターマンに行けばよかった!」と言ったのよ。
組み合わせ発表
グラハム
小さい子供がたくさんいました。実際にイベントで勝負していると言えるのは15人ぐらいだけかもしれないと感じましたね。考えてみてください、12歳で17歳と対戦しなければならないのは不公正でしかないでしょう。私は《ネクロポーテンス》デッキを使っていて、そのイベントにいたんです。私のマッチはどれも10分か12分ぐらいで終わっていました。
私が初めて《Demonic Consultation》をプレイしたのを見てジャッジが笑ったのを覚えています。私は「笑いたければ笑えばいいよ」と思いましたね。最後にはジャッジも真顔になっていました。早いマッチがとても多かったのを覚えています。負けた相手は、メインデッキに《因果応報》を入れているプレイヤーだけでした。私はジャッジに、本当にそれがメインデッキに入っているのか確認してもらいましたが、ジャッジはメインデッキにあったと言ったのです。
チャーリー
僕はジュニアのヘッドジャッジで、イベント主催者でもあったんだ。メモと、鉛筆、消しゴムを持ち歩いていた。僕は前もって対戦組み合わせの方法を把握していた。チェスの大会に参加していて、大会進行のやり方を知っていたんだ。メモを取り出し、1勝0敗を全部1つの束にして、0勝1敗を全部1つの束にして、それぞれで第2回戦の組み合わせを作った。すべての結果をメモに書き記していったんだ。そして、ディナーの後でメモの束をホテルの部屋に持ち帰り、時間はかかったけど手計算でタイブレーカーの計算をしたんだ。全員の順位を確定させるためにね。順位は重要なので、ダブルチェックが必要だった。タイブレーカーを計算しただけでなく、その結果のダブルチェックもしたんだ。120人ぐらいの参加者全員の計算をしなくちゃならなかったんだ。
エレイン
覚えているのは、部屋の中、テーブルの下に何も仕掛けがないか調べるというので第1回戦の開始が大きく遅れたことね。部屋に持って入れるのはデッキとイベント用具だけで、他の何も持って入れなかったの。コートやバックパックは有料で預けるように突然言われたわ。その頃私たちは貧乏なマジック・プレイヤーだったから、誰も荷物を預けるのに何ドルか払いたくはなかったのよ。私たちは強く抗議して、支払わなくてもいいと言われたけれど、あれが私たちだけの例外だったのか、みんな無料になったのかは知らないわ。
スカッフ
イベントが始まった後のことはあまり覚えてないな。ジュニアに何回か呼び出された。フィンケルが喚いていて、俺はその相手をしなければならなかったんだ。
ジョン
俺が最初のラウンドで勝った10分後、俺たちのテーブルに3枚のカードがあった。第2ゲームで《道化の帽子》を食らっていて、第3ゲームまでもつれ込んだんだ。ジャッジは、そのカードが俺のかどうか聞いてきた。俺はそうだと答え、第3ゲームは俺の負けにされた。マッチには勝っていて――そのカードは、なぜかそこにあったんだ。俺は控えめに言って癇癪を起こした。喚いたのは間違いない。ビデオがなくてよかったと思うよ。それでスカッフが駆けつけたんだ。俺は返金と代償を要求した。彼らと話して落ち着きはしたが、今考えてもあのゲームの敗北は不公正だったと思っているよ。
チャーリー
僕はルールに関する問い合わせに関して不安があったんだけど、幸いにもそこにはルールにものすごく長けたベス・モーザンド/Beth Moursandがいた。それで僕の不安はいくらか和らいだんだ。何も難しいことはなかったと思うけどね。
マーク
今は当たり前だと思われているプロツアーのやり方はいろいろとある。たとえば、フィーチャー・マッチを作ったのは私で、第2回プロツアーのときのことだった。そのときは、プレイヤーが行って見たくなるようなマッチが行われるテーブルのリストを作った。そして第3回で、観客として近づける特別な場所を作ったのだ。第1回プロツアーでは、観客はどこでも行けてどのマッチでも見られたのだ。
エレイン
私はひどい成績で、早々に負けたの。キーリンと私のどちらもトップ16に残れる可能性がなくなったところで、私たちは昼食に行くことにした。ブライアン・デビッド=マーシャルのところに行ったら、彼は私たちに残るように言ってきたの。足切りに及ばなくても、トップ32だったかトップ64だったかに入ればロサンゼルスで開催される次のプロツアーに招待される可能性があるっていうのよ。「ほんと!? またこんなイベントをやるの! 私たちは何をしてあげればいいの?」と答えたのは覚えているわ。それで、私たちは棄権したけれど、それから2年間はまたプロツアーに参加するために過ごしたのよ。
ジョン
俺はそれから5ラウンド勝って、ロス・スクラファニー/Ross Sclafaniと対戦していた。勝った方がトップ8入りだった。タイブレーカーはゲーム勝率で、俺はロスに勝った方が2-0で勝ったことにしようと持ちかけた。彼はジャッジを呼び、ジャッジはそれはできないと答えた。今は、もちろん、わかりきったことだ。だが、当時は? 何もわからなかった。結局俺は負けて、それでもトップ8には入ったが、準々決勝で負けた。
ついに!
スイス式で1日プレイし、タイブレーカーの計算に一晩費やして、日曜日、シニアのトップ16、ジュニアのトップ8がプレイするために戻ってきた。シニアの決勝戦はバートランド・レストレイ対マイケル・ロコント、その頃ジュニアではグラハム・タトマーがアーロン・クラインを下していた。
グラハム
決勝戦はアーロン・クラインの白ウィニーが相手でした。本当に厳しい対戦で、私は何度かトップデッキして勝ち残りました。《ネビニラルの円盤》をトップデッキして勝ったのを覚えています。危ない勝負でした。
ゆっくりプレイして、全部説明しろと言われました。私はいつも非常に早くプレイしていたのです。ゆっくりやり過ぎると、ゲームに関する直感を見失ってしまうと感じていました。途中で、アーロンがマッチに勝ったと宣言されたのを覚えています。そのとき、私たちは充分に意思疎通をしていませんでした。私は次のターンに相手を倒せる状況でしたが、相手は《因果応報》を出していました。私は《Zuran Orb》を出していたので、土地を生け贄に捧げてライフを得ることができました。私は彼を見て、彼は「わかった」と答えました。私はカードを片付け、彼も片付けました。見ていた人は、彼が勝ったと思ったのです。私は、土地を生け贄に捧げなければ《因果応報》で死んでしまいますが、土地をすべて生け贄に捧げれば相手を倒せる状況でした。
それ以降のプロツアーでは、何をしているかについて各手順ごとに明確にすることが必要です。アーロンはいい奴だったので、「《Zuran Orb》が出ているんだから《因果応報》で死ぬはずない」と言ってくれました。私は、このときのことについて深く考えました。私はもっとプロフェッショナルになるべきだったでしょうが、私はまだ子供でした。周りの人たちが彼が勝ったと考えたことで混乱してしまったのです。そのゲームで彼の優勝になるところでしたが、第5ゲームまでもつれ込んだのです。
マイケル
僕のデッキはライブラリーを削りきる《石臼》を使っていた。《神の怒り》《剣を鍬に》《天秤》と、全体除去を大量に入れた防御的なものだった。《またたくスピリット》や《ミシュラの工廠》で相手の攻撃を防ぐんだ。ゲームを可能な限り長引かせて、相手のライブラリーが尽きるようにするのさ。
決勝が4本先取で、このデッキはあまりにも長い時間がかかるものだったのを覚えてるよ。たぶん、彼らはこんなことを想定もしていなかったんじゃないかな。それで、僕とバートランドを――確か、1本目は僕が負けて、2本目は僕が勝った、その後だったと思うけど――呼び出して、あまりにも時間がかかりすぎていて、会場をそこまで長くは借りていないと言ったんだ。彼らは優勝を決めたかった。賞金は均等に分けて、優勝者を決めるためだけに1ゲームしてほしい、と言うんだ。それが事の顛末さ。
グラハム
なんですって、つまり――4本先取が、2本先取になったわけですか。私たちのほうはそんなことはありませんでした。私たちは普通に5ゲームやったんです。ビデオの中で感想を述べまでしています。「ジュニアは手加減はいりません、プレイはすごく速かったです」と。アーロンも、とても早いプレイヤーと言っていいと思います。彼は普通の白ウィニー・プレイヤーで、コントロール・デッキを使うようなことはないでしょう。アーロンと私がそれぞれのデッキを使っていた中では一番遅かったと思いますが、のんびりできるのはそれだけです。《惑乱の死霊》が出たらおしまいですよ。
チャーリー
ジュニアのイベントを終えて降りてきたとき、ジャッジの1人に交代してくれと頼まれたのを覚えているよ。決勝戦が長すぎて、休憩が必要だったんだ。もう1つ覚えているのが、僕の友人の1人と他のジャッジが夕飯に出かけたときのことだ。彼らはかなり遠くに行って、しばらく待ってから食事をして、戻ってきたときにまだ決勝をやっているとは思わなかったってさ。
マーク
彼らは2人とも、これが第1回プロツアーで、優勝者を決める必要があるということを理解していた。そして――人々は忘れがちだが――バートランド・レストレイは世界選手権に参加し、決勝でザック・ドラン/Zak Dolanに敗れているのだ。相性的にはバートランドが有利だったが、実際ザックが勝っている。彼は、第1回プロツアーでも決勝で敗れた男、にはなりたくなかったのだ。彼は時間をかけた。彼らは時間をかけてプレイし、立ち上がりの遅いデッキを使い、ミスを犯さないように細心の注意を払った。予定では4本先取だったが、5時間経って、我々は2本先取にすることを決めたのだった。
マイケル
最後のゲームで、彼は俺の天敵の《疾風のデルヴィッシュ》を出していた。はっきり覚えてはいないが、たぶん《ミシュラの工廠》がらみでミスをしたんだと思う。俺は《剣を鍬に》をトップデッキするしかなくて、そのゲームではもう何枚か使っていたんだ。ラッキーなことに、手札には《平地》が1枚あった。土地は出ていない。俺はその《平地》を手に持ったまま笑った。ここで《剣を鍬に》を引くしかなかった。彼は何が起こっているかわからなかったんじゃないかな。
その後、俺たちは本当にいい友人になった。彼は本当に面白い奴だった。彼は「ハマー」ショーン・レニエと似ていた。彼はいつも皮肉屋でいろいろ言って内面を探ろうとしてきたが、それ以降本当に馬があった。プロツアーの後、俺たちはいつも一緒にいた。彼にサインを頼んだところ、彼は「[伏せ字]剣!」と書き、その後で「バートランド」とサインを入れたんだ。俺は今でもそれを持っているし、手放すつもりはない。

夏が来る
そのプロツアーの前には、《ネクロポーテンス》は競技レベルのカードだとは見られていなかった。
マーク
インクエスト/Inquest誌では、《ネクロポーテンス》は1つ星の評価だった。このイベントの面白いところは、《ネクロポーテンス》デッキでグラハム・タトマーが優勝したのはもちろん、レオン・リンドベック/Leon Lindbeckも非常に初期型のそれでトップ8に入賞しているということだ。そのデッキが実力を発揮するのは、その夏のことである。
リチャード
そのカードがどれほど強いのか正確にわかっていたかどうかは覚えていないが、驚きはしなかった。当時の私のデザイン理念は、カードを禁止に追い込むほどでなければアグレッシブすぎるとは言わないというものだった。チャンスをつかまなければならないのだ。私の理念は、プレイヤーに興味深い道具を大量に与え、その道具を自由に使わせるというものだった。発見という私の理念は、カードに関しては棚上げになっていたが、コンボに関してはマジックの重要な一部分であった。プレイヤーは常に、私たちが考えていなかったようなマジックのカードの新しい組み合わせを見つけ続けるのだ。
マイケル
俺は間違いなくあの日の組み合わせでいくつか弾丸をよけていたな。
グラハム
あなたが強力だったから、対戦相手が怖じ気づいたんですよ。私も可能な限り対戦相手にプレッシャーをかけましたが、そのデッキは本当にそうでした。そのデッキに押されて、相手は失敗するか、早々に諦めるかするんです。
終わりに
リチャード
人々が私に会って興奮したり、私にサインを求めたり、私とプレイしたりしたがるようなイベントに行くという経験は新しいものではなかった。数年来やってきたことだ。しかしその趣旨は変わりつつあった。プレイヤーが本当に強くなり、マジックを本当に真剣に取り組むようになり始めた瞬間だったのだ。表面上はそれまでの会合とそう変わらないように見えるが、私は何かが変わりつつあることを感じていた。プロツアーまでは、私はどこのカードショップに行っても、コモンだけのデッキでほとんどのプレイヤーに勝つことができた。ばかげた話だ。プロツアーが始まってからは、そこらのカードショップに行き、コモンだけのデッキで誰にでも勝つなんていうことはできなくなったのだ。
グラハム
もちろん、すごいものでした。父も一緒に来ていて、彼も興奮していました。彼自身もオタクです。彼は最強ではなく最高でした。彼の息子にとって、勝利は大イベントでした。ジョエル・アンガーがいたことも大きかったですね。すごいものでした。私にとっては幸せでした。私がサンタ・バーバラに戻ったとき、まだ誰も知りませんでした。テキストメッセージもインターネットもなかったのです。でも、私が優勝したということを知って皆が興奮しました。とても好意的でした。
スカッフ
プロツアーは俺が関わった中でも一番誇りに思っていることだろうな。プロツアーはマジックの標準だ。プロツアーがない世界にいるわけじゃないから、マジックの成功のためにどれだけ重要かを理解できるとは思わないな。
マーク
第1回プロツアーがやったことは、イベントの運営についての標準を作ったことだ。おかしいのは、その最初のイベントでは、我々はいろいろと間違っていたということだ。我々はいろいろなことを学ぶことになったが、それでも第1回プロツアーはそれ以前からは大きくかけ離れていた。
ジョン
第1回プロツアーを見て、ジュニアとシニアを区別して、生涯プロポイントを見ると、ジュニアにはすごい奴らがいたのがわかる。シニアに参加していた中で一番はダーウィン(・キャスル)/Darwinだろう。ジュニアには、俺、スティーブ・オマホニー=シュワルツ/Steve O'Mahoney-Schwartz、ボブ・メイヤー/Bob Maher、ブライアン・キブラー/Brian Kiblerがいたんだ。
エレイン
私にとっては、ブラック・ロータス・プロツアーはマジックがゲーム全体、あるいは私全体の中で占めるスケールを変えてくれたターニングポイントね。
チャーリー
20年前、僕たちはあらゆることを考えついたところだった。イベントがどうあるべきか、フォーマットがどうあるべきか、マジックの楽しいことは何か――あらゆることだ。僕は様々なことを達成したと感じていた。この最初のイベントから本当に多くのことを学んで、次のイベントをよりよいものにするためにどうすればいいか考えることができたんだ。
マイケル
何年か経って、ある人物が俺のところにやってきて、再び雑誌に載っていると言ったんだ。その雑誌を見て、俺は驚いたね。それを母に見せたら、母はウィザーズに電話をかけて、俺やバートランドの写真がまだあるか尋ねたんだ。ウィザーズはすごくクールで、写真を額縁に入れて母に送ってくれたよ。その写真は、俺のデッキのアンカットシートと一緒に飾ってあるんだ。

マーク
文字にすべきでない話はまだあるから、ここからはオフレコで――
(Tr. YONEMURA "Pao" Kaoru)


