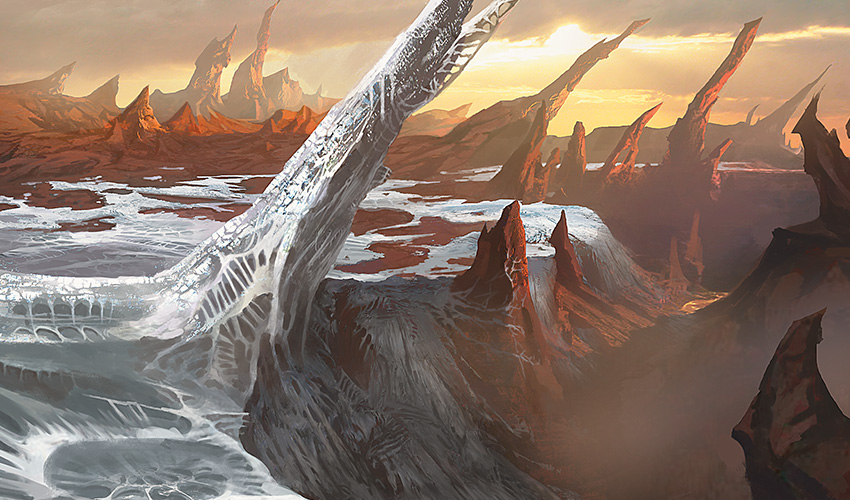霊気より生まれしもの
前回の物語:改革派の長
ギラプールの霊基体は遊び好きかつひたすらに興奮と熱狂を追い求める種族である。最大でも四年程の寿命を過ごすべく彼らはその都市に生き、遊び場として浮かれ騒ぐ。その生涯は短いながら、彼らは周囲のエネルギーを感じ取り共感する能力もまた保持している。
投資家にして博愛主義者、社交家のヤヘンニは自身の寿命が近いことを知っていた。そして発明博覧会前に途方もなく大規模なパーティーの一つを開催した際、三人の予期せぬ客が危険な知識を求めて訪れた。

I
午後から着飾るというのは良いものだ。最期のパーティーの際に見逃す可能性のある用心や準備のため、夜通しのパーティーは日中に準備する方が良いとされている。私は今から二時間のために着飾っているのではない――今から二日間のために着飾っているのだ。
寄せ集めのような姿で十六時間がかりのパーティーに出席する主催者がいるだろうか? それでは主催者失格だ。
私室のカーテン越しに差し込む午後の陽光が、この部屋でも最大の壁を占領する純金の整理棚を照らし出している。光の揺らめきはこの豪奢極まりない宝石箱のあらゆる引き出しから覗き見える、また全面を飾りきらめく宝石、装飾品、秘宝を透過して豊かな黄金色に染め上げている。私は霊基体。それゆえ自身がいつ死ぬか、どのように過ごしてその時へと向かうかを正しく把握している。そして、私が良いとみなすものの真価を認識しないような愚か者のために費やされる時間はない。
二番目にお気に入りのブローチで身を飾る頃には、パーティーの準備をする召使の興奮する声が下階から聞こえるほどだった。宴会係は台所を実に適切に利用している――有機生命は「食事」についてとても神経質だ。幸運なことに我が宴会係ニブドは一度たりとて私を失望させてこなかった。彼は現在も胃袋持つ人々の為に忙しく台所で働いている。沿岸地方から輸入した椰子ワインの泉、様々な調合と風味の紅茶、何皿ものサモサ、パーニープーリー、アルーティッキ、そして巨大なテーブルに山と盛られた甘味(シュリーカンドの前には常に行列ができる。それほど美味ということらしい)。他の召使は今まさに屋根の天蓋を忙しく組み立てている。パーティーが終われば肉体を持つ者らは下でしばし眠るだろうが、我が霊気の兄弟と私は夜も昼も、その次の夜も踊り明かし、祝祭の絶頂に熱中するのだ。
だがそれは後だ。二秒と少し、思案とともに棚を漁り、ジャスミンと霊気の吹き込まれた香油を今夜のために使用すると決めた。個人的に大のお気に入りだ。我が映し身が鏡に映った。洒落ている。三日を過ごした後にはとても見えないではないか!
この部屋からでも、屋上にいる召使らの幸せな興奮と白檀の香りの期待が感じられる。他の種族は我々のような感覚を持たない、私はそれを気の毒に思う。五十年前、精製霊気から我らが種族が初めて姿を現して以来、彼らは「共鳴と共感」とそれを呼んでいる。「近隣周囲の存在の感情的状態を正確に察知する興味深い能力」。彼らは我々の発明に大いなる信用を寄せている、我々は自身を発明したのだと考えることもなく。私は悲しく憤慨し笑った。以来、我々が発明してきたものは、自身を楽しませる方法だけだった。
手首と首筋に香油をざっと塗りながら、私は皮膚の小片が穏やかな煙の筋へと消えゆくのを見つめていた。固い皮膚が消えるほどに、私は終わりへと近づく。ひび割れの下に流れる我が霊気の青色が見えた。そしてその美にとらわれた。愛おしかった。急げ、という穏やかな催促。私はそれをもう一つの腕輪で覆い隠した。
我らが種は生来、時間の経過と各人に残されたそれがわかる。まるで列車を待っているようなものだ。あらゆる雑音に顔を上げ、風が席を揺らす。だがまだ来てはいない。
私は服装と装飾の準備を終えた。残る生涯は五十四日。
II
適切に着飾り、屋上へと続く階段を昇っていくと、音の壁に当たった。パーティーの音楽という固い手に平手打ちをされるよりも良い感覚は存在しない。
我が召使らが下階から引き上げてきた長毛の絨毯へ、天蓋が喜ばしい影を投げかけていた。装飾担当がテーブルの上に木蓮を置き、館の壁に揺らし、そして美しい絹が手すりに添えられ、装飾の金線が遅い午後の陽光に揺らめいていた。歩きながら私は空のグラスを滑らかに満たし、口付けを交わす人間二人をさっと避けて(嬉しいことだ、前回のパーティーで私が引き合わせたのだ――自分の力を役立てられるというのはいつも良いものだ)、ドワーフらを休憩室へ案内し、そして一般向け型パンハモニコンの音量を調整した。
存在を忘れ、そして熱狂する――パーティーというのは最高の悪徳だ。私は客人らの歓喜を味わった。焼いた動物を食べるのがどのような感じかはわからないが、想像はできる。私は主催者としての義務に耽溺し、客人らは称賛を弾けさせた。
我が親友にして一流操縦士のデパラ嬢(あのデパラ嬢だ!)はやや離れた長椅子に寛いだ様子で座し、黄金色の繋ぎ紐をもてあそんでいた。その横では彼女のハイエナが休息しつつ、嬉しそうに一本の骨を噛みしめていた。

「愛しのデパラ、貴女がいてくれるだけで我がパーティーはいつも華やかになる」 私は彼女を真剣に抱擁すると、屈んでハイエナの耳の後ろを優しく掻いてやった。そのハイエナは我が手に鼻をすりつけた。
「ヤヘンニ、この子はあなたがお気に入りね」 デパラは信頼の笑みとともに言った。「引退して、気楽になった?」
「社会の動向を急いで追い続けなくとも良くなりましたよ」 私は彼女のグラスを満たしながら小言のように言った。
「大体はレースの結果でしょう。でも私も仕事のニュースはしっかり確かめてるわよ」
我が家系は発明家として財を成した。残る寿命が六十日を切ったところで私は引退を宣言した。生きて結果を見られないとあれば、大胆な投資戦略は遥かに簡単なものになる。
私は彼女の隣に座った。「ならば、一か月ほど先になるが直前パーティーに参加して頂けますか? ギラプール最高の操縦士が不在とあっては退屈の極みですからね」
デパラ嬢は笑顔を見せ、上の空で手でハイエナを撫でた。「見逃せませんね。霊基体の慣習は最高です」
「心から同意します。我々は単純に他のことに費やす時間がないのですよ、愛しのデパラ」
デパラ嬢は口を固く閉ざした。彼女の眉がひそめられ、耳をそば立てているかもしれない何者かへと両目を向けた。「あなたは……伸ばす気はないの?」
私は思わずぞわりとした。
「ヤヘンニ、それができることは知っています」 彼女は意味深な視線とともに言った。
「伸ばす気はありませんよ、デパラ」 私は腕の崩れつつある一片を摘んだ。少し前から、他者の精髄を吸収することが可能だとは知っていたが、それを使うつもりはなかった。それは暗黙にしておくべき、稀な能力だった。自分の終わりの日を伸ばすことにすがり、他の知的生命の生命力を盗むなどとは。そんな事をしたら、友人らは私のことをどう思うだろうか?
「選択肢、ですよね」 図々しくも彼女は続けた。「それがどう機能するのか、あなたが……他の誰かからどれほどの時間を得られるのかはわかりません。あなたが、考えたことがあるのかどうかも」
「心によぎりはしました。ですが私は昔ながらの流儀で行きたい」 私は努めてそう言った。
その時、宴会係のニブドが、デパラ嬢好みの飲み物の瓶を持ってきた。実に思慮深い――私に匹敵する良い人物だ。
「ヤヘンニ、あなたは善いお人」 再び我々だけになった時、デパラ嬢は言った。「それで数日を得たとしても、苛まれる罪悪感に比べればその価値はないでしょう」
その言葉の通りなのかどうか、私は定かでなかった。
III
女性が三人、我が住居の玄関外に立っていた。パースリー夫人は即座に認識した(世界で最も有名な発明家の一人であり、同じく私が知る限り最も熱心な盤上遊戯好きだ)。その右にいるのは時代遅れの身なりをした赤毛の女性だった。何年も前の流行だ――それで外に出るのか?
そしてその反対側にいた人物に、私はかつてない程に魅了された。

その両目は果てのない、鮮やかな緑色でその中央から瞼までを満たしていた。居心地の悪そうな態度に反する鮮やかな美。こんなにも緊張した人物をこれほど興味深く見るというのも痛ましい。鮮やかな花で飾られた(本物だろうか?)衣服はまさに彼女だけに似合うものだろう。魅惑的な人物には興味を抱き、魅了されるものだ。だが彼女の魅惑は、私にとっては厳密に社会的獲得という視点からのものだった。当たり前だが主催者としての私の目的は客人を喜ばせる事であり、だが楽しむ人々を見るというのは私にとっても思いがけぬ贈り物となっていた。
パースリー夫人は言った。「ヤヘンニさん。こちらはチャンドラさんとニッサさん。お二方、こちらはヤヘンニさん。若き発明家が必要とする投資家であり、私が知る限り最も気前のよい博愛主義者ですよ。参加させて頂いても宜しいですか?」
「勿論です、パースリー夫人」 何という紹介だろうか。私は顔が熱くなったような気がした。
私はエルフの女性を迎え入れるように扉を開けた。「何と素敵な瞳だ」 そうニッサ嬢へ挨拶すると、彼女は硬い笑みを浮かべた。
赤毛の娘は居心地悪い様子で外に立ったままでいた。私はその娘を不審に見て、そしてパースリー夫人へ顔を向けた。
「この方はチャンドラさん。ピア・ナラーの娘さんです」 彼女はそう言った。
私は脇に立ち、ギラプールで最も危険な人物の娘を中に入れた。「パーティーは上階です。もっと静かな所でお話しましょう」
私は三人を地上階背後の中庭へ案内した。歩きながら、パースリー夫人が私の耳に囁いた。
「ご存じかと思いますが、ピア・ナラーが逮捕されました」 それは知らなかった。私にとっては珍しいことだった。
「ピア女史はそのような過ちをしない筈です。何があったのですか」
我々は歩き、パースリー夫人は状況を説明した。鉢植えの植物と心地良い噴水の流れが休息所を囲み、その中央には四つの古めかしい椅子が置かれていた。パーティーの音が屋上から漏れ聞こえており、我々の会話をありがたくも覆い隠してくれた。私は三人に座らせ、客人のための飲み物を持ってくるよう召使へと合図した。パースリー夫人が説明を終えると、私はピア・ナラー女史の逮捕について熟考した。
「困ったことに、領事府がピア女史ほどの囚人をどこに収監しているのかは、私も存じません」
パースリー夫人は頷いた。「そうですか」
「申し訳ありません。我が人脈を活用したい所ですが、この件は私にとっては八方塞がりです」
右からけぶる怒りの熱い波を感じた。「捕まったのがあんたの両親だったらどうするのよ」 チャンドラ嬢は拳を突き出した。
「私に両親はおりません」 私は軽く肩をすくめて言った。チャンドラ嬢のしかめ面が強張った。馬鹿なことを言った、と本心から思っているのだ――私は全く気になどしない。
召使が戻ってきた。私はパースリー夫人に椰子ワインを、そしてエルフには森の酒を渡した。経験から、エルフはこの強い酒を好む――私が称賛し、そして大いに嫉妬する特色だ。
「上に、力になってくださる方がいらっしゃるでしょうか」 パースリー夫人はそう付け加えて、優しくも年季の入った両手で杯を受け取った。
私は上階の客人を考え、人脈をたどった。
突如、玄関が騒々しくなった。ニッサ嬢は飛び上がり、チャンドラ嬢は興味を持ったように顔を向けた。中庭の我々の位置から、霊基体の一団が玄関へ飛び込んでいった様子が見えた。彼らは頭上に椅子を掲げ、そこには急速に消滅しつつある霊基体が乗っていた。椅子の上の霊基体は瀕死の光に輝いていた。その皮膚は消失し、既に姿というより煙だった。きまりの悪さに、私は目をそむけた。
「これが僕の直前パーティーだ!」 その霊基体は熱狂とともに言った。雑多な一団は椅子を持ち上げ、生者の間を抜けて屋上へと階段を昇っていった。
面白いといった様子でチャンドラ嬢が私を見た。「今の誰?」
「私も存じません」 私はそう言って、この日の早くに隠した手首の一片を摘み上げた。細い煙が逃げ出た。自分がこのように死ぬのを見つめるのは嫌なものだ。
チャンドラ嬢は机に手を置き、目的をもって立ち上がった。「ふうん。みんなに聞いてくる。ニッサ――」
「私は大丈夫」 そのエルフは柔らかに返答した。だが彼女のエネルギーは不安に冷たく苦かった。大丈夫などではない、そのため私は介入することを決めた。
「ニッサさん、宜しいでしょうか? 私と来て頂けますか。その御召し物をどこで手に入れたのか、是非教えてもらわねばなりませんからね」
IV
我々は階段を昇り、屋上すぐ下の階に着いた。私はニッサ嬢をバルコニーへと連れ出した。自身のパーティーに居心地の悪そうな客を迎え入れたなら、主催者は何をすべきだろうか?
「ここから逃げたがっているのではないですか」私は言った。
「大丈夫です」 そのエルフは腕を組み、そう繰り返した。大丈夫ではない、だが彼女から好奇心が溢れ出て来た。「直前パーティーって何です?」
「我々霊基体は最後に死にます。そのため最後から二番目に、主席を命じた客人とともに直前パーティーを行うのです。もし多くの友がいなければ、他の者のパーティーを乗っ取ります」 私は屋上を示した。上階ではパーティーの音に混じって、死にかけの霊基体が声を上げていた。「その敗者は、不幸にも、滞在を歓迎されます」
そのエルフは返答しなかった。多くを語らぬ性格なのだろう、だがそのエネルギーはとても読みやすかった。
「それでは、一から始めて死にたくなるまで、貴女はどれほどパーティーがお嫌いですか? どうぞ正直に」
「八か九ですね。ベイロスに足を噛みつかれるくらいに」
私は曖昧な声を発した。「それは悪いことなのですか?」
あの途方もない瞳は定まっていなかった。何かを思い出そうと、彼女がまとうオーラはほろ苦さに染まった。
「故郷では、パーティーに参加したこともありました」
私は黙って彼女の杯を満たした。「あなたはそこで何を?」
「お話をして、互いの関係を再確認しました。時々、皆で特別な場所へ出かけることも」
「今もその場所では頻繁に?」
ニッサ嬢は黙っていた。その場所はもう存在しない、私はそう察した。「でしたら。今このパーティーで貴女に寛いでいただくには、私に何ができますでしょうか」
「どこか離れた所に座れませんか?」
「可愛らしいお方、貴女のためでしたら私はこの都市の果てまでも行きましょう、純粋に精神的に。ただ貴女がお願いしてくれさえすれば良いのですよ。それと雨などでなければ」 彼女は私のこの言葉に笑った。少しだけ彼女は力を抜いた。そしてそのエネルギーは上階の歌へと向けられた。何と素晴らしいことだろう、彼女は音楽を愛しているのだ。私は首の後ろで消える皮膚の煙を無視した。「屋上へ聞きに行きましょう。どうぞ私と腕を組んで――皆に注目されるというのは素晴らしいものですよ」
私はニッサ嬢の不安を察し、群集の中を穏やかに道をあけさせた。上階へ向かいながら、私は一人の新たな客人に挨拶をし、そして顔にサモサの塊のついた別の客人へと素早くハンカチーフを渡した。パーティーは自然な中休み状態となり、客人らはお互い歓談していた。私はそのエルフを天蓋の端、鉢植えの植物で意図的に隔離された場所まで連れて来た。
我々が座ると、随員の一人がやって来た。私は香油の瓶を受け取り、その耳に告げた。「客人のためにパンハモニコンの音量を下げ、そしてもっと穏やかな曲を」 気のきく給仕係というのは何よりの宝物だ。
「無遠慮かもしれませんが、貴女は街の女の子とは違う風に私を魅了する」 私はさらりと言った。エルフは小さな笑みを見せた。私は長椅子に座り直した。「貴女は霊基体に初めて会う、そうではありませんか?」
「そうです。教えて頂けますか」 ニッサ嬢は柔らかく、真剣さとともに言った。彼女は私が実際に目の前にした最も積極的な聞き手だ。その見つめる視線はほんの僅かに私を狼狽させた。
「我々は霊気循環の副産物である知的生命です。家系はその若者が発生した場所によって決定されますが、後にそれぞれが選択します。完全に姿を成した日から、その寿命は四週間から四年程です」
「私が会ったことのあるエレメンタルに似ているかもしれません」 少し悲しそうに眉をひそめ、ニッサ嬢は言った。
「でしたら貴女は私よりもずっと多くに出会ってきていることになる。私が知っているのは、私自身についてだけです」
「わかりません……」
「何がですか?」
彼女は身振りをしようとしたが、その意味は私にはわからなかった。
私は少しのきまりの悪さを感じた。「どうしましたか?」
彼女はまた別の身振りをしかけて止め、言葉を探していた。そしてようやく口を開いた。「わからないんです、この都市にとっての自然はどんなものなのか」
「我々が、この都市です。私は霊気から生まれ、やがてそこに帰ります。自然は我々を取り巻いています、ただ、貴女が見ていたものとは異なる見た目かもしれませんが」
ニッサ嬢は小さな声を発した。明らかに、そのように考えたことはないらしかった。
会話が途切れている間、私はもう一人の客人へと無言で休憩室の方角を示した。
その沈黙は続き、私はニッサ嬢の目を見つめた。何をしているのだろう? その表情は混乱しているようだった。耳を傾かせ、何かを聞いているようだった。私に聞こえない何かを聞いているのだろうか? 彼女の口の端が笑みに上げられた。

「感じます。この世界の構造を。循環を」
いかにしてか、このエルフは我が故郷の自然を感じ取ってくれたらしかった。
私は力を抜いて座り直した。「大導路は常に存在します、ここギラプールにあっても。我らが民がその証です。この都市が混雑していようと、我々の自然は気にかけません。その律動はずっと同じように続いているのですから」
ニッサ嬢の顔に大きく笑みが広がった。
私は近くのエルフ製水差しを持ち上げた。「いかがですか?」
「お願いします」 ニッサ嬢は機械的に応じ、私は彼女の杯を満たした。多くを明かしたくないのかもしれない、だが彼女の心が驚嘆にはやるのを私は感じた。今夜はきっと、新たな発見に満たされるに違いない。
V
下階に騒動の音を聞き、私は立ち上がった。ニッサ嬢は杯を置き、その果ての無い瞳に疑問を抱いて私を見た。年月によって私の感覚は高められており、どこで何がおかしいかを直ちに察知した。
私は階段を駆け下りたりはせず(そのようなことをすれば更に身体が崩れてしまうだろう)、堂々と階下の休憩室へ向かった。客人らが道をあけ、気が付くとニッサ嬢とチャンドラ嬢が私を追ってきていた。
廊下の突き当り、浴室の前に領事府警備隊の職員が一人、堂々と立っていた。その浴室の扉は明らかに鍵がかかっており、その者は無理にでも押し入ろうしていた。長身の執行人だった――扉の隣に置かれた鉢植えの木の高さ程もあった。その衣服は古くぼけて、だがその縁取りは新しかった。肉体的な戦いは得意ではないのだろう。脇に構えた武器は街路の巡視に適したものではなく、そして鎧に映える鍵の束がその地位を暴露していた。刑務所内で働く者に違いない。
曲がり角に隠れているようチャンドラ嬢とニッサ嬢に合図し、私だけが近づいた。
「どうなさいましたか?」
その執行人は浴室の把手を放して私を上から下まで見た。「手配中の犯罪者が現在、扉を塞いでこの中に籠っております、貴方には無断で。私はそれを追ってきました」
「つまりあなたは我がパーティーに、我が家に、招待もなく入ってきたというのですか」
その執行人は半歩近づき、胸ほどの高さの私を見下ろした。
「貴方のパーティーを騒々しい命令で妨げられたいとお考えですか?」
「……いえ……」
「では領事府の公的任務を邪魔しないで頂きたい」
この執行人は扉の向こうに隠れた何者かを確保するためには私のパーティーを中止させるだろう、それは疑いようもなかった。領事府というのはそういう輩だ。嫌いな輩だ。
私はその嫌な者に背を向け、チャンドラ嬢とニッサ嬢へ向かった。簡単な解決策がある。この二人は逞しい――戦えるということだ――そして二人に私からも報いることができる。「もし手を貸して頂ければ、貴女がたの必要な情報が提供できそうです」
「何をすればいいんですか?」 ニッサ嬢が穏やかに尋ねた。
「ニッサさん、あの招かざる客人を外へお連れして頂けますか」
そのエルフは微笑み、穏やかな確信とともに言った。「喜んで」そして片手を挙げ、あの果てのない瞳に穏やかな光が輝いた。
私の胸の中で何かが短くうたった。だがその歌は私のためのものではなかった。遠くで感じる奇妙な響き、だがそれを無視するようにと私の心ははっきりと告げた。私はチャンドラ嬢へと向き直った。
「チャンドラさん、あの者が去ったなら、扉を壊して頂きたい」
ピア・ナラー女史の娘は純然な驚きとともに私を見ると、奇妙なほどの小声で言った。「本気?」
「ええ、本気です。私の身体にもう力はない、そして自分では開けられないでしょう。お願いできますか?」
対する唯一の返答は、少々警告的な、かろうじて抑えた笑みだった。若い人間女性からそのような音が発せられるのを聞くのは実に当惑するものだった。
角の向こうで重い音がした――私は覗きこみ、小さな驚きの声を発せずにはいられなかった。不可解にも、扉の隣に置かれた鉢植えの木がその執行人の脚に絡みつき、その者は呆然として横たわっていた。どうしてそのようなことが起こったのかは……方法は考えないのが得策に思えた。何にせよ気にする時間はなかった――私は角を曲がり、その者の隣に屈みこんだ。
「よし」 私は囁いた。「ピア・ナラーだ。どこの監獄にいる?」
その執行人はうなり声を上げた。倒れた時に歯が折れたのかもしれない。問題はなかった――彼女の居場所を話したり告げたりする必要はないのだが。私は感覚を開き、早口に尋ねた。
「コハリ監獄か?」
男はうめき、激昂のエネルギーを放った。
「グーファ刑務所か?」
苛立ち。
「ドゥーンド監獄か?」
私と目を合わせたその男に、かすかな香辛料と塩の記憶が狼狽へと花開いた。エネルギーを読まずとも、顔色からここまで推測できると思ったことはなかった。役に立つ男だ。私はこの者の頭を叩いた。「協力に感謝する」
私はエルフへと向き直った。「ニッサさん、お好きなように」
彼女は歩いてくるとその男を消防士流にたやすく肩へと持ち上げ、そして軽々とその男を外へ連れていった。うむ、実に上等だ。
「この場所はどれほど残せばいい?」 ゴーグルを目にはめ、チャンドラ嬢が割って入った。
「この扉以外全部、それが理想的です」
チャンドラは頷き、両耳まで広がるような笑みを見せると、白熱した指で素早く鍵の金属を融かした。私は自分の目を疑ってかぶりを振った。人間とそのパーティーの手品だ。
チャンドラ嬢が終える頃には、ニッサ嬢が背後に戻ってきていた。多すぎる香油の悪臭が扉と壁の隙間から漏れ出ていた。
「肺を持つ方々はパーティーへお戻り下さい」 私は見物人らへ告げると、三人の客人へと向かった。パースリー夫人が合流し、心配そうに見つめていた。私は彼女らへと近づいた。
「ピア女史がいるのは、ドゥーンド監獄です」 私は囁いた。
夫人は唖然とした。「そんな。嘘だと言って下さい」
私はかぶりを振った。パースリー夫人はチャンドラ嬢へと言った。「あそこにはバラルが」
周囲の大気が即座に熱を帯びた。「行かないと」 チャンドラ嬢は確固たる決意とともに言った。パースリー夫人が頷き、二人は出発すべく階段へ向かっていった。ニッサ嬢が振り返り、私と目を合わせた。
「ありがとう、ヤヘンニさん。話してくれて」
私は頷いた。「何も問題はありませんよ、お嬢さん。もし一か月の間に予定がなければ、またおいで下さい。人生最大のパーティーを開催いたします。その気がなくとも来て頂きますよ」
彼女は微笑み、そして去った。
VI
今や開錠された扉から入ると、芳香の波が襲いかかった。背後で扉を閉め、私はここに閉じこもった者を見た。押し殺した苦痛を早くから感じていたが、その通りに、ここに源があった。浴室の端、壁に背をつけて座るのは、先程の死にかけた霊基体だった。皮膚はほとんど消え、真髄の青い輝きが、窓から差し込む夕日の光と奇妙に混じりあっていた。足元には空になった香料の瓶が散らかっていた。

「良いものは惜しみなく使った方がいい」 心を軽くできればと私は言った。だがこの言葉も大きく開いて血を流す傷を無力に覆う絹でしかないとはわかっていた。
「僕はもうあと一分くらいだ」 その霊基体は喘いで言った。「領事府に追われてた。あいつらの前で行きたくはなかった」
「刑務所か何かから逃げてきたのか?」 私は尋ね、そして壊れた足枷が目にとまった。その霊基体は呻くだけだった。
私はその隣に座った。仲間が欲しかったのは、私なのかもしれない。「上の誰かは君の名前を知っているのか?」
「いや。あいつらはパーティーのために来ただけだ」
「それはまさに、我々がここにいる理由だな」
私は大気に残る香りの雲を吸い込んだ。この霊基体は消滅を続け、そのエネルギーは零された香油と混じり合った。私は多くの同類が死ぬ瞬間を見てきたが、それはほぼ常に、歓喜とともにあった。彼らは戦い、蹴り、かきむしり、生きるという栄光を満喫し、こうして最後を迎える。
私はその手の残骸をとった。
掌の下で、エネルギーが脈動するのを感じた。
「走り切ったか?」
その霊基体は私に顔を向け、そして私をざっと見た。話そうと懸命に力を込め、だが絞り出せたのは一言の断言だった。「ったり前だろ」
瞬時に私は嫉妬に襲われた。私に残された時間はあまりに短い。私の生涯、この霊基体の生涯、我らが種の生涯は、痛ましいほどに短い人生の中にあまりにも多くの経験を追いかけ、詰め込む。こんなにも早く燃え尽きるというのは不公平だった。
次は私だというのは不公平だった。
この霊基体は激しく震え、黒い煙を発した。皮膚は崩れ去り、内在霊気は逃げて穏やかな蒸気となって天井へと昇っていった。
私は霊気のもやの下、静かに座していた。愛おしかった。
少しして私は立ち上がり、窓を開けた。悪臭とエネルギーが大気へ、世界へ、大導路へ逃げていった。私は床に残された衣服の山へ向き直り、それと宝石と装身具を集めた。財布、時計、領事府の書類の束。素早く目を通した――些細な窃盗罪。そもそも刑務所へ送るほどのものではない。
私は怒りにその書類を握り潰した。あの領事府の馬鹿どもはただ我々の死を早めている。
この異邦人の宝石と腕輪を集めながら、突然の思考が浮かんだ。
もしパーティーをそのままに離れたなら? この霊基体を収監して死ぬに至らせた領事府の汚物を狩り立てるのはどうだ? 私は以前、他者の真髄を吸収したことがある(一度だけ、それも偶然だ)。そして素晴らしいと感じた。もう一度やってやろう。何百回でもやってやろう、もしそれを受けるに値する者がいるなら……
皮膚から、細い煙の筋が開かれた窓へ向かっていくのを見つめた。
家の外の街路、意識なく放り出された領事府の執行人。
数時間はあのままだろう。
ほんの数分間密かに出ていけば。
誰も気づくことはない。
駄目だ。いずれ時は来る。浴室の床、空の香水瓶に囲まれて傷跡から弾けるのが私だというなら……そうするだろう。
だが私には、残された時間でやるべき別のことがある。
私は半ば空になった霊気込め香油の瓶を一本掴み、自身にぶちまけた。強烈で鮮明な発香杉。エネルギーの稲妻が私の身に走り、新たに借り受けた黄金を首筋に輝かせ、そしてパーティーの響きが屋上から届いた。
私は階段を駆け上り、沈んだばかりの太陽と金線の柵に輝くランタンの光の中へと飛び出した。私が作り上げた人脈、その中の我が力に敬意を表して群集が分かれ、パンハモニコンが黙った。私は意図的に両腕を挙げ、堂々と大天蓋へ歩いた。客人らは声をひそめ、私へと注意を向けた。
「今から一か月後、暦に印をお忘れなく。名高い賓客も平凡な有象無象も大歓迎です!」
友人らも客人らも歓声を上げた。私と同じだ。地位の高きも低きも、彼らは満喫している。
「発明博覧会の閉会後に人生最大のパーティーを開催致します。皆様方のご参加をお待ちしております。そしてこれを見逃すのは愚か者だと、皆様のご友人方にもお伝え下さい」
歓声。私は、まるでもう十年の寿命を得たかのように感じた。
「それはさておき、私についてもっと聞きたい方はいらっしゃいますか?」
パーティーから叫び声が上がった。「勿論です!」
「ああ大変だ! 私は会話に飢えているのです! 踊りましょう、音楽の音量を上げて、そして誰か料理と酒樽を皆のためにここへ運んでくれたまえ!」
群集は有頂天に達した。圧倒的な享楽の興奮が流れ込み、私はその奔流に自身を見失った。人々が踊る嵐に飛び込むと、誰かが宙に投げた霊気香油の飛沫がかかった。音楽は加速し、歌の律動が皆の身体の動きを急かし、何もかもが生きていると感じた。霊基体の輝きは踊る人々の汗を微かに反射し、柔らかな霊気の煙が上空へ消えゆく中、私は生きて、生きて、生きて、このただ一つの瞬間に、この身の歓楽に溺れていた。
(Tr. Mayuko Wakatsuki / TSV Yohei Mori)