燃え盛る炎
前回の物語:この荒廃に生を受けて
チャンドラ・ナラーがゼンディカーに到着したまさにその時、巨悪が解き放たれた。悪魔オブ・ニクシリスはその「プレインズウォーカーの灯」を取り戻し、一体の巨人を覚醒させ、海門の破壊を引き起こした。今、エルドラージの巨人二体は自由にゼンディカーを徘徊し、人々は散り散りとなった。チャンドラは仲間達との再会を決意するが、この全くの混乱の中、彼らの居場所すら定かではない――復讐に燃えるあの悪魔についても。
チャンドラは岩の露頭に這い上り、見知った二つの顔を探した。だが目にしたのは破壊と撤退だけだった。今やコジレックとウラモグはその背後の大地に荒廃の峡谷を二本切り開きながら徘徊している。それらは彼女が放った炎の突風にひるむことはなかったが、もしも自分が十分に厄介な相手だと知られたなら、それらはただ振り返って自分を貪ってしまうだろうと実感できた。
荒廃の刈り跡が戦場を行き交い、落とし子の足跡を記していた。各種のエルドラージが人々を追い回していた。ゼンディカー人の多くはコジレックが覚醒し防波堤が破れた時に逃げ出していた。だが多くが貪られた。チャンドラが探し求める顔が見つかる気配はなかった。
そして、この全てを引き起こした元凶、あの悪魔の気配もなかった。
「ギデオン?」 彼女は叫んだ。一度、二度、三度。その度に声と熱意を増しながら。
カチカチと鳴る甲殻質の音が聞こえ、エルドラージの新たな群れが丘を越えて向かってきていると告げた。すぐにやって来るだろう、一人で相手をするには手に余る数が。
彼女は拳を握りしめるように目を閉じ、思った。『ジェイス?』 力一杯大きく。彼女はすぐさま馬鹿らしさを感じた。
返答はなかった。精神的にも、その他の手段でも。
近づいてくる群れをチャンドラは睨みつけた。不自然に多い膝と肘、関節にはまじろがない目がついていた。背後を一瞥すると、大地はエルドラージに破壊されたきらめく谷へと落ちこんでいた。彼女は背筋を伸ばし、足を広げて群れの前に立った。そして勢いよくゴーグルを目にはめ、首を傾げて音を鳴らした。
その姿勢を取った時、何か金属質のものを踏み、彼女は見下ろした。それは大型の丸盾で、泥の汚れに縁取られていた。彼女はエルドラージの前線を睨み付け、慎重に屈むと視線を外すことなくその盾を拾い上げた。凹んではいたが、それが何なのかはわかった。
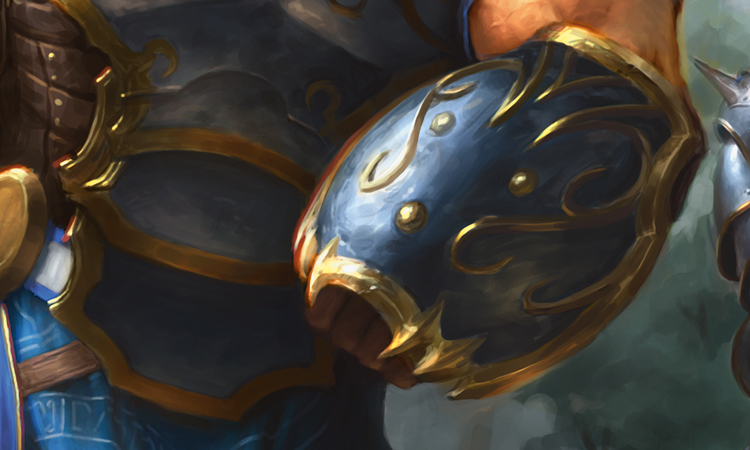
《ギデオンの密集軍》 アート:James Ryman
チャンドラは息をぐっと呑み込んだ。そしてその盾をしばし額に押し当て、刺すような痛みが喉にあった。彼女はその金属の丸盾を強く掴んだ、その端が歪むほどに。
どうしたわけか、両親の顔が脳裏に閃いた。こんな奇妙な時に何故彼らのことを考えたのかは全くわからなかった――ただ、二人はやって来た。心の中、彼らは歳をとっていなかった。二人は彼女が最後に見た時、まだカラデシュの子供だった頃に見た時のままだった。両親の最期については考えなかった。父が腹部にナイフを受けて膝をつく様も見なかった。燃える村の中、同じように端の焦げた母の肩掛けが泥の中に落ちていたのも見なかった。彼女が見たのは、親の目で自分を見てくれる二人だけだった。優しく、誇らしく。
彼女は歯を食いしばった。ゼンディカーに来たものの、完全に遅すぎた。
背後の峡谷の下から、女性の声が聞こえた。「そこの炎魔道士!」
彼女は振り向いた。
「それは司令官の?」 長身の、板金鎧をまとった女性がコジレックの荒廃の溝に屈んでいた。その隣の壁にはゼンディカー人の小集団が寄りかかっていた――ほとんどは斥候と歩兵で、多くが負傷していた。

《タズリ将軍》 アート:Chris Rahn
チャンドラは浸食するような群れにもう一度視線を向け、小走りに自分へと向かってくるそれらを見つめた。彼女は溝の中へと滑り降り、その盾を掲げた。「ギデオンのよね。あいつに何があったの?」
「悪魔と戦った」 先程の女性が答えた。「だが打ち負かされた。激しく」
チャンドラは肩を落とした。
「だが、あの人は生きている」 その女性は付け加えた。
「タズリ将軍――」 斥候の一人が口を開いた。
「生きている」 彼女は繰り返した。
「タズリ将軍」 チャンドラは言った。「私、急いであいつを見つけないと」
「それは私達もだ」 タズリはそう言って、包帯の一切れを歯で裂くと、コーの斥候の脚に巻き付けてきつく結んだ。「悪魔は彼と、もう二人を連れ去った」
「連れ去った? 何処へ?」
「ある洞窟へと向かった」 別の斥候の一人が言った。その瞳と牙から彼は吸血鬼だとわかった。彼は遠く、岩がちの絶壁の方角を指さした。「入口はあの付近、二つの峰の間の裂け目にある。空からだったら大した距離じゃない」
「ありがとう」 チャンドラは言って、丸盾を自身の腕に取り付けるときらめく鉱物を掴んで溝を登ろうとした。
「待ってくれ」 タズリが彼女の兵達へと顔を向けた。「私も怪我を負っている。今、救助隊を組めるような状態ではない」
チャンドラは何をどうするべきかを考えた。「私が助けに行く。ここで待ってて」
「エルドラージの群れはどうするつもりだ?」 タズリが尋ねた。
チャンドラは溝から顔を出して覗き見た。エルドラージは今もまっすぐに向かってきていた。「私が引きつけるから」
タズリは眉をひそめながら、チャンドラを上から下まで見た。そして重鎚を手にして頷いた。「ならばあなたの脱出を守ろう。感謝する」
「とにかくここにいて、隠れてて」
チャンドラはよじ登って溝から出た。彼女は立ち上がり、土埃を払い、そして全てを燃え上がらせた。
彼女の髪が炎と燃え、両手が熱く輝いた。筋肉を張りつめさせる、拳を放つような憤怒が四肢を温めた。その憤怒は馴染み深く快適で、彼女はまるで頼りになる友のようにそれに寄り添った。チャンドラは身体をよじり、その回転とともに周囲の大気が発火した。炎の竜巻が咆哮とともに現れ、渦を巻きながら前方へと駆け、エルドラージの群れを引き裂くと彼女はそれを追いかけた。エルドラージの破片が宙高くへ舞い上がり、そして煙を上げながら地面へと降り注いだ。
エルドラージの群れは耳障りな焦げ音を立て、タズリの兵達から彼女へと目標を変えた。チャンドラの鼓動が速まり、髪が更に熱く燃え上がった。
「それでいいわ。怪物ども、私こそマナと光に輝く標よ」
チャンドラはその絶壁へと足を向けた。髪の炎を旗印のようにたなびかせ、彼女は駆けた。
岩山を乗り越え、小さな裂け目を跳び越え、彼女は足を止めることなく背後を確認した。その場所から、コジレックの落とし子が落ち着かない様子で荒廃とともに進んでくる様子が見えた。群れの背後には荒廃の軌跡が広がっていた。かつてはゼンディカーの生きた大地であったものは、異様な四角形の模様と化していた。

《形状の管理人》 アート:Jason Felix
彼女は熱を保ったまま走り続け、猛り狂う炎の爆発を背後へと放った。時折彼女は旋回して炎を斉射し、数体のエルドラージを始末して残りを駆り立て、タズリ軍の負傷者からそれらを引き寄せ続けた。
しばし進んだ頃には、彼女は群れを引き離していた。それらの頭上に浮かぶ黒い板ははるか遠くほとんど見えなくなっており、彼女は大地の奇怪な狩り跡を越えて先へと進んだ。チャンドラは前方の二つの峰に集中した。
頂上に達すると、そこから地面は斜面となって下り、巨大な空洞へと続いていた。洞窟の口は尖った面晶体に囲まれており、それらの先端は全て洞窟内へと、深い底へと向いていた。
近づくと、道が塞がれているのがわかった。入口は最近築かれた固い殻で覆われており、そこには正方形の螺旋模様がぎらついていた。悪魔が皆をさらっていった洞窟、だがその玉虫色の殻が彼女の道を塞いでいた。
チャンドラははっと息を呑んだ。そのよじれた表面に、ばらばらの映像があった。彼女自身の顔ではなく、母と父のそれが。優しい瞳。口が動き、安心させるように頷き、だが二人の顔はその面に沿って奇妙に動き、何と言っているのかはわからなかった。彼女は二人へと近づき、だがその映像は無数の角度に壊れた。意図せず、彼女の思考はカラデシュ次元のあの村の外、母の焼け焦げた肩掛けへと向かった。そして父の申し訳なさそうな瞳、膝をつき、腹部から流れ出る血を押さえながら……
チャンドラは歯を食いしばり、拳を眼窩に押し付けた。そして拳を解いて目を開けた時、目にしたのは螺旋状の鏡写しになった自身だけだった。炎に縁どられ、両目は白熱した石炭のようだった。彼女は改めて障壁に向き直り、両手を一瞥した。それはもう子供の手ではなかった。両親が死んだ時の、プレインズウォーカーの灯が点火した時の手ではなかった。今、この両手は紅蓮術師の武器だった。彼女は両手の指を組んで握りしめ、一つの拳とした。そして両腕を掲げ、両手の周囲に白熱した火球を集中させた。彼女は歪んだ螺旋に向き直り、無言で、自身の反射を打ち砕いた。
殻は弾け飛んだ。破片の雲と土の塊が降り注いだ。彼女は自身が入れるほどの穴を拳で開けることを意図していたが、そうではなく障壁は完全に崩壊し、洞窟の口が大きく開いた。
洞窟の内部は更なる荒廃模様に刻まれていた。この大地の窪みは浸食され、枯渇され、変質させられていた。
チャンドラは思い出した。あの悪魔がコジレックへと呼びかけて覚醒させたのを、眼下の軍へと冷酷に笑っていたのを、世界の全てへと笑っていたのを。コジレックはここにはいない。ここは悪魔の巣。

《炎呼び、チャンドラ》 アート:Jason Rainville
怒りをしっかりと保ち、チャンドラは曲がりくねった小道を上り下りしながら進んだ。辺りを取り巻く、螺旋に刻まれた荒廃は彼女の炎の明かりを受け、異様に揺らめいた。
彼女は前方の部屋から深い、ゆっくりとした声が何かを詠唱しているのを聞いた。「……この惨めな世界にて、苦悶の生涯を」 その声は言っていた。「我が共有できる時間は僅かではあるが、世界にも劣らぬ痛みを保証しよう」
その部屋に駆け込むと、三人が魔術によって操り人形のように宙に吊るされている様子が見えた。ギデオンは、顎が胸に触れるほどに俯き、苦悶の皺がその額に刻まれていた。ジェイスは首を横倒しにし、顔はフードに覆われ隠されていた。そしてエルフの女性、その編んだ髪と腕は力なく垂れ下がり、瞼はわずかに開かれて、とはいえ緑色に映える目に見えている様子はなく、涙が頬から顎へと流れ下っていた。彼らの身体は衰弱の魔術に取り巻かれ、宙に揺れていた。その近くにはコジレック種のドローンが三、四体いて音を立てていたが、彼女に気付いてその刃のような足先を向ける様子はなかった。

《無情な処罰》 アート:Ryan Barger
「申し訳ない、招いた覚えは無いのだがな」 その悪魔、深く響く声の主が脇道から姿を現した。その身体はむき出しの黒い腱に鎧の一部が溶け合ったようで、継ぎ目からはその内部の、地獄のような熱が見えていた。瞳は憎悪と、どこか楽しむような興味深さとに燃えていた。
「私は自分で来たの。皆を放しなさいよ、じゃなきゃ死んでもらうわ」
「まだ仲間がいたとは」 悪魔が言った。
チャンドラは指を固く握りしめて拳を作り、自身と魔法とを敵へ放った。悪魔は前腕で彼女の炎攻撃を逸らし、傷ついた翼をドラゴンのように広げた。それは笑ったのか顔をしかめたのか、鋭く尖った歯列を見せつけた。
だがチャンドラも素早く立ち直り、旋回し、回転し、悪魔の目へと炎の投げ矢を続けざまに放った。
悪魔は翼で顔を覆い、最も強い攻撃に肩をすくめ、だが同時に呻き声を上げた。悪魔は片足を回転させ、チャンドラをその鉤爪で逆手打ちにした。
チャンドラは壁に叩きつけられ、石に頭を強打した。彼女は咳込み、うずくまって息をしようともがいた。近くでエルドラージのドローンがその鋏を向けたが、彼女へ向かってはこなかった。
彼女は血を吐き捨て、体勢を立て直すとともに炎を更に大きくすべく、苦痛で自身の魔術を焚き付けた。両手から炎の鞭が長く伸び、そして腕を引き、怒りを集中させた。拳で音を立てる熱が洞窟の大気を歪めた。
彼女は跳躍し、二発の炎を素早く放った。逸らされた。
だが跳躍からそのまま肉体的な攻撃へ移った。ギデオンの丸盾を鈍器として振り下ろし、それは悪魔の肩甲に音を立てた。
彼女は悪魔の脇に素早く立ち直り、旋回した。拳を二発、更に両の掌から音を立てて炎を発射した。それは悪魔の鉤爪に受け止められ、無へと潰された。
悪魔は殴りかかり、だがチャンドラの頭はその鉤爪の軌跡を避けた。それでも顔面に突き刺すような痛みが走るのを感じた。
酸を受けたように顔の皮膚が痛み、彼女は息をのんだ。炎が明滅し、彼女は炎を混ぜ込むように両手を振るった。
駄目! 消えたら駄目。消し炭になるまでこの悪魔を燃やしてやる。痛みは燃料。
チャンドラは両の拳を胸につけ、自身の核へと炎を一つに集中させた。そして彼女は自身の持つ全てを悪魔へと放った、閃光一つではなく流れ続ける炎の奔流を、激怒を全部込めて、沸き立つ大気の円錐の中へ――
シュウウゥゥ――
悪魔はその呪文の中を、彼女へと向かって歩いてきた。炎がその胸を焦がしたが、悪魔は腕を掲げてチャンドラの顎の下を掴み、喉首から持ち上げた。
――ごくり。
チャンドラの呪文が消えた。彼女はもがき、悪魔の鉤爪を掴み、その間に指を差し込んだ。「化け物」 息を詰まらせて彼女は言った。
牙をひらめかせ、悪魔は笑った。「これまで、我を止められたものなどない、小さな蝋燭よ。そしてそれはお前でもない」
彼女は悪魔の指を緩めようともがき、その手の皮膚に歯を立てた。悪魔は彼女を落とし、チャンドラは手と膝から崩れ落ち、だが無理やり顔を上げて呟いた。「私が止めてやる」 そして身体を支えるように脚へと命じたが、片足は応じずただ震えるだけだった。
悪魔はチャンドラの言葉を嘲るように首をかしげた。「そんなにも速く燃え尽きるというのにか、小さな蝋燭め。その後に何が残る?」 悪魔は呪文を唱え、それを鉤爪とともに突きつけてきた。
悪魔の魔術に裂かれ、チャンドラは身をよじった。それはまるで浸食のようで、年月が山を削るようで、だが忌まわしい一瞬に圧縮されていた。彼女は力が奪われるのを感じ、まるで生涯続く衰弱の病に突然掴まれたようだった。四肢のそれぞれがひどく重く感じた。
チャンドラの頭はとても必死に、落ちたがった。石の床に触れたがった。だが彼女はそうはさせなかった。両腕は震えながら、もろい柱のように身体を上へと支えた。視界が揺らぎ、洞窟はおぼろげな形と影へと化した。
洞窟が暗くなっていった。自身がちらつき、次第に陰っていくのを感じた。彼女は消えようとしていた。
駄目、消えたら駄目。
掌を洞窟の床にこすりつけ、彼女は両手に集中した。両手の炎が消えない限り、まだ生命は残っている。紅蓮術師の武器が残っている。
彼女はあの悪魔がすぐ側にまで近づくのを感じ、耳に暗い気配が触れた。「助ける気だとでも言うのか?」 尋ねるような響きがあった。「だが――理解できぬ。お前ごときに何ができるというのだ?」
チャンドラは目を開き続けようと、頭を上げ続けようと粘った。筋肉がその奮闘に震えた。
「ならば我はお前も同じく罰せねばならぬ。このような事などしたくはなかったのだが、やむを得まい。屈服するがよい」
チャンドラはゆっくりと顔を悪魔へと向けた。湿った睫毛の向こう、曇った視界越しにかろうじてそれが見えた。
悪魔の顔の斑が変化し、優しい、よく知ったものになった。
「私の可愛いチャンドラ」 はっきりとしないその顔が、父の声で言った。父の優しさと、温かさと、辛抱強さのある声で言った。
こんなものは欲しくなかった。会いたいなどとは思っていなかった。今はまだ。
「もういいんだよ、私のチャンドラ」 父はそう言い、チャンドラはひるんだ。「君はよくやった。横になっていいんだよ、その地面に」
チャンドラは父の顔のぼやけた輪郭を睨みつけた。重力が彼女の隅々までを押し付け、反抗を削いでいた。瞳に涙が溢れた。
「チャンドラ、私の愛しい娘」 顔が、今度は母の声で言った。愛のこもった、強い意思のある声で。「もう十分よ、チャンドラ、あなたは失敗してしまった。諦めていいのよ、倒れていいのよ」 チャンドラは震えた。肘がくじけた。「チャンドラ、あなたは彼らを失ったの。私達を失ったように」
チャンドラの身体は息を吐きたがった。胸から生命を咳と吐き出したがった、諦めたがった。彼女はその顔をあざ笑い、途切れない悪態を呟きたかった。だが力が出せなかった。世界が狭まった。
洞窟、顔、全てが光を失った。母の顔は消え去り、そして彼女はあの悪魔の、地獄のような両目の光が奇妙に浮かび上がるのを暗がりの中に見るだけだった。
彼女の炎は消えた。両手の炎は消えた。顔に髪がかかり、汗で貼りつくのを感じた。
『チャンドラ、』『ドロ……』 声があった。それは奇妙なこだまで、耳に囁かれたものではなかった――それは、どうしてか、囁きよりも近かった。『ドロー……ン、だ、チャ……ンドラ』
「お前個人の敗北と思わぬ方がいい」 悪魔が言った。その声は今や明瞭で、普段の冷淡な棘があった。「我はその者の弱点を引き出すことに長けているのでな」
『チャンドラ。あいつ……あいつの、エル……ドラージの、ドローン』 こだまする声が言った。それは頭痛のように響いた。それはまた、明らかに、両親のものとは異なっていた。『や……れ、あの、ドローンを』
ジェイス。ジェイスは――意識がある!
『ほ、ほ、ほの』 彼女の心の中、ジェイスの言葉は不明瞭だった。『ほの、炎、で』
ジェイスは――何とか、意識を保っている!
『でき、ない……』 チャンドラは鈍い思考で返答した。
『馬鹿言うな……』 ジェイスは彼女の脳内に言葉を成そうともがいた。チャンドラもまた、それを吸収するのは同じほどに困難だった。『馬鹿言うな、できる……くせに。起きろよ』
『嫌』 チャンドラは声を上げた。実際の声が自身の耳に奇妙に響いた。頭が重かった。涎を垂らしていたかもしれない。
「今のは何だ?」 悪魔が尋ねた。「処刑を待って欲しいなどという嘆願は止めるのだな。それは互いにとって侮辱であろう」
「言わ……ない……で」 チャンドラはかすれた声を出した。両手が拳となり、拳が炎を上げ、部屋を再び照らし出した。「言わないで」 そう繰り返し、彼女はよろめき揺れながら立ち上がった。
悪魔の姿が目の前で揺らいだ。悪魔は僅かにかぶりを振ったが、彼女はその中に喜びを見た。そして止めを刺そうと鉤爪の先に暗いエネルギーの核を呼び起こす様に、悪意を見た。「屈服せよ、小さな蝋燭よ」彼は言った。
「言わないで……私に、何かをしろ、とか」
チャンドラはその拳を泳がせ、悪魔は何事もなく首を傾げただけその攻撃を避けた。だが彼女が放った炎は意図した対象へと弧を描き、友人達の傍に潜んでいたエルドラージのドローンを直撃した。それらは震えながら燃え、小さな太陽に貪られて皮膚が乾いた音を立てた。

《食い荒らす炎》 アート:Svetlin Velinov
ギデオン、ジェイス、そしてエルフは折り重なるように地面に崩れ落ち、同時に三人とも姿を消した。
悪魔は束縛呪文を中断され、そして獲物の姿が消えて唸り声を上げた。彼はチャンドラへと向き直り、止めの一撃を放つべく身をのけぞらせた。
チャンドラはひるんだ、回避する力は、もしくは倒れるための力すら残っていなかった。だが一瞬の後、彼女はまだ生きて悪魔を見ていた。悪魔は腹立たしそうに暗黒の言葉を吐きながら、落ち着きなく辺りを見回していた。
『君は見えなくなってる、あいつの目には』 ジェイスの声が脳内に響いた。『今のところは』
悪魔が自分達を探す中、チャンドラは洞窟の壁に寄りかかってよろめき離れた。
『もう二人は生きてるの?』 チャンドラは心で尋ねた。
『かろうじて』
『あいつに一斉に攻撃する。私の合図で。いい?』
『無理だ! 俺達はとても戦える状態じゃないんだ。そんな力は残ってない』
チャンドラは拳を握りしめた。『私達がまだここにいるってばれるまでどのくらいあるの? やらなきゃ!』
『チャンドラ。俺達はずっと――苦しめられてたんだ。どのくらいか……長い時間だったと思う』
チャンドラはジェイスの思考の中にある不確かさが、あまりに簡単に苦しみを認める様が好みでなかった。悪魔は洞窟の床を蹴りつけ、踏み鳴らしていた。姿は見えず、とはいえ見事に消え失せたと考えるほどあの悪魔は愚かではなかった。
チャンドラは肩を怒らせた。炎が指先にちらつき、掌ほどの熱の球となった。『なら、なおさらあいつを倒さなきゃいけないでしょ』
ジェイスの躊躇した返答があった。『皆、休息が要る』
『ジェイス、私達はやる事があって来た。それは終わっていないんじゃないの』
『チャンドラ――』
チャンドラの炎が大きくなった。『違う?』
『チャンドラ、俺は無理だ――』
隠蔽呪文が破れ、一瞬にして全員が再び現れた。ジェイスとあのエルフの女性は、チャンドラが最後に見た時よりも部屋の遥か後方に下がっていた。二人とも意識はあるようだが、弱っていた。
ギデオンもまた現れた。悪魔は既に彼の首筋を掴み、足元から持ち上げていた。
「ギデオン!」
その悪魔はチャンドラに顔を向け、にやりと大きく歯を見せ、その内深くから沸き起こる笑い声を上げた。その響きは永劫の時をゼンディカーに囚われていた悪意から成り、そして遂にその仕返しができるという満足感があった。
「お前の友人共は感謝すべきだな、小さな蝋燭よ」 悪魔は言った。「希望をくれたからではなく――そう、実際には、お前がもたらした苦痛に。だがまたお前がいなければ、この者達の死を見届ける観客などいなかったであろう」 悪魔はギデオンの喉を握り締め、チャンドラは骨がひび割れる音を聞いた。
チャンドラは身動きできなかった。一歩でも動いたら、ただギデオンの死を早めるだけだとわかっていた。
だが彼女はギデオンがもがく様を見た。彼は手を悪魔のそれに差し込み、振り解こうとしていた。その弱った状態ですら、光の火花が彼の肉体を守っていた。彼女はジェイスの瞳が空色の煙を上げて輝くのを見た。彼は立ち続けることにすら苦労しながら、精神貫通呪文の類を唱えていた。そしてエルフの女性が起死回生の魔術を呼び起こし、その髪が後方へと揺れた。絡み合うマナの蔓が地面から弾けて彼女へと流れ込んだ。
まだ皆、生きてる。生きて、共に戦ってる。
チャンドラは地面を踏みしめた。炎の筋が足元から悪魔へと走り、悪魔が立つ床に火をつけた。ギデオンは悪魔の腕に肘鉄を入れ、胸を蹴り、力づくでその掌握を抜け出すと転がって離れた。そして次の瞬間、炎が悪魔を飲み込んだ。
悪魔は取り囲まれていた。ギデオンは今やスーラを放ち、ジェイスは呪文を構え、エルフの瞳はマナで輝いていた。
「行くぞ!」 ギデオンが叫び、チャンドラは彼の意図を正しく理解した。
閃く鞭の刃、エレメンタルの蔓、鋭い精神魔術、そしてチャンドラの腹の底からの炎の嵐。全員が悪魔へと、一斉に襲いかかった。

アート:Svetlin Velinov
悪魔は顔を歪め、防御のために二枚の翼で身体を包んだ。そして呪文を返そうとしたが、ジェイスの方が速かった。悪魔の呪文はかき消され、同時にギデオンが別の方向から切りつけた。悪魔はエルフへと突進したが、チャンドラが炎の柱でそれを遮った。
悪魔は翼を叩きつけ、チャンドラを壁まで飛ばしてジェイスの腹部に蹴りを入れた。だがギデオンが悪魔の脚にスーラの刃を絡ませて強く引き、ニッサの蔓とともに悪魔を地面に倒した。
チャンドラは腕にはめた丸盾を外しながら、ギデオンへと視線を向けた。彼は頷いた。彼女がその盾を宙へと放り投げると、ギデオンはそれを一息にはめた。そしてチャンドラが悪魔の兜の金属を軟らかく溶かした瞬間、彼はうつ伏せになった悪魔の頭蓋へとその金属盾を肘で叩きこんだ。ひび割れ音が響いた。
悪魔は咆哮を上げ、ギデオンを吹き飛ばすように立ち上がると自身の頭部をわずかにぐらつかせた。チャンドラは炎の斉射で悪魔を再び倒そうとしたが、苦痛が彼女の血管にうねった。
「上等だ」 悪魔はその牙を見せつけて言った。チャンドラの鼓動は鋭い痛みを送り出し、まるで針が血管を流れているかのようだった。
ギデオンは悪魔の胸へと肩をぶつけ、同時にジェイスは四人のジェイスとなって悪魔の心に穴を開けようとしていた。チャンドラはエルフの女性の手が腕に触れるのを感じた。そしてその接触に彼女の心臓は宥められ、その自然の律動を取り戻した。
「何か大きなものを準備して」 そのエルフが囁いた。「合図するから」 そして彼女は生命魔術をうねらせて悪魔を攻撃した。
何体もの幻影のジェイスに、ギデオンの鋭い肉体的攻撃に、そしてエルフの容赦ない野生の魔術に、悪魔は攻撃よりも更なる回避を強いられていた。顔を歪め、鉤爪で頭を押さえながら、肘と翼で物理的攻撃を精一杯防御する間に、ジェイスの魔術がその精神を貫いた。
悪魔が気をとられている間に、チャンドラは小さな炎の竜巻を宙に作り出した。彼女はそれとともに回転し、炎を増し、力を築きながら成長させた。彼女はその内に浸され、それに貪られ、その一部となって熱風の螺旋とともに踊った。
『いいか?』 ジェイスの声が脳裏に響いた。
「いつでも!」 チャンドラは大きく叫んだ。
三人は同時に離れ、チャンドラから悪魔へと続く道をあけた。彼女は叫び一つとともに竜巻を放ち、それは部屋を横切り、悪魔に激突して壁まで吹き飛ばした。
そしてチャンドラの呪文が散った。悪魔は焼け焦げ、煙を上げ、肩を部屋の壁で支えていた。その燃えさかる地獄の目が彼らを、一人また一人と見た。「よかろう」 悪魔は言った。「よかろう。お前達は我を打倒すべく力を費やし、達成した。だが我にかまけている間に、お前達はゼンディカーを苦しめていた。つまりお前達の、敗北は、明白だ」
チャンドラと三人は互いの顔を見合わせた。
「約束しよう」 悪魔は低い唸り声で言った。「我はあらゆる次元を渡り、あらゆる惨めな世界を一掃し、やがてお前達の心得違いの生涯に相応しい罰をもたらすと」
大気が折り重なり、悪魔を飲み込み、そしてその姿は消えた。
チャンドラは三人とともに立っていた。ジェイスの髪は少年のように乱れ、普段の彼の神秘的な雰囲気は無かった。ギデオンは痛めつけられたようで、だが彼は歯を見せ、頬の髭を歪ませて笑った。
「来てくれると思っていた」
「断ったのに?」 チャンドラは眉をひそめながら言った。
「それでも思っていた」
「私は、ニッサ」 そのエルフが言った。
「チャンドラよ」 彼女も、掌を差し出して言った。
ニッサはそれを両手で包み込んだ。彼女の指は柔らかく、緑色に染まった瞳は苔むした井戸のように深かった。「ありがとう」
共鳴するような、騒々しい、さえずり音が四人の耳に届いた。部屋へと続く通路を振り返ると、エルドラージの群れ、チャンドラが海門から誘い出したものと同じ群れが、足音を鳴らして部屋へ侵入し、あらゆる表面に這い登った。
チャンドラは落とし子らを、続けて三人を見た。四つの頷きがあった。そして調和する演奏のように、四つの呪文が生命を得て弾けた。
(Tr. Mayuko Wakatsuki / TSV Yohei Mori)

