太陽の向こう側
ファートリ

ファートリ、八歳当時のこと。
午後の陽光に塵の粒が舞い降り、薄暗いトカートリの中で訓練場を橙色の輝きで照らしていた。石造りの床板には彼女と共にもう十人ほどの子供らが座しており、小さな両手で木製の訓練用武器を握りしめていた。彼女は千もの疑問を尋ねたいと思う程には年若く、だが適切な時まで待つべきとわかる程には成長していた。だからこそ彼女は小さな両手で足指を掴んで座り、太陽帝国の神官がその長話を中断する時を待っていた。その男性は若き見習い戦士らへと太陽の三相を講義しており、その話し方はファートリが聞いてきた中でも想像を絶するほど退屈極まりないものだった。それらの物語はすべて彼女の頭に入っていた。物語は大好きだった。
「太陽の向こうには何があるんですか?」 彼女は思わず口にした。
その神官は瞬きをした。
ファートリは両手で足を掴み、確固たる意志で目を合わせ続けた。
神官は溜息をついた。「ファートリ、いつの日かあなたは自分の手に刃を持って戦い、太陽の力と語るのでしょう。太陽の向こうに何があるのかは、問題ではありません」
ファートリは他の誰かが自分の未来について言及するのが嫌だった。語りに秀でていることから彼女は神官とシャーマンから特別な訓練を受けていたが、他の戦士見習いらと共に学ぶ時間を過ごすことができなかったことは彼女を苛立たせていた。
「けど、太陽の向こうに何があるのか知りたいんです」 彼女はそう言って、可能な限り不満を純粋な好奇心で隠そうと努めた。
他の戦士見習いらは苛立ちと共に見つめていた。ファートリは顔を赤らめた。
「ファートリは、大きくなったら僕達の戦場詩人になるんです」 八歳の少年としては大胆な声で、従弟のインティが言った。「太陽の向こうについての物語はないんですか?」
残りの子供らも同意に頷いた。
その神官は少々狼狽したようだった。彼は助力を求めて戦闘教官を見たが、わずかに肩をすくめられただけだった。彼は眉をひそめてファートリと目を合わせた。
「太陽の向こうについての話は存在しません」
他の若き戦士らは一斉に失望の声を上げた。
神官は溜息をついた。「皆さんが今見ることのできるものに集中して下さい。成した物事を誇るのです。未知のものに時間を無駄にしないように」
ファートリは混乱した。「でも、本気で知りたいんです」
神官は戦闘教官を見た。その様子は、子供達に囲まれて退屈した大人が降参するそれだった。
戦闘教官は熟練の権威をもって手を叩き、若き戦士らへと告げた。「訓練生! 二人組になって型の練習に入りなさい。最初に負かされた者に片付けをして頂きますよ」
他の子供らは急ぎ立ち上がると訓練場の奥へと駆けた、黙り続けていることを強いられる講義の間よりもずっと興奮して喋りながら。ファートリは座る場所に根を下ろしたように残り、その神官を熱い視線で見つめていた。
神官は溜息をつき、どこか親のような怒りとともに彼女を見た。「ファートリ、皆が貴女には詩の才能を感じています。太陽帝国の戦場詩人になるのであれば、その時は、貴女の言葉が真実となるのです」
訳がわからず、少女は眉をひそめた。「私が作っていいってことですか?」
「いいえ。物語を伝えるということは、誰かの真実を語るということです。彼らの経験をよく知り、そうすることで彼らとあなたで共有することがあなたの義務です。私達誰もが、貴女が語るものの活躍を決して忘れないように」 その神官は力強い意思で続けた。「戦士として帝国のために生きるなら、いずれはっきりとわかるでしょう。貴女は山頂から叫ぶただ一つの声でなければなりません。帝国の声、その全ての声です」
ファートリは唇を噛んだ。自分は山頂からの声になりたいのか、それもわからなかった。彼女は神官と戦闘教官を、そして叔母と従弟インティを思った。そして帝国のあらゆる人々を思った。いつの日か、自分が語る真実を皆は聞いてくれるのだろうか。
大切なのは帝国、彼女はそう自らに言い聞かせた。太陽の向こうに何があるかじゃない。

アングラスとファートリはとある空き地に立ち、足元が激しく揺れる中で転ぶまいと腰を低くした。二人はオラーズカの黄金の尖塔が、眼下の谷の梢から遥かに高く伸びゆくのを見つめた。その尖塔群が都を引き上げているようで、上昇しながら木々を倒しては莫大な量の土や岩を崩していった。
ファートリは息を止めていた。
都は想像を遥かに超える美しさだった……そして幻視で見たあの都市とは似ても似つかなかった。
地面の揺れは収まり、彼女は涙を払った。目の前にあった。そびえ立つアーチと彫刻は家ほども大きく、迷宮のような建造物にはかつて目にしたこともない程の黄金が飾られていた。その地は魔力に脈打っているようだった。今なお二人の場所からは結構な距離があり、大まかに徒歩で半日ほどだろうか。だがこの数世紀の間の太陽帝国の誰よりも、オラーズカに近づいているのだ。
左に立つミノタウルスは興奮に鼻息を鳴らした。「やっとか」 決然とそして気短に、彼は足を踏み鳴らして下り坂を駆けはじめた。
ファートリは自身の任務を思い出し、追い付こうと駆けた。
心がはやっていた。都を見つけた、けれど戻らねばならないだろうか? 中に分け入って不滅の太陽を見つけるのは憚られるだろうか? ファートリは喜びを抑えようとしたが無益だった――物言わぬ笑みが顔に広がっていた。
「つまりお前は黄金の都を見つけてこいって言われたのか? 使い走りの小娘みたいに」 アングラスが嘲った。
ファートリは現実に引き戻された。彼女は笑みを抑え込んだ。「皇帝陛下が任務を下さったのです。黄金の都は我らが祖先の故郷、私達こそイクサランの正当なる支配者なのです」
木々が次第に密集してきた。頭上で枝が交差し、密林の梢の影を二人が歩くと、昆虫と鳥の声がファートリの耳に満ちた。
アングラスはファートリを見つめた。「で、お前は何を貰えるんだ?」
「正当な地位を。私は幼い頃から戦場詩人になるべく鍛えられてきたのです」
アングラスは鼻を鳴らした。
ファートリは眉をひそめた。「何ですか?」
「地位は自由をくれんよ」
彼は鎖を放って道を塞ぐ一本の枝を引いた。ファートリは苛立った。「あなたにはわかりません。我らが民の勝利を伝えることこそ、私の義務となるのです」
アングラスは肩越しに彼女を振り返った。「そうするために地位が要るのか? 蟻みたいな考え方をする奴だ」
ファートリは大いに侮辱されたと感じたが、口を閉ざしたままでいた。この男がいかに怒りやすいかを彼女は身を持って知っており、この新しくも奇妙な同行者をあえて挑発し、攻撃を受ける気はなかった。
「『蟻みたいな考え方』とはいかなる意味ですか?」 彼女は努めて穏やかに尋ねた。
アングラスは肩を回し、音を鳴らしながら雄牛の頭部を左右に揺らした。「お前はただ蟻塚のてっぺんに登りたがってるだけなんだよ、そしてその眺めで満足するってな」
「太陽帝国を蟻塚だと?」
ミノタウルスは笑い声を上げた。それは低くかすれた雑音で、首長竜の騒々しい声を思わせた。「蟻塚の蟻だよ。太陽帝国、川守りとトレゾンも、この次元の馬鹿ども全てがな」
「そうですか、少なくともあなたが私達全てを侮辱していることは判りました」
アングラスは頭上へ手を伸ばし、巨大な花の茎を脇に引いてファートリにその下を通過させた。「俺らは何よりも自由を重んじる。プレインズウォーカーはそのためには殺しだってする。全員がそれを理解している」 真剣な表情だった。「お前はたかがうろ覚えの物語に自分を縛り付けてるだけだ」
「たかが物語と言いました?」 彼女は声を荒げた。「私の何がわかるのですか、私がずっと何のために生きてきたのか! 私はずっと、相応しい言葉を見つけることに身を捧げてきたのです。私達全員の思いを伝え、太陽帝国の歴史を真実と誇りで守ることです」
その言葉にミノタウルスは含み笑いをした。ファートリは舌を噛んだ。彼はミノタウルスの顔が可能な限りに笑みを浮かべた。「なら川守りの歴史はどうなんだ? あいつらの歴史は覚えておかなくていいのか?」
「それは……確かに。記憶しておくべきだと考えます。けれど戦場詩人は彼らの歴史を学んではいない……」
「お前らはどっちの歴史が強いかを決めるために殺し合ってる。上に立つのは誰かを決めるために言い合いをしてる、けれど誰も本当の意味では自由じゃねえ。小娘よ、お前が正しいって誰が言えるんだ?」
ファートリは葛藤を覚えた。
これほどまでに自分へと無遠慮に話すアングラスは何者なのだろうか。この男は粗野でそっけないが、その言葉が真実なのだとしたら、自分が想像したこともなかった物事を知っているということになる。こことは異なる世界から来たというなら、その世界での物事の仕組みは異なるのかもしれない。ファートリは子供のような衝動を感じた。しつこく熱烈に答えをせがみ、自身の重要性を厚かましく主張する。もっとよく知るべきだという含蓄は好きでなかった。正直、一体どうすればいい? 自分がこれまでに人生に歩いてきた道の両脇には、視界の果てよりも遥かに高い壁が続いていた。
震えがひとつ肩を横切った。
目の前でアングラスが立ち止まった。彼はファートリを振り返った。
「お前も感じたか?」
ファートリは頷いた。小さな疼きがひとつ首筋を駆け下り、密林の暑さにもかかわらず彼女は震えた。
アングラスの耳がひねられた。「真似をしてみろ」
天の太陽よ、何という無礼な男でしょうか。ファートリは苛立ちとともに思った。
ミノタウルスは動きを止め、ファートリは目の前に突然の熱気を感じた。呪文を唱えているのだ。いや、何か違う。暖かな石炭のそれに似た輝きがアングラスの身体を内から照らし、彼女は悟った。以前一度だけ試した、あの通りにやれと。
ファートリは集中した。太陽の向こう側をどう見るか、思い出そうとした。
それはすぐにやって来た。その感覚は彼女の皮膚に震えを走らせ、胸で引っかかった。怖くもあり慣れたものでもあった。まるで背中から回転跳びを試みるような、もしくは足のつかない場所で泳ぐような。見つめる中、自身の皮膚が真昼の眩しい光に輝いた。視界が揺れ、彼女は前のめりになって分かたれた世界へ入った。色と光の眩しい嵐、今やそれは慣れたもので、アングラスは前方にいた。歩みを進め、一つの出口を目指していた。
密林から離れて無へと踏み出すような感覚があった。身体は支えられていたが、ここの物質には重さも目的もなかった。彼女は両脇に青色の流れを見た、そして一歩ごとが感じたことのない力に震えていた。ここで時は無意味だった。
アングラスの目の前には門があり、彼はその先を見るよう示した。そのミノタウルスは今も使い込まれた暖炉のような魔法的効果を維持していた。そしてファートリは悟った、今の自分は眩しすぎてアングラスは直視できないのだと。
宙に裂かれた窓から、彼女はその先を見た。
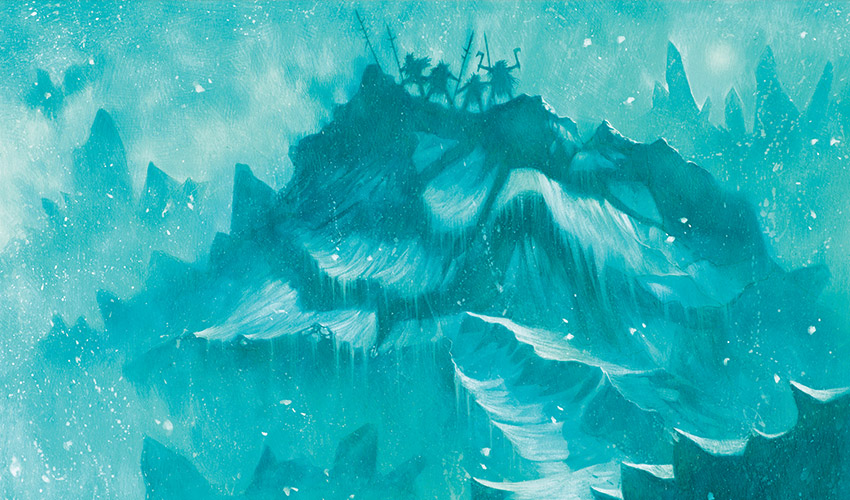
その寒さはかつて感じたことのないものだった。山々は渦巻く雲まで届き、白い破片が重苦しい空から静かに舞い降りていた。
その風景にファートリは目を奪われた。彼女は前へのり出し、そして直ちに強引に引き戻された。
ファートリは空間と色彩を引き裂いて現実の構造へと帰ってきた。彼女は密林の冷たい湿気と湿った土の悪臭へ、背中からあおむけに落下した。
今や見知った内側に円を持つ三角形がその頭上に揺らめいていた。
アングラスは近くに立っていた。その魔法的排除には彼女よりも慣れた様子で、衝撃を受け止めていた。彼もまた頭上に輝く三角形を浮かべてファートリを見下ろしていた。その牛の瞳は「言っただろう」と告げているように思えた。
彼は低くうめいた。「俺らをこの次元に閉じ込めてるものはすぐそこだ」
ファートリは震える息を吐き出した。「あの場所は何?」
「カルドハイムだ」 アングラスは力強く言った。「こことは違う次元。今なら俺の言ってることはわかるか?」
ファートリはかぶりを振った。
アングラスは鼻を鳴らした。「自分が捕われてることを自覚して初めて、自由が始まるもんだ」
昼は次第に夕となり、ファートリとアングラスは隣り合って進んだ。ファートリの案内によって雨林を進むのは容易で、二人の足取りは速かった。都へ近づくごとに、周囲は更に変化した。木々の葉は黄金にきらめき、地面には深い裂け目が開き、それは更に深い黄金の小道へ続いていた。
次第に増す寒気にファートリは不安を覚えた。不滅の太陽がプレインズウォーカーの魔法に関係しているのでは、そんなアングラスの呟きに彼女は溜息をついた。思い思いの勢力が、思い思いに不滅の太陽を考えている。その全てが真実などというのはありえない。ふと、ファートリはアングラスへ尋ねた。この次元を離れられたらまず何処へ行きたいのかと。「娘らの所へ」、それが彼の簡潔な返答だった。
ファートリは彼の脆さに触れた気がした。「最後に会われてからどのくらいになるのですか?」
「十四年だ」 アングラスは低い声で言い、一瞬ファートリは心を動かされた。同情を口にしようとしたが、それは続いたアングラスの言葉に遮られた。「あいつら、お前の皇帝の血を大喜びで飲んじまうだろうよ、馬鹿野郎」
ファートリをこの世界から投げ出す何かがあるとしたら、それはアングラスの人格かもしれない。
二人は地面から現れた建造物までやって来た。それは質素な規模の神殿だった。横長の意匠が一つ、その前面に飾られていた――一匹の蝙蝠、その恐ろしい表情が縞模様の岩に刻まれていた。構造の劣化具合から、これはオラーズカの一部ではなくその近くに建てられた墳墓だとファートリは推測した。その墳墓は時代外れで、密林の中で奇妙な程に場違いに思えた。目立っていた。落ち着かなかった。
ファートリは歩みを緩め、立ち止まった。
彼女はとある昔話を思い出した。ほとんどの者は長く忘れてしまったもの、だが彼女は覚えていた。太陽帝国の戦場詩人は忘れていなかった。
「東の蝙蝠」 彼女は囁いた。
アングラスの耳がぴくりと動いた。「何の蝙蝠だって?」
ファートリは目の前の建築物を指し示した。それは蔓に覆われ時に摩耗し、前面の扉は乱されて半開きになっていた。「伝説があります、東の蝙蝠がアクロゾズに出会い……」
ミノタウルスは不愉快そうにうめいた。「その蝙蝠は伝説でどうなった?」
「魔法の眠りについたと」
ファートリは入口へ向かい、その神殿を調査しようかとぼんやり考えた。オラーズカが目覚めたとあれば、あるいはこの場所もまた……
「何をしてる!?」 アングラスが呼びかけた。
ファートリは笑みを浮かべて思った。私は太陽の向こう側にあるものを見ている。
彼女は神殿の入口に近づき、だが青白い手が内部から伸ばされると驚いてひるんだ。そして女性の手が分厚い黄金の扉を掴むと、ファートリは凍りついた。
即座にファートリは無言で呪文を唱え、近くの恐竜を呼び出した。呼びかけが伝わって鼓動が高鳴り、彼女はその手が扉を持ち上げて神殿の入口から除ける様を見つめた。
その人物が光の中へ歩み出ると、ファートリの恐怖は消え去った。彼女は畏敬とともに唖然とした。

吸血鬼の女性、それは疑いようもなく、その長い巻き髪と若々しい顔は同族の危険な性質を示していた。ファートリよりもやや低いほどの平均的な上背、だが高貴な者の物腰をまとっていた。
ファートリの息が胸で詰まった。彼女はアングラスが相手を殺そうと突撃してくることを予想し、一瞥した。だが彼もまた同様に凍り付いていた。
「聖エレンダだな」 アングラスの声は冷ややかだった。「吸血鬼どもがいつも喋っている」
アングラスが自分の知らない話を知っていたことに、ファートリは僅かに狼狽した。
その女性の動きは慎重かつゆっくりとしていた。彼女は唇に笑みを浮かべてアングラスを、そしてファートリを見た。
「遂にオラーズカが目覚めました」
その声は軽やかで穏やかだった。静寂を破る鈴の音のような。
ファートリは畏れを抑え、刃の柄を握りしめた。近くから低い咆哮が届き、ファートリは召喚したばかりの恐竜へ臨戦状態での待機を命じた。伝説というものがいかにして生まれるかを彼女は知っていた。物語がどのように始まり、発展していくかを誰よりも知っていた。ほぼ全ての物語が真実から生まれる。ファートリは素早く推理した、東の蝙蝠の伝説は数世紀前、まさにこの実在する吸血鬼から始まったのだと。
吸血鬼の態度は穏やかなままだった。その女性はファートリと目を合わせ、その表情はまさしく静寂の精髄と言ってよかった。
「武器など構えて、いかがなされました?」 女性は純粋な好奇心から尋ねた。
ファートリは顔をしかめた。「薄暮の軍団に都を渡すわけにはいきません。お前達侵略者には死よりも悪い運命を被って頂きます!」
吸血鬼の額に皺が寄せられた。その唇が開かれ、彼女は傷ついたような表情を浮かべた。その声は穏やかで非現実的だった。「我々が侵略者となったのですか?」
「私達がお前と薄暮の軍団をどう語るか、聞かせてあげましょう!」
ファートリの怒りが爆発した。彼女はほんの二年前に記した物語を、苦々しい言い回しを加えて詠じた。
影を纏いて東より訪れ
時に失われし宝物を求める者よ
薔薇の棘、アダント、我らが南方を汚す血の汚れ
生命を飲み干し、名を貪る者よ
アングラスは怒りとじれったさに震えていた。「ファートリ、お喋りをしてる暇はない。不滅の太陽を手に入れてこの世界から出るぞ」
エレンダはアングラスを無視した。その穏やかな物腰は静かな怒りに変わった。彼女は目に見えて張りつめ、その黄金の瞳はファートリとアングラスを行き来した。「薄暮の軍団は何を求めてここへ来たのです?」
ファートリは辛辣に言葉を吐き出した。「奪うために。あいつらが何のために来たと思っていたのですか?」
「我らのものを取り戻すためです」 エレンダは慎重な、だが怒りの声色で返答した。「そして平和のうちに立ち去るため。それが我らの至聖なる任務です」
アングラスが低くうめいた。「それをお前らのお仲間全員に言ってやれ。ファートリ、行くぞ」
ファートリはそれを無視し、刃の柄を強く握りしめた。聖エレンダは密林の猫のように張りつめて立っていた。流れるような物腰と細く尖った鉤爪が、瞬時に攻撃へと移れるように。
吸血鬼は牙をむき出しにした。「私は教会に、この責務を負う儀式を伝えておきました。彼らはそれを用いて……侵略者になったというのですか?」
ファートリは睨み付けた。「どういうつもりでそれを残したと?」
「慎みを学ぶためのものでした」
ファートリは唖然とした。薄暮の軍団が? 慎み?
「そして我ら全てにとっての救いを求めるために」 エレンダは続けた。「彼らに対面し、忘れられてしまったものを伝えねばなりません」
エレンダは背筋を伸ばし、大きな影がその顔にかかった。彼女は踏み出し、ファートリとアングラスを過ぎ、そして宙の暗い裂け目へ姿を消した。
一瞬おいて陽光が戻り、頭上の梢からの琥珀色の木漏れ日が差し、そして吸血鬼は去っていた。
ファートリは瞬きをし、エレンダの行き先を探ろうとした。「出てきなさい!」 彼女は溜息とともに憤慨した。
「もういいか!?」 アングラスは立腹とともに叫び、傍の木をその鎖で叩いた。その衝撃に木は折れて倒れ、何十匹もの小動物と昆虫が逃げ出した。
ファートリはミノタウルスを睨み付けた。「どういうつもりですか! 私達の居場所を知られるだけですよ!」
「お前はよそ見をしてばっかりなんだよ! あの吸血鬼と話したせいで時間を無駄にした!」
「あの女性は生きた聖者で、私は思う所をぶつけてやりたかったんです!」
「お前の話なんざどうでもいい、これ以上時間を無駄にできるか!」
アングラスは一本の鎖をファートリの顔面へ放ち、彼女はかろうじて避けたがその熱は頬を焼いた。
反射神経に優れ、鍛錬された彼女は跳びのくことができた。そして体勢を整え、凄まじい速度で刃を抜き、だが反撃しようとアングラスへ集中できた時には彼は既に背を向け、オラーズカの尖塔を目指して驚くほど遠くを駆けていた。
アングラス、無礼で度し難く苛立たしいアングラスが、自分よりも先に辿り着こうとしていた。
そしてファートリはそれを許すつもりはなかった。
ジェイス
ジェイスの内面は感情に浸されていた。息詰まる力に握り潰され、一直線に固定され、そして風の中へと散った。消耗が苦しみを語り始めたのではなかった。
彼は慎重に両足を前へ出しつつ、そして背後にヴラスカの存在を大いに感じながら、オラーズカへの階段を登っていた。あまりの疲労に、自らを制御できないことを恥じる余裕はなかった。身体の不調は手に負えない熱でわかる。テレパスの精神の不調は何でわかる? 爆発。精神魔術の暴力的な流出。
思考の大半は今も流れ込む記憶の洪水を分類し吟味すべく懸命に働いていた。心の井戸は今や計り知れないほど深く、周囲の世界のように多彩で果てがなかった。何かに集中する必要があった。そうしなければ、またしても悲嘆に圧倒されてしまうのは確かだった。
(記憶の閃き。十二歳の自分が、寝室の隅にうずくまり、毛布にくるまって涙を拭っている。一家のペットが死んだ日だ)
記憶はまだ流れこんでおり、だが今は留めておくことができた。もう精神の流出はなかった。ヴラスカはもう見ない(良かった)。見られた量の多さには当惑したが、同時に多くをわかってくれた事には大いに安らぎを感じた。
そう、彼女も苦しんできたのだ。だからこそ。
頭を使わずに何かを反復する時間があるのがありがたかった。心を整頓することに集中できた。都を目指して一歩、一歩、また続く一歩。左足。右足。左足。
固い黄金の長い階段は露出したばかりの基盤岩に張り付いており、何度も曲がりくねって伸びていた。すぐ後ろのヴラスカと共に登りながら、ジェイスはその岩に太い黄金の鉱脈を見た。まるで誰かの宝物で足を拭っているかのようで、一歩ごとに不安が増した。黄金は伸びやすく柔らかい。この都には長年の摩耗と損耗を魔法的に防ぐ何かがあったのだろうか。
黄金に思いを馳せたことで、未だ解放される時を待つ辛い記憶、その微かな暗示が戻ってきた。
(金色の鱗。砂岩。熱。唇と目と喉に感じる粗い砂。傷つき絶望した友。自分はあるドラゴンの精神に割り込もうとしていた。計画を察して、危害を止めて、そして僅かな一瞬、成し遂げた、目的を見て、最終段階を――)
その記憶を解析するには手際を要した。ジェイスは詳細を思い出せないかと観察した。
(ドラゴンは俺の存在に気付いていた、そして心を読まれることに応酬しようとした。けれどそのドラゴンが侵入しようとした時、何かが介入して、そして全てが暗転した)
上手くいかない。ジェイスは眉をひそめ、苛立った。彼は隙間の欠片を思い出そうとした。金色のドラゴンの名を知りたかった。もどかしくも一つに戻したかった。そうすれば全てがわかるのに。
だが一体のドラゴンから、彼はもう一体を思い出した。
(巨大な洞窟の中、ウギンが翼を広げている。「幸運を祈る、ジェイス・ベレレンよ」、それは別れの言葉だった。銀の長い尾をその身体に巻きつけながら)
ジェイスは瞬きをした。ウギン。その名は苦もなく出てきた、だがこの記憶の感触は奇妙だった。心でその会話を感じ、その端に親指を触れ、アルハマレットが何年も前に記憶を翻弄した時と同じ注意深さでその両脇を詳細に調べた。自分より年長で秀でた者についての記憶は、絶対に信頼するな。彼は顔をしかめた。その辛い経験を覚えていなかったら、調べようなどとは決して思わなかっただろう。
あった。髪の毛一本ほどの線が、引っかかるのを待っている。あの精霊龍が気付かれることなく埋め込んだ、巧妙に隠された精神魔術の賢い一片。その呪文が残していたのは単純な命令だった。もし何者かが記憶を読もうとしてこのウギンとの遭遇を発見したなら、その記憶は隠されるとともに直ちにプレインズウォークで強制的に離れる。ここへ。イクサランへ。
ジェイスは狼狽した。何故ウギンは俺が持つ記憶を隠す? 何故俺をよりによってここに? 俺は寄せ餌になるってことなのか?
……そして俺は記憶を消される前に、金色のドラゴンの精神に何を見つけたのだろう?
彼は精霊龍と金色のドラゴン両方の記憶を脇に除け、時間が許す時に熟考しようと結論づけた。
彼とヴラスカは階段を登りきった。果てのないような登攀に身体は火照り心臓は早鐘を打っていた。ヴラスカは黄金の柱で身体を支えて脚の腱を伸ばした。
二人は巨大な広場の端に立っており、その果てには巨大な一本の塔がそびえていた。そして全面を黄金の通路また通路、きらめく迷路に取り囲まれていた。
「他の道を来たらここで立ち往生だっただろうね」 腰に下げた水袋から一口飲み、ヴラスカは言った。「滝を落ちてくれてありがとうよ」
「どういたしまして」 ジェイスはそっけなく言った。「必要があれば、向こう側にだって飛んでいってやりますから」
中央の塔が視界を圧倒していた。ヴラスカは魔学コンパスを取り出すと、それはまっすぐに前方を指していた。彼女はコンパスを仕舞うとジェイスを見た。「私らの目指すものはあそこにある。幻影を作ってこの場所を皆に知らせてくれるか?」
ジェイスは聞いていなかった。精神的な存在が彼の注意をひいていた。ジェイスは心が発する雑音の方角へ首をかしげた。
「どうした?」 ヴラスカが小声で尋ねた。
「大きいです」
ジェイスは幻影をうねらせて自分達を覆った。今やそれは、イクサランへやって来た当時よりもどこか簡単だった。
(また別の記憶:十代の自分。寝台で遅くまで起きていて、学習灯の下で何時間もかけて記述と技術を記憶している。外からは魔道士輪の稼働音。ミラードの手順。状況別操作法。トリシエンの法則。名前、技術、精神的処置の実行方法、息をするように容易くなるまで何度も何度も)
ヴラスカは登ってきたばかりの階段の方を見て唖然とした。
とてつもなく巨大な恐竜の頭部が都に迫っていた。

それは翼を広げて宙へ舞い上がった。翼の羽ばたき一つごとに木々は揺れ、これほど巨大な生物が飛べることにジェイスは驚嘆した。それは獲物を探すように油断なく上空へ向かい、だがジェイスは動かなかった。彼とヴラスカは幻影の下、安全だった。
その時、ジェイスは自身の内なる変化に気付いた。ゼンディカーとイニストラードとラヴニカのジェイスは自らに対する神経質な活力があり、常に退屈していて悲惨なほどに内省的、精神の地平線に居座る欠けた記憶の裂け目を常に意識していた。過去のないジェイスは今という時に生き、油断なく、状況に関わらず目の前に来るものを楽観的に歓迎していた。それぞれがどのようなものかを彼は思い返し、だが後者の方がずっと自然だと悟った。一瞬にも満たない間、ジェイスは自らに驚き、ここイクサランでの真剣な自分は、作られたものでも記憶喪失の状態が成せた何かでもなかったのだと実感した。ずっと自分であったもの。ただ忘れていただけのもの。
(ある記憶。母親が、日中の仕事から帰宅した。癒し手の仕事着を纏い、開いた窓から遠くの嵐を見ている。片手にはコーヒーの器、疲れた顔に小さな笑みを。ブリキの屋根に大粒の雨音。大気は湿ったコンクリートと我が家の匂い)
ジェイスは笑みを浮かべた。母親のことを思い出せるのは嬉しかった。
生きていてくれるといいな、彼は密かにそう思った。
「いなくなったぞ」 ヴラスカはそう言って呪文を破った。
ジェイスは我に返り、そして幻影を解いた。
「その幻影を作る技、前より速くなったな」
ジェイスは硬い笑みで頷いた。「先生に教えられた技を思い出したんです。子供の頃に沢山学びました、それ以前に自分で学んできたよりも」
「つまり、子供の頃のお前は大人の今よりも上手かったのか?」
「それに、今の俺には両方の知識があります。何だか……奇妙です」
ヴラスカはジェイスの目を見つめた。「お前は凄い。それはわかってるだろ?」
ジェイスは彼女へ笑みを返し、頬が熱くなるのを感じた。「全力を尽くしますよ」
「ああ、お前の全力は凄いからな」 ヴラスカはそう言って中央の塔へと向き直り、その裏側と思しき巨大な門へ近づいた。
凄い、リリアナからそう言われたことは一度もなかった。
リリアナなら冷やかしただろう。軽蔑的な冗談を言って、目をそらして、目立ちたがりだと言っただろう。何日も会話を避けるだろう。クロコダイルの顎で悪魔の身体を貪って、その肉が引き裂かれる音に笑い声を上げるだろう。そんなこと全てをやってのける、けれど俺のことを凄いなんて絶対に言わないのだろう。
ジェイスは前を歩くヴラスカに追い付き、二人は中央の塔へ近づいた。彼女は魔学コンパスを取り出した――その針は目の前にそびえる塔、その裏口をまっすぐに示していた。
頭上の空が心をかき乱すような黒に変わり、塔の頂上を取り囲むように煙が渦巻いた。ジェイスとヴラスカは懸念の表情を見合わせた。
「吸血鬼どもが先に来てたのか?」
頭上に荒れる黒い雲がその回答だった。
ヴラスカはその門を押し開けようとしたが、固く閉ざされていた。彼女は下がって扉の前の模様をじっと見つめた。
「「迷路だ」」ヴラスカとジェイスは同時に口にした。そして二人はぎこちなく、わずかに顔を見合わせた。
ヴラスカはジェイスへと譲った。「やってくれ。お前は迷路の達人だ」
ジェイスは迷路を解き始めた。指先を動かしながら、青色の魔力を線で描いていった。頭上の空に渦巻く黒色が彼に速度を上げるよう促した。
「これが俺ですよ」 彼は楽しみとともに言った。「ジェイス・ベレレン、ギルドパクトの体現にしてテレパスにして幻影術師にして迷路の達人」
「言いやすい名前なことだ」

その指が扉の中央、迷路の終点に到達した。そしてジェイスは驚きと恐怖に愕然とした。彼は感覚を伸ばして扉の向こうにいる存在を察し、自身とヴラスカに精神防御を張った。
「どうした?」 唖然と口を開くジェイスに気付き、ヴラスカは尋ねた。彼は扉の模様を示した。
「これ、俺達がプレインズウォークを試すと頭の上に必ず出て来る模様ですけど……これ、アゾリウスの紋章です」
ヴラスカは額に皺を寄せた。「アゾリウスはラヴニカだろ」
胃袋がひっくり返ったようだった。手短な精神探査で、彼はその部屋の中に何かを察知した。狼狽を僅かだけに抑え、彼はヴラスカを見た。「アゾリウスに名の知れたプレインズウォーカーはいますか?」
ヴラスカは額に皺を寄せた。「心当たりはないね。プレインズウォーカーがいるみたいな様子もないし」
「組織の中でも地位のある人物に違いありません。この紋章を自分達の証とみなすような」 彼はそう言うと、目の前の扉を示して言葉を切った。
「アゾリウスの創設者、アゾールです」
ジェイスは再び部屋を探査して凍りついた。誰が中にいるかはわからなかったが、何が中にあるかは即座にわかった。この存在の心は馴染みがあり、迷宮のようで、かつて一度だけ遭遇したとある者の精神のようだった。
『アゾールはスフィンクスだったのか?』 恐怖を抑え、彼はヴラスカへと心で尋ねた。
彼女は心配そうな表情でジェイスを見た。スフィンクスが彼にとって何を意味するか、ヴラスカはそれを知っていた。彼女はこめかみを指で叩き、ジェイスは心で声を聞いた。
『もうスフィンクスにお前を傷つけさせはしないよ』 彼女は決意とともに言った。その両目に残酷な琥珀色のひらめきが走った。
その言葉に、ジェイスは彼女を抱きしめていたかもしれなかった。だがヴラスカが接触を好まないことを思い出し、感謝の笑みを見せた。
『石化の魔法を備えとくよ。合図してくれれば、奴は死ぬ』
ジェイスは頷いた。不安が神経を支配し、口内には恐怖の鈍い金属臭があった。
彼は扉を押し、それが軋み開くのを見つめた。塵が落ち、中の小部屋が露わになった。
その部屋は細長く、蔓に覆われていた。最奥には巨大な玉座があり、頭上の天井には巨大な輝く円盤が埋め込まれていた。乾いた草と布が玉座の土台に散らばっており、そしてジェイスとヴラスカが扉を開くと、巨大な影がその長い髭の頭をもたげた。

「何者だ?」 スフィンクスが言った。長く使われていないその声はかすれ、人間の言葉というよりも動物の咆哮に近かった。
確信と平静をまとってヴラスカが歩み出た。その物腰は隅々まで船長のそれだった。「この世界にやって来た二人の異邦人さ。名を名乗ってそこをどきな。そして死にたくないなら不滅の太陽を差し出しな」
スフィンクスは二人を苦々しく睨み付けた。巨大な身体、そしてその凝視に宿した知性とは裏腹に捕食者の緊張をまとっていた。
「我が名はアゾール、法をもたらす者」 スフィンクスは低く吼え、首を傾げてヴラスカを見つめた。「ゴルゴンよ、三度虜囚となるか?」
ジェイスはスフィンクスとヴラスカとの間に精神的防御を急ぎ張った。彼女はスフィンクスの精神的侵入に驚いて固まり、衝撃を受けていた。無意識にジェイスは彼女の心を僅かに感じ取った。
『まるでアルハマレットだ』 ジェイスは思い、記憶の痛みに胸を緊張させた。彼は恐怖を抑え込んだ。スフィンクスにいいようにはさせない。二度と。
「この人のことは、船長と呼んだ方が良いですよ」 ジェイスは慎重な声色で言った。
スフィンクスは低く唸り、ヴラスカからジェイスへと視線を移した。「そのお前は何者だ?」
彼は確固とした態度で言った。「ジェイス・ベレレンといいます。ギルドパクトの体現者です」
スフィンクスの翼がぴくりと動いた。「あの安全装置が!?」
「今は海賊です」
(Tr. Mayuko Wakatsuki / TSV Yohei Mori)

