約束の刻
前回の物語:栄光の刻

そして見よ、暗き三柱が帰還し、神々を斃し、約束の刻が訪れる。次に大蝗の神が大いなる約束を叶える。ヘクマは引き裂かれ、王神の帰還を前にその守りは解かれる。
ハパチラは力の神殿の階段に立ち、ルクサの血が上流へ浸透する様を、その汚れが広がって川の水を真紅へと変える様を見つめていた。両腕は胸の前できつく組まれ、口元は厳しい真一文字に閉ざされていた。両脇には他の侍臣らが控え、乾いた川底とその真紅の汚れを同じく凝視していた。
右にはクフが立っていた。厳つい肩の巨体、その側頭部の髪には灰色の斑点が混じっていた。幸福な時であれば、彼の年齢をからかっただろう(何と三十五歳だ)、だが今彼女はかぶりを振るだけだった。
「神々の意図はまだわからないのか。イプトは何処に?」とハパチラ。
「じき戻るだろう」 クフが言った。その声には鐘の音のように確信が響いていた。
ハパチラは小指にペットの蛇を絡めた。先程、伝令からの知らせによれば、新たな神が三柱出現し、そしてその一柱がロナス神と戦闘に入ったとのことだった。彼女はロナス神の傍で新たな神を歓迎したいと願ったが、ひとまずは神殿内で待機するのが得策だと侍臣らは合意していた。
ハパチラは唇をかんだ。同僚と同じく、彼女は不安に包まれていた。新たな知らせが欲しかった。「栄光の刻の間、ロナス様の御側にあるべきだろうに」
クフは腕を組んだ。「栄光の刻は神々も定命も同じくその力を示す時だ。輝かしい来世へ加わるために」
ハパチラは小さな声とともに頷いた。「つまりあの新たな神々はまず五柱を試すと? その次に私達や試練を経ていない者らを?」
クフは肩をすくめた。
ハパチラはそわそわと体重を片足から片足へと移し、両手の間に蛇を滑らせた。心臓は不安に高鳴っていた。ロナス神は素早く勝利を収めるだろうとその心は知っていたが、知らせを待つというのはひどく苦しいものだとわかっていた。
「預言の時に私達が何処にいればいいのか、それは何もかも不確かだ。試練を受けるに至っていない修練者をいつ新たな神々へと連れて行けば良いか、どうすればわかる? そして血と化した川は何の関係がある?」 ハパチラは眉をひそめた。
掌を上に、クフは両手を掲げた。
「王神様が答えて下さるだろう」
王神の慈悲はその言葉よりも潤沢でありますよう。ハパチラは内心そう思った。
彼女は視線をルクサ川へ戻した。鳥たちは歌を止め、通常では幸福な訓練の音が満ちる街は、完全に沈黙していた。ハパチラは居心地の悪さを感じた。より心配なのは川の水が――血が――引いたことだった。水のない川底には死から蘇った魚が満ちていた。奇妙な、瘤だらけの、血まみれの生き物が泥の上に跳ね、ぎこちなく転がっていた。それらの移動に水が必要という事実を放浪の呪いは汲んでいなかった。
何もかもが奇妙だった。あまりに異常だった。預言は漠然としたものであり、その兆候もまた曖昧だった。
馴染みない疑念がハパチラの心に忍び寄った。彼女はあえてそれに名を与えなかった。
何の前触れもなく、息が喉に詰まった。
突然、不快な痛みがハパチラの胸に弾けた。彼女は苦痛に身体を折り、心臓を掴んでその痛みに悪態をついた。
必死でその源を周囲に探すと、他の侍臣らも同じように胸元を掴んでいた。彼女は心を落ち着かせ、痛みに対処しようとした。ハパチラは毒の専門家であり、焼け付く痛みを身体に通しながら人生の多くを過ごしてきた。息を吸い、吐き、意志を集中して心の恐慌と身体の痛みを宥めようとした。
肉体的な痛みは過ぎ、だが心に恐怖は残ったままでいた。
街のどこかで悲鳴が上がっていた。ハパチラは街の屋根と神殿の上を見渡して源を探った。その音は門からのようで、だがまるで何かがナクタムンを素早く駆けてくるように大きくなっていった。遠くにケフネト神が飛び立つのが見え、そして彼女にはわからない奇妙な黒い姿が続いた。
頭上に、奇妙な音を聞いた――虫の鳴き声、長い肢でひっかくような小さな雑音がヘクマの揺らぎから漂ってきた。ハパチラは顔を上げ、宙を飛ぶ蝗の群れを見た。
啓示の刻には怪物が打ち負かされるとされていた。だからこそあの悪魔が街へと飛来した。あれはヘクマの外のあらゆる獣と同じく、楽園を追放された者。何故あの怪物らはまだ残っているのだろう?
蛇が指の間から滑り下り、神殿の壁のひび割れへと消えた。
ハパチラは再びケフネト神を見た。そして理解した、神を追いかけるその暗い姿は新たな神の一柱以外にありえないと。

とてつもなく巨大だった。それは近くの塔によじ登ろうとしているらしく、鉤爪が石造りのオベリスクを掴み、その巨体を引っ張り上げた。上昇の途中でそれは羽根の存在を思い出したように、素早く上昇して頂きに着地した。その羽根は暴力的な異音を止めず、まるで大気そのものが、巨大な昆虫の羽根に打ちつけられる痛みと傷をこらえているようだった。
ハパチラはクフへと向き直った。
「ケフネト様を助けなければ!」
謎の痛みに苦しみながらも、侍臣はかぶりを振った。「これも全て栄光の刻の一部だ。神々も私達のように試されているのだろう」
「なら、この痛みは何? 試されているの?」
クフは頷き、ハパチラは唇を歪めた。彼女はベランダの逆側へ向かった。この感覚は何一つ正しいとは思えなかった。
その瞬間、彼女は小さな足音が階段を駆けてくる音を聞いた。イプト、力の神殿にて最年少かつ最も俊足の侍臣が、素早く階段を上ってきていた。その顔は涙でくしゃくしゃだった。ハパチラは膝をつき、彼女を両腕で受け止めた。
「イプト、何を見たの? 新たな神々は何と?」
「ロナス様が斃されました!」
ハパチラはうつむき、かぶりを振った。
「ありえない。神が。神が殺されるなんてありえない」
イプトは悲嘆に震えた。「蠍の神がロナス様を。神様全員を殺す気です」
ロナス神は神々の中でも最強だった。その力に獣は後ずさり、闇の力は神の影の中にすくんだ。ロナス神が殺されるはずなどなかった。
だがハパチラの心臓の痛みが、そうではないと告げていた。
背後でクフが叫んでいた。
「これは試練だ! イプトの言葉は嘘だ! ロナス様、最も偉大なる神は王神の御側に――」
「いいから黙りなさい!」 ハパチラは声を上げた。
預言の解釈について言い争っている場合ではなかった。約束は破られ、見知らぬ毒が信頼に穴をあけた。悲しむのは後でもできる。今目指すべきは他の神々の安全、そして神が斃れる苦痛を民が被らないようにすることだった。
ハパチラは顔を上げ、昆虫の暗い雲が障壁の外にしがみつくのを見た。遠くの尖塔にとまる蝗の神は両腕を伸ばし、頭上の空へ向けて何か不浄の魔法を行使した。
蝗の羽音が頭上の大気を満たした。
灰色の雲がヘクマの内側に密集した。当初それは希薄で、だが蝗の神の呪文が続くと、その塊は次第に規模を増し、虫の羽音もまた止まることなく高まっていった。
ハパチラは目を狭め、蝗が何をしているのかを確認しようとした。それらは互いの身体によじ登り、ヘクマの揺らめく魔術に触れようとしているらしかった。そしてそれらが動くと、障壁があるはずの箇所から明るい光の柱が差し込んだ。ハパチラは恐怖に唖然とした。蝗はヘクマそのものを食らっている!
ハパチラは侍臣らへと向き直った、「約束の刻は世界が輝かしい楽園へ変わる時とされていた。『最早ヘクマは砂漠と卑しき死者を隔てる必要はなく、ルクサの水は荒野へと自由に流れるだろう』だったな?」
侍臣らは頷いた。ハパチラは遠くの蝗の神を指さした。そして肩を正し、背筋を伸ばして立った。「ルクサの水が荒野へと自由に流れる、ヘクマが無くなるから!」
侍臣らは恐怖とともに顔を上げた。自分達を外の世界から守る魔術を蝗が食らっていくのを、彼らはその高所から見つめた。
クフですら、見ずにはいられなかった。「蝗の神がこれを……?」
ヘクマは無数の蝗で覆われ、その群れはあまりに濃く、双陽からの光すらちらついて翳った。不気味な暗い夜がナクタムンに降りた。ハパチラは瞬きをして目を慣らした。昆虫の群れは動き、揺れ、力の神殿の石材に光の斑模様を作り出した。
中に向かう頃合いだとハパチラは決断した。
「呆けていないで! 全員中に入りなさい!」 ハパチラは声を上げた。他の侍臣らもその悲嘆を飲み込み、絶望の涙とともに渋々立ち上がった。
「ロナス様は私達がただ座って泣き続けているなど望まれていない! 武器をとって戦いなさい!」 ハパチラは大きな身振りで言った。
全員が鼻をすすり、頷き、武器を手にすべく神殿の内部へと向かった。
頭上で、昆虫の黒雲から光のひと刺しが漏れた。
光の柱が障壁の向こう側から入り込んだ。当初は僅か、そして十を超え、突然、ヘクマの障壁の四分の一が消え去った。
ハパチラは罵り声を上げた。
街に混乱が弾けた。

神殿から彼女が見つめる中、ケフネト神が飛び上がってヘクマを修復する呪文を唱えはじめたが、それは空しい努力だった。蝗がその神に群がり、ケフネト神は何千何百という昆虫に攻撃されながら魔法を維持しようともがいた。街を見通せないことをハパチラは呪った。
街を覆うヘクマが消失し、その先の荒野から暴れるミイラの波が殺到した。
彼女は踵を返し、全速力で力の神殿へと駆けこんだ。
修練者らは取り乱し、安心を求め身体を寄せ合っていた。侍臣は武装し、あるいは神殿の獣を街へ放って暴れるミイラと戦わせるべく住処から連れ出していた。力の神殿内部は「占有地」と呼ばれる広大な訓練場であり、修練者らが粘り強さと生存技術を鍛える場として野生の環境が注意深く維持されていた。ハパチラは占有地の外環部を進み、更に危険な内環部をめざした。この神殿に仕えて人生を過ごしてきた彼女は、あらゆる通路と近道を知っていた。自室はすぐそこだった。
心のざわつきを顔に出さぬよう、ハパチラは全力を尽くした。来世でロナス神の傍にいられればとずっと願っていた。神々は死んだら何処へ行くのだろうか?
自室は毒の蔦に隠されていた。馴染みある痛みとともに彼女はそれを通過し、武器庫へ駆けこんだ。
槍。曲刀。毒の薬瓶また薬瓶。
ハパチラはほんの数か月前に伝えた教訓を思い出した。
彼女は修練者に囲まれて立っていた。皆健康で才能あり、力の試練を通過すべく身構えていた。毒の専門家として、その技術を教えることはハパチラにとって喜びだった。
彼女は誇らし気に顎を上げてみせ、生徒の一団に単純な質問を投げかけた。「暴れるミイラは砂ばかりの砂漠をどう動く?」
ハパチラは一瞬だけ待ち、そして眩しい笑みを広げた。
「すなおに、動く!」
修練者全員が不満にうめき、ハパチラは自己満足ににやりとした。
ハパチラはその記憶に微笑み、毒の薬瓶を取り出した。ミイラがどう動くかは熟知していた。ひとたび放浪の呪いに捕まれば、筋肉は脊髄と神経を通って送られる刺激で動く。
彼女は曲刀の刃に毒を塗りつけた。
「神経を殺せば、ミイラも死ぬ」
そんな軽口に続けて、ハパチラは鋭い口笛をふいた。
何か巨大なものが動く振動が自室に届き、ハパチラは笑みを大きくした。彼女は蝗から身を守るべく分厚い肩掛けを掴み、外のものへと声を上げた。
「チュウヤ、おいで!」
蔓の背後から息の音が聞こえた。ハパチラは後方に曲刀を振るって蔓を除け、目の前の巨大なバジリスクへと柔らかな声を出した。
チュウヤの体高はハパチラの倍、体長は測るたびに長くなっていた。彼女らの間には魔法的な絆があり、そのバジリスクは主の手に鼻を寄せた。ハパチラは蛇の鼻に口付けをした。
「私達の知っている世界は終わってしまったのよ」 ハパチラはそう囁いた。バジリスクは彼女の首筋に鼻をすり寄せた。
毒使いは悲しみをこらえた。
「泣いている時間はないわよ。街を守らないと」
身体をくねらせて占有地を進むチュウヤの背にハパチラは掴まっていた。もはや修練者の姿はなく、辺りも奇妙にがらんとしていた。
ハパチラは片手を伸ばし、呼集の呪文を編み上げた。『私のもとへ』 彼女はそう伝えた。『私とともに外へ出て、復讐をしよう。ロナス様は亡くなられた』
その言葉が届いたように、占有地の獣らは顔を上げた。まずは一体が、そして多くが追いかけ始めた。やがてアンテロープ、カバ、サイ、象の群れがしなやかなバジリスクの後についた。
占有地の密林を突き進むと、蔓や葉がハパチラの顔に叩きつけられた。彼女はチュウヤの脇腹を引いて中央階段を登らせ、目を固く閉じたまま扉を破ると眩しい日の光の恐怖へと出た。
光と同時に、悲鳴と異音の嵐が顔を叩いた。仕事を終え、蝗は見境なく近くの身体へと群がっていた。呪われた死者は外の砂漠から迷い込み、荒野の怪物も何体かが生者を見つけ次第襲いかかっていた。
かつて眩しく輝いていたナクタムンは、虫と獣に汚されていた。
分厚い肩掛けをまとっていても、蝗がぶつかる衝撃を感じた。ハパチラはチュウヤを止めると、後に続く力の神殿の動物の群れもまた止まった。
昆虫の群れが頭上の双陽を翳らせていた。ケフネト神は今や遥か遠くを飛び、必死にヘクマを再建しようとしていた。蝗の神が今も尖塔の上に立ち、無力なケフネト神へと蝗の群れを続けざまに放つ姿がかすかに見えた。
ハパチラは素早く別の呼集呪文を唱えた。『あの偽の神を襲いなさい! 害虫の侵略者を殺しなさい!』
獣たちは狂喜と憤怒に咆哮し、チュウヤは上体を起こすと牙をむき出しにした。ハパチラは曲刀を抜き、チュウヤへと攻撃を命じた。
彼女らはナクタムンの通りへ突入し、暴れるミイラを可能な限りなぎ倒し蝗を潰した。ハパチラは蛇の横に身をのり出し、数体のミイラの胸を毒の曲刀で切り裂いた。刃を振るうごとにミイラは足を止め、固まり、のたうち、地に倒れ、体を震わせていた。
ロナス様が私を見て下さってくれていたなら。彼女はほろ苦い笑みとともに思った。
チュウヤの牙が数体の略奪ミイラの身体に食いこみ、ハパチラは地面に飛び下りた。
「呪いの死者を街から追い出せ!」 彼女は叫んだ。バジリスクは愛らしく舌をちらつかせ、ナクタムンの外縁へと身体を滑らせていった。
ハパチラは顔を上げ、街の遥か上空で苦闘するケフネト神を見て、駆けた。
肩掛けは皮膚に食いつく蝗を防いでくれるが、今や自分を取り囲むミイラに対しては無意味だった。構わず、ハパチラは死者の群れへと駆けた。ロナス神への祈りを唱えようとして止め、そして呪った。それでも彼女は続けざまに切り進んだ。危険なほどに優雅かつ洗練された軌跡でその刃が踊り、死者の群れから脱出した。
毒はそれだけでもミイラの動きを止めるものだった。ハパチラは近くの死者の群れへと走り、可能な限り多くを切った。その毒は生者も死者も同じく動きを止める。放浪の呪いを解くことはできなくとも、動きそのものを困難にすることはできた。
ハパチラは切り、また切り、その背後にのたうつ屍を残していった。
その時、彼女は我を忘れていた。視界を塞ぐ蝗と耳に満ちる羽音の中、右へ左へと刃を振るいながらハパチラは年齢を感じた。彼女は三十四年生きてきた――それは人生二度分に相当する経験を意味した。物心ついた時から、ロナス神はすぐ傍にいてくれた。とても善良で、とても真摯だった。その神がこのように裏切るというのは一体?
違う。裏切ったのは神々ではない。
それはここにいない者。ここにいない王神。
それの仕業なのだ。
ハパチラは憤怒を叫び、ミイラの首を鮮やかに切り落とした。
黄金のひらめきが目にとまった。
見やると、子供二人が背中合わせになってやつれたミイラの群れと戦っていた。
二人は盗んだ槍で突き、戦術的助言を叫び合っていた。その動きは未熟で、惨めな恐怖から出たものだった。
ハパチラの心が重くなった。彼女は突撃し、襲いかかるミイラに素早く対処した。子供二人はその隣で悲鳴とともに槍を突き出した。
毒を受けて敵が倒れると、ハパチラは二人へと向き直った。
「世話人はどうしたの?」
「止まらないんです」 年長の子が答えた。
ハパチラは疑問に眉をひそめた。そして近くの家の扉を蹴破り、中へ入った。
選定の死者が数体、台所で昼食を準備していた。そこかしこに山となった食物や器は貪り食う蝗で覆われていた。昆虫と腐った食物の悪臭が空気に立ち込めていた。ある選定のミイラは器を使い果たし、ひたすら一匙また一匙と食物をただ床に落としていた。蝗の群れがせわしなく次の食べ物を貪り、だがミイラは気にもしなかった。混乱が街に充満しようとも、選定の死者らはその義務を止められないようだった。
ハパチラはひるみ、素早く外へ出た。彼女は膝をついて子供達と視線を合わせ、毒瓶を取り出した。
「槍を貸しなさい」
少年たちは槍を手渡し、ハパチラは毒の栓を抜くと、指で彼らの刃に塗りつけた。
「誰か大人を見つけて近くにいなさい。これで、できるだけ沢山のミイラを切りなさい」
悲鳴が彼女の耳をとらえた。ハパチラは立ち上がり、曲刀を抜き、その音へと駆けた。蝗が一人の男性の身体に群がり、その隣に女性が立って、両手で昆虫を叩いていた。平手打ちの音は増すばかりの羽音にかき消された。
気が付くと、ハパチラはお気に入りの中庭、噴水のそばに立っていた。
その噴水はルクサ川から直接引かれたものだった。それは今や血に汚れていた。
ハパチラは心に引っかかる何かを感じ、するとチュウヤが鱗の巨体を荒々しく壁にぶつけながら、広場の区画を曲がって姿を現した。その鼻面は血と昆虫の体液で覆われていた。
ハパチラは友の背に登り、前進させた。ケフネト神は近くの塔の上にとまり、その翼は疲労にうなだれていた。
彼女はチュウヤを急かし、縫うように街を進んだ。
今や更なる市民が抵抗し、ある者は選定の死者を同じように戦わせていた。ハパチラは時折、占有地から来た獣とすれ違った。彼らは暴れるミイラを引き裂き、噛みつき、引っかいていた。数体はバジリスクが通過すると気付き、共に駆けた。
「ハパチラ侍臣!」
ハパチラはチュウヤを止め、自分の名を呼んだ者を探した。
見下ろすと、造反者のサムトがいた。
「『言ったでしょ』とでも言うつもりか?」 ハパチラは叫んだ。
サムトはかぶりを振った。その左を見ると、闘士デジェルが角を曲がって姿を見せた。
「オケチラ様を見つけてお守りしなければ」とサムト。
「ロナス様が……斃されるのを見ました」 デジェルは否定したいかのように首を横に振った。「他の神々に、ロナス様と同じ運命を被らせるわけにはいきません」
ハパチラは溜息をついた。
「乗りなさい」
元修練者二人は身軽にチュウヤの背へと乗り、ハパチラはバジリスクを前進させた。
バジリスクを進ませながら、ハパチラは誰ともなく呟いた。「約束の刻とはヘクマが晴れ、楽園が姿を見せる時だとずっと思っていた」
「それも全て王神の欺瞞です」 そう言ってサムトは口を固く閉ざした。デジェルはその背後でかぶりを振り、黙ったままでいた。
ハパチラはバジリスクの冷たい鱗を撫でた。「ロナス様に仕えることは生涯の目的だった。あの方がご存知の上で嘘をついていたとは信じたくない」
「知って嘘をついていたのではありません。神々はもっと大きな力に操られていたのです」
ハパチラは頷き、考えた。そして肩越しに振り返ってサムトと目を合わせた。
「それは倒せるものなのか?」
サムトはゆっくりと首を横に振った。「わかりたくもありません」
「多くを知っていると言う割に、君の視界は狭いな」 ハパチラは言い放った。
背後からデジェルの声が甲高く届いた。「何をおいても、ナクタムンの民と神々の生命を守ることが重要です。余所者は余所者同士で戦わせておけばいい」
案の定、その余所者二人が彼女らの道を横切るように駆けてきた。一人はギデオン、頑健な戦士でありオケチラ神が自らのものと主張していた。もう一人は紫色の衣服をまとった色白の女性だった。
「止まる必要はありません」 デジェルが言い放った。
ハパチラは振り返り、その異邦人らの姿を今一度眺めた。ナクタムンの他に街はなく、それでもあの余所者らはここの文化について何一つ知らなかった。一昨日、侍臣達からハパチラは知らせを受け取っていた。神々はその客人らを受け入れると。彼女は鼻を鳴らした。その余所者と王神を戦わせておけばいい。もし王神も違う世界から来たというなら、全部彼らだけでやり合っていればいい。
一陣の風が新たな蝗の群れをバジリスクに叩きつけた。ハパチラは背後の二人とともに縮こまって肩掛けで身を包み、そして往来を見つめた。
ケフネト神とオケチラ神がそこにいた。ケフネト神は宙に留まり、オケチラ神は彫像のように確固として動かず、耳だけをひらめかせていた。ロナス神に仕える者として、ハパチラはオケチラ神へと然程多くの信仰を捧げたことはなかった。だがその神の存在下、安堵に包まれるのを感じた。ロナス神の死以来、初めて感じた温かさに感謝した。
二柱は彼女の背後の何かを見つめていた。ハパチラはバジリスクを止め、二柱が見つめているものへと振り返ったが、視界は壊れた柱や、砕けた岩、そして飛び交う蝗の果てしない群れに塞がれていた。
ハパチラは心に嘆願を抱き、神々へと向き直った。
「ケフネト様! オケチラ様! ヘクマは失われました! 安全な場所へお連れ致します!」 ほんの一日前であったなら、この言葉はいかに馬鹿げた響きだっただろうか。
二柱は彼女を無視し、遠くを見つめたままでいた。オケチラ神は弓を手にして、白光を放つ一本の矢がつがえられていた。
「オケチラ様、どうか!」 これまでに失ったものを、これから失うものを思ってハパチラは声をかすれさせた。「オケチラ様! お守り致します!」 ロナス神の死が彼女の心に空けた穴は既に大きすぎた。それが広がるのは耐えられなかった。
オケチラ神が見下ろした。その淡い色の瞳が柔らかに輝き、ハパチラは馴染みある温かさに浸るのを感じた。結束の神はハパチラを見下ろして微笑んだ。小さく、悲しく。神が彼女の魂を覗きこむと、周囲で人々が恐怖に逃げ惑う音が和らいだ。
「ロナスの子よ、其方が我等を守るのではありません」 オケチラ神はごく僅かにかぶりを振った。「我々が其方らを守るのです」
ハパチラの心が軋んだ。「オケチラ様、おやめ下さい!」
だがその退去を命じる言葉とともに、オケチラ神は今一度背を向けて弓を掲げた。ケフネト神は更に上空へと舞い上がり、ハパチラは二柱が見つめていたものをようやく視界にとらえた。
それは姿を成した悪夢そのものだった。
それは、ヘクマの向こうの荒野に見たどんな怪物よりも圧倒的だった。その体躯はどの神よりも、ロナス神よりも巨大で、ハパチラにとってはそんなものの存在そのものがありえなかった。人間の身体に蠍の頭部、だがどういうわけか、蠍は人の身体の上にまっすぐ立っている――そしてあらゆる蠍よりも遥かに屈強で大きかった。その背後には自由に、律動的に、旋回するように蠍の針が踊り、先端は毒液にぎらついていた。止まらない蝗の群れですら、不承不承その怪物へと広く道をあけた。ハパチラは虫が立てる大きな音を聞いた。とはいえそれが怪物の口から出たものなのか、尾からなのかはわからなかった。
ケフネト神はオケチラ神を振り返った。ケフネト神が恐怖を露わにしていることにハパチラは驚愕した。
「怯えている時ではありません、同胞よ!」 決断的なオケチラ神の声が、ハパチラの心に鳴り響いた。「この獣に対峙し、其方の力を振るって戦うのです!」
ケフネト神は顔を上げた。肩を一度回し、その神は更に高く舞い上がって蠍の側面へ向かっていった。
オケチラ神は再び矢を掲げた。
「下がりなさい、神殺し、恒久の命の禍よ。さすれば今日は見逃しましょう」
オケチラ神の言葉は辺りに響き、その声色は純銀のようだった。とはいえ強めた「今日」の言葉からは、神がいずれロナス神の仇討ちに向かうであろうことは明白だった。神は弓を掲げ、その白い矢は今や白熱し輝いていた。蠍はその頭部を回してケフネト神とオケチラ神を認め、とはいえそれが言葉を発したのだとしても、止まない虫の音の中でハパチラは何も聞き取れなかった。
それが近づくと、ハパチラは存在を感じて息をのんだ。蠍の神が何であったのかを認識し、彼女の心に恐怖が満ちた。それが神であることは――とはいえ他の神々とは正反対に、悪意の存在――紛れもなかった。
三柱は静止し、相手を探った。まるでハパチラがよく知る、神殿の壁の彫刻のように。
そして無秩序が弾けた。
ケフネト神は蠍の神へと飛びかかり、続けざまに呪文を放ちながら一撃離脱を繰り返した。巨鳥、鰐に似たドラゴン、一連の幻影が蠍の神の気をそらし、その隙にケフネト神はかろうじて蠍の針を避けた。オケチラ神は続けざまに矢を放ち、だがいかにしてか蠍の神はその分厚い攻殻であらゆる矢弾を弾いた。蠍の針がケフネト神を絶えず攻撃する間にも、オケチラ神の白いエネルギーがその鎧に立ち消えた。
ケフネト神はすぐに幻影による攪乱を止めた。蠍の神は標的を違えることも、好機を逸することもなかった。オケチラ神の矢は巨大なサンドワームや悪魔を貫き倒したと、多くの物語が語っていた。だからこそ、そのような攻撃を意に介さない蠍の神がどれほどの力を持つのか、ハパチラは畏れおののいた。彼女はチュウヤへと影の中に留まるよう促し、そして気が付くとオケチラ神とケフネト神を声高に称えていた。それが二柱の戦いの力になればと願ってのことだった。
ケフネト神は更に高く飛んで蠍の神の攻撃を避けたが、その神は代わりに即座に狙いをオケチラ神へと定め、恐るべき速度で距離を縮めた。オケチラ神は焦って後退せざるを得ず、その足取りは地面を震わせた。その間にケフネト神は飛びすさり、間断ない攻撃で蠍の神を攪乱した。
蠍の神は正確無比の能率で、ケフネト神とオケチラ神は詩的と言えるほどの優雅さで戦った。二神は一つとなって動き、その風のごとき攻撃と反撃は蠍の神の側面や攻殻の弱点を正確に狙っていた。蠍の神は遥かに手強く、とはいえハパチラの目に、二柱は数千年を研鑽してきた戦闘の達人として映った。
蠍の神もまた数発攻撃したが全て外れ、もしくは素早く受け流された。その針がケフネト神の片翼を素早くかすめたようで、朱鷺頭の神は宙で何かを呟き、片翼の動きが鈍くなった。ケフネト神はひるみ、蠍の神は直ちにそれを好機と見て続けざまに攻撃した。針はケフネト神の頭部や胸をわずかに外した。ケフネト神は強張りながら、必死に左右へとよろめいてそれを避けた。
オケチラ神は大通りの端にじっと立ち、弓を掴んで狙いを定めたまま動かなかった。ケフネト神は今や彼女と蠍の神との間でもがき、それを誤射する危険は冒せなかった。生き延びようと舞踏する中、朱鷺の頭部がふらついた。蠍の神は突撃し、ケフネト神の翼が力を失った。
その時、オケチラ神が放った光の矢が蠍の頭部で爆発した。攻撃は不意に止まった。虫の音は止まり、蠍の神は頭を失って倒れ、その衝撃は瓦礫を塵へと崩すとともにハパチラとバジリスクとその乗客を地面から持ち上げた。その身体を動かしていた何らかの力が失われ、蠍の神が塵と化すのをハパチラは見つめた。
ケフネト神は翼を伸ばして立ち上がった。見たところ無傷のようだった。そして喜びを共有するオケチラ神へと意地悪そうに微笑んだ。
バジリスクの上で人間三人は歓声を上げ、オケチラ神の勇気とケフネト神の明敏さを称えた。
私が信奉する神々は無敵だ、ハパチラはそう驚嘆を抱いた。サムトとデジェルは固く抱き合い、そしてハパチラの背中を叩いた。ハパチラは二人と喜びの涙を共にすることは拒んだ。それは後でいい。
だが死したロナス神をどう悼めばよいだろう、そう熟考していると、蠍の神であったはずの塵と破片が動きだした。
破片は地面から浮き上がり、そして瞬く間に、つい先ほど殺されたはずのその獣が再び姿を成した。
その獣は完全な、無傷の姿で立ち上がった。まるで地面深くまでも揺るがした先程の戦いなど存在しなかったかのように。ケフネト神は倒れた敵へと振り返った時、蠍の神は目の前にいた。そしてその針が額の中央を正確に突き刺す寸前、汚らわしい虫の音が神の耳に届いた。その傷は深くも広くもなかったが、美しく聡明なケフネト、知識の神は絶命し、そして倒れた。
ハパチラは、そしてサムトとデジェルも悲鳴を上げた。一柱の神の死に、彼女らの心はまたも痛んだ。オケチラ神は憤怒を囁き、無益に矢を放った。
「定命よ! 霊廟へ逃げるのです!」 神は叫んだ。
ハパチラははっとした。どの霊廟?
彼女はその命令を無視し、背後に座るサムトとデジェルへ叫んだ。「降りなさい!」
二人は言われた通りにした。そしてハパチラは踵をチュウヤに叩きこみ、前進させた。
その蛇は毒液を吐き出し、毒の顎をきしらせながら身体をよじって蠍の神へと曲がりくねって進んだ。ハパチラは両腿でしっかりと騎乗したままバジリスクを鋭く曲がらせ、乗騎を敵へ向けた。
ケフネト神の血が広場の敷石に流れており、チュウヤは蠍の神に掴みかかろうとして足を滑らせた。ハパチラはチュウヤの鱗を掴み続け、黙って前進を促した。心はケフネト神の死に痛んでいたが、その痛みを可能な限り深層へ押しやった。この侵略者に死を、私の手で。
オケチラ神がバジリスクと蠍の神との間に飛びこんだ。
胸が痛みに詰まった。ハパチラは見上げ、そして恐怖に叫んだ。すぐ頭上で、蠍の神の針がオケチラ神の腹部に打ち込まれていた。
ハパチラの悲鳴と同時に、聞き慣れない悲嘆の叫び声が耳に届いた。中庭の向こう側にギデオンが、苦悶そのものの表情を浮かべていた。
蠍の神が足を向け、彼女とバジリスクは恐怖に凍り付いた。だがそれは空を見上げ、何かを探し、足元の定命を無視してナクタムンの街路を進んでいった。
街路は無人となり、ハパチラの目の前では二柱の神が斃れていた。
この日初めて、彼女は憚ることなく涙を流した。
敬愛する神の死に。神々の死に、戦いを強いられた子供たちに、蝗に貪られた男に、そして自身の手の下で恐怖に震える愛蛇に涙を流した。彼女の悲嘆は堰を切って溢れ、闘士と異端者の腕に受け止められた。デジェルとサムトはむせび泣く侍臣を抱きしめ、そして二人もまた、その多すぎる喪失を悼んだ。
生き延びた市民が一人また一人、神々の死体を見ようと小路や隠れ処から顔を覗かせた。
ハパチラは悲嘆の間に息を切らし、そしてギデオンが今も立ち尽くしたままオケチラ神を見つめているのを見た。
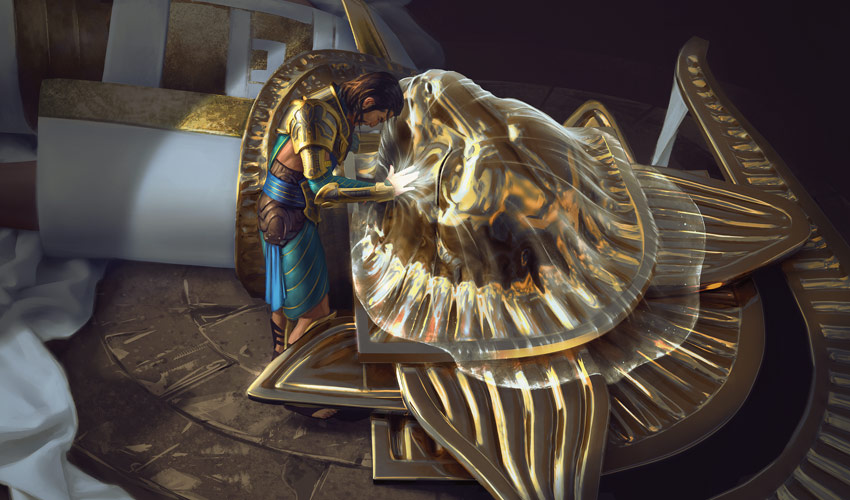
彼女は心を落ち着かせてサムトとデジェルへ頷いた。二人はその肩を放し、ギデオンへと向かわせた。
ハパチラは軽蔑の視線でギデオンを見下ろした。彼女の頬の化粧は涙で崩れ、唇は激しい悲嘆と憤怒の両方に歪んでいた。
「この地獄を引き起こしたのはお前達と同じ余所者、そうなのだな?」
ギデオンは何かの言葉を懸命にこらえ、頷いた。
ハパチラは睨みつけ、毒の滴る声で言った。
「ならばそれはお前たちが殺すのが道理だ。仕事を終わらせて出て行け」
毒使いは背を向け、神々の体液を避けつつサムトとデジェルへ近づいた。
決意の眼差しで彼女は二人を見つめた。「バントゥ様とハゾレト様を見つけねば、そして何としても生き延びて頂かねばならない。私達に残されたのは二柱だけだ」
(Tr. Mayuko Wakatsuki / TSV Yohei Mori)

