ドミナリアへの帰還 第11話
ウェザーライト号が海上を過ぎてアーボーグの沿岸地域へ至る頃には、太陽は沈もうとしていた。
ギデオンは艦橋にリリアナと共に立ち、ジョイラは湿原や草に埋もれた水路の上に船を進ませていた。蔓と苔の下には、この大地の長い歴史を示す古の遺跡が埋もれていた。
外縁の島近くを通過した所で、ジョイラは機械梟を短い偵察任務へと送り出していた。それが戻ると、彼女は苦々しく説明した。「ファイレクシア戦争の死者を悼む記念碑があったのよ。辛い時代には希望の象徴として巡礼者が訪れていた。ベルゼンロックが陰謀団に破壊させたという噂だったけれど、梟が見たところ、それは本当だったわ」
「それは私も聞いたことがある」 テフェリーは艦橋の隅に立ち、腕を組んで緑深い沼地をじっと見つめていた。その口元が侮蔑に歪んだ。「何でも、陰謀団はそれを愚蒙の墳墓と呼んでいるとか」
リリアナは顔をしかめた。「そうなの。私の希望の象徴は黒き剣がベルゼンロックを切り裂いてその生命を食らい尽くす時の、終わることのない想像を絶する苦痛よ」
ジョイラは微笑んだ。テフェリーは笑い声をあげ、そして言った。「君の考え方は好きだよ、リリアナ」
リリアナは彼を見つめた。「それに慣れないでくれるかしら? 私のことを知るのは大変よ」
ギデオンは溜息をつき、リリアナは彼を睨み付けた。
ウェザーライト号が内陸部へ向かうほどに、辺りは暗くなっていった。空は火山灰で曇り、ジョイラは船の航行灯をわずかな火花ほどにまで落とした。ギデオンはスランの建築物の重厚な姿をかろうじて視認したが、遺構のほとんどは有機的かつ尖ったファイレクシアの残骸だった。

あるものは巨大な円形の姿を木々の上に突き出し、またあるものは植生の下に鋭い形状をわずかに残す程度だった。壊れた壁や時折現れる塔がもっと新しい時代の都市や街を示し、だがそれらも破壊されて植生に埋もれていた。だが遺構だけではなく、アーボーグは無人とは程遠かった。あらゆる大きさの光が木々や蔦の下にきらめき、飛び交い、もしくは緩慢に動いていた。植生の塊はどれも生物の住処のようで、常にそこには気配があった。
闇の中を進みながらも、船には落ち着いた雰囲気が漂っていた。テフェリー達は下の船室へ向かったが、カーンは船首に残って監視を続けていた。ギデオンはリリアナとジョイラと共に艦橋に留まっていた。明日の戦いに備えて休むべきだとはわかっていたが、今眠れる気はしなかった。目標はまもなくだった。これさえ終われば、全力をニコル・ボーラスへ向けることができるのだ。
「そのお友達が力を貸してくれるのは間違いないの?」 わずかに疑いながら、リリアナはジョイラへと尋ねた。先だってジョイラは沼地へと機械梟を送り出し、ここで落ち合おうという伝言を届けていた。「私達の姿を見るなり陰謀団に告げ口はしないってことも?」
ジョイラは片眉をつり上げ、だが既にリリアナの物言いに慣れた彼女は気分を損ねはしなかった。「間違いありません。陰謀団を倒すと決めた時から連絡を取り合ってきましたから。ここに住む多くの人々が、生きるために陰謀団に降伏しました。けれどそうでない人々の多くが、ベルゼンロックの勢力を島から追い出すために戦って死にました。今では抵抗勢力は秘密の隠れ処に集まっています。私達が話す人達もそこから来ます」
「私もここの変化については聞いたことがあるわ、自分で計画を立てた時にね。でも実際に会うのは全然違うものよ」 リリアナは認めた。「勿論、この場所の戦死者が多ければ多いほどいいのは確か。少なくとも私達の目的にとってはね」
「アーボーグでは長い間、多くの死が積み重なっています。黒豹人の戦士はほとんど滅ぼされてしまいました」 ジョイラの表情は悲しみに染まった。「そして霊やリッチが沼地のそこかしこに街や住処を築いてきました」
「霊?」 ギデオンは眉をひそめた。「死者のですか?」
「ええ。そして暗黒の魔術の純粋な顕現です。この地に住まう不死者の数と種類は計り知れません」ジョイラは説明した。
「それなら私にはきっと快適ね」 リリアナは冷淡に言った。
それが冗談ではないとはわかっている、ジョイラの皮肉的な表情がそう告げていた。彼女は続けて言った。「死者のほとんどはもはや私達以上に陰謀団に関わろうとはしませんし、彼らもまた陰謀団の狂気魔術が作り出したナイトメアや他の脅威から身を守らねばなりません」 そして彼女は身をのり出し、霧と闇の中を見通そうとした。「梟が戻ってきました」 使い魔と会話をし、ジョイラは表情を落ち着かせた。「抵抗勢力は私達との会合を了承してくれました」

「わかりました」 ギデオンは応えた。全てを片付けてこの奇妙な土地を離れる心構えはできていた。
夜も更けた頃にウェザーライト号はとある沼の端、苔と生い茂る木々に半ば埋もれた小さな街近くに着陸した。石の壁と重厚な門が様々な色とりどりの光で照らされていた。ウェザーライト号の甲板から、ギデオンはこの上なく極めて奇妙な街並みを垣間見た。奇抜な形状の建築物を橋が繋ぎ、鐘楼らしきものがその脇に横たわって新たな建築の一部を成していた。
ギデオンとジョイラが門のほど近くの狭い空き地へと梯子で降り、他の乗組員は乗船したまま待機した。二人が降りると、一人の若いジャムーラ人が影の中から滑り出た。「こっちだ」 その男は言って、草むらの中を先導していった。
ギデオンはウェザーライト号から離れすぎることを心配したが、隠れ処はすぐ近くだった。それは奇妙なファイレクシアの構造物の上に倒れた巨木に作られていた。
そこでは四人が待っていた。地面に布を敷いて座り、近くに浮遊する小さな霧が放つ光に照らされていた。二人は人間、だがもう二人は黒豹人の戦士だった。背は高く筋肉はしなやかで、艶のある肉食獣の頭部と顔がその種族の名を示していた。全員が重装備で、ありふれた革や金属の鎧だけでなく明らかに陰謀団から奪ったのであろう黒い棘のある衣服をまとっていた。
女性の黒豹人が近寄るよう身振りをした。「ジョイラ、私がサイラだ。私達の力を借りたいそうだな」
彼らの案内人は一同に背中を向けて木々の下の影を監視していた。ギデオンも同じ見張りに立った。ジョイラは腰を下ろして言った。「応じて頂き、感謝致します」
サイラは首をかしげ、わずかな皮肉を込めて言った。「あのジョイラがあの高名な飛翔艦と共にここに来たとあっては、出て来ざるを得まいよ」
ジョイラはすぐに本題に入った。「要塞を攻撃するために来ました」

驚き、サイラは幅広い鉤爪の片手を挙げた。「戦士を求めて来たのなら、我々の中でも応じられる者はごく僅かだ」
「いいえ、この戦いに同行を求めているのではありません」 ジョイラは身を乗り出した。「必要なのは二つだけです。まず、陰謀団の斥候か戦士の衣服を。要塞のピットへ攫って行くために狩りをしていたであろう者のです」
「それは簡単だ」 サイラが仲間へ身振りをすると、人間の一人が立ち上がって暗闇の中へと消えていった。「もう一つは?」
「情報です。アーボーグで最後に起こった大きな戦いの場所を、地図で教えて頂けますか?」
「それも簡単だな」 サイラは腰のポーチを開き、小さく折り畳まれた地図を取り出した。
何かが茂みの中で動き、ギデオンは剣の柄に手をかけた。だがジャムーラの男が言った。「大丈夫だ。街の霊だ。あいつらは陰謀団を憎んでるから、裏切ることはない」
影から現れた姿は膨れた小さな身体、平らな頭に皮膚は暗い灰色だった。それは歩くというよりも転がるように移動し、だが少なくとも三本の脚があるのをギデオンははっきりと見た。一つ目が動いて彼の姿を認め、そしてそれは去った。
スライムフットは下の船室にいるよう新芽に指示した。この場所は奇妙かつ独特で、過ぎてきたばかりの広大な海よりもずっと危険だった。だがそこには呼びかけてくるような何かがあり、スライムフットは恐る恐る甲板へと続く階段を上った。アルヴァードとティアナが手すりから降ろされた梯子近くに立ち、他の人間らは船首にいた。
スライムフットは艦橋近くの影の中に立ち、だが何か奇妙な衝動に引かれて手すりへ向かった。スライムフットは身をのり出し、眼下のもつれた草木を見下ろした。
暗闇の中、輝くものが下草の間を動いていた。その何かが言った。『きみはだれ、どこからきたの?』
スライムフットは返答した。『スライムフット。ウェザーライトで来た。きみたちは?』
『いぐざりと、いるぐす、しるすとーか、それに――』 スライムフットは名前の洪水に圧倒され、そしてその声が尋ねてきた。『でもきみはなに? きみはまるで――』 続く言葉は映像や香りへと転じた。太陽に熱せられた鮮やかな緑の葉、花、豊かで湿った土。
『ヤヴィマヤ』 スライムフットはそう伝えた。スライムフットはヤヴィマヤから来たとラフは言っていた。そしてベルゼンロックを倒したなら、スライムフットと新芽はそこへ帰るべきなのだろう。だがスライムフットは決めかねていた。スライムフットはウェザーライト号しか知らないのだから。
「いるぐす」が言った。『ここにやびまやある、だいちに、ずっとむかしから。たたかいにきた』
『ぼくたちは悪魔と戦いに来たんだよ』 スライムフットはそう伝えた。
『あくま、あのあくま』 幾つもの声が囁きあい、言葉を伝えていった。『あのあくまとたたかう』
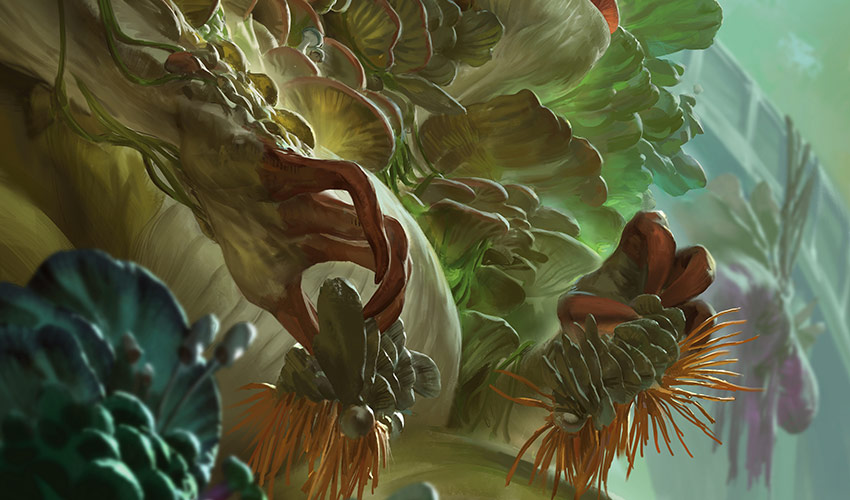
スライムフットはそのまま、新たな友と会話を続けた。このように理解されるというのは良いものだった。
次の夜明け前、ギデオンは頭をかがめてチャンドラの船室へ入った。「どうだ?」
「もう少しです」 ラフが言った。彼は卓のそばに腰かけ、通常はベルトに鎖で繋いでいる呪文書をめくっていた。その重力を無視する呪文を解除はしておらず、呪文書は彼の顔の高さにまで浮かんでいた。部屋の奥にはリリアナとシャナが立ち、チャンドラの姿をじっと見つめては批評し合っていた。
考え込むようにリリアナが言った。「頭を剃った方がいいかもしれないわね」
チャンドラは頭皮を掻きむしった。「むしろそうしたいわよ、髪をこんな泥まみれにされてるよりは」 彼女は陰謀団の賞金稼ぎに変装し、黒い革鎧の下に黒色のズボンと上着をまとっていた。その衣装は血と泥に汚れており、死んだ陰謀団員から奪ったものであるのは明らかだった。
シャナは反対した。「頭を剃るのは司祭だから、そういう類の注意を引きつけるのは良くないかな。けれどこう傷痕が要るね」
ラフが立ち上がった。「もうできます。ちょっと確認することがあっただけです。この呪文はアカデミーで習ったんですが、しばらく使っていなかったので。幻影術の高度な応用です」
今回、ギデオンはラフのその言葉を自慢とは思わなかった。少年の表情はとても真剣で没頭していた。ラフはチャンドラの前へと歩み出て言った。「まっすぐ前を向いて、じっとしていて下さい」
指にかすかな光をまとわせ、彼はチャンドラの顔をなぞった。その皮膚が縮れて隆起し、剣傷が額の脇から顎まで走った。その変質にギデオンは感心した。ラフは一歩下がって言った。「どうですか?」
リリアナは頷いて認めた。「完璧ね。愉快なくらい悪党そのものよ」
シャナはラフの背中を叩いた。「よくできました!」
チャンドラはその傷に恐る恐る触れた。「うっわ、変な感じ」
ギデオンが言った。「迅速に行動しなければな」 彼自身の変装はずっと簡単だった。鎧を脱いで武器を外し、衣服を破り、停泊した際に泥の中を転がり、そしてシャナが彼の顔面を数度殴りつけた。
「すぐ行くから」 身をよじって武器の装具を取り付けながら、チャンドラが言った。
ギデオンは廊下へ出て、甲板への階段を目指した。その後ろにリリアナが続いた。彼は尋ねた。「君の準備はいいか?」
「やる気十分よ」 彼女は両手で顔をこすった。「この契約文を身体から外してやるわ。ベルゼンロックを木端微塵にしてね」
「すぐに終わるさ」 ギデオンは努めて励ますような声色を出した。
リリアナの表情は皮肉を帯びていた。「どちらにせよね」
甲板へ続く階段を上ると、曙光のアーボーグが目の前に広がった。

空は今も灰に曇り、朝の陽光を暗くぼやけさせていた。ウェザーライト号が着陸した沼がちの低木林を住処とするものはいないようで、半ば埋もれた輪のような形状をしたファイレクシアの構造物があるだけだった。カーンとテフェリーが手すりの所に立ち、望遠鏡で何かを観察していた。ギデオンが近づくと、テフェリーはそれを下ろして顎を動かした。「あれだ」
暗い空に浮かび上がる火山の姿は昨晩も見ていたが、今では火口から伸びる要塞の外壁が見えていた。元々はファイレクシアの基地として作られ、そしてそれが打倒された際の噴火によって一部が破壊されていた。テフェリーが評した。「ベルゼンロックは幾らか改装を施したようだ。前に私が見た塔のほとんどが無くなっている」
ギデオンは距離を見積もった。「ここから徒歩で長い道のりになりますが、シャナさんの言う通り船をこれ以上近づけるのは危険です」
カーンの表情は読めなかったが、その点に関して心配はしていないように思えた。カーンは言った。「行きましょう」
チャンドラ達もジョイラと共に甲板にやって来た。チャンドラは陰謀団の剣を背負い、両腿には長ナイフをくくりつけていた。「すさまじい見た目だね」 テフェリーは彼女を力づけるように言った。
「ありがと」 チャンドラは微笑んだ。「臭いもすさまじいのはわかってるけど」
テフェリーは笑い声を上げた。「それについては言及するつもりはないよ」
ヤヤはチャンドラの肩を軽く叩いた。「忘れるんじゃないよ。もう大丈夫、あんたにはできる」
チャンドラは歯を見せて笑った。「ヤヤのお陰よ。ありがとう」
そして全員が集まると、ジョイラは言った。「陽動を開始しましょう。上手くいけば、すぐにわかる筈です」
「そうね、何も問題なく進むわよ」 リリアナはそう言い、だがそこで躊躇した後、ギデオンとチャンドラへと続けた。「殺されたら承知しないわよ。……何もかもが駄目になってしまうのだから」
チャンドラは鼻を鳴らし、だがギデオンは真剣に応じた。「私達は大丈夫だ」 ここに至るまでに、彼はリリアナという人物をよく知るようになっていた。その感情は自衛のための何層もの皮肉の下に埋もれているが、彼女の心配は本物なのだと。求めるのは契約の破棄とベルゼンロックへの復讐、だが同時に自分達が傷つくのを見たくはないのだと。
アルヴァードが彼らへと梯子の一本を下ろした。カーンが最初に降り、ギデオンがそれに続き、最後の数フィートは柔らかな苔に覆われた泥に飛び下りた。灰が舞う空が陽光を遮っていたが、地面は温かかった。背の高い草や蔓に覆われた木々が風をさえぎり、昆虫の群れが泥や水草に埋もれた池の上を飛んでいた。
ギデオンはカーンの隣に立ち、テフェリーとチャンドラが梯子を降りて合流するのを待った。カーンが先導して森の中を進み始めると、チャンドラが言った。「さあ、出発よ!」
ギデオンは励ますようにチャンドラの肩を抱き、言った。「上手くいくさ」 そう、上手くいかねばならなかった。
チャンドラは懸念とともにギデオンを見上げた。「でもさ……本当にリリアナは変わったってあんたは思ってるの?」
「思っているよ」 ギデオンは正直に言った。そして肩をすくめ、微笑んでみせた。「彼女自身がそれに気づいているかはわからないがな」
そう思う方が信じられない、チャンドラの表情はそう告げていた。
遺構が散らばる道を縫うように進みながら、辺りの風景は夜に見た以上に奇妙だとギデオンは感じた。カーンはまとわりつく蔓と棘の茂みをかき分け、自身の重さに地面が耐えられるかを試しながら前進した。空はひどく陰鬱で、下草には影が落ち、彼らが通過すると小さな光の粒が背の高い草から逃げ去った。
しばし歩いた後、地面に一つのほら穴が開いていた。その中には霊のような生物が数体、どうやら何かを話し合っているらしかった。身振り一つでテフェリーはそれらを取り囲む時間を遅らせ、全員がその場を通過して見えなくなるまで留めていた。そういった霊は陰謀団の味方ではないとジョイラは言っていたが、彼らは万全を期すと決めていた。昆虫よりも大きな何かが幾つか、輝きながら飛んで彼らをしばし追ってきたが、攻撃してくるものはなかった。

彼らは崩れた古い石壁に出くわし、それを乗り越えねばならなかった。その上まで来るとギデオンは、蔓と根に埋もれた大きな鉤爪らしきものの輪郭を見た。ファイレクシアの兵器がこの石の建築物を破壊した名残だった。
「本当に残骸だらけなのね」 チャンドラは飛び降りて言った。「ここにはどれくらいの人が住んでたの?」
「かなり沢山です」 カーンは言って、彼女を一瞥しつつその鉤爪を迂回していった。「友人のヴェンセールもかつて住んでいました」
「その友達って、灯をくれたっていう?」 チャンドラは尋ね、そしてはっとした。「ジョイラさんが言ってた――その人は死んだって。ごめん」
テフェリーは重々しい表情を見せた。カーンは頷き、言った。「良い友でした」
沈黙が破られた今、ギデオンはヤヴィマヤから考えていたことを提案しようと決めた。「ベルゼンロックを倒したなら、お二方――テフェリーさんとカーンさん、ボーラスとの戦いに加わって頂くことは可能でしょうか?」
テフェリーはからかうような笑みとともに彼を一瞥した。「罠にかかりに行く、ってことかい?」
ギデオンが返答するよりも早く、チャンドラが言った。「ちょっと。少なくとも今回は罠があるってわかってるわよ!」
テフェリーは首をかしげ、その言葉を認めた。「私は以前、ニコル・ボーラスと戦ったことがあるんだ」
ギデオンは驚いて声を上げた。「本当ですか?」
「とても昔のことだ。壮絶に敗北したがね」
「それは私達も。前回戦った時に」 とチャンドラ。
「それは頼もしい情報ではありませんね」 カーンはチャンドラへと言ったが、その声はどこか楽しそうだった。
ギデオンが言った。「リリアナが契約から解放されたなら、彼女は全力で戦えます。それをボーラスへの罠にできます……そう願います」
テフェリーは肩をすくめた。「私が灯を受け取った理由の一つは君達のその話だ。私はボーラスを知っているし、遅かれ早かれその計画がいつかは私の故郷にも及ぶであろうことも。それに今の私には守るべき娘と孫と曾孫がいる。物の見方も変わった」 彼はカーンの金属の肩を叩いた。「君はどうだ? 一緒に来る気はあるかい?」
「私はファイレクシア人がドミナリアへ再びやって来る前に、新ファイレクシアへサイリクスを持って行って滅ぼさねばなりません」
「ファイレクシアはそこから出られないだろう」 テフェリーは指摘した。「それを倒すための時間はいくらでもある。私が――」
カーンはそれを遮った。「あなたが時間に言及すると、意味が異なってしまいます」
テフェリーは笑った。「わかったよ、けれど私の言いたいことはわかるだろう」
カーンが断らなかったことにギデオンは気付いた。彼はすぐさま言った。「カーンさん、あなたの力をお借りしたい。加わって頂けたなら、私達にとって大きな戦力増になってくれるでしょう」
カーンはしばし黙ったまま、深い茂みをかき分けて進んだ。「その者が示す脅威というのは、火急を要するのですか?」
チャンドラは額の汗を拭った。「あいつ、アモンケット次元に酷いことをしたの。他の世界で同じことが起こるのを見たくはない。止めないといけないのよ」

ギデオンは頷いた。「ボーラスの計画の内容については定かでありませんが、時間がないのは確かです。ボーラスとの次の遭遇が重大なものになることも間違いないでしょう」
テフェリーは両眉を上げた。「どんな結果になるにせよ?」
「認めたくはありませんが、その通りです」
カーンは少し考えたように見え、そして言った。「その勧誘ですが、考えさせて下さい」
ギデオンが持ってきた食料と水で小休止をした後、要塞へと向かう道程はそれまでよりも楽なものとなった。
彼らは高所で足を止めた。高い瓦礫の壁を泥と植生が半ば覆っており、身を隠して偵察するには都合の良い場所だった。空は更に暗くなり、火山灰の雲の上空には嵐の気配が漂っていた。とはいえ要塞をつぶさに見る明るさはまだ十分にあった。
トレイリア西部にいた陰謀団の工作員が描写した通りだった。火山へと続く坂に掘られた古い運河と濠に、一本の長い石の通路がかかっている。運河は今や泥水に満たされ、ひどく飢えた鱗の生き物が棲んでいる。通路には厳重な門のある壁が幾つも立てられており、その全てが武装した冷酷漢とローブの司祭に固く守られ、合言葉と身分の証明が求められるという。火山自体の表面は滑らかで、そこから伸びるように築かれた半円形の城壁へと通路は続いていた。城壁を通る門は円形で、恐らく機能を停止したファイレクシア兵器の刺々しい形状を今も残していた。
黒く巨大な塔が頭上にそびえ、その上の空は灰と煙で更に暗く、威圧的な風景だった。この堅固な防衛と戦わずに進む方法があることをギデオンは感謝した。
ギデオンは物資の鞄をカーンに手渡し、彼はそれを肩に担いだ。テフェリーが言った。「呪文は君達が十分に余裕をもって門を通過できる間続く筈だ。入り込めたなら、まずは人目につかない場所を見つけるのがいいだろう、少なくとも物陰を。呪文が解けた際、どこか場違いな空気が漂って注意を引いてしまう可能性がある」
「わかったわ」 チャンドラが返答し、ギデオンを見た。「準備はいい?」
これ以上ないほど準備はできている、ギデオンはそう思った。長く汗ばむ行軍を経た後では、自分達二人ともウェザーライト号にいた時よりも陰謀団の狩人と虜囚らしく見える気がした。彼はテフェリーへと尋ねた。「中からも呪文はわかりますか?」
テフェリーは一歩下がり、顔をしかめて笑った。「大丈夫だよ。効果は目に見えるくらいだ。さあ、じっとして」
彼は片手を掲げた。ギデオンは反射的に身構えたが、何も感じなかった。そしてテフェリーとカーンがその場に凍り付いたのがわかった。葉を揺らす風の音も、虫の羽音も鳥の声も、全てが不意に止まった。再び要塞を見ると、様々な検問に立つ武装した人影の全てが今や彫像のように動かなかった。
チャンドラはギデオンの視線を受け止め、眉をつり上げた。「うわ、すご」
ギデオンも同意せざるを得なかった。そして、今も停止したままらしきテフェリーの声がした。「今だ。急いで、なおかつ落ち着いて進んでくれ」
「よし、行こう」 ギデオンが声をかけた。チャンドラは彼の腕に掴まり、そして彼女と歩調を合わせるよう気をつけてギデオンは坂道を降りていった。背の高い草と葦から踏み出し、低い外部城壁から冷酷漢が見通す開けた場所へ出るのは勇気を要した。だがギデオンとチャンドラが堂々と通路へ向かっても、世界は沈黙の中で動かなかった。
テフェリーいわく、その呪文は二人の周囲に時の流れの遅い空間を作り出す。そのため通常の速度で歩けば、自分達はその空間内部のあらゆる者には見えないほど素早く動くことになる。二人が通路の始点に着くと、足元の踏み固められた泥は滑らかな黒い敷石へと変わった。
最初の壁は、巨大生物の歯のような形状をしたファイレクシアの建造物だった。あまりに生物的なその見た目は、まるで地面から生えてきたかのようだった。それは陰謀団の赤い旗で飾られ、壁を通過するための巨大な金属の門は優に十二フィートの高さがあった。
二人は立ち止まり、チャンドラが言った「これを開けるのは無理そうね。時の泡より大きいもの」
それを押し開けようとしたらどうなるか、ギデオンにはわからなかった。わからない方が良いように思えた。「登ろう」
離れないよう気をつけながら、二人は門を登った。太い横材が良い足場になった。不恰好だったが、陰謀団の冷酷漢が自分達に毒矢を向けた条件ではもっとずっと困難だとギデオンは心した。門の向こう側で、二人は動かない衛兵や侵入者を捕えるための黒い呪文球を避けて進んだ。「思ったより時間かかったかも」金属の棘で覆われた落とし戸二つを注意深くくぐり、チャンドラは厳めしく言った。「テフェリーが十分な時間をくれるといいんだけど。いや、言葉遊びじゃなくて」

ギデオンは答えた。「わかっている。先に進もう」
ウェザーライト号は沼地のすぐ上を進んでいた。艦橋ではティアナが舵輪を握り、リリアナとジョイラは並んで立っていた。船は黒豹人と陰謀団との最後の戦いが行われた地域を目指していた。ジョイラは言っていた。「戦いというよりも虐殺だったと聞いています」
「私達にとっては、虐殺の方が好都合なのは確かよ」 リリアナはそう返していた。
ジョイラが身をのり出し、ティアナへと言った。「南に霊の街があるので、それを避けて」
持ち場につくまで、陰謀団にウェザーライト号の所在を知られたくはなかった。だがリリアナは前方に死を感じ取った。古い死と冷たい怒り。多くがここで死に、木々と深い緑を遺体安置所とし、植物が残骸を飲み込んで土へと腐らせ、そして長い時が過ぎた。残された骨は復讐を叫んでいた。リリアナは喜んでそれを叶えてやりたかった。彼女は言った。「かなり近いわ。ここで止まって」
早くもウェザーライト号の下の静まらぬ死者に呼びかけながら、リリアナは踵を返して甲板への階段を下りていった。
外は風が強くなっており、火山灰や雨や稲妻の気配が重く立ち込めていた。ギデオンとチャンドラが黒き剣を探し出してベルゼンロックを倒すまでの間、この不死者の軍勢は陽動として要塞を攻撃する手筈だった。だがリリアナの思い通りにいけば、その軍勢は同時にアーボーグにおける陰謀団の後ろ盾を壊すことになる。今日もたらされる痛手から、司祭と死の信者らが立ち直ることは決してないだろう。
彼女は船首へと歩き、段の上に立った。両腕を掲げると、皮膚に刻まれた契約文が紫色に輝いた。彼女は囁いた。「聞こえるでしょう。私のもとへおいでなさい。陰謀団に復讐と破壊をもたらすのよ」 鎖のヴェールに潜むオナッケの霊が彼女の心に囁いた。
そして下草と葦と茂みの中、死者が身動きをした。
永遠を要したようにも思えたが、ギデオンとチャンドラは門を開けることも自分達の存在を偽ることもなく、全ての検問を突破した。見つかることについては然程心配していなかった。自分達は非常に素早く動いているため、相手は呪文を唱えられたと思う余裕すらないのだとわかっていた。とはいえ扉や門の変化に気付かれ、要塞内への侵入を察知されるわけにはいかなかった。
開いた扉をくぐり、二人がようやく最初の広間へ入ると、チャンドラは疲れた声を上げた。「思ったよりずっと大変だった」
「三番目の罠で水の上を歩けるとわからなければ、決して辿り着けなかったな」
「もっと早く思い付けばよかった」 辺りの様子を把握しながら、チャンドラは頷いて言った。そこは広く薄暗く、内側へと屈曲した柱が天井を支え、まるで巨人の胸郭内を歩いているかのようだった。赤い旗が天井から垂れ、陰謀団の信者らが小さな集団で床に倒れ込んでいた。香炉が発する煙のもやが、浮遊する松明の暗い明かりとともに宙に留まっていた。ファイレクシアに作られ、陰謀団によって改造されたこの広大な部屋を異質と表現するのは簡単だった。チャンドラが言った。「隠れた方が良さそう。テフェリーの呪文はもうそんなに長く続かないみたいだから」

「下へ向かおう。ピットへ」 広間の隅、湾曲した柱の間に開いている入口へとギデオンが先導した。アカデミーにいた陰謀団の工作員から、広間の数層下にピットがあり、その近くに宝物庫も位置していると彼らは大まかに知っていた。チャンドラが陰謀団の狩人に、ギデオンがその虜囚に扮装し、ベルゼンロックの栄光と陰謀団員の娯楽のためにピットへと連行されるのを装う。そうすれば比較的容易にその区画を移動できるだろうという計画だった。ひとたびリリアナと仲間達が不死者の軍勢を引き連れて到着したなら、陰謀団の兵のほとんどは戦いのために要塞を出ることが見込まれる。その隙にギデオンとチャンドラは黒き剣を発見し、ベルゼンロックと戦う。
少なくとも、そう進むことを二人は願っていた。
広間を出ると、肋骨のように湾曲した柱が支える広い通路が伸びていた。肋骨というよりも食道か、ギデオンは顔をしかめてそう感じた。宙に浮かぶ松明は増え、だがねじれ曲がった通路には多くの暗がりがあった。二人は広い下り階段近くに、今のところ陰謀団員も衛兵もいない小部屋を発見して入った。ギデオンはすぐ近くの松明が揺らめきだすのを見た。彼はチャンドラへ向き直り、両腕を差し出した。「急いでくれ、呪文がもうすぐ切れるようだ」
チャンドラはギデオンの手首を縛る鎖を締め、心配するように尋ねた。「痛くない?」
「大丈夫だ」 ギデオンは安心させるように言った。光が再び揺らめき、二人は共に身構えた。
ゆっくりと、椀を満たす水のように周囲の静寂へと音が満ちていった。まず声が入口から響き、それはベルゼンロックの高名を繰り返し詠唱していた。悪魔王、アーボーグの王、荒廃の王、闇の末裔。そしてかすかなうめき声、悲鳴、金属音、叫び。松明が揺らめき、黒いローブの信者が広間を駆け、鎧をまとう冷酷漢がそれを追った。
ギデオンとチャンドラは厳めしい視線を交わし、そして階段を下りはじめた。
ジョイラはシャナと共に甲板に出て、リリアナが死者の軍勢を呼び出す様を見つめていた。
灰が立ち込める空は重苦しさを増し、どこか遠くで雷鳴が響いた。ウェザーライト号の下、草と茂みの中で人影が動いた。それらは黒豹人の死骸で、かつてまとっていた肉体の残骸が骨にまとわりついていた。武器はそれまで泥の下に埋もれていた錆びた剣や槍、もしくは棍棒や地面から拾い上げた岩だった。それらは群れ、集団を形成し、最後の戦いの際の編成を組み上げた。彼らは死ぬまで陰謀団と戦い、この沼に揃って埋葬されていた。
「何百体もいますね」 シャナが手すりから身をのり出して言った。ラフとアルヴァードはヤヤと共に甲板の向かい側に立ち、油断なく見つめていた。サリッドが階段を登って現れ、しばしそこに立っていたが、新芽たちを階下へ急ぎ引き返させた。
十体ほどの黒い人影が船首に現れ、シャナは剣に手をかけた。ジョイラがその腕を掴んだ。「駄目、あれはきっとリリアナに呼ばれたリッチだから」
それらは手すりの上にうずくまり、黒豹人の姿へと凝固した。彼らはその致命傷を負ったままで、鎧の上から胸や腕を切り裂かれ、とはいえもはや血は流れていなかった。シャナは剣の柄を手放し、だが用心深く見つめて評した。「奇妙な感じ」
「もっと奇妙になると思うわよ」 ジョイラがそう告げた。
リリアナは穏やかな声色で不死者らに話し、黒豹人らが返答した。その言葉はジョイラの耳にも届いたが、知らない言語を聞いているかのようだった。そしてリリアナが振り返って言った。「準備はいいわよ。船について来てくれるわ」
「わかりました」 ジョイラは息を吐き出し、手すりから離れた。長い待ち時間はようやく終わり、いよいよ陰謀団と対決するのだ。「ラフ、ティアナに伝えてきて――」
「ジョイラ船長!」 アルヴァードの叫びが響いた。
ジョイラは振り返り、そして目を見開いた。離れた沼から、一体の巨大な生物が立ち上がっていた。身体は斑模様の暗緑色、頭部は優にウェザーライトの半分ほどもあった。ねじくれて長い四肢が沼の木々の間から這い出たが、それは頭に比較して明らかに貧弱だった。頭の半分ほどもある大口が開き、洞窟のようなその中には牙が並んでいた。
シャナが叫んだ。「リリアナ、あれもあなたが呼んだの!?」
船首でリリアナは罵った。驚きというよりも苛立ちがそこにあった。「呼んでないわよ! それにあれが何なのかはともかく、死者じゃないわ!」
ジョイラが呟いた。「もっと奇妙になるとは言ったけど、こういう意味じゃなくて」 彼女は魔力を引き出し、光と大気を震わせて防護呪文を唱えた。
ラフが隣に駆けてきて、その生物を見つめた。「うわ、あれが何なのかわかれば、たぶん――」
ジョイラは振り返った。「リリアナさん――」
黒豹のリッチが屈んでリリアナへと囁き、彼女はそれを翻訳した。「あれはヤーグル、ベルゼンロックがヤークルとかいう馬鹿を蛆虫に変えて、それを食べた蛙がああなった、ですって」 彼女は憤慨に片手を振った。「何の役にも立ちやしない!」
「殺し方は知ってないの?」 シャナが尋ねた。
リリアナは顔をしかめた。「そこまでは。私達全員を殺そうとしてるってことくらい」

ジョイラは覚悟を決めた。「こんなもので止められるわけにはいかないのよ」 だが遅れてしまうだろう。ギデオンとチャンドラはウェザーライト号の到着を待ちわびながら、要塞内に閉じ込められるかもしれないのだ。
そしてヤーグルが咆哮し、ウェザーライト号へと飛びかかった。
ギデオンは気を張りつめて待っていた。彼とチャンドラはピットを取り囲む観客席のすぐ外に立っていた。巨大なアーチの廊下の先ではベルゼンロックを賛美する詠唱が音を増し、ピットから聞こえる武器の激突音と悲鳴をのみこんでいた。
「もう皆来てもいい頃なのに」 チャンドラが声をひそめて言った。「何かおかしいよ」
それこそギデオンが怖れていたことだった。二人は二度移動し、人目につかない場所で待とうとした。だが観客席を取り囲む廊下も広間も、信者と司祭とで更に混雑を増すばかりだった。彼らは自分達の虜囚がピットで死ぬまで戦う様子を楽しんでいた。黒き剣が収められているらしい宝物庫の入口は近く、そのためギデオンは撤退したくはなかった。だが群集に飲み込まれずにいるのは困難で、二人は次第に観客席へと流されていった。
リリアナが不死者の軍勢を作り上げる所で何かが上手くいかないか、もしくはもっと悪いことに、何かの攻撃を受けているか。もう来てもいいはずだった。そして信者らは召集されて外の防衛へ向かい、この場所全体が開ける。今はとにかく待てば――
信者の群れが廊下になだれこみ、チャンドラは前方へと押された。ギデオンは鎖で彼女を受け止めようとしたが、多くの手が彼の背中を押し、二人は群集とともに観客席へとよろめき出た。
二人はピットの端へ続く広く開けた通路に出た。悲鳴と激突音は更に大きくなり、だがギデオンの位置からピットの中は見えなかった。何百人もの陰謀団員が巨大な空間を取り囲む棚のそばに立ち、賛歌を詠唱していた。松明がピットの上に浮遊し、湾曲した天井からは赤い旗が下がっていた。チャンドラは出口を探したが、ギデオンは人々の頭の上から、最も近い出口は群集に塞がれているのを見ることができた。
「ウィスパー様がお見えである」 周囲の信者らが詠唱した。「ピットへ来たれとお呼びである」
群衆が道をあけ、赤いローブの司祭が進み出た。信者らは床に這いつくばり、その女性司祭は彼らの背中を踏みつけて高座へと上った。そして両腕を広げてローブを脱ぐと、邪悪が瘴気のように放たれた。「悪魔王様!」
ギデオンは聞こえないように罵った。詠唱は強まり、観客席の奥にある巨大な両扉が低い音を立てて開いた。松明は揺らめき、影の中から巨大で凶悪な姿が現れた。ベルゼンロック。悪魔は翼を広げて詠唱と信者の悲鳴に浴し、火明かりがその青白い皮膚を照らし出した。頑強で筋肉質の身体、頭部には屈曲した太い角が伸びていた。悪魔は進み出て、闘技場隅の玉座らしきものに腰を下ろした。続けて悪魔は身振りで何かを指示し、ウィスパーが深く頭を下げた。そして女司祭は背筋を伸ばし、叫んだ。「ピットへ入り、ベルゼンロック様を称えよ!」

観客席のそこかしこで、狩人と信者が虜囚をピットへ突き落した。ウィスパーが振り返り、その凝視がギデオンとチャンドラに注がれた。「そなたもその男を送り出すがよい! 共に死にたいのでなければな」
チャンドラは驚いてギデオンを見上げた。自分達がやってはならない過ちを犯したと彼はわかっていた。ギデオンはチャンドラから離れ、小声で言った。「私をピットに落とせ」
「ギデオン――」 チャンドラはためらった。
「やってくれ。時間を稼がなければ」 ウィスパーは獲物を察した捕食者のように二人を見つめていた。「急げ!」
チャンドラに押され、ギデオンはよろめくふりをして背中からピットへと落ちた。
