贄
前回の物語:招かれざる訪問者
ネファリアの高地、ガヴォニーとの州境近くに深く暗いザヴァ湖が横たわっている。その岸に居住し、漁を行ってきた者達は湖の深淵に怪物が棲んでいると昔から伝えてきた。だが村人の請願にもかかわらず、アヴァシン教会は彼らを守る聖戦士も天使も派遣しなかった。イニストラードに狂気が増大する中、村人はどのように湖の怪物と向き合うのだろうか?

ミアは怪物の昔話を信じていなかった。
怪物を信じていなかったからではない。その真逆だった。彼女は多くの物事を信じていた、大人のほとんどは考えることすら恐ろしいと感じているようなものすらも。生者に取り憑く霊魂。狂人に縫い合わされ、動き出した屍。残忍で貪欲な狼男。食物を選ぶように村人を見る吸血鬼。彼女はこれらを信じていた、口に出すべきではないとされている物事を――口に出さなければ、現実にはならないとでもいうような物事を。
違う。世界にはとても多くの怪物がいるのだ。村の年長者がそれを口にすることを怖れる怪物は、彼女にとっては街の噂話に根拠のない証拠を加えるだけの、細かい所は曖昧でひどく怯えさせるだけのものだった。
ウィルバーは全く異なる意見だった。
「あれは絶対本物だよ」 彼はそう力説し、牧草の地面を拳で打った。「ヴェリルが言ってた、前に見たって――ほんのちょっと見ただけ、でもあいつの船くらいの幅があったって」
ミアは目を丸くした。「ヴェリルは前、天使に口付けしたなんて言い張ってた。ずっと長いことギトラグの話を聞いてきたけど、本当に見たって人はどれくらいいるの? そんな馬鹿話はそろそろ卒業する年齢じゃないの?」
ウィルバーは立ち上がり、かぶりを振った。「ミア、これはつまらない作り話じゃない。君は毎日ザヴァ湖に行ってないし、僕が何をしてるかも知らない。特に最近のことは。霧は異常だし、寒気がすごい。深い所には魚じゃない何かがいる」
「それはあなたの漁師としての専門的な意見? 十五歳になっても自分で漁に出ることを許してもらえない漁師の意見なの?」
ウィルバーは顔を赤くした。「そういう話じゃないんだ、ミア! 僕は真剣に言ってるんだ、君は鈍すぎる」
ミアは羊の群れへと歩きながら肩をすくめた。数頭が彼女の意図よりも少し離れつつあった。「ウィル、暗闇を怖がるのは無意味よ。怖いのは、暗闇の中にいる何かなんだから」
ウィルバーは顔をしかめて彼女を追いかけた。「何だよ、それは君の立派な親父さんの受け売りかよ?」 ミアはその餌には食いつかず、だがそれでもウィルバーは続けた。「スキルトの民の一員として世界を旅する名高い処刑者、でも忙しすぎて故郷の怪物は倒せない」
「けちくさい町人の妄想とやり合うのに忙しいのよ!」 ミアは素早く振り返り、牧羊杖を振り回した。「見なさいよ、ウィルバー。何も問題じゃない。この村人も、私達も。本物の怪物が取り憑くほどの大きさもない、おかしな小さな村! ただ行き過ぎた想像力からゆっくり自分達で勝手に狂気へ堕ちてく、名も無いどこかの田舎の村」

彼女は背を向け、羊の群れを見て、溜息をついた。一頭が群れから離れてさまよっていた。その羊は石だらけの丘の冒険を続け、首の小さな鈴がかすかに鳴った。彼女は追い始めた。
「それは君の親父さんが言い残していった事か? それは問題じゃないのか?」
ミアは足を止め、怒りを込めてウィルバーを睨み付けた。彼は少し青ざめた様子で、たった今口から流れ出た言葉を飲み込もうとしているかのようだった。ミアは顔をしかめた。
「そんなことを言わないで」
「……もしかしたら僕が――」
「わかってるでしょ、私の方が喧嘩は強いって。そんなことは言わないで」
彼女はウィルバーが返答するよりも先に踵を返し、頭上で牧羊杖を振り回すと小走りに駆け出した。短い突き、幾つかの鋭い命令、そして強情な羊の顎の下に杖を入れて、彼女は群れのほとんどを牧草地へと移動させた。
ウィルバーは逃げ帰ったのかと彼女は肩越しに一瞥した。驚いたことに、彼はまだそこに立っていた。言葉を失い、迷っているかのように。
「あんなことを言うつもりはなかったんだ!」 牧草地の向こうから彼は叫んだ。ミアは溜息をついたが、その顔には思わず笑みが浮かんだ。
「わかってる」 ミアは鋭い口笛を発し、羊を帰らせようとした。ウィルバーは彼女に追い付こうと牧草地を横切って駆けてきた。
「言っとくけど、君が喧嘩で僕に勝てるからじゃないぞ。君はできるだろうけど、そうじゃない」 ウィルバーは彼女の隣を大股で歩きはじめた。ミアは声をあげて笑った。
「わかってるわよ、ウィル。あなたのそういう所がいいの」
二人は歩き続けた。互いの間の心地良い沈黙を羊の鳴き声が時折遮っていた。
その週遅く、ミアは肌寒く灰色の夜明けに目覚め、羊小屋の一部が壊れているのを発見した。素早く数えると羊が一頭いなくなっており、彼女はその朝を捜索に費やしたが無益だった。おそらくは乱暴な羊が柵を壊したのだろう。時々そういう事があり、そしてさまよい出て森の狼に食べられてしまうのが常だった。ミアは自身の不運を呪い、柵を修理し、それ以上は考えなかった。
ミアは市場を歩き、乏しい売り物を見繕った。村の市場が繁盛したことはないが、特に先の季節の収穫は乏しく、山道をやって来る隊商の数も減少したために普段よりも選択肢は更に少なくなっていた。魚すら品数は僅かに思え、最も良いものですら何ということのないタラの一袋だった。
「レーレン、今週は獲れてないの?」 ミアは年老いた漁師へと会釈した。
レーレンはかぶりを振り、溜息を発した。「水の上でも多くの時間を過ごせんよ。霧がいつもよりも濃すぎる。危険だ」
「危険なのは確かさ」 しわがれた別の声が言った。「それに霧だけじゃない。賢い漁師は湖に近づこうとはしないよ」

ミアはその声の主を見て目を丸くした。「ヴェリル。もし漁師全員があなたみたいに賢いなら、もうみんな飢え死にしてるでしょうね」
「賢い奴はわかってるのさ、ギトラグが再び目覚めるってな!」 ヴェリルが押した。彼の声には冷笑がひそんでいた。「湖で漁をするのは馬鹿だけだ」
「湖をそんなに怖がる漁師も、そんなに熱心に自分の下手さを架空の獣のせいにする漁師も見たことないわよ」 ミアはそう言いながらレーレンの袋から最も太ったタラを取り出し、彼へと追加のコインを渡してみせた。
「何を架空の獣と言うのかは注意したほうがいいぞ、嬢ちゃん」 低い声が轟いた。
ミアはその声の主に対峙しようと振り返り、驚いて止まった。カリム。樽のような胸、どの商人達よりも長身の巨体がそびえ、普段通りに厳めしい顔をしていた。太い眉に濃く黒い髭、引き網の跡がついた太い腕。釣り用の湾曲したナイフが革帯に下げられ、それが彼の身体のうち唯一細いものだった。
「ギトラグは本当にいる。当然、処刑者の嬢ちゃんは世界の怪物を疑うのではなく、そう知っている筈だろう」
ミアは他の商人や買い物客ら数人が近寄り耳をそば立てている、もしくはこっそりと見つめているのに気が付いた。彼女は歯を食いしばった。
「処刑者の娘は知ってるんです、『怪物だ!』っておびえた子供みたいに叫ぶ前に、まず他の可能性を全部考えることを」
ヴェリルはカリムの背後へと忍び足で移動し、油ぎった金髪が彼の目の上で揺れた。「羊飼いの娘の無礼な言葉だね。まるで自分が処刑者だと言っているようだ」
「あんたが漁師だって以上に私は処刑者よ、ヴェリル」 彼の顔から自己満足を(と、ほんの数本の歯を)叩き落したいと思いながらも、カリムが見ている所で拳を放つべきではないと知っていた。ミアは彼へと注意を向けた。
「カリム長老。当然、皆誰も、本当にギトラグを見たなんて言うヴェリルのほら話を信じてはいません」
「わしは信じておる。この目で見たからな」
市場は一斉に沈黙し、ミアは礼儀も何もかもを忘れてカリムを凝視した。ヴェリルは何かを言おうとしたが、カリムはその手をヴェリルの胸に当てて若者を黙らせた。長老は振り返り、市場全体へと向けて演説を始めた。「昨晩、長老達は会合を持った。これより湖での漁は更なる通知があるまで禁止とする。午後に広場へとその告知を貼る予定だ」 彼は片手を挙げて不満の声と不安の叫びを制した。「村の安全が最優先だ。わしは……わしはアヴァシン教会へと助力を求める書をしたためた」 彼は視線をミアへと移した。「君も父上へと書いてくれるだろうが」
静かな沈黙が群集に降りた。カリムの凝視を受け止めると、ミアの鼓動は高鳴った。その冷静さと威厳に満ちた外面の下に、彼女はそれを見た――深く低く響く恐怖、その毅然とした視線の中に荒れ狂う下層流。彼女は息をのみ、恐怖の感覚が這い上がってきて喉を掴まれるのを感じた。
「父さん、やっとコリアンダーがあったよ!」 ミアとカリムが振り返ると、ウィルバーが市場の通りを駆けてきた。彼は緑の葉のようなものを振りかざし、その顔には奇妙な笑みが貼りついていた――つまずいて敷石の上に大の字になるまでは。ミアは不安な笑い声を上げ、息を吸い――そして息を止めていたことに気が付いた。周囲では、傍観していた者達がそれまでの活動を再開し、何人かはウィルバーを嘲り、多くは小声で囁き合いながら散開した。場の緊張は砕けた。
カリムはコリアンダーを取り上げ、ウィルバーの髪をかき回した。ウィルバーは恥ずかしそうに辺りを見て、そしてミアと目が合った。彼の表情は間抜けな困惑から一瞬で真剣なものとなり、彼は眉をひそめた。大丈夫か? 彼はそう口を動かした。
ミアは瞬きをし、驚き、そして肩をすくめた。彼女は口を開こうとしたが、ウィルバーは既にカリムへと向き直り、早口で喋りながら長老を市場から連れだすように彼女から離れていった。ミアは独りで立ち、感情と、思考と、疑問の渦に揉まれていた。
「親父さんに手紙を書いてくれって言われたのか?」 ウィルバーは疑い深く見つめた。ミアは頷き、ゆっくりと身動きをした。「でも……君の親父さんを嫌ってるのに」
「信じて。私は忘れていないから」
ミアはスープを味見し、匙をウィルバーへと手渡した。彼は一口すすって顔をしかめ、鍋へと塩をもう一つまみ入れた。
二人はミアの小屋の中、小さなかまどの傍に縮こまっていた。ゆらめく炎が部屋へと温かな輝きを投げかけ、薪の煙が羊肉のシチューの味わい深い香りと混じり合っていた。ウィルバーが袋から新しいパンの塊を取り出し、ミアは注意深く鍋を炎から上げ、近くの机の上に置いた。彼女は椅子へ座ると腰からナイフを抜き、パンを切った。ウィルバーは眉をひそめた。「今朝それで羊の柵の縄を切っただろ。洗ったか? シチューの羊肉を切ってからも。三か月前に君の髪を切ってからも」
ミアは顔をしかめた。「これは私の最高のナイフ。何にでも使えるんだから」
ウィルバーは肩をすくめ、近くの棚から椀を掴み、座るとシチューを惜しみなくすくい上げた。「親父さんと連絡をとる方法は知ってるのか?」ミアは混乱したように顔を上げた。「君の親父さんと」
「ドルナウにスキルトの民の分隊があるとは知ってる。父はそこに」 ミアは答え、ナイフを鞘に仕舞った。彼女はパンをシチューに浸し、一噛みして、ウィルバーが調理を手伝ってくれた時にはいつも味が良くなることを喜んだ。
「返事が来たことはあるのか?」 ウィルバーは真剣に、自身の椀ではなくミアを見つめた。
「手紙を書いたことはないの」
「なんで――」
「些細なことで困らせたくなくて」 ミアはシチューをもう一匙ほおばり、ウィルバーの椀を示した。ウィルバーは唸り、そして一噛みした。
「今回は手紙を書くのか?」
ミアは歯を食いしばらないように食べ続けた。ウィルバーは気付いていないようだった。
「親父さんは来てくれると思うのか? 誰かを連れてきてくれる? 言わせてもらうけど、僕は思わないんだ、親父さんが一人でギトラグを倒せるなんて――」
「知らないわよ!」 ミアは机に拳を叩きつけ、彼の言葉を遮った。「わからないわよ、手紙を書くかどうかも」
「でも――言わせてもらうけど、それが親父さんの仕事なんだろ? 怪物を倒すのが」

ミアは立ち上がり、激高して両手を宙に振るった。「私達はまだ知らないじゃないの、本当に怪物がいるのかどうかも!」
ウィルバーは息を呑み、言葉を失ったようにミアを見た。「まだ信じてないのか?」
「まだ、確信できないの。本当かどうかもわからない噂の証拠しかないし――」
今やウィルバーは立ち上がっており、その声には鋭い怒りの棘があった。
「僕の父さんが見たって言うんだ! ヴェリルも! ミア、何で君は嫌がるんだ――」
「ヴェリルは馬鹿な奴だし、あなたのお父さんは、……あなたのお父さんは」 ミアはウィルバーと目を合わせた。二人は机越しに対峙し、上気して熱くなっていた。この時頭に血を上らせながらも、自分とウィルバーの目線が同じ高さにあるとミアは気付かずにはいられなかった。夏の頃には自分は彼よりも掌一つほど高かったのに。
「僕の父さんは何だよ、ミア?」
「長老よ。注意しすぎるのが仕事の」 ミアは下がった。
「父さんは見たって言ったんだ。用心深いから布告を出したんじゃない、見たからだよ」
「そうじゃないかもしれないでしょ」 ミアは腰を下ろし、ウィルバー製のシチューを再び口へと運び始めた。
「父さんを嘘つき呼ばわりするのか?」 ウィルバーの声は苦痛を持って、先程の怒りの叫びよりもずっと深くに切り込んだ。
「誰もが間違うものよ、霧の中の物を見て。皆いつもそう、処刑者は見分けないといけない――」
ウィルバーは不満にうめいた。「そんなふうに言うのはやめるんだ、ミア! 君は処刑者じゃない!」
「あなただって漁師じゃない!」 ミアの両目は憤りにひらめいた。
ウィルバーの両眉が一瞬、怒りに歪み、そしてその表情はゆっくりと戻った。彼は溜息をついた。
「そうだよな、僕達は。漁師でもないし、処刑者でもない。教会から助けが来るまでは」 ウィルバーは鍋へと向かい、ミアの空の椀を掴むとシチューを更にすくった。ミアは眉をひそめた。馬鹿なウィル、本当に喧嘩をする程に怒ることもできない。彼女はウィルバーが座り直すと、シチューを口へと運んだ。
二人はしばしの間黙ったまま食べていた、それぞれの思考にふけりながら。
「ただの噂じゃないんだ」
ミアは椀から顔を上げ、興味深くウィルバーを見た。彼は自身の椀を見つめていた。「小舟が壊された。建物に傷が。それに最近、家畜が行方不明になってる。誰も怪我をしていないのは幸運だって父さんが」
ミアは動きを止めた。行方不明の羊……
ウィルバーは顔を上げた。「ミア、お願いだ。君も信じてくれ。少なくとも信じるふりをしてくれ。ただ……ええと安全のために? 僕は――僕は、君に怪我をして欲しくない」
ミアは躊躇した。ウィルバーは市場で会った時と同じ真剣さで見つめている、とてもよく知った顔に、奇妙に思えるほどの真剣さで。それは彼を大人に見せた。それは自分を……彼女はその感情を言い表すことができず、顔をそむけた。
「そうね」 彼女は溜息をついた。「確信したってわけじゃないけど」 ウィルバーの興奮を視界の端に認め、彼女は付け加えた。「でも疑う証拠は十分にある。可能性はある。そして『ありえなさそう』が『ありそう』になる時は、監視しないといけない。今、必要なのは用心と努力――監視に就く時は、無害な雑音も無視できぬ影もない」

「何で君はいつもそんなふうに、処刑者の手引きか何かの引用みたいに話すんだよ」 ウィルバーは手の上に顎を休め、ミアへと眉をひそめてみせた。その表情には歪んだ笑みが浮かんでいた。
「私はまだ処刑者じゃないかもしれないけれど、もう二か月もすれば十五歳になるわ」 ミアは棚へと向かい、その中をかき回しはじめた。何かを探すために、同時にウィルバーの奇妙な顔を見ないために。奇妙で、間抜けな、優しい、素敵な顔を。
「スキルトの民に入るのか?」
ミアは棚の中の古い羊皮紙と書物を幾つか脇によけ、探し続けた。「やってみようと思うの。羊の世話をする人生をずっと続けるつもりなんて――あった!」 ミアは振り返り、小さな箱を持って机へと戻った。単純ながらそれは頑丈に見えた――樫の板は鉄で補強されており、ずっしりとした鍵が手前についていた。ミアは上着の中に隠していた首飾りに手を伸ばし、鍵を手に取り、箱を開錠した。
「うわあ」 銀で装飾された小さな弩弓を彼女が取り出すと、ウィルバーは目を見開いた。薄暗い炎の明かりの中でも、その素晴らしい作りが見てとれた。銃身の両脇には聖印が並んでいた。ミアは慣れた手つきで弦を引く操作をすると、細く軽量ながらもその力が感じられた。彼女は狙いを前方の窓へと定め、指でそっと引き金をこすった。弾ける重い音が響き、震える弦から放たれた埃がゆらめく明かりの中へと飛んだ。
「それは君の親父さんの?」
「私のよ」 ミアはにやりと笑った。「スキルトの民の盾持ち、有名なオルガードは知らない? 自分の身を守れない娘の窮地に立ち上がったっていう」
「君がそれを扱えるのはわかったけど、なんで撃ち方を知ってるんだ?」 ウィルバーはその武器に感心し、もたれて座った。「何でそれを隠してたんだ?」
「目の前に何もなくとも、武器は緊張と危険を高める」 ミアは矢筒を取り出し、その中身を数えた。「必要な時は自分の腕だけを構えておきなさい。そうしなければならない時にだけ、武器を取りなさい」
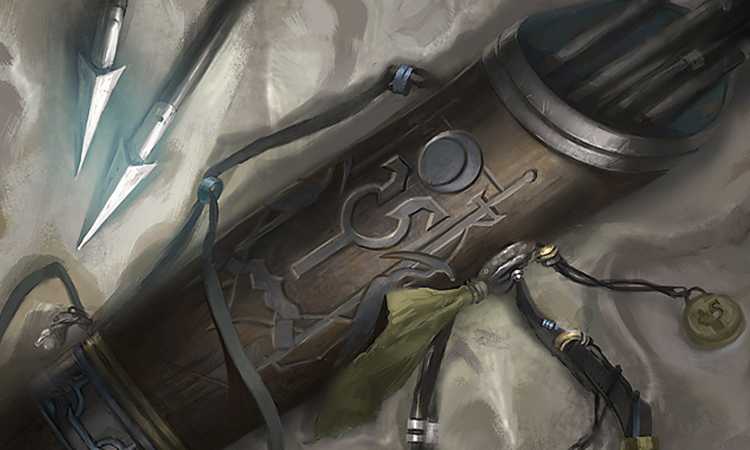
ウィルバーはかぶりを振り、にやりと笑った。「僕が思うに、『処刑者みたいな口をきくのは止めろ』なんて、すぐに誰も君に言えなくなると思うな」
「心からそう願うわ」 ミアは弩弓と矢を手にとり、後方の小部屋へ向かうと寝台の傍にそれを置いた。戻ってくると、ウィルバーは既に椀を空にしていた。彼はミアへと微笑みかけた。
「ありがとう、ミア。僕だけのためだったとしても」
「うぬぼれないでよね」 ミアは彼へと笑みを返した、自身の胃袋の中にはためく想いに目をそむけながら。
ウィルバーは立ち上がった。「そうだな。教会が助けてくれるよ。それとも、君が手紙を書いてくれるなら、君の親父さんが戻ってきてくれるさ。でも何にせよ、僕達はできる事をしよう、ギトラグを近づけないために」
「本当にいるのならね」 ミアは自身にそう言い聞かせずにはいられなかった。親切にもウィルバーはそれを無視した。
「僕は父さんを信じるよ、僕達の安全を守ってくれるように」
ウィルバーはそして彼女を見た、またも真剣に。
「僕も、僕達の安全を守るようにできる事をするから」
ミアは彼へ向かって歩き、近づいた。二人の鼻先が触れる程だった。
そして彼女は彼の頬に掌を触れ、軽く押しやった。
ウィルバーは驚きに声を上げ、よろめいて一歩後ずさった。ミアは目玉をぐるりと動かした。
「もう帰りなさいよ、ウィル。でないと家に着くまでに暗くなってギトラグに食べられちゃうわよ」
ウィルバーは口の端を歪めて笑った。そして彼女へと小さく手を振り、背を向けて小屋から出ていった。ミアは扉まで出て、彼が視界から歩き去るのを見ていた。
そう、あいつの馬鹿な顔への正しい反応がこれ。
その夕の喜びは長くは続かなかった。冷気と侘しさが忍び寄り、数週間をかけて日は短くなっていった。冬が近づき、霧はその灰色の触手をザヴァ湖から長く遠くへと伸ばし、弱々しい太陽がそれを岸へと追い返すよりも早く村の中深くまで這い進んだ。ひときわ寒い朝には、霧は丘の上のミアの小屋までも包み込んだ。
ミアは夜には弩弓を寝台の側に置き、時間を作っては狙撃の練習をした。
その間もずっと、教会からの処刑者は来なかった。間もなく隊商も完全に途絶え、更に多くの漁師が市場をぶらついては互いに身を寄せて不満を囁きあった。ミアも折れて父親へと手紙を書いた。十枚ほどの紙屑を作りながら、助力を願う短く堅苦しい手紙を書き上げた。
返信は来なかった。そのすぐ後に、郵便配達員が街を訪れなくなった。二日のうちに、ギトラグが郵便配達員を食べたのだという噂がまことしやかに語られるようになった。あの気の毒な青年は寒く危険な旅をしてまでこの哀れな小村へ来たくはないのかもしれない、代わりにドルナウで冬を過ごそうと決めたのかもしれない、ミアはそう考えた。
しかしながら、ミアには説明しきれないギトラグの噂が幾つもあった。初雪とともに更に三頭の羊がいなくなった。その度に羊小屋の異なる箇所が壊されていた――まるで何かが柵の強さを試しているかのように。それとも、ミアが思い込もうとしたように、驚いた羊がやみくもに柵を壊しているのだろうか。だが何がそれらを驚かせているのだろう? 最近では、彼女は夜に柵が壊れる音を聞いた。だが弩弓を手に小屋を飛び出した時には、壊れた木と警戒する羊の鳴き声以外には何もなかった。
その後、彼女はついに観念し、父が残していった金に手をつけて地元の大工を雇い、羊小屋の補強を手伝わせた。自身で稼いだのではない金を使うのは嫌だったが、この蓄えがあるのは幸運だとわかっていた。季節の早くに湖から遠ざけられた漁師たちの生活は、降雪が始まるとともに苦しくなった。多くが隣人の親切に頼った――だが村の痩せた土からの収穫は限られていた。地元の酒場では頻繁に喧嘩が起こるようになった。ギトラグを呪う声が強くなった。染み通る霧がかつてないほど濃く深く立ち込める中、更に多くの町民が昼の早いうちに家へと退散し、扉を固く閉ざして窓に板を打ちつけた。
その間にも、父親が何かをしてくれるだろうというウィルバーの言葉は正しかったと証明された。冬が深まると、武装した男女が街路を見回り始めた。何人かは松明と剣を手にしていたが、多くはただの三つ又や肉切り包丁だけだった。彼らは常に分厚い外套に身を包み、フードをかぶっていた――それは忍び寄る冷気を防ぐためと同時に制服でもあった。どんなパン職人が包丁でギトラグと戦えるのだろうかとミアは訝しんだ。それは彼女を悩ませ、ある午後に彼女はウィルバーに尋ねるという過ちを犯した。

「巡視だよ、臨時の監視。ミア、前に『用心と努力』って君自身が言っただろ。僕達は監視して、何かを見たら警報を鳴らす」 ウィルバーは苛立っているように見え、彼の痩せた姿は雨を滴らせていた。
「私は単に疑問なの、それが本当に有用なのか」 ミアは同じく疑問に思った、何故ウィルバーが上着とブーツを脱がないのかを。もしくは何故座らないのかを。笑わないのかを。
「僕が単に疑問なのは、羊毛を売ってくれるのかどうかだ。そうしたら帰る」
「夕食は食べていかないの?」
「僕達の中に、沢山用意してくれてる人がいるから」 ウィルバーは腕を組み、ミアは訝しんだ。いつ彼は自分よりも背が高くなったのだろう。
「何なの、あなたは釣り竿を振り回して歩き回って、それで皆を守ってるの?」 彼女の心は黙ってくれと懇願していたが、その言葉は口をついて出た。
「君には言えない事もあるんだ。君が見ているのは僕達が村の安全を守るためにやってる事の、皆を生かすためにやってる事の上辺だけだ。なのに君にできるのは笑うことだけだ」
その言葉にある真実はやすりで心臓をこすり、血と生傷を残すように思えた。
「ミア、どうして君はまだここにいるんだ?」
ミアは彼の引き結んだ口元と、ひそめた眉を見た。彼の目は冷たく、疑問を投げかけていた。胃袋が怒りと悲しみにかき回され、苦味が喉元へと上ってきた。ウィルバーは続けた。
「どうして君は試験を受けにスキルトの民の出張所へ行かないんだ? 君の親父さんがそうしたみたいに僕達を置いてさ」
「私はお父さんとは違う。それに、私は……私はまだ十五になってない」
ウィルバーは笑った。そしてミアの胸が締め付けられた。彼がそのように笑ったのは初めてだった――何の喜びもない、棘だらけの笑い声。
「わかってるだろ、君の誕生日が来るより先に雪が降るって。そうしたら道はほとんど通れない。もし本当に試験を受けたいなら、君はもうここを発ってるはずだ」 彼は言い放った。その言葉は凍り付く大気のように鋭く尖っていた。「君は怖がってる。君にあるのは覚えた規則と虚勢だけだって怖がってるんだ」
ミアは羊毛の束を掴み、彼へと投げつけた。「これを持って出て行きなさいよ」
ウィルバーは革帯の小袋へと手を伸ばし、だがミアは力を込めて彼を押しやった。「出ていけって言ったの! お父さんのお金は取っておきなさいよ、そんなものはいらないわ」
「必要じゃないって言いたいのか」
ミアは唇を噛んだ。どうすれば自分が一番傷つくか、彼はそれを知っている。それがミアの過ちだった。
ウィルバーは片腕に羊毛を抱えて背を向け、敷居を越えながら小袋を投げてよこした。コインが弾け出て散乱し、床に音を立てた。
ミアは手を止め、冷気にもかかわらず汗をぬぐった。飼葉桶にできた氷を砕いて羊のために水を替えるのは今日三度目だった。この仕事や他の用事や雑用の間、彼女は息をつく間もなかった。太陽は既に地平線の下に沈み、最後のわずかな弱々しい光線を鉄色の雲の空に投げていた。小屋へ戻ると風がうなりを上げはじめ、コートの上からも寒さが骨身にしみた。
少なくともまだ雪が降ってない、彼女はそう思った。
二時間後、ミアは窓越しに白い突風がゆっくりと風景を圧倒していくのを見ていた。そうよね、寒くて惨めな誕生日の、何て完璧な終わり方なのだろう。
彼女は村の中へ行ければと願っていた。ウィルバーの家へと向かいたかった。あの喧嘩以来二人は話をしておらず、その空白の時は日ごとに重苦しくなり、今や二人を隔てる沈黙と広がりは増すばかりだった。期待こそしていなかったが、かつてのように自分の誕生日にウィルバーが訪ねてきてくれることを願わずにはいられなかった。
彼女はガラスに額をつけ、溜息を吐いた。それは息で白く曇った。
いつ目が覚めたのかはわからなかった――ただ、眠ってから少しして何かが自分を目覚めさせた。
彼女は伸びをした。炎は消えて柔らかな橙色の燃えがらが残っており、外では月光に照らされた雪のかすかな輝きが風景の輪郭を縁どっていた。嵐は止んで晴れ渡り、墨色の空には星がまたたいていた。何もかもが平穏に思えた。何が自分を起こしたのだろう?
そして彼女はまたも、それを耳にした。
ミシッ――バキッ! 裂け、砕ける大きな音が小屋の外で響いた。ミアははっとして上体を起こした。心臓が高鳴っていた。彼女はじっと耳を澄まし、緊張と警戒心を強めながら銀色の薄暗闇を覗き見た。だがそこにあったのは静寂だけだった。
彼女は大きく息をついて再び横たわり、眠気に再び頭を腕の上に置いた。あの音はおそらく凍りついた木が、冷気で樹液が膨張して割れたのだ。心配することは何もない、何も――
突然、ミアは跳ね起きて弩弓を掴み、コートをまとって外へと飛び出した。恐怖と怖れが胸を掴んでいた。
怖れたのは音ではなかった。
それに続く静寂だった。
驚いた羊の鳴き声がなかった。鈴の鳴る音もなかった。雪の中へと走りながらも、耳には何も聞こえなかった。彼女は弩弓を構え、速度を緩めながらも早足で羊小屋へ近づいた。
出迎えた光景に、寒気が止まった。
羊小屋の一区画が完全に裂かれ、囲いの杭が地面からそっくり引き抜かれていた。割れた板が雪の上に散乱しており、彼女が見ていると、一本の杭がひび割れて倒れ――そして差し掛けの屋根が崩れた。
ゆっくりとミアは忍び寄った。祈り、願いながら、とはいえ既に知りながら。羊小屋へ静かに足を踏み入れると、彼女の恐怖は現実のものとなった。

一頭の羊すら残されていなかった。その代わりに血と臓物が地面を覆い、今も立っている数本の杭に飛び散っていた。冷たい風が残骸の間から吹き込み、臓物の鋭い匂いが彼女を打った。彼女は身体を折り、コートの袖越しに息を吸いながら、胃袋を落ち着かせようとした。
気力を振り絞ると、雪の中の奇妙な影が目に入った。彼女は反射的に直立し、弩弓を構え、その……何かを見定めた。そして松明を持って来なかった自身を呪いながらゆっくりと横へ移動し、影を隠した。
薄い月光が新雪の巨大な足跡を露わにした。彼女は近寄った。その足跡は巨大な、水かきの脚のように見え、踵の先端には三つの鉤爪らしき穴があった。羊小屋の周囲を探すと、掃くような、引きずるような跡の中に、そして更なる血だまりの中に、更に幾つかの足跡がまばらにあった。
ギトラグ。
それを見つめながら、耳に心臓の高鳴りが聞こえた。羊小屋から出ていくのは幅広の引きずり跡と三つ又の踵を持つ水かきの足跡だった。それらは湖沿いの森を目指していた。
彼女の心が揺れ動いた。ギトラグが本当にいたなんて! それが羊の群れを食らったのだ。同時に、それが湖からこれほど遠くまでさまよい出ていることを意味した。つまり、もう村にも入り込んでいるかもしれない!ウィルバーに知らせねばならなかった。謝らねばならなかった。皆に警告しないと! 彼女はブーツで雪を踏みしめながら遠くのかすかな光を目指し、だが内なる、つきまとうような声が足を止めさせた。
もしも、ある脅威が人の仕業ではなく、怪物によるものであると判明したなら、処刑者はそれを追跡し、可能なら遠ざけねばならない。民や都市から離れてその怪物を殺すべし――恐慌を避け、怯えた無辜の者を混乱させぬために。
ミアは立ちつくし、白い息を激しくつきながら、何をすべきか迷った。間違いなく、ギトラグのようなものとやり合える方法はない。街へと警告せずにいることは信じられないほど愚かに思えた。ウィルバーと話さねばならなかった――むしろ、ウィルバーの父親と。カリムと長老達は何をすべきか知っているかもしれない。
けれど彼らは自分に手を貸してなどくれるのだろうか? あれほど疑っていた自分を? もし彼らが力を貸したいと言ったとしても、何ができるだろう? パン切りナイフや三つ又で武装したパン職人と農民の姿が脳裏にひらめいた。もしギトラグが羊の群れをほとんど音もなく食らい尽くしてしまったとしたら……
ミアは手に持った弩弓を見下ろした。月光にその銀が輝き、彼女はその側面に刻まれた魔法文字を指でなぞった。彼女は腰に手を伸ばし、そこにある長ナイフの柄に触れた。馴染みあるその刃は万能ナイフとして役割を果たしてきたが、その冷鉄の刃は霊魂や魔女を殺すために作られたものだった。
彼女は父の足跡を追い、処刑者となることを夢見ていた。だが彼は娘をこの「安全」な場所に残し、羊の群れを与えて忙しくさせておいた――気を散らし続けさせておいた。彼女の武器は埃をかぶり、もしくは生活道具となった。とはいえ彼女は自身の技術を磨こうと努めてきた。今、ここに自分はいる――十五歳となった自分に、危険が降りかかっている。彼女はとても長い間、羊飼いという役割を演じながら、最も望んだものになる許可を待っていた。
鼻から深く息を吸うと、冷たい大気が集中を研ぎ澄ませた。時が来た。処刑者となる最初の一歩。実地試験。例えギトラグを倒せずとも、少なくとも追跡し、その行動様式を多く学び、湖へと滑り込む前に目撃できるかもしれない――そうしたならその情報をカリムへと、もしくは父親やドルナウのスキルトの民へ伝えられるかもしれない。
ミアは弩弓を肩に乗せ、念入りにその跡を追跡した。彼女の無謀な、恐怖に駆り立てられた足取りは目的に直面して注意深いものとなった。
全くわけがわからなかった。
彼女は足跡を注意深く追って森へと入った。追うのはたやすかった――ギトラグはそれを隠そうとはしていなかった。だがその足跡は木々の間へ入るとすぐに途切れた。ありえなかった、ギトラグが細い木を登れるか、もしくは固く凍った地面を掘れるかでもしない限りは。これほど大きな足跡を残す何かが姿を消すなどありえなかった。
彼女は引き返し、足跡を更に念入りに調査し、周辺地域へと捜索を広げた。そしてそれを見つけた――新しい、人間の足跡が、ギトラグの足跡が途切れて少しの距離にあった。当初、彼女は誰かが捕えられたのではと怖れた。だがその微かな、孤立した足跡に抵抗の痕跡はなかった。何かが合致しなかった。
ミアは再び弩弓を構えると渦巻を描くように足跡から離れつつ手がかりを探し、あらゆる音へと耳をそば立てた。その足跡から更に二歩ほど離れた所で、一連の足跡と引きずった痕跡が再び現れていた――だがそれらはギトラグの足跡ではなかった。人間の足跡がそりの跡のような長い溝と混じり合い、湖へと向かっていた。
怒りが恐怖に取って代わった。ミアは足を速め、足跡と周囲との間に視線を走らせた。何者かが襲撃を装い、足跡を偽装し、そして足跡を消した。何者かが自分を欺こうとした。何者かが羊の群れを殺戮した。
その者は報いを受けるべきだ。
その跡はほぼまっすぐに湖へと続いていた。近づくごとに彼女は足取りを緩めた。湖岸には松明の灯りが揺れていた。彼女は木から木へと身を隠し続けながら素早く移動し、やがて夜の冷気から滑り出る声が聞こえるほどに近づいた。松明は幾つかの人影を照らし出していた。全員が黒い外套をまとい、フードを引き上げていた。ミアの場所からは誰の顔も判別できなかった――彼らが話す言葉も全く聞き取れなかった。彼らは円を描いて立ち、頭を下げ、低くゆるやかに何かを詠唱していた。少しの時が過ぎ、彼らは近くの船へと列を成して向かった。結構な大きさの船――レーレンの船だった。それを把握してミアは愕然とした。何が起こっているの?
フードの人影が乗船していくのをミアは観察していた。彼女は歯を食いしばり、それぞれが立ち止まって荷物を――近くのそりから羊の死骸を抱え上げて積む様子を見ながら、怒りの叫びを押し殺した。説明を要求しようと彼女は矢をつがえ、その時、奇妙な光景に動きを止めた。
フードの者が一人、乗船用の板の上で立ち止まった。後ろに続く人物は彼よりもずっと大柄で、ミアが身を隠す高所からも、月光の中に堂々とした影を投げかけているのが見えた。長身の人物は前に寄ると板の上のもう一人へと何かを囁き、そして先に乗船していった。二人は肩をぶつけ、板の上にいる者の顔に月の光が当たった。ウィルバーが最後に名残惜しい一瞥を森へと投げかけ、そして振り返ると船へ乗り込んだ。ミアは唖然とした驚きをかみ殺した。
万の疑問が心に弾けた――だが船が岸から離れはじめ、それを考える時間はなかった。背中に弩弓を背負ってミアは駆け、船尾に小さな梯子をぶら下げたまま進水する小舟に追いつこうと跳ねた。目撃されるかもしれないとは知っていたが、甲板を一瞥するとフードの者はほとんどが船首へと移動し、前方を見ていた。数人が松明と角灯を掲げて一団をかすかに照らし出していた。彼女の近くには一人だけが立ち、船の舵をとりながらその目は地平線へと集中していた。もう二人が両側に立ち、氷の塊を船から押しのけていた。船が揺れると足が水に浸かり、そして彼女は梯子を一段登った――だがあえてそれ以上は動かなかった。
船にしがみついていると、声が流れてきた。数えきれないほど聞いた、よく知った声だった。彼らは天気と氷の状態について話していた、まるで皆、市場で噂話をしているというだけのように。フードの外套と、甲板の中央に高く積まれた羊の死骸がなければ、これは湖へのちょっとした遠出だとミアは考えたかもしれない。この状況は眩暈がするほどに非現実的だった――実体となった恐ろしい夢だった。
船の脇にどれほどの時間掴まっていたのか定かでなかった。水面を先へ進むごとに気温は下がり、霧は次第に濃くなっていった。これ以上は掴んでいられないと思ったその時、船が傾いて止まった。ミアは周囲を見た――辺り一面に灰色の霧が広がって視界をぼやけさせていた。水は穏やかな様子で、近くには尖った氷の塊が幾つか揺れていた。
「ここだ」 低い声が宣言した。ミアはその声がわかった。顔もわかった。甲板へと上って見るよりも早く、カリムがフードを降ろし、群衆の前に立つよりも早く。
「兄弟姉妹らよ、今宵わしらは平和をもたらすことを願って贄を捧げよう。望まず与えられたものを、無信仰の者から与えられたものを捧げよう。今宵わしらはギトラグへと処刑者の娘の羊を捧げよう」

呪いの声と暗黒の囁きが集まったフードの人影に広がり、だがミアはこの時耳をそば立てるのを止めていた。彼女は身体を引き揚げて小舟の端を乗り越え、レーレンだと確信する後頭部に弩弓の狙いを定めた。一発、素早く鋭い一発。彼女は思った。
その人物は哀れな、息を切らす咳を発した。ミアは顔をしかめた。痩せこけた老人を撃つことはできなかった。
痩せこけた老人、でも私の羊を皆殺しにした村人を助けたのは間違いない。
彼女は溜息をついた。レーレンは振り向こうとした。
刺さる音。呻き声。
レーレンは芋の袋のように崩れ落ちた。ミアは直ちに弩弓を返し、フードの人影の塊へと狙いをつけた――その時彼らは羊の死骸を船外へと投げようとしていた。
「あんたたち、何をしているの?!」
フードの人物が一斉に振り返って彼女を見た。一人も喋らなかった。ミアは不安から一歩後ずさり、弩弓を高く掲げた。
「嬢ちゃん、お前は何もわかっておらん」 カリムが静寂を破り、進み出た。彼は落ち着いて静かな様子だった。ミアが弩弓を向けると、カリムは立ち止まった。
「説明する事が沢山あるでしょう」 彼女は非難の声色で言った。「それと弁償も」
「お前の羊は偉大なる目的に捧げられるのだ」 カリムは言った。フードの人影の多くがカリムの言葉を繰り返し、同意を呟いた。
「何の目的よ?」 彼女は弩弓を振るい、にじり寄ろうとした人物へと定めた。その人物は止まり、フードの下からヴェリルの顔が彼女を見つめていた。彼のかつての面影は僅かで、ミアは少し震えた。頬は見たところやせ衰え、両目は彼女を見つめ、カリムを睨みつけ、そしてでたらめな方向に外れ、荒々しく動いていた。
「ギトラグを称えるのだ!」 フードの一人が叫んだ。
「ギトラグを!」 群集が声をこだまさせた。
「ギトラグなんていない! よくも私の羊小屋を壊して羊を皆殺しにしてくれたわね!」 突然の実感が湧き上がった。「全員のしわざなんでしょ――前にも時々一頭ずつ、私の羊を殺したのも」
「あれを止める唯一の手段なのだ」 右手を腰へと動かし、カリムが再び彼女へと向かってきた。ミアは再び弩弓を掲げたが、この時彼はゆっくりとした歩調を保ち、ミアを少しずつ後ずさらせた。「あの飢えを満たす唯一の手段なのだ。わしらへと向かってくることを防ぐ唯一の手段なのだ」
「狂ってる。見たのはあんただけなのに」 ミアはもう一歩下がり、足が小舟の端に当たった。
「わしら全員が見た。何故わしら全員がここにいると思うかね? 真実を見たからに他ならない。その両目を見つめた。止められないと知った。わしらは食わせることしかできぬ、わしらが食われぬためには」 今やカリムは彼女に迫ろうとしていた。彼女の視線はフードの村人へと跳んだ。見知った顔が影と月光に歪み、空ろに彼女を見つめ返していた。彼女はカリムを撃ちたくはなかった、だが止まらないならば……そして突然の考えが脳裏にひらめいた。
「だったら、見せなさいよ」
カリムは足を止め、彼女を見た。ミアは背筋を伸ばした。「あんた達のギトラグを見せてみなさいよ」 カリムは長いこと彼女を見つめていた。
やがて、彼は一歩下がって手を振った。他の村人が皆羊の死骸へと群がり、それらを船首へと運んで水へと放り投げた。大きな水飛沫が次々と、静かな水面と夜の静寂を破った。そしてすぐに、木の甲板の上には血の汚れだけが残された。フードの人物は全員が船の端から下がった。ミアは弩弓をカリムへと定めたまま、船の端を背にして歩き、やがて船首越しに向かい側を見通す場所まで来た。彼女は羊の血が水を汚し、暗い染みが広がる様子を見た。幾つかの泡が水面へと上り、そして静寂が戻った。
船上の全員が穏やかな水面を見つめる中、緊張に満ちた静寂が刻まれていた。
「何もない」 ミアが囁いた。「何もないじゃないの」
彼女は船上の村人たちへと向き直った。「皆見たでしょう? そんなものはいな――」
突然、水の爆発と咆哮がミアの非難を遮った。骨を噛み砕くおぞましい音が水中から響き渡り、フードの村人たちは悲鳴を上げて船尾へと退散した。ミアは怯えた群集をかき分け、何が起こったのかを見ようと船首へ向かった。
船のすぐ傍で水が渦を巻いて乱れた。ミアは月光の中で目をこらし、そこに何がいるのかを見ようとした。水が静まると、彼女はそれを見た。怪物を。ギトラグを。
彼女はあざけった。
「え? あれが? あれがギトラグなの?」 彼女は船の向こう側に縮こまる村人たちを肩越しに見た。「あんなの……ただのでっかい蛙じゃないの」
ヴェリルがフードを脱ぎ捨ててミアへと駆け、彼女が弩弓を構えるよりも早くその肩を掴み、乱暴に揺さぶった。彼の両目には純粋な恐怖があった。

「ミア、お前はわかってない! もし羊で足りなければ、俺達は皆――」
皆が何なのか、ミアがそれを聞くことはなかった。その瞬間、ヴェリルは悲鳴を上げて宙へ舞上がり、船の後方へと吹き飛び、そして飛沫とともに水中へと消えた。何が起こったのかミアには理解できなかった――ギトラグが再びその口を開け、暗い何かが船へと飛んでくるのを見るまで。その何かが頭上を横切り、マストに直撃して木片を落とすと彼女は甲板へ跳びのいた。村人たちは悲鳴と叫びを上げ、ミアは理解した――その「何か」はギトラグの舌だと。
ギトラグが再び舌を放つとまたも大きな砕ける音が響き、この時はマストの大きな破片が落ちた。ギトラグが舌を引くと、ミアは甲板上で跳ね起きて弩弓の狙いを定めた。だが引き金を引こうとした時、強い力が突然背中を打ち、彼女は勢いよく甲板に転がった。
振り返ると、フードの人物が両脚にしがみついているのを見た。「何をするのよ!」 彼女は叫び、その掌握を振り解こうと身悶えした。
「ギトラグを怒らせてはいけない! あの怒りは手に負えないんだ!」 フードの人物は苦闘しつつ暴れ、ミアは村のパン職人が脚へと更に強くしがみつくのを見た。彼の叫び声は金切り声となっていた。
「もう遅いわ」 ミアはうめき、片足を引き抜いて自由にした。彼女はパン職人の顔面を靴で強く蹴り、それは鼻を直撃して耳に聞こえるほどの砕ける音を発した。パン職人は離れ、ミアは転がると立ち上がった。
「羊ではもう満足してもらえない!」 彼女はフードの村人たちが叫ぶのを振り返った。
「もっと要る」
「あの娘を食わせるのよ!」
「今何て言ったの?」 彼女は最後の言葉を叫んだ女性を見つめた。鍛冶職人の妻サラ、以前、誕生日に焼き菓子を焼いてくれたはずの。
「殺してギトラグの贄にするのよ!」 サラは粗末に見えるナイフを抜き、凍り付くような悲鳴を上げてミアへと駆けた。叫びとともに、間に合わせの武器を振りかざして数人が続いた。狂った村人が迫り、ミアは新たな矢を弩弓へとつがえながら急ぎ後ずさった。サラはナイフを振りながら近づき、ミアの顔へと切りかかった。その時ギトラグの舌がまたも放たれ、彼女ともう二人の村人を船外へと奪い去っていった。
悲鳴が上がり、突然のごぼごぼという音に途切れ、助けを求める訴えも小さくなっていった。混乱の中、背後から別の手が二つ伸びて彼女の喉を掴み、力を込めた。ミアは肘で盲目的に突いた。掌握が緩み、彼女は振り返ると攻撃者の腹部をやみくもに撃った。
その人物は後ずさり、ミアは見知った青い瞳を見た――靴職人の弟子、カイルだった――そして直後に別のフードの人物が彼女に迫った。フードが脱げ、ヴェリルの弟テレンスが現れた。ミアはもう一本の矢に手を伸ばしたが彼は本物の剣を手に迫り、大きく振るってきた。ミアはよろめき後ずさって転び、剣の先が肩をかすめて血を吸った。テレンスはとどめの一撃を与えようと下がり――そして別の人物から後頭部を棍棒で殴られた。テレンスが甲板に倒れると、ミアはようやく矢をつがえた。彼女は棍棒を持った人物の顔へと弩弓を定め、指を引き金に当てた。
「待ってくれ、ミア、僕だ!」 その人物がフードをはだけると、ミアは叫んだ。
「ウィルバー! 何が――」
「本当にすまない。何もかも手に負えなくなった。僕達はただ村の安全を守りたくて、でも皆が君の羊を盗みはじめて――」
ギトラグの舌が振るわれ、またも大きな激突音が二人の背後で響いた。
「前にもこれを見たの?」
ウィルバーはかぶりを振った。「泡だけを」
木片が弾けて二人に降り注いだ。二人は見上げ――その時マストに巨大な穴を残してギトラグの舌が引かれた。ゆっくりと軋む音を立ててマストがぐらつき、傾き、そしてついには折れて倒れ、船の脇に叩きつけられて水へと落ちた。
「後で聞かせて」 ミアは彼の手を握り、三つ又で攻撃してきた別の村人へと――花売り娘のヴェルナへと――弩弓を撃ち、船尾へと駆けた。
「どこへ行くんだ?」 ウィルバーが叫んだ。
「わ――わからない!」 ミアは取り囲む混乱を見た。ギトラグの舌が振るわれるごとに更なる村人が水に叩きつけられ、もしくは掴まれて丸呑みにされた。数人は船の中で縮こまり、隠れようとしていた。数人は今や水へと飛び込んで泳ぎ去ろうとしていた。ミアも同じように飛び込むことを考えた――ある泳ぎ手が(イーサン長老の息子だ)水面下に消え、その軌跡に泡だけが残ったのを見るまでは。

「逃げ場などない」 ミアとウィルバーは振り返り、その言葉を発した人物を見た。カリムが二人の前に立ち、その両目はミアを凝視していた。
「父さん! 僕達は何をしているんだ? これは……これは狂ってる!」 ウィルバーは今もミアの手を固く握りしめ続けていた。この完全な大混乱の中でも、ミアは彼の鼓動が激しく打つのを指から感じていた。
「あなたのお父さんの言う通り」 ミアは言って、突然の明晰さとともにウィルバーを見た。「逃げることはできない。倒すことを考えないと」 ミアはウィルバーの手を放し、弩弓を掲げ、カリムを見ながら矢をつがえた。「今、私達の希望はそれだけ」
驚いたことに、カリムは声をあげて笑った。
「馬鹿な娘だ。ギトラグを殺すことなどできん。すべきことは一つだけだ」 カリムは目を細くした。「贄だ」
カリムは前へよろめき、漁のナイフを不意に引き抜くとミアの喉をめがけてまっすぐに振るった。ミアは驚いて後ろへよろめき、甲板に転げながらかろうじてその攻撃を避けた。カリムはナイフを逆手に振り下ろし、ミアは急ぎ後ずさった。ミアは続く攻撃を転がって避け、弩弓を大雑把な狙いで撃った。その矢は幸運にもカリムの肩に当たったが、彼は気付いていない様子で再びミアの顔へと切りつけ――その瞬間、ウィルバーが体当たりをしてカリムを転がした。
二人が甲板上でもがく中、ミアは新たな矢をつがえたが正確な狙いは定まらなかった。だが丁度その時、突然の叩きつける音とともに船が傾いた。全員がその音の源へと顔を向けた。カリムとウィルバーも直ちに離れ、立とうとした。ミアが弩弓を構えながら可能な限り体勢を維持しようとした。
ギトラグが船上へとその身を引き上げ、その水かきの四肢が船腹を乗り越えて甲板へと湿った音とともに着地した。カリム、ウィルバー、そしてミアは凍り付いて見つめていた。ギトラグは空ろな、死の目で三人を見つめ返した。稲妻の速さでカリムは手を伸ばし、熊のような握力でミアを掴むとナイフを彼女の喉にひらめかせた。
「おお、偉大なるギトラグよ! この娘を贄として捧げましょう! 食らい、そしてこの罪深き村をお許し下さい。そしてわしらが静かに生きられますようお眠り下さい!」
彼は狂っている。ミアはその手を押しのけようとしたが、カリムの掌握はあまりに強かった。ウィルバーは何かを叫んでいたが、ミアに見えたのはカリムが手を掲げ、松明の光にダガーがひらめく様子だけだった。
スパンッ! ギトラグの舌が突然放たれ、カリムの顔面を直撃した。驚きに彼の手からダガーが離れ、彼はミアを放すと両手でその舌を掴んだ。ギトラグは舌を引き、ミアは床に激突してカリムは宙へ放り上げられ、彼の悲鳴は巨大な舌に頭部を包まれて聞こえなかった。ミアは跳ね起きると続けざま三発の矢をギトラグへと放った。その獣はカリムを床に引きずり、矢が肉に埋まってもひるむことすらなく、ゆっくりとその舌を引き続けた。ミアは恐怖とともにカリムの頭部がその喉へと消える様を見ていた。彼の足が必死に宙を蹴った、一度、二度、そしてギトラグの口が閉じられた。飲み込む音、そしてカリムの足もまた消えた。
ウィルバーが叫んでいた。彼女はほとんど無意識に振り返り、再び彼の手を掴んだ。彼女は弩弓を投げ捨てて船尾へと駆けつつ、ほんの少し立ち止まって松明を蹴り倒した。炎がさっと広がり、彼女はギトラグが樽の背後に縮こまる村人を食べるのを止めてよたよたと自分達へ歩いてくるのを見た。それが意識のないレーレンをのみ込むのを見た。それが炎を無気力にまたぎ、ゆっくりと向かってくるのを見た。
そしてようやくミアは我に返った。彼女は前方を向き、ウィルバーを連れて躊躇うことなく氷で覆われた水の中へと飛び込んだ。
恐怖とアドレナリンに突き動かされ、二人は限界を超えて必死に泳いだ。ゆっくりと、小舟は霧の中の明るい燃えがらだけとなっていった。氷水は皮膚を千本の針で突くようで、のたうって泳ぎながら、爪先と指先、そして手が、全身が麻痺していった。今この時にもギトラグが自分達を見つけ、水面下へと引き、丸呑みしてしまえるとミアにはわかっていた。
何とか、二人は地上へと戻ることができた。
二人は水から這い出した。ウィルバーは小石の地面へと顔からばたりと倒れ、震えていた。ミアは自身に座るよう強いて、考えようとした。小屋まで戻らないといけない。温かい所まで。そうしなければギトラグに食われるよりも先に凍死してしまう。そして、身体を乾かして温まったら……ここを離れよう。村を離れよう。何もかもから。どこか別の場所へ逃げよう。千の吸血鬼、狼男、グールから顔をそむけて。ギトラグのいない何処かへ。
びたん。湿った足音が背後で響いた。
彼女は座ったまま凍り付いた。
びたん。もう一度。
立たなければ。見なければ。逃げなければ。
だが何もできなかった。
びたん。足音が更にもう一度、そして突然ウィルバーが彼女を引き倒した。二人は石の上に倒れ、這い進んだが僅かだった。ミアの筋肉が悲鳴を上げた。アドレナリンは尽き、恐怖に硬直した身体だけがあった。ゆっくりと、彼女は仰向けになった。
ギトラグが大きく迫り、その胴回りが視界を埋めていた。それは彼女を見下ろしていた。黒い二つの目、底なしの穴、感情はなく、思考もなく。ミアはその目を見つめて……何も見なかった。ウィルバーは彼女を再び引っ張りながら、逃げろと何かを叫んでいたが、ミアに彼の言葉は聞こえなかった。ギトラグの視線という終わりのない穴に落ちると、低い唸り音が頭蓋に響き、音量を増していった。彼女は落ちた。にじみ出る影の中を転がり落ち、自身の心の裂け目を落下し、薄膜を破って狂乱という海綿状の粘体へと落ち、そして骨へと染み通る奇妙な温かさに包まれ、疑いと怖れと不安のしつこい寒さから逃れた。彼女は知った、今や全てを知った。真実をその真に暗黒の姿の中に見た、千の人生を一瞬に圧縮した明晰の中に見た。
彼女はまだ自分の腕を引くウィルバーへと向き直った。彼の唇が動くのを見た。紫色に震え、何かをギトラグへ言っていた。請い、懇願していた。ミアは優しい手を彼の頬へと伸ばし、そのうわごとを止めさせた。彼は見ていなかった。聞こえていなかった。まだ知っていなかった。ギトラグが二人にそびえる中、ウィルバーは振り向き、その狂乱の瞳がミアに定められた。水晶のように透明なその緑色は、今や涙に揺れていた。ミアはその中に自身の姿を見た、その砕けた斑の水面に。彼女は微笑み、そのほんの一瞬、ウィルバーはわずかに落ち着いたように見えた。ミアは彼の瞳に信頼と信念を見た。そして微笑みながら頬を撫で、砂のついた髪を撫でながら、鞘からダガーを引き抜いて一挙動で彼の胸骨へと差し込んだ。
そして彼女はついに頭蓋の中の雑音から浮上し、聞いた。彼の驚愕の喘ぎを、低体温症の乱れた息が苦痛と衝撃へ変わるのを。ミアは柔らかく微笑み、彼の唇に指をあててダガーを引き抜き、そして再び刺した、この時は腹部へと。ウィルバーが倒れこみ、弱々しく彼女の名を囁くとミアは微笑んだ。彼女はその耳へと静かに囁いた。
「ギトラグのために」 息をするようにその言葉が出た。彼女はウィルバーの胸に耳を当て、彼の鼓動が弱まり止まるまでを聞いていた。彼女はギトラグを見上げ、哀願に頭を下げた。
「全ては贄」
ギトラグは彼女を見下ろした。そして、ゆっくりとその口を開け、巨大な舌が音を立てて彼女の隣の壊れた身体を掴んだ。ミアはその場所に座ったまま、顔に大きく笑みを広げていた。飲み込む音、骨が砕ける音、血と臓物が彼女に飛び散った。水かきの足の湿った音が石の上を離れていく間も微笑んでいた。再び静けさが訪れ、昇りはじめた太陽が冷たい霧を突き刺すまで微笑んでいた。そして微笑んだままで彼女は立ち上がり、岸からよろめき離れていった。
その年の春が訪れて雪がようやく融けると、一人の年若い見習いが馬に乗って小道を駆け、ザヴァ湖近くの小さく活気のない漁村へとやって来た。彼は手紙の鞄を持っており、多くが前の冬の降雪前に書かれたもので配達はかなり遅れていた。彼は駆けながらも、あまりに多くの窓や扉が固く閉じられていたことに気付いたが、あまり深くは考えなかった。多くの小村には怖がりの、疑い深い村人がいるものだ。特に厳しい季節の後には。彼はまた明らかに放棄された家屋へと手紙を届けながら、見た所多くの家が無人らしいと気付いたが、こちらも深くは考えなかった。
最後の手紙の宛先は丘の上の小屋だった。上りながらも彼は壊れた羊小屋か何かがその近くに朽ちていることに気付いた。また無人の家だろうかと心配したが、それは小屋の煙突からわずかな煙が上がっているのに気づくまでのことだった。彼は扉を叩き、そして野性的な瞳の女性が答えた。彼女は郵便に興味はないようで、ドルナウのスキルトの民からの手紙にすら無感動だった。しかしながら、彼が湖について言及すると彼女は目を輝かせた。そして彼女は夜を過ごしていくように彼を誘い、食事と休息を提供し、そして望むならば湖へ連れて行くとすら言った。船や湖にずっと興味を持っていたその少年は顔を赤らめて同意し、彼女の親切へと礼を告げた。
ミアは微笑んだ。

(Tr. Mayuko Wakatsuki / TSV Yohei Mori)


