石と血と
前回の物語:黄金夜の大魔道士
『異界月』の物語から六千年前、三人のプレインズウォーカーがゼンディカー世界に巨怪なエルドラージを封じ込めるべく共闘した。ゼンディカー次元生まれのコー、ナヒリは囚人を監視する不寝番となった。精霊龍と呼ばれるウギンと吸血鬼ソリン・マルコフは助力が必要となった時に戻ることに同意した。だが千年前、エルドラージが脱走しかけた時、ソリンもウギンもやって来ることはなかった。ソリンはナヒリの友であり、その不在を彼女は心配し、また疑問に思った。エルドラージの逃走の試みを抑えた後、ナヒリは友人を探すべく出発した。我々は、二人の対面が良いものではなかったことをソリンの回想から知っている。だがあらゆる物語に表と裏の面がある……
再会
千年前
ナヒリは世界と世界の狭間、久遠の闇の混沌の中へと身を投じた。彼女はとても長い間、石の繭の中で眠りについていた。意識へと幾つかの確かな物事を滑らせた。彼女は既に事態を軽視したことの最悪の結果を正しており、囚人らの牢を固める防護を強化し、それらの下僕どもを無へと引き渡していた。自分の世界は安全だった、ひとまず少しの間は。
そして今は、古い友人に呼びかけ、あまり明白でない物事を修復する番だった。
彼の存在を知覚して狙いをつけ、周囲の世界を曲げてその隣に立つまで長くはかからなかった。二人の友情は今や古く、消えかけの遺産で、それでもだがソリン・マルコフは彼女が得た最初の仲間だった。彼が何処にいようとナヒリにはわかった。
そして彼女は、暗く波立つ海を見下ろす高い崖の上に立っていた。ここへ来るのは初めてだったが、何も驚くべきことはなかった。イニストラードとソリンは共に姿を成し、この世界は彼に相応しいように思えた――憂鬱で危険、意思を持つかのように不親切。そして月――海上高くに浮かぶその月は何かが奇妙だった。その何かが彼女の感覚を引っ張った。
連れて来られたことはなかったが、ソリンは懐かしむような口調で話をしてくれた。この世界を守るために自分を呼びたがっていることを彼女は知っていた――自分がゼンディカーを守るために彼を呼びたいと願ったように。だが結局、どちらの願いも叶えられることはなかった。
ソリンはいなかった。
崖の頂上、彼の存在を感じた場所に、その代わりに立っていたのは一つの巨大な、少なくとも四十フィートに達する荒く削られた銀の塊だった。それには幾つもの面があったが、いびつで不揃いだった。まるで素人の石術師が地面から引き上げたまま、表面の仕上げを怠っているかのように。

だがこれは完成していた――疑いようもなく。彼女の感覚から、それが製作途中ではなく計り知れない努力の成果であるのは明らかだった。表面が粗いままなのは、この物体が存在すべき、果たすべき役割に対して仕上げは関係しないためだった。
そしてこれが――この物体こそが――彼女が知覚したものだった。ソリンではなく。この物体が久遠の闇の希薄な媒体を越えて、彼を越えて語りかけたのだった。
崖の上には風と、この銀の一枚岩と、紅葉した成長不良の木が一本生えている以外には何もなかった。木はそのままに、彼女は巨大な銀塊の周囲を回った。
面。その面は八つ、もしかしたら七つ、滑らかな一つの面を辺と考えるなら。だがそれらの面は、慎重に形成されていた、まるで……けれどイニストラードに面晶体はない。そしてソリンは自分に作らせたことも、作るよう求めたこともなかった。
そして面晶体と同じく、その物体は物理的な素材以上のものだった。ナヒリは自身の石術でそれを試し、純粋な金属音を響かせて内部構造を感じ取ろうとした。
何もなかった。全く何もなかった。彼女は足元、半マイル地下の基盤岩をその粒まで、大陸を乗せた岩盤が緩やかで容赦のない円舞曲を踊る一定の鼓動を感じることができた。だがこの銀の砕片については、何も見えなかった。かすり傷をつけることすら叶わなかった。まるで底無しの井戸のように、彼女の力はその中に消えた。これはまるで……だが違う。繰り返すが違う。これは面晶体ではない。ここにある筈がない。
彼女は屈んでその物体の根元を、それが地面から浮いていると半ば予想しながら見た。だがその底はナヒリ自身よりも大して太くはない、比較的細い銀の茎が土に埋まっていた。
彼女は立ち上がり、深部の調査が叶わない代わりに指先でなぞりながら、ゆっくりとその物体の周りを歩き続けた。どれほどの間そうして銀の一枚岩を調べていたかは定かでなかったが、よく知った声が背後から聞こえた時、月は空に高く昇っていた。
「私の粗末な石術を大目に見てくれるかな、君は」
はっと彼女は振り返った。ソリン!
白い髪、黒の上着、不可思議な橙色の瞳。何と恐ろしい外見、何と危険な視線――だがそれでも彼女は笑みを抑えられなかった。
ようやく、彼女は言葉を発した。「ソリン! 生きていたんですね!」
彼はナヒリへと微笑みを返し、歩いてくると肩に手を置いた。その仕草は彼にとって誇らしさを意味した。

「そうでない訳があるか?」
彼女はソリンの手に自身のそれを重ねた。今や目覚め、彼女の身体は生命の熱に満たされていた。彼の指はかつてと同じく、死者のように冷たかった。
「来なかったじゃないですか、ゼンディカーに。ウギンの目から合図を送りましたが、あなたは応えなかった。私、もしかしたらって――」
ソリンは手を引っ込め、眉をひそめた。
「エルドラージが束縛を破ったのか?」
「そうです」
「ウギンはどうした?」
「彼も来ませんでした」 声に恨みがましさが出ないよう、彼女は努めて言った。「でも、私が一人で対処しました。使える力は全部使って、巨人の牢獄をもう一度封じました」
今や自分は、出会った時のソリンよりも遥かに歳を経ている。唐突に、そのことに衝撃を受けた。記憶の中の彼、一千歳以上も年上の古い師匠は大きくそびえ立っていた。今や、千年の差が何だというのだろう? 自分達は同等だった。少なくとも。
「ひと段落ついたので、あなたを探しに来たんです。あなたがまだ生きているかを確かめたかった。そして、ここにいた」
ここにいた。彼に会えた喜びは消え去った。心から、とても心配していた――何かが起こったのではないか、もしくは彼も、自分のように、数千年の倦怠に沈んでいるのではないかと。自分はここへ彼を探しに来た、救いに来た――だが、どうやら、彼は救われる必要は無さそうだった。
「それで、ソリン、どこにいたんです? どうして呼び出しに応えなかったんです?」
「それは私に届いていない」
「そんなことが?」
「ふむ」 彼は言った。それは興味も、幾らかの切迫した様子もないただの軽い返答だった。
彼は腕を伸ばし、ナヒリの背後、その物体の表面に掌を押し付けた。
「君は捕らえたエルドラージを監視することに専念していた。こちらはというと、この次元は差し迫った状況にあり、保護を必要としていることが明らかになった。特に私が不在となっている間は。この獄庫はそういった守りのために私が創造したものの片割れだ」
獄庫。彼女は震えた。これは貯蔵庫なのだ。これほどの物の中に何かを入れるというのだろうか?
どこか退屈したような声で彼は続けた。「『目』から君が送った合図がこの次元を守る魔法を破れなかったというのは想像できないでもない」
ソリン自身の製作物が彼自身への接触を阻んでいた? 彼女は突然の眩暈を感じ、次の言葉を注意深く選んだ。
「そうなるかもしれないって、知っていたんですか?」
「それは考えもしなかった。とはいえ今、その可能性はあるかもしれないと思う」
石と空よ!
出会って早くのこと。彼の正体を知る以前、そして彼女が今や何者になったのかを知る以前。彼は尋ねてきた、自分のような戦い方を学びたいかと。頷くと――彼はナヒリを殺そうとした。
もしくは、その時はそう思った。理解したのはそう後のことではなかった。手すら動かさずに彼女を殺すこともできながら、彼は力を抑え、物理的に攻撃していた。ナヒリは僅かな間耐えたが、彼のずっしりとした両手剣が優雅に振るわれて彼女の上腕をとらえ、病的なひび割れ音とともに苦痛が感覚を圧倒した。
『上出来だ』 彼はそう言ってナヒリを見据えた。『六呼吸ほど耐えたか……まあ妥当な所だな。さあ、立て』
『立て?』 彼女は叫んだ。『私の腕を折っておいて!』
『ならば治せ』 彼は言った、彼女を見ることすらせずに。
『治す? 治すって? 一体どうやって――』
その時初めて、彼は説明した。彼女はもはや限りある命を持つ身ではないのだと。その身体を好都合に、意志のままに投影できるのだと。
『どうして最初に言ってくれなかったんですか』 怒りの涙をこらえながら、ナヒリは言った。
『ああ』 彼は答えた。気だるい、だが優しい声だった。『それは考えもしなかった』
彼は今、同じ声で同じ言葉を、同じ彼女に言っていた。だが彼が教えを与えた少女は遥か昔に亡くなり、石の墓所に埋葬された。残ったのは一人のプレインズウォーカー。侮ってはいけないプレインズウォーカー。
「あるかもしれない? あなたは私の次元を危険にさらして、それだけでなく」 彼女は声に苦痛を抑えきれなかった。「それだけでなく、私を見捨てたんですか」
見下すようにソリンは青白い手を振った。
「私は単純に、自分の次元を守る用心をしたに過ぎない、私はとても考えられなかった――」
もういい。これ以上はもう沢山だ。
「同意したじゃないですか、あなたと私で」
彼はそれを否定できなかった。五千年前、ナヒリは自身の世界ゼンディカーにエルドラージを封じることに不承不承同意した。そして力を貸したもう二人のプレインズウォーカーは、万が一エルドラージが牢を破ろうとしたなら連絡を取る手段を用意した。

五千年に渡って、ナヒリはその巨怪な囚人を監視してきた。石の中に閉じ込もり、太陽を過ぎる雲のように何十年何百年と時が流れる中監視を続けた。そしてエルドラージは牢獄の檻を試し、彼らの存在によって既に変化していた世界へとその忌まわしい落とし子を放った。その方法は彼女にとっても未だ定かではない。ナヒリは自ら定めた孤独を解いて目覚め、警報を鳴らした。
誰も来なかった。動機も起源も不可解な、彼女が完全に信頼したことのないあの龍、ウギンは来なかった。そしてソリン――師であり、友である彼も、来なかった。
世界に大きな犠牲を出しながら、彼女はその危機に独りで対処した。その犠牲は仲間二人がその同意を全うした場合よりも遥かに大きいものだった。その悪行が鎮められるまでにエルドラージが世界とその人々に与えた傷がどれほどか、彼女は未だ把握できていない。だが彼女はやり遂げ、全てが片付くと友の生死を不安に思い、彼を探すべく出発した。
そして判明したのは、彼は助けを求める呼びかけを無視したのではなく、更に悪いものだということだった。彼は自身の世界を外の影響から守るために、それを遮断していたのだった。
彼は背を向けた。
「忘れたとは言わせません。私は自ら、エルドラージを引き寄せることで自分の世界を危険にさらしたんです。あれらを監視するため、牢番となって自分自身をゼンディカーに縛りつけることを誓ったんです。あの怪物と数千年を過ごしたんです。それがどれほどか、わかるんですか? 私が必要とした時に、あなたは来てくれないといけなかったのに」
地面が鳴動を始めた。足元の岩盤が彼女の増大する怒りに共感して震えた。周囲の岩も金属も全てが震え、ただ銀の獄庫だけが彼女の手中になかった。
「子供が私の行動を勝手に決めつけるな。私は何の義務も負わない。君にも何の義務も負わない! 君のプレインズウォーカーの灯が点火した時、私が君を発見したな。そこで殺すこともできた、だが生かしておいた」
彼は振り返った。突きつけられた橙色の両目は敵意に満ちていた。
「私は君を保護し、君が何者かを形作った。もし誰かを悩ませたいのなら、ウギンを見つけに行け。私は辛抱強くはないぞ」
辛抱強くはない。辛抱。怒りが一瞬にして白熱し、苦痛を追いやった。
五千年もの長い間、ナヒリはエルドラージの監視を続けた――自分の次元のためだけでなく、あらゆる次元のために。イニストラードのためにも。そして五千年の間に一度だけ、ただ一度だけ、彼に呼びかけた。ただ、一つの単純な約束を果たしてくれと――ただ自分の世界を安全に保つためだけに彼が交わした、利己的な約束を――そして来なかった。……来なかった。
彼女自身の辛抱はエルドラージの終わりなき監視に使い尽くされていた。もう沢山だった――待つことは、言い訳は、そして何よりも、子供のように扱われることは。自分がもはや弟子ではないという証拠をソリンが必要としているのなら、それを見せつけてやろう。
彼女は足元深くから石柱を呼び出した――古く頑強な花崗岩。地面が持ち上がり、ソリンは倒れぬよう踏ん張った。石の柱が彼女の足元から弾け、ナヒリを宙高くへと運び上げた。
「私は何処へも行きません」
彼女は地面から更に多くの石を引き上げ、尖らせ、それらはプレインズウォーカー二人の間を渦巻いた。
ソリンは剣を抜いた。
「君を脅したことはなかったな」 ナヒリを見上げてソリンは言った。「一度もだ。悪い子になったな、もし私達が敵となるなら、それは君だけの罪だ」
「私は子供ではありません。私達の関係が何であったとしても、今は同等です。お判りでしょう」
そこに一瞬の躊躇があった――その橙色の瞳に、かすかな怖れだろうか? 彼女が正しいのかもしれないという一瞬の推量、それでいて辛辣な罰が必要だというのは彼の矜持だろうか?
「それはただの癇癪だ。もしも君が同等の存在として会いに来たのであれば、休戦協定に従って来るべきだった。他のプレインズウォーカーと対面する際の協定通りにな」
「私は友人に会いに来たんです」
「ならば私は不平を言うことはあるまい。友が示す真実は辛いものだ……違うか?」
遠い昔、とある愚かな娘がこの見下げた存在を友と呼んだ。その若い感傷の最後の名残が蒸発し、ナヒリは攻撃を放った。
彼女は最初の岩にまたがってソリンへ迫った。彼女は剣を持っていなかった。必要としていなかった。大地そのものが武器だった。
ソリンは死魔術を放ち、それが胸に直撃して彼女は後ずさった。石柱は後方へよろめきながらも、彼女の足元に留まった。
壊れた地面から跳躍し、ソリンは歯をむき出しにして彼女へと向かった。その手の剣はあの奇妙に圧倒する月の光にぎらついた。彼女は石柱から飛び降り、膝を曲げて地面に着地した。ソリンは石柱に足をかけ、そこから再び攻撃のため跳躍しようとし――だがその石柱が事もなげに彼をのみこんだ。
彼女は立ち、拳を握りしめ、ソリンを石の中で押し潰そうとした。
ひび割れが走った。まず一本、次に数本、吸血鬼の魔法によって内部から光を放った。石柱は光の飛沫の中に飛び散り、ソリンは力づくで脱出すると地面へ優雅に着地した。
だが彼は痛みをこらえているようだった。
「あなたと敵対したくはありません。ソリン、私が求めるのはあなたの助力だけです。約束をしてくれたでしょう。私と来て下さい」
「今ではない」 ソリンは言った。穏やかな口調、だがそこには激怒があった。「後にしてもらおう、今は大事な時――」
「何が大事な時ですか! エルドラージはもう少しで逃げるところだったんです。あなたは長い時代の視点で物事を考えていますが、私が知っているのは、今エルドラージが逃げ出そうとしているという事だけです。私達がやり遂げた事、全てが無と帰すかもしれません。あなた自身の次元も危険に――それはいいんですか!」
そして、その事実はナヒリを打った。彼女にとってエルドラージの幽閉は一世一代の偉業となっていた。その不断の努力は自分が生きたほぼ全ての期間、自身を次元に縛り続けていた。だが彼にとってそれは瞬きほどの時間なのだ――五千年前に、たったの四十年の努力、そして数千年の安らぎを得る。そして今、彼の反抗的な態度から察するに、イニストラードは危険ではなかったのかもしれない。ソリン・マルコフの心の奥では、ナヒリとゼンディカーと、何百万もの注意深く位置された面晶体こそが役割を果たすべきものだったのかもしれない。
彼女は唸り声を上げ、石の矢の嵐を彼へと飛ばした。その一本一本が彼女の上腕ほどもあり、先端は危険なほどに尖っていた。
ソリンはそれが届く前に破片の幾つかを吹き飛ばし、もう幾つかを剣で払い、だが三本に身体を突き刺されて呻いた。
彼の両目が眩しいほどに白く閃き、そして凄まじい重量がナヒリの肩にのしかかり、膝をつかせた。何もかもがあまりに眩しく――
彼女は見上げた。
月。彼は月光の柱を手招いたのだった。巨岩のように重く、だが実体のないものが彼女を束縛した。そしてやがて、その光に包まれ、その匂いを呼吸し、彼女はイニストラードの月の何処がこれほど奇妙なのかを理解した。
それは銀でできていた。獄庫と同じように。
ソリンは身体から石の矢を一本ずつ引き抜き、その傷は血を流すことなく塞がった。彼はナヒリへと近づいた。だがその足取りは定かでなく、剣は下げられていた。彼はここまで老いてしまったのだろうか?
だとしても、彼の魔術は強力だった。その光は彼女の身体だけでなく、魔法もまた束縛した。この月光に掴まれている限り、彼女は無力でその外へと何も成し得なかった。
「帰るんだな、ナヒリ」 彼はうんざりしたように言った。「この茶番を終わらせろ。そうするならば許そう――」
彼女は土に手を埋め、意思を外ではなく下方へと伸ばし、大地そのものに飛び込んだ。
石の胎内へと沈み、そして束の間、彼女は憤怒とソリンの忌々しい傲慢と、その奇妙で断固とした未だ目的不明の銀塊から離れた。そこにあるのは自身と石だけ、緩慢かつ絶えることのない世界の鼓動だけだった。あの五千年間のように。
次元を渡り、ゼンディカーへ帰って縁を切ることもできた。事実、ソリンの助力は必要ではなかった。誰の助力も。だがこの物事を解決しないまま放っておくのは計り知れない危険となり、報復を招くかもしれなかった。そうなれば本当に敵を作ることになるだろう。そして、それを防ぐ機会がまだ残っているうちに、去るわけにはいかなかった。
獄庫へ近づくソリンの休みない足音が頭上にこだました。
彼女は下方の石をまた一本の石柱に変え、頭上の岩の密度を水ほどに薄くすると勢いよく地面から飛び出した。ソリンは月光の柱を散らしており、幾らかの防御のためか今や獄庫を背に立っていた。
彼女は花崗岩の柱の上に立ち、彼に迫り、石の群れを地面から引き出して自身を囲むように配置した。
彼を殺す気はなかった。傷つける気も本当になかった。求めていたのは、互いの間の物事を正し、かつてのような関係に戻ることだった。だがそのためには、彼の尊敬を得る必要があるだろう。そしてそのためには、彼を打ち負かさねばならないだろう。
今、彼はその剣にもたれかかっていた。もし互いを同等と見做したいのであれば、それを願うべきは彼の方であるように思われた。
正確にはそうではなかった。ソリンはあまりに弱っていた、彼女がまだ若かった頃の彼よりも。この獄庫が放つ彼の気配を察し、自身のどれほどをこれに費やしたのかと彼女は考えた。
彼女は石柱を滑らせて彼へ向けて送り出した。その一つとすれ違いさまに手を触れるとそれは瞬時に赤熱し、溶解した、まるでその内の金属が彼女の意思に応じたように。
石術製の剣が完全な形でその岩から引き出され、彼女はなおも前進を続けた。ソリンは下から、白熱したその剣先を見上げた。
「ソリン、約束を果たしてもらいます。私と一緒にゼンディカーへ帰りましょう。牢獄を確かめて、エルドラージが閉じ込められていることを確認します。それから逃げ帰って下さい」
ソリンは唾を吐き捨てた。
次の瞬間、何もかもがまたも眩しく輝いた。月よりも眩しく、そして鋭い叫びとともに一つの姿が天空から現れた。その姿が激突して石の台座から叩き落される直前、ナヒリは羽根の翼と輝く槍を垣間見た。二人は共にもつれ合い、地面に叩きつけられて深い窪みを作った。集中が切れ、ナヒリが配列した石はよろめいて地面に落ちた。
ようやく、仰向けにナヒリは攻撃者を近くで見た。

天使だった。大型で、白い髪に白い肌、そして黒く感情のない瞳。天使から攻撃を受けていた。
ゼンディカーで天使に会ったことはあった。よそよそしく、あるいは恐るべき存在。だが彼女らは庇護者であり、正義と善のための存在だった。そして彼女が会ってきた天使は皆、プレインズウォーカーに攻撃するような愚か者ではなかった。
ナヒリが口を開くよりも早く、何が起こっているのかを完全に把握するよりも早く、その天使は槍を振り上げた。その二又の先端は双子の太陽のように、彼女の目を眩ませた。
今一度石に潜った瞬間、自分が横たわっていた地面にその槍先が刺さるのを感じた。
この時は休んでいる余裕はなかった。剣を手にしたまま地面から岩片の飛沫ともに飛び出し、天使がその岩の爆発から身を守ると、ナヒリは攻撃した。振るった剣は今も鍛冶の熱に輝いていた。
その天使は槍を持ち上げてかろうじて攻撃を逸らし、ナヒリは再び、続けざまに繰り返し攻撃し、天使を後ずらせた。天使と戦うことにはぼんやりとした過ちのようなものを感じた。だが違う――この天使が攻撃してきたのだ、挑発されたわけでもないのに。そして何故? ソリンを守るため? その考えは受け入れ難いものだった。
天使は宙へと舞い上がった――だが逃げるためではなかった。そして再び攻撃するためにナヒリの上空へと進んだ。ナヒリは再び石柱に乗って空へ上がった、天使を退散させるか、再び地面へ落とすために。
天使は戻り、だが退かなかった。ナヒリは攻撃を続けた。天使は強かった。それは間違いない、だがプレインズウォーカーではなかった。ナヒリは再び攻撃し――
――そしてその剣は間に入ったソリンのそれに当たった。
「止めろ!」 彼は息を切らしていた。「止めろ」
彼女はソリンの先、漆黒の瞳の天使を見つめた。その天使にはどこか見知った何かがあった、どこか心をかき乱すような、だが会ったことがないのは確かだった。
「ソリン、これは何なのです? どうやって天使を支配したんです! この女は何ですか!」
「片割れだ」 彼はそう返答した。
稲妻の速さでソリンの手が振るわれ、ナヒリの剣を掴んだ。彼の皮膚が音を立てて焦げ、だが気にする様子はなかった。ナヒリの指の感覚が鈍り、心は揺らいだ。今も理解していなかった。彼は自身の剣先をナヒリの喉元へ向け、彼女の剣をその手からもぎ取ると投げ捨てた。
天使はソリンの背後に音もなく着地し、だが彼が片手を挙げて制すると待った。天使が待った、彼のために。
「このような事はしたくなかった……というのも本心か否か、私にすらわからないが」
そしてソリンは剣を掲げ、汚れた光の柱とともに迫り、押した。
ナヒリは後方へ吹き飛び、獄庫の銀の表面に叩きつけられた。それはもはや固くも冷たくもなく、だがしなやかだった。招いていた。引き寄せていた。

欲するような銀の糸が彼女の身体を包み、内側へ引き寄せた。ナヒリの怒りに足元の岩盤が持ち上がり、岩片が宙に渦を巻いた。だが獄庫そのものには何の影響はなかった。
「どうして!」 彼女は叫んだ。「信じていたのに!」
今やソリンは彼女にそびえ、天使の翼がその背後に広げられていた。そして溶けた銀が彼女の耳に流れこむ直前、一度だけ口を開いた。それは悲しいとも思えるような声だった。思えるような。
「信頼など求めた事はない。服従だけだ」
そして獄庫に求められるように、彼女は広大で完全な暗黒へ消え去った。
静寂
幕間
暗黒の中を、彼女は落ちた。
他の感覚はないとわかっていた――音も、光もなかった。わずかな風すらも、大気すらも、この場所の中には何もなかった。自分と、決して終わりのない落下する感覚以外には何もなかった。顔の前に持ち上げた手すら見えなかった――そもそもこの場所で、身体があるのかも完全に定かではなかった。
彼女は感覚を外へ伸ばした。石術師の力をもって押しては引き、獄庫の銀の内部の何らかを掴もうとした。だが周囲にあるのは銀ではなかった。無だった。次元を渡ろうと試みるも、久遠の闇には、次元の狭間の混沌にして無の空間に手は届かなかった。
ゼンディカーで過ごした石の繭、五千年間を断続的にまどろんで過ごした岩盤とも違っていた。あの繭の中では、夢をみるように、ゼンディカーの全てを感じられた。その何処へでも手を伸ばせた。そして望むままに外へ出ることができた。
これはもっと、ずっと悪かった――ただ暗闇と、落下と、ソリン・マルコフの紛れもない匂いだけがあった。
ソリンはこの裏切りの報いを受けるべきだろう。この牢獄から脱し、報いを受けさせてやろう。自分達は仲間だと思っていた。友だと思っていた! 今や彼女は真の彼を知った。怪物、明白かつ単純に。
怪物、だが愚か者ではない。ゼンディカーで何か差し迫っていたかを彼は知っていた。エルドラージの逃走を単純に許すような彼があれほど自身の防御を、隷属させた天使と獄庫を信頼しているというのはありえなかった。力を取り戻し、対峙する覚悟ができたならば彼は自分を解放するのだろう。不意打ちして倒し、故郷へ帰らせるのだろう。ただここに残してはおかない筈だ。それは考えられないことだった。
だが考える時間は豊富にあった。
やがて、彼女は一つの決定に至った。
「もう終わりです」 彼女は静かに告げた。
返答は、音は何もなかった。彼女の声は響かず、だが果てのない暗黒へと消え去った。
「終わりです!」 もっと大声で。「あなたがくれた教えは何であろうと学んできました。終わらせましょう、私はイニストラードから離れて二度と戻りません。もう、お互いに言うべきことは何もないのは確かでしょう」
返答はなかった。そして彼女は謝罪するつもりはなく、頭を下げる気も全くなかった。彼を満足させるつもりはなかった。
彼女はしばしばゼンディカーを思った、その尖った峰と大きく広がる空を、その心臓を貪る腫瘍を。自分達が知っていたよりも奇怪な神々の彫像を建て、地表をうごめく吸血鬼を。それを放っておくべきではなかった。
孤独が正気の端を噛みはじめた。プレインズウォーカーですら、石の中で数千年を過ごした者ですら、このような孤独には慣れるものではなかった。プレインズウォーカーですら精神を失うことはありうる――そして精神の体現であるプレインズウォーカーにとって、その結果は恐ろしいものとなりうる。彼女は一度だけ、狂気のプレインズウォーカーに出会ったことがあった。一度で十分だった。狂気に堕ちるつもりはなかった。
当初、彼女が拠り所としたのは復讐心だった。自分への行いの仕返しに、ゼンディカーに今も起こっているかもしれない事の仕返しに、ソリンを打ち砕く。だが彼を殺す方法はとても沢山あるとはいえ、今ですらその考えは復讐心の冷たい満足よりも悲しみと疲労をもたらすのだった。彼女の憎悪は決して揺らぐことはなく、結晶化して静かに成長していった。
ゼンディカーの記憶が、暗闇の中の灯となった。
彼女は自分の世界をその骨まで知っており、その記憶は完璧だった。ある場所を思い浮かべた――アクームの地溝。定命の生を捨てて石へと沈む以前、同族とともに放浪していた場所。心の中に彼女はその地溝の模型を組み立て、玄武岩の層を一枚一枚、表土を成す赤い火山ガラスの破片を一つ一つ、岩盤を形成する砂粒と石の全てまでをも再現した。
それはゼンディカーではなく、記憶の中のゼンディカーだった――エルドラージの後、だが彼女のまどろみが世界を無秩序へと滑らせるよりも前の。
計り知れない時が過ぎる中、彼女はアクームの外側へと向かった。堆積した全ての砂粒を、地表の下で脈動するマグマの熱と粘り気を思い出しながら。彼女は何マイルも下方へ、行こうと決意した限りの深くへ潜り、そしてアクーム全土をその肩に乗せる基盤岩の端を再現した。
彼女はその全てを心に留め、何年にも思える間ずっと変化させないままに置き、そしてやがて正確に同じ姿で残されているのを見た。自分の心は自分のもの、そしてゼンディカーは自分のもの。どちらも手放させはしなかった。
その夢想が破られた時、どれほど長く落ちていたのかは判断できなかった。暗闇の中、彼女はもはや孤独ではなかった。当初、それらは遠くにいた――ただ遠くの甲高い声、もしくは皮の翼の音。彼女を束縛する無音は不変のものでなかった。ただ空虚がゆえの無音だった。
ゆっくりと、数えきれない年月を経て、獄庫に住人が現れていった。今や彼女はその目的を理解した。ソリンは大切なイニストラードの脅威を見逃そうとはせず、これを創造した――この穴を、この何処でもない場所を――その脅威を閉じ込めるために。
脅威、悪魔や怪物のような、そして自分のような。それを知り、彼女は一年かもしくは十年を怒りの中に過ごした。
片割れ、ソリンはそう言っていた。彼が個人的にこの悪魔全てを封じ込めたのかは甚だ疑問だった。ここに至って彼女はあの天使の存在意義を理解した――とはいえソリンはあの天使を騙したのか、そそのかしたのか。
やがて彼女は心の中のゼンディカーの地図に、アクームの全てを創造し終えた。アクームの歯、巨大な峰から硝子池の静かな水まで。彼女が覚えている大陸を囲む水は、比較するとただの素描であり、慌ただしい駄作だった――彼女は水の動きを真に理解していなかった。そのためアクームの赤い崖を洗う波はただ前後に動くだけだった。その幻影を壊さぬよう、彼女はそれを注視はしなかった。
小さな海底を作ると、オンドゥに取りかかった。彼女は冠の諸島、その燃え立つ宝石ヴァラクートに心を傾け、だがそれを無秩序に作りたくはなかった。時間は幾らでもあった。

果てのない暗闇の中、他の囚人がナヒリにぶつかり、一瞥するようになった。それらの姿は見えず――それは変わることがなかった――だが囚われる直前の叫び声を聞いた。ここに鉤爪、そこに翼、一瞬の、名もなき人ならざる皮膚との接触。そして離れ、暗闇の中へと消え去る。
彼女は暗闇に住まうものとの束の間で無感覚のいざこざに気を散らされ、足踏みをした。それらを憎くは思わなかった。住人の数が増し、自身の身体――と言えるか定かでないもの――との衝突回数が更に頻繁になり、更に辛いものになろうとも。悪魔に愛着はなかった――世界を苦しめることはないよう、一体ではない数を打ち倒してきた――だが憎いとは思わなかった。ここでは思わなかった。
彼女はそれらを憐れんだ。自分と同じ囚人なのだ、ソリン・マルコフとその天使の執行者の。そして自分とは違い、彼らに復讐の機会が訪れることはない。それらは泣き叫び狂乱する惨めな生き物だった、狂ったか恐怖のためか、その両方か――暗闇の中で永遠に声を上げ続ける、下等な精神だった。
ナヒリは孤独に慣れており、その心は自身のものだった。この暗黒の中、それが彼女の持つ全てだった。正気、怒り、ゼンディカーの記憶……そして過ごすべきとても長い時。
彼女はオンドゥを終えると、ヴァラクートの霊峰に追加の時間を費やした。その火山のカルデラの中で長い年月を瞑想して過ごしたことがあった。彼女のゼンディカーは錨であり、自分が何者か、何処から来たかを思い出させるものだった。正しい姿のそれが必要だった。
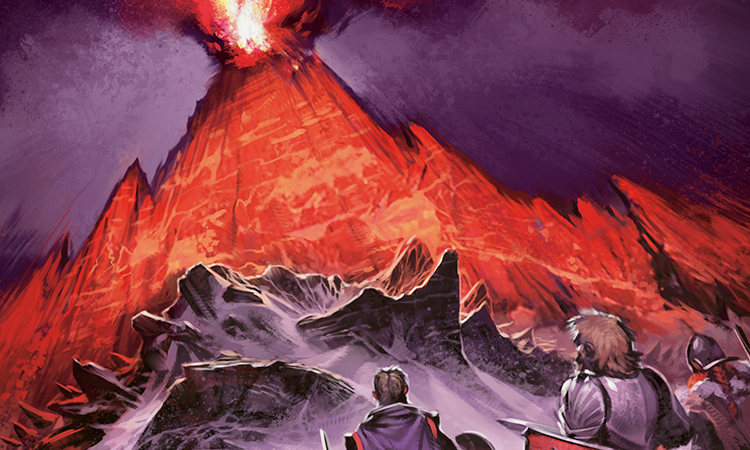
心の中、時折彼女はそのカルデラへと戻った。だが彼女のゼンディカーの中にただ住まい続けることはできなかった。作り終えるまではできなかった。
ムラーサは素早く作り上げた、海から飛び出した巨大な岩盤。その大陸の森は目覚ましいものだったが、彼女は興味を惹かれず、再生産しようとは思わなかった。バーラ・ゲドはとても長い時間をかけた。ボジューカ湾の移りゆく輪郭を、グーム荒野地下のねじれた洞窟網をなぞった。
そしてグール・ドラズ――表面は退屈、だがバーラ・ゲドと同じように興奮するような地下を持つ。その時、地熱で沸き立つ沼地、その地下に走る溶岩洞窟を半分ほど創造したところで、計り知れない時の果てに――何かが変化した。
光が――暗闇の中に束の間の眩しい閃きが一瞬、彼女の集中を散らして狼狽させ、ゼンディカーをぼやけさせた。そして何かがいた、か細くすすり泣く悪魔よりももっと実体のある存在が。ソリン? 一瞬彼女はそう思った――だが違った。全く……違った。ナヒリの遥か下方で双子の太陽が点火し、無を照らし出し、そして彼女は羽根のかすかな音を聞いた。
あの天使――ここに? 自分自身の牢獄に? それは何て興味深い。
その光は近づき、ナヒリは見た――目で見た、この数世紀の間で初めて。天使の槍が閃き、唸り声と奮闘ともに彼女はそれを大きく振るった。その翼は無益に広げられ、無を押しやろうとしていた。
金切り声と羽ばたきとともに、悪魔がその天使に群がった。長い間、それらはナヒリを偶然一瞥しただけで放っていた。だがそれらは自分達の看守を知っていた。復讐を果たす唯一の機会だと知っていた。
天使はナヒリへ向かって昇ってきた――ゆっくりと、ゆっくりと、時のない虚無の中を――やがて隣り合うまで。群がる悪魔はソリンの守護者が優勢とわかるや否や散った。天使はナヒリを見下ろし、しばし二人の目が合った――そしてようやくナヒリは理解した。ソリンは天使を隷属したのではなかった。騙したのでも、強いたのでもなかった。この天使はソリンと同じ匂いがした、この獄庫と同じように。
彼はこの天使を作ったのだ、この獄庫と同じように。
天使はナヒリを認識した、遠い昔に戦った相手と。黒い瞳が憤怒にひらめいた――ソリンが吹き込んだ憤怒が。彼はこの天使を自身の思うがままに創造したのだ、始めからねじ曲げていた。憎しみを持つように。自分の天使として。
彼女もまた、ソリン・マルコフによって嘆かわしいほど不当に扱われた存在なのだ。復讐も矯正も望めない。自由も望めない。彼が失った生徒の代わりを埋める陶器人形。
どれほど長く、互いの目を見ながらそうして落ちていたかはわからなかった。その間もずっと、喋ることは不可能らしかった。
そしてやがて光があった、本物の光が、周囲の虚無がひび割れて裂け、ついに……
彼女は……
その外へ……
廃墟
一年前
ナヒリは両手と両膝から地面に叩きつけられた。ついに終わりのない落下が終わった。両眼は光という概念を拒否し、耳は不快な雑音の爆発にさらされた。視覚に集中すると眩しい光自体が姿を成し、騒音は声へ、身体の下の粗い表面は小奇麗な敷石の道へと変化した。彼女は顔を上げた。人々がそこかしこで叫び、駆け、炎は燃え、屍はよろめき――屍?――その全ての上に、ソリンのあの忌々しい天使が、白い光の柱の中、宙へと舞い上がっていた。
そして辺り一面に銀の破片が落ちていた。

両手が奇妙に感じた。感じた……それ自体が奇妙だった。掌を見ると、それは血に濡れていた。血。その傷に塞がるよう命じたが、何も起こらなかった。彼女の身体はもはや自意識の延長ではなかった。もう一度、遠い昔のように、ただの……身体だった。肉と骨。血管に血が脈動するのを感じ、持ち上がるような喘ぎとともに空気が肺に送り込まれるのを感じた。何千年もの間、必要としていなかったものだった。世界がよろめいた。
ここから離れなければ。彼に見つかる前に。離れられるのだろうか、自分は今もプレインズウォーカーなのだろうか。
彼女は試しに世界の壁を押し、そしてプレインズウォーカーだけが感じる非現実的な向きへ動かそうとした。周囲に世界の壁を感じた――自分は今もプレインズウォーカーだった、自分の身体に何が起こったのだとしても――だが調べたところ、その壁は彼女が覚えているよりも遥かに強固だった。かつては石鹸の泡ほどだったそれは今や、乗り越えるには意思と時間を必要とする障壁と化していた。自分はこんなにも弱体化してしまったのだろうか?
だが違う。違う。彼女は押した、常にそうしてきたように。問題は力ではなかった。その壁は本当に高く、分厚かった。久遠の闇とこの場所との繋がりは、ここにやって来た時よりも希薄だった。落下している間に宇宙の姿が変わったのだ、彼女はそれを感じた。
それがどうあれ、自分は今もプレインズウォーカーだった。
奮闘の末、彼女は久遠の闇へと飛び込んだ。それは常にそうであったように彼女を裂き、翻弄した。まごつきながらも、手の届くであろう次元がただ一つだけあった――自分が逃げ込むと彼は予想するだろう、もし探していたなら。だが探しているとしても、救助のためではない。
彼女の足がゼンディカーに、その岩がちの地面に触れた。幽閉されてから初めて、固い地面に足を触れた。ゼンディカー、本物のゼンディカー。故郷。遠い昔に出発した場所からそう遠くはなかった。アクームの尖った心臓、ウギンの目があると思しき場所の近く。
だが目は廃墟となり、重なるように崩壊していた。足元にも周囲にも瓦礫の平原が広がり、宙には赤い火山岩の破片が物憂げに回転していた。あの注意深い幾何学的構造が、それを囲んで慎重に位置された面晶体の配列が、そしてあの小部屋そのものが、単純に……無くなっていた。
そんな。そんなばかな。
エルドラージの巨人三体は逃走していた、ゼンディカーの庇護者がソリン・マルコフの牢獄の中で衰えていた間に。ここに築いた全てが、捧げてきた全てが、長い幽閉の間に廃墟と化していた。
ナヒリは血に濡れた拳を握りしめた。どこ? あいつらは何処に? あるいはエルドラージはゼンディカーを離れたのだろうか。自分の世界はついに解放されたのだろうか。
彼女は石を通して周囲へ感覚を伸ばし、そしてよく知った微震を近くに感じた。ごく僅かな震え――コーの同族の、軽やかで素早い足取り。ナヒリは彼らに接触すべく尾根に登り、石を宥めると出血する両手に代わって身体を支えた。その傷は今も塞がっていなかった。

一人の斥候から叫びが上がり、ナヒリはかすれた声で応えた。自身の声すら奇妙に聞こえた。それは返答の叫び、単純に「私はコー」を意味する言葉なき合図だった。
数呼吸待つと、疲労の見えるコーが十人ほどで彼女を取り囲んだ。
「怪我をしていますね」 彼らの一人が言った。長身の女性、そのむき出しの肩には奇妙な皺のような傷が走っていた。抑揚は異なり律動は奇妙だったが、かつてと同じ言語を話していた。その長身の女性は両手を掲げ、癒しの魔術に輝かせた。ナヒリが頷くとその女性は掌を当て、別の世界の敷石と月の欠片で負った、怒れる擦り傷を塞いだ。
「テンリと申します」 ナヒリの傷が塞がると、その女性は言った。
ナヒリは返答せず、治癒の過程に夢中になっている様を装った。彼らのどれほどが自分を覚えているのかは定かでないのだ――もしくは、もっと正確に言えば、不吉の予言者ナヒリを、獄庫に入れられる以前に見た自身の彫像を。
「一人でいるなんて」 武器と縄で身を飾った斥候が言った。「道具もなしに」
「長い話になります」 ナヒリは口を開いた。「私は……隠遁者のようなものです。長いこと他と接触を絶ってきました。そして何か変化した。世界に何があったのですか?」
彼らは唖然とした。
その斥候が言った。「エルドラージとその食い跡がそこら中にあるじゃないですか。何処にいたのかはともかく、知らないんですか?」
「エレム、黙りなさい」 その長身の女性、テンリが言った。「装具を帯びていないのはこの方が石鍛冶だからです。きっと、お独りで技術を磨いておられたのでしょう」
「そんな感じです」 ナヒリはそう言い、腕を伸ばして石鍛冶師の証である赤い腕輪を見せた。導きも無しに、自分の民の伝統がこれほどの激動と長い時を越えて生き残っていることに驚きながら。
「去年のことでした」 テンリが切り出した。「三体の巨大な怪物がアクームの歯から出現しました。どうも、その地下にとても長い間眠っていたらしいのです。その落とし子はあらゆる地へと広がり、ですが三体は、巨人は、もっとずっと悪質です。あれらが行く所には……何も残りません」
「あいつらを……カムサとタリブ、マンジェニが肉体を得たものだと信じる者もいます」 エレムが続けた。
数人のコーが唾を吐いた。ナヒリは一体、タリブの名だけを知っていた。自分自身の彫像の下にその名があり、彼女はその予言者とされていた。長い不在の間に、そしてその前のもっと長い夢想の間に、多くは彼女が最初に語ったエルドラージの半ば忘れられた物語が――伝説と化していた。世界の内にうごめく怪物は、世界の神々となっていた。
ナヒリも唾を吐いた。
「何も残らない……」 彼女は繰り返した。「何処? あいつらは何処に? 何が失われたの?」
「バーラ・ゲド」 エレムが言った。
ナヒリは続く言葉を待った、バーラ・ゲドの何処が失われたのかを。彼は何も言わなかった。
バーラ・ゲド。大陸一つが完全に……
「自分の目で見ないと」
エレムは鼻を鳴らした。バーラ・ゲドはここから遥か遠くなのだ。テンリも頷いた。
「行く前に、武器を作れます」 ナヒリは言った。「私にできるのはそれくらいです」
エレムはかぶりを振った。
「道具には不足していません。多くは失っていませんから」
「神々が共にありますように。今、あなたが呼びかける神が何であろうとも」 テンリが続けた。
ナヒリはその長身の女性の肩を掴んだ。
「手助けを感謝します。そして、何もできなくてごめんなさい」
ナヒリは足元の石へと沈んだ、同族のコーを残して――自分にとって彼らは異邦人、ソリンにとって自分がそうだったように。
傷の広がりを彼女は感じた。世界の深部は新たなトンネルで満ち、感覚を混乱させる何か奇妙な物質で覆われていた。あらゆる所に破壊を見た。あらゆる所にエルドラージの兆候があり、風景は理解すらできない様に腐食していた。そして遥か遠くに、世界を横切って、バーラ・ゲドに――
彼女は集中した――今や、集中が必要だった――そして世界を横切り、その間違いの源を探した。頭がぼんやりとして吐き気を感じた。待つべきだろう、そして休み、力が戻るのを。
待つのはもう沢山だった。何が起こったのかを見なければならなかった。かつては肥沃な密林だったのであろうバーラ・ゲドに彼女は出現した。目の前に広がっていたのは、白亜の灰色の塵の、果てのないような広い場所だった――どんな砂漠よりも命のない、まるで月の表面のように。
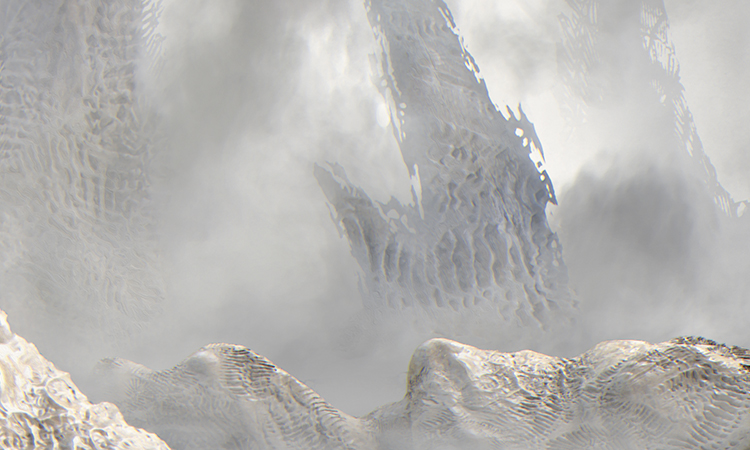
今も脳内に残すゼンディカーには、幽閉の中で丹精込めて作り上げた精神的模型には、このようなものは無かった。自分のゼンディカーでは、バーラ・ゲドは生き生きとした野生の地だった。このゼンディカーでは、死だった。ここでは何も生きていなかった。岩ですらも沈黙していた。
足元で地面が鳴動したが、彼女はその微震の源を察知できなかった。塵がおののいた。
振り返ると、そこに、地平線上に、巨大で禍々しく、かつて二度見た姿があった――一度はエルドラージによって失われた世界で、もう一度は彼女がそれとその兄弟をゼンディカーに封じた時に。貪るもの。ウラモグ、そうウギンが呼んでいたもの。

ナヒリは膝から崩れ落ち、両手を命なき塵の中に押し付けた。
もし、あれが私の世界に放たれたら――
ここに起こりうることは、何処にでも起こりうるとして――
何の備えもなく、かつての力はか細い欠片となり、そして何世紀を費やした面晶体のネットワークも狂ってしまったとすれば――
ならば、自分の知るゼンディカーは死んだ。守るものはない。空の太陽を止めることが叶わないように。彼女は目を閉じ、自分のゼンディカーを見た、かつてのゼンディカーを。ソリン・マルコフに破壊させたゼンディカーを。怒りの熱い涙が流れ、囁き音とともに忌まわしい塵に落ちた。
「ゼンディカーが血を流したように、イニストラードもそうなるでしょう」
彼女は目を開け、両手を見下ろした。石を成型し、巨人を閉じ込めた手を。それらは灰色の塵に覆われていた。
「私がそれを嘆いたように、ソリンも嘆くことでしょう」
彼女は地平線のそれが、まるで自然災害のように風景を動いていく様を見上げた。
「ここに、私の世界の灰に誓いましょう」
ナヒリは立ち上がった。
成すべきことが沢山あった。

(Tr. Mayuko Wakatsuki / TSV Yohei Mori)



