ニッサの決断
前回の物語:故郷の海
ニッサは若い頃に故郷の大陸バーラ・ゲドを後にして長く旅をしてきた。かつて多くの過ちを犯しながらも、彼女はゼンディカーの魂と結びつきながら、更に無謀な自身の本能を抑えることを学んできた。強くも頼もしい、世界全ての力が隣にいる間は、彼女は内なる野生の精髄に触れる必要はなかった。だがゼンディカーとの繋がりが引き裂かれた時、ニッサは大地の力と世界の魂がエレメンタルとして顕現した友アシャヤから独り取り残された。その喪失を受け入れられず、そして世界の未来を怖れ、ニッサはゼンディカーの何らかの兆候を捜してタジームを捜索し、そしてついに理解するに至った――ずっと間違った場所を探していたと。エルドラージに脅かされた魂は撤退したのだろう。そして何かとても貴重な存在に庇護を提供できる場所はただ一つ、力強い花、カルニの心臓。躊躇することなく、ニッサはその場所へとプレインズウォークした。新たな花が開くと言われている場所へ、バーラ・ゲドへ。故郷へ帰る時が来た。
ゼンディカーのために。
ギデオンが言うようにではなく、戦鬨のようにではなく、だが大地の最深部のために、世界の魂のために。だからこそ、ニッサはこうしていた。今一度思い出し、そして目を開けるよう、自身に言い聞かせた。
ここバーラ・ゲドへとプレインズウォークするにおいて、ニッサは到着した時に見るであろうものについて考えていなかった――カルニの心臓以外は。そこでゼンディカーの魂が自分を待っているだろうと思っていた。
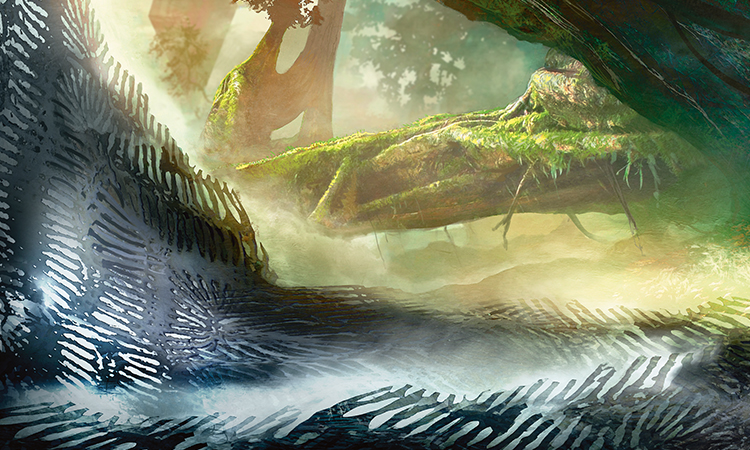
《荒廃した森林》 アート:Jason Felix
だが彼女を迎えた風景は、果てしない白色、果てしない荒廃だった。その惨状に彼女はすぐさま故郷の大陸から目を閉じた。
もちろん、こうなっているだろうとは判っていた。バーラ・ゲドはエルドラージに陥落したと、世界の全てが知っていた。だがそれを耳にしてからもずっと、このような風景だとは考えていなかった。彼女は荒廃した大地を、白亜の荒廃の大きな刈り跡を、枯れた木々を思い描いていた。だがそういった情景は彼女がタジームで見てきたものを基にしていた――陥落しつつある大陸、だがまだ陥落してはいない。
彼女は目を開けた。
バーラ・ゲドには、何もなかった。全てが、全てが、一体どうやってただ――真白く、虚ろに、消えてしまったのだろう?
ありえなかった。
とはいえ、どこか現実的だった。
大地は荒廃していなかった――ただ完全に消耗され尽くしていた。

《塵への崩壊》 アート:James Paick
枯れた木々はなかった。枯れた木々の形跡すらなかった。白い風景は完璧に平坦で、木々は全て分解されていた。全てが分解されていた。そして荒廃の刈り跡はなかった。何かの刈り跡とは、何かを刈った跡として定義される。もしくは少なくとも他の何らかが細くでも残っていると。辺りには荒廃以外の何もなかった。ニッサは自身に強調した――カルニの心臓以外は。カルニの心臓以外には何もなかった。
もし噂が本当ならば――そしてそれは本当に違いない――ゼンディカーの力の心臓は大地を蘇らせるためにここにやって来る。この大陸のどこかに新たな蕾を育てている。それが何処であろうと、大地の魂を見つけられるのはその場所だろう。ゼンディカーが避難したのはその場所に違いない。彼女は一歩前に踏み出すよう自身に言い聞かせた。そしてもう一歩、更にもう一歩。彼女が歩くと足の下で白亜の荒廃がひび割れて砕けた。彼女の足跡はその塵の大陸が陥落してから初めての、異なるものとなった。
おかえりなさい。バーラ・ゲドを横切り始めながら、彼女は思った。
この何処もかしこも荒廃した不毛の地にて、何らかの特定の場所を認識できるとはあまり思えなかった――丸一日歩き、彼女が思った通りに全ての風景が変化していた。だがその大陸の奥深くで足を緩めて立ち止まると、ニッサは自分が何処に立っているかが正確にわかった。
ニッサは数え切れないほどここを踏みしめていた。事実、人生において自分の足はこの大地だけを知りながら進むのだろうと考えた時があった。同じ道を歩き、同じ炎を囲み、同じ木々から果物をもぎ、やがてジョラーガの長老達の一員に加わるのだろうと想像していた。ここは自分の村だった。まさにこの場所に、そびえ立つジュウォーレルの木があった。そしてその向こうに、ジョラーガがあらゆる肉や果物を乾かし、森の茸の世話をする貯蔵テントがあった。そしてここ、最大の火炉で、秋になると自分達はヌーマ村長が先導する詠唱に従い、棘の血茨を火にくべた。
ニッサはそのすべてが見えた。全てが聞こえた。母が煮るシチューの匂いすら感じた。その香りは記憶の扉を開いた。思い出すに心地良い記憶、そう願った。だが母がシチューを作る度に、彼女の心は戻った。ある夜に、最後の夜に、決して思い出したくない唯一の夜に。彼女はシチューの匂いと……声に幻視から目覚めた。それは彼女に村を去ろうと決心させた声だった。そして夜闇に隠れてそっと去った。
ニッサは影の中に滑り込む自分自身を見た。そしてその光景に、かつての自分というエルフから顔をそむけた。彼女は長いことそのエルフの事を考えていなかった。事実、彼女はそのエルフを忘れようと努めてきた。多くの過ちを犯してきたエルフを――恐ろしい過ちを――この村を離れてから。今もニッサに取り憑く過ち、永遠に自分に取り憑く過ちを。

アート:Izzy
だが彼女はもはやそのエルフではなかった。そしてそうでない唯一の理由は、ゼンディカーの魂だった。彼女を変えたのは、救ったのは大地との繋がりだった。彼女を集中させ、安定させ、確かにさせるのはゼンディカーだった。彼女を導くのはゼンディカーだった。彼女はゼンディカーを必要とした。
その瞬間、ニッサは理解した。自分はここバーラ・ゲドへと世界の魂を救うべくやって来た、大地だけでなく、次元だけでなく、その人々だけでなく、その力だけでなく、世界の魂を救い、自分自身を救うために。そうしなくては、自分は再びあのエルフに戻ってしまうだろう。かつてここにいた時の、荒々しく、無謀で、確実に道を踏み外すエルフに。
再びあのエルフに戻るわけにはいかない。戻れない。戻ってはいけない。ニッサは誓った、ゼンディカー無しにバーラ・ゲドを離れることはしないと……
ニッサが自身と村との間に置いた距離は問題ないように思えた。彼女はその記憶を心から押しやったが、その閃きと回顧は止められなかった。まるで未熟で不慣れなエルフに尾行されているように感じた。更に悪いことに、その記憶と自分自身が混じっているように感じた。
突然、全てが馴染み深くなった。大地は単調な白い荒廃の塊だったが、彼女にはもつれ谷を横切って進む正確な道がわかった。数えきれないほど、ここで狩りをしてきた。人間の一団がナーリッドのために設置した罠を、どこで避ければいいかをわかっていた――そして彼女はそれを避けた。そこに罠が無くとも、望まない追憶に足が反応するのを止めようと努めても。存在しない丘を登ろうとして、彼女の膝は本能的に力を込めた。そして丘の頂上に達するほど歩いた時、彼女の口は湿り胃袋が鳴った。いつもその頂上で、分厚い輝き茸の軽食をとっていた。そしてゴーマゾアの鋭い鳴き声を聞き、それを避けようと隠れた――恐るべき狩人の記憶の亡霊を。

《護衛のゴーマゾア》 アート:Rob Alexander
彼女はそれを記憶から押しのけたが、その呼び声は彼女の後を追い、彼女を嘲笑した。望まぬ記憶から現実を切り離せない彼女を。彼女の手は本能的に剣へと動いた。愚かなエルフ。そこには何もない――ニッサは急いだ。
彼女が視界の端にとらえたものは記憶ではなかった。そしてゴーマゾアでもなかった。だがそれは十分に近かった。触手と柔らかい肉質の身体の、中型のエルドラージがまるで過去からの侵略者のようにそこにいた。
動くよう意識が伝えるよりも速く、ニッサは剣を抜いてそれに迫った。以前にもこうした事があった。まさにこの場所で。数えきれない程に。最初に真中を切り裂き、次に脇を。彼女はその怪物を素早く四つに切断した。その生命が途切れてからも、鋭い叫び声のこだまが少しの間続いていた。
ニッサの内の何かがかき回された。彼女は立ち上がり、エルドラージの死骸の上で重く息をついた。人生そのものに感じるほど長く、このように戦ってはこなかった。これほどの正確さと力で刃を振るうことを忘れてしまっていた。
彼女の内には更なる力があった。もっと振るえる力が――いけない。ニッサは自身を解きほぐそうと脅かす糸を無理やりに飲み込んだ。
自分はもうあのエルフではない。ここはあのバーラ・ゲドではない。そして自分の前にいるのはゴーマゾアではない。エルドラージ。

《氷の猛進》 アート:Deruchenko Alexander
エルドラージ!
ニッサはこの怪物の一体を見てこれほど興奮したのは初めてだった。人生において、これほど興奮することもないだろうと思った。だが今、この不毛の大陸で、このエルドラージの存在が意味するものはただ一つ。生命。
これが食らう何かがあるに違いない。そうに違いない、でなければここにいる筈がない。
ニッサはゼンディカーに現れたこの別世界の怪物について多くを知っているわけではなかった。だいたいにおいて、それらは不可解だった。だが一つのことは知っていた。それらは絶え間なく飢えており、貪るような破壊の道を進み続けると。それらが向かうのは貪るものがある所のみ、そしてそれはすなわち生命。
バーラ・ゲドのどこかに、生命がある。
カルニの心臓。
カルニの心臓に違いない。
心臓が胸骨の中で跳ね、彼女の瞳はひっかき進むエルドラージがその背後に残した波打つ跡に定められた。ニッサはその大地を駆けた。その怪物が何処から来たのだとしても、自分を食らうべく何を背後に残してきたのだとしても、そこに自分が願う、探している生命を見つけられるだろうと。
ニッサにとってこの類の追跡は造作もなかった――かつての野伏のエルフはまさにこの大地で何百体もの生物を追ってきた。訓練されていない目にあばたの荒廃にエルドラージの足跡はくっきりと見えないかもしれないが、ニッサはその足跡を輝く標のように見た。彼女は谷を貫いていたウムング河へと降りる道を進んだ――そこは今やただの白亜の荒廃だった。彼女はグウム荒野を駆けた――かつては密林で最も深く最も毒の濃かった場所を、無計画な奔放さで駆けようと思ったことなどなかった。そしてサラカーが巣として使っていた洞窟へと一直線に向かった。
何処に向かっているかを理解した時、ニッサはわずかに速度を緩めた。その地に住まう陰険な獣のことを考え、震えがひとつ彼女の背筋に走った。

《サラカーの匪賊》 アート:Kev Walker
彼女の心はバーラ・ゲド地下に走る深いトンネル構造を思った。そこもまた荒廃したのだろうか? エルドラージは地表下へも行ったのだろうか? それともトンネルを無視し、サラカー達は今も地下に隠れて生きているのだろうか?
直面したいのはどちらだろう、飢えたサラカーの群れか、更に衰えた大地か? ニッサは自分の願いが定かでなかった。
答えられなかった。少なくとも、答えられないことを認めたくはなかった。そして長く考えることはなかった――部分的に崩壊し荒廃したサラカーのトンネルの入り口に、エルドラージの足跡が円を描く所に、彼女は生命の最初の兆候を見た。
薄緑色の苔が、かろうじて留まっているように、崩れかかった入口を優美に覆い、縁どっていた。
ニッサは膝をつき、指をその短い緑に走らせた。それは柔らかく、もろく、わずかに温かかった。
ゼンディカー。
心が満たされ、衝動的に彼女はその地へと手を伸ばした、世界の魂の何らかの兆候を捜して――だが同じように素早く引っ込めた。広大で響き渡る空虚から引っ込めた。ここがその場所に違いない、けれどそれならばゼンディカーは何処に? まだカルニの心臓を感じることができないとは? 彼女はその疑いと不安を心から押しやった。ここの筈だった。
緑の鮮やかな薄皮はトンネルの下方へと伸びていた。それは闇と自身の希望が混ざり合ったものなのか、それとも現実なのか、ニッサには定かでなかった。トンネルを深く潜るにつれ緑は濃く、更に逞しくなってそれは現れた。どちらにせよ、それはそこにあった、彼女を故郷へと導く手がかりのように。
心が望むよりも手足の動きは遅かった。トンネルを這い、狭い空間を力の限りの速度でよじ登った。彼女の目は頭上の様子に騙されなかった。トンネルを深く進むごとに指と掌の下の苔は厚くなり――だがもっと脆く? 疑いの痕跡がもう一つ、心の背後をくすぐった。ここは何かが正しくない。彼女は不安を感じた。
前へ進むごとに、未知への警戒に彼女の感覚が強まった。
狭いトンネルが開け、青みがかった輝きに洗われた空洞となった。奇妙だった。彼女は険しい目つきで更に前方を睨み、耳を交互に傾けてそば立てた。だがその青い光がどこからやって来ているのか、それ以上の手がかりは確認できなかった。そのため彼女はゆっくりとその高い天井の空洞へ足を踏み入れた。
息が止まり、心がはやった。自分が目にしているものを整理しようとした。輝く力線が交差して繋がった、狭い円を描く面晶体。青い光はそこから発せられていた。その力線は彼女が見たことのない様式で配置されていた――不自然だった。

《回収蔦》 アート:Bastien L. Deharme
何故これがここに? 何が――誰が――これを?
サラカーではない。彼らは面晶体を配置することに何の興味も持っていない、それはかなり確かだった。
エルドラージが?
皮膚がぞわりとした。彼女はもはや不安を振り払うことはできなかった。
彼女はその円へゆっくりと忍び寄った。目はそこに定めたままで、腕の毛が逆立っていた。ここでは何もかもがおかしい。洞窟に入ってからは、何もかもがおかしかった。
彼女の内をかき回していた力が、エルドラージを殺した時のそれが再び湧き上がった。それは前方に待ち構える何かに備えていた――それを保つかどうかはニッサ次第だった。今はその時ではなかった。あまりに多くのことが危うい状況にあった。彼女はそれを黙らせ、面晶体に注意を向けた。
各面晶体はかき集められたような土の山で底から支えられていた。意図的に、誰かの、もしくは何かの指で――もしくは鉤爪で――かき集められたような。
当初、面晶体の円は完璧なものに見えた。だがニッサは、正確に面晶体一つ分だけの隙間に出くわした。
そしてその隙間から、ニッサはそれを見た。カルニの心臓を。
ゼンディカー。
彼女の心臓が跳ね――そして次の鼓動は落ち込んだ。未熟な花がその石の山の上に横たわっていた。その半ば萎れた花弁は乾いて粘つく泥の塊に分厚く覆われ、力なく傾いて根にもたれかかっていた。
根をむき出しにされたその光景を目にして、苦悶の記憶がニッサの心に閃いた。その苦痛、引き裂かれた感覚。突然彼女はタジームの巨森の端の岩棚に戻った。まるでゼンディカーと彼女の繋がりが今一度壊されたかのようだった。
ゼンディカーの魂は邪魔されることなくカルニの心臓へと戻ってはいなかった。何者かがこれをやってのけた。エルドラージが大地を貪る間にも、何者かがこの大地の魂を根こそぎにし、ここに捕えて死なせようとした。これほど残酷なことを一体誰が?
麻痺してしまいそうなその衝撃よりも強く、本能がニッサを動かした。脚が前方へ動き、花へと向かわせた。それを守ろうと、腕が伸ばされた。だが彼女が面晶体の牢獄に侵入するよりも早く、一陣の風が彼女の皮膚を撫で、そして何か固く熱いものが彼女の脇腹を激しく打った。彼女は空洞内を飛ばされ、地面を滑った。
叩き出された息を再び吸おうと喘ぎ、ニッサは手と膝をついて起き上がろうとするも、再び打ち倒されただけだった。
彼女は空洞の地面によろめき転がり、あおむけになった時、一体の悪魔をまっすぐに見上げた。

《灯の再覚醒、オブ・ニクシリス》 アート:Jason Chan
「何故ここにいる?」 その悪魔の低い声はどこか共鳴し、かつ虚ろだった。その悪魔はニッサにのしかかるように迫った。翼は半ば広げられたに過ぎないながらも空洞の広さを満たし、面晶体の牢獄と花から彼女の視界を遮った。長く鋭い棘がその四肢に並び、そして五本の太い角が頭部を縁どっていた。「誰に寄越された?」
この悪魔の仕業に違いなかった。その輝く赤い瞳を見据えて、ニッサは疑いなくわかった。ゼンディカーを根こそぎにしたのはこの悪魔。友を彼女から奪ったのは、計り知れない痛みをもたらしたのは、世界の魂を傷つけたのはこの悪魔。それゆえに、ニッサはこの悪魔を憎んだ。
「答えろ!」 悪魔が怒り狂った。熱く、溶岩のような魔術がその胸から腕へと放たれた。「いかにして我を発見した?」
悪魔は彼女に迫った。流れるような動き一つでニッサは剣を抜いたが、悪魔もまた速かった。悪魔はその手で彼女の手首を掴んでねじり、彼女の武器を落とさせた。
刃が音を立てて岩に落ちると、悪魔は自身の体重をニッサにぶつけ、彼女を後ずさらせて倒した、彼女をそこに埋葬しようとでもいうように。「ナヒリか?」
ニッサは悪魔の体重の下でもがいた。それは彼女の三倍ほどもあり、そのために優勢だった――少なくとも優勢だと信じただろう。エルフはゼンディカーでも最も軽い種族だが、経験を積んだエルフはこの世界のもっと重い種族を――もしくは重い生物を――打ち負かすことができる。そしてニッサは経験を積んだエルフ、少なくともかつてはそうだった。かつてのエルフは、ここバーラ・ゲドで生きていたエルフは、かつて棘のベイロスと格闘し、勝利を収めていた。

この悪魔はベイロスと何ら変わりなかった。一体の生物、一体の獣、ならば打ち負かせる。ニッサは格闘しながら彼の動きを測り、彼女がその重心を把握するまで長くはかからなかった。それを見つけてしまえば、彼女はそれを操作し、動き一つごとに更なる優位性を得た。十分な効力を得ると、彼女は足を押し込んで彼の胸を蹴り上げた、彼が平衡を失うまさにその場所を、そして彼を彼女から離した。
その悪魔はよろめいて後ずさり、皮の翼の力強い羽ばたき一つで宙に留まった。
悪魔は再び彼女に迫ったが、この時ニッサは更に素早かった。戦いの動きと本能が戻ってきていた。剣を拾い上げ、彼女はその刃で切りつけ、悪魔は避けたが脚の脇をとらえて血を流させた。
目が合い、悪魔は吼えた。だがニッサはひるまなかった。
悪魔は彼女の上に浮かび上がり、だがその表情は彼女にも正確には読めなかった。憎悪があるのは明らかだったが、何か別のものもあった、何かの当惑が。悪魔は不快そうに囁いた。「またも我を止められるとナヒリが考えたのならば、あの女は全くもって間違っている」
悪魔が何を言っているのかはわからなかったが、ニッサは気にしなかった。彼女は再び剣とともに突撃し、だが反撃に備えてはいなかった。悪魔は彼女へと素早く身体を向け、その内から燃える力が湧き上がって掌から弾け、彼女の胸を直撃した。それは生命を吸い取る力で、ニッサの精髄を真正面から打った――そして悪魔の暗黒の力となった。
彼女は自身の内なる力を無視することに長けてきたが、それを抑えつけてきた。だがそれは衰えてはおらず、今や脅かされ、彼女から引き出されようとしていた。根深い、激しい苦痛の波が彼女に襲いかかった。
ニッサは喘ぎ、よろめき、力を失った病的な感覚にふらついた。もし行動しなければ、これで終わりとなる。この悪魔は彼女を吸い尽くすだろう、その次にゼンディカーを。
彼女はやるべき事をわかっていた。選択肢は奪われた。そのほんの断片を、ほんの一瞬使えばいいだけだった。
当初、それを振るうのは容易くはなかった。その力は解き放たれることに不安があり、それを用いるのは場違いのように感じた、まるで暗い、見知らぬ家の中を進むように。その力が繋がり、胸から腕へと上ってくると彼女はよろめき、もがいた。
剣の重さはジャディの木を一本持ち上げるほどに感じた。だが彼女は刃を掲げて自身の精髄をそこに流し込んだ。更なる力が流れるほどに、それがわかった。内なる何かが目覚め、そしてそれは遂に訪れた朝に興奮していた。
ニッサは力が込められた刃をその胸と悪魔のエネルギー吸収の波との間にねじ込み、内からの全力をもって押しやった。突然、ニッサの精髄の全力が彼女に向けて逆流した――そしてそれとともに全ての記憶、全ての恐怖、全てのつまずき、全ての過ちが。自分は全てを荒廃させるために何度、この力を振るってきたのだろう? 良いことよりも悪いことをどれほど成したのだろう? 自身が信用できなかった。
だが遅すぎた。悪魔の攻撃は彼女の刃に込められた力に跳ね返され、そのまま直撃した。その攻撃の力はニッサと悪魔を共に後方へ吹き飛ばし、二人は洞窟のそれぞれ反対側の壁に激突した。
ニッサの頭部がぐらつき指は力に震えた、気短な力に。彼女は悪魔がゆっくりと向かってくると跳び上がった。
「大したものだ」 彼は言った。「その見た目に欺かれた。貴様はただのジョラーガのように見えるが」 悪魔は彼女の周囲の匂いをかいだ。「だが貴様からは久遠の闇の匂いがする。プレインズウォーカー」
ニッサは身体を強張らせた。彼もまたプレインズウォーカーなのだろうか? そうに違いなかった。彼女は感覚を悪魔に集中し、そのエネルギーを感じた。悪魔の存在の端には何かがあった。だがそれは何か違うようで、そしてそれが何故なのかは判別できなかった。
「ナヒリの使いに手こずるとは思わなんだ」 悪魔は言った。「だが聞かねばならぬ。何故あの女は貴様を送り込んだ? 何故あの女自身が来なかった?」
「何のことよ」 ニッサは悪魔を攻撃したいという衝動を抑えた――かろうじて。内に湧き上がる力は浮足立っており、長くは我慢できそうになかった。
「恐らくナヒリは我と対峙することを怖れたのであろう。一度これが完成したなら、我は更なる力を振るう。ただ一人のプレインズウォーカーがこの長い時に支配してきたよりも多くの力を」 悪魔はその花を一瞥した。ニッサは彼の凝視を追い、ゼンディカーのために彼女の心臓は高鳴った。「一つの世界の力全てが我がものとなる」

《解き放たれし者、オブ・ニクシリス》 アート:Karl Kopinski
「お前の為の力じゃない」 血管にうねる力に浮かされ、ニッサの言葉は強さと確信をもって発せられた。「カルニの心臓は大地のもの」
「無邪気なものだ」 悪魔は言い放った。「力はそれを手にしたものに属する。我が手にする。よってそれは我がものだ」
「なら取り返してやるまでよ」 ニッサはもはや自身を止められなかった。野生の精髄に駆り立てられ、彼女は面晶体の隙間に飛んだ。ゼンディカーのためにここに来た、それを置いてはいけない――だが悪魔はもう一撃を放ち、ニッサは避けざるを得なかった。
「エルフ、貴様はここで死にたくはなかろう」 彼は言った。「そこまでする価値などない。ナヒリが貴様に何を約束したかは知らぬが」
「ナヒリって誰よ」 ニッサは言い返した。だがその悪魔の言葉は正しかった。ここで死にたくはなかった。自分は何をしている? 自身の命に対して、カルニの心臓の命に対して騒々しい無視を示していた。それは自分のすぐ目の前にあり、弱って消えかかっている。彼女の行動を管理するのは内なる暴力的なエネルギーだった。こんなはずではなかった。接触するのは一瞬だけだと想定し、自身にそう約束していた。自分はもうあのエルフではなかった。力を制御するエルフ、内から湧きあがる不規則で不安定な力を黙らせるエルフだった。大地との繋がりから必要な力を、信頼できる力を、過ちを犯さない力を引き出すエルフだった。
足取りの確かなそのエルフはゼンディカーを救うためにここに来たエルフ、そしてそれを成し遂げるであろう唯一のエルフ。奮闘とともに、しきりに突いては熱望してくる精髄を下方へ押しやり、再びその悪魔にまっすぐに向かわせようとする意思に噛みつき返した。だがそれでは駄目だろう。あの悪魔の向こうへ行くためには純粋な力ではない別の方法がある。考えねばならなかった。集中しなければならなかった。
問題は、面晶体の輪に入る道は一つだけだということだった。そのため悪魔は常に彼女が何処へ行こうとするかを把握できた。だが円にもう一つの穴があれば……そう! それはかつての彼女というエルフだった。
「ナヒリが貴様を送り込んだのでないならば、何故ここにいる?」 悪魔は彼女を横目で見た。
ニッサは彼の向こう、カルニの心臓へと頷き、面晶体の輪を観察する容赦を願った。「あの花を救うために。ゼンディカーのために」
「ゼンディカーのために?」 悪魔は大声で笑った。「嘘か妄想か。貴様は近頃のゼンディカーを見たのか? 救うものなど何も残されていない。まもなくエルドラージは全てを貪るだろう」
「そうはさせない」 ニッサは一つの面晶体から悪魔の左へ視線を移した。
「大層な自信ではないか」
「そうよ」 ニッサは身体を緊張させ、駆け出そうと備えた。
「そして誰がエルドラージを止めようなどというのだ?」 その悪魔は尋ねた。「貴様か?」
「そう、私が」 ニッサは駆け出した。

《ニッサ・レヴェイン》 アート:Jaime Jones
悪魔は牢獄の入口を塞ぐべく動いた、だが彼女が目指すのはそこではなかった。
彼女は飛び上がり、彼の左の面晶体を、目の前の明白な道をめがけて宙返りをした。そして打ちつけるべく刃を構えた。
だがその面晶体が近づくと、彼女はわかった、成功はしないだろうと。遥かな記憶のこだまが心に待った。自分はかつて、一つの面晶体を壊した。これと同じような、洞窟の中の一つの面晶体を。だがそのために彼女は精髄の力を必要とした。もし今その岩をただの裸の刃で叩いても、傷をつけられれば良い方だろう。
もっと力が要った。自分の力がもっと。
それは選択だったのかは定かでなかった――そもそも選択したのかも定かではなかった――だが彼女の刃が面晶体に衝突すると、ニッサの内なる精髄が弾け飛んだ。そして悪魔が彼女に襲いかかった。
二人は地面を転がり、もつれ合い、互角に格闘した。ニッサは面晶体に目を留めたまま、ひび割れが現れるのを待った。彼女が知る混沌の奔流が続くのを待った。間に合ったかどうかを見るべく待った。
一瞬の後、力の亀裂が面晶体の表面に弾け、蜘蛛の巣のように両脇に広がり、そして次の瞬間、巨大なその岩は砕け散った。それとともに、繋がれていた力線のパターンが震え、揺れ、壊れはじめた。その反響は別の面晶体の基底に伝わった。牢獄は無傷ではなくなった。すぐにそれは完全に崩れると思われた、そして洞窟そのものもまた。
今がニッサの唯一の好機だった。彼女はすべき事を知り、再び自身の力を引き出した。この時彼女はそれを、悪魔を振り払うことに使用した。彼女は跳ね、カルニの心臓へと急いだ。
「やめろ!」 悪魔が吼えた。「そうはさせん!」
悪魔はニッサの後を追い、だが彼女と不安定にぐらつく面晶体との間で躊躇した。彼女は悪魔の目に疑念を、そして決意のひらめきを見た。彼が最も近くの角ばった岩へと飛び上がり、その太い腕を巻き付け、力を込めてそれを持ち上げようとした。

《カルニの心臓の探検》 アート:Jason Chan
ニッサは悪魔を追い越し、カルニの心臓に迫った。
そして指が花に触れた時――全てがあった。
ゼンディカー。
その言葉、その存在、その魂が彼女の内に響き渡った。
そしてその時悪魔の手が彼女のそれを包み、握り潰そうとした。彼女は思った、花を絞めてしまうと。「愚かな」 悪魔の内なる炎が怒り狂った。「愚かにもほどがある」
だが悪魔はもはや振動する面晶体を支えていなかった。二人の周囲に石がなだれ落ちて砕け、力線は拡散した。
悪魔はニッサを見た。熱をもった憎悪がその凝視から放たれていた。「償ってもらおう」 彼の憤怒がニッサへと注がれ、留め具のように彼女をその場から動けなくした。彼女は離れようともがいたが、一息ごとに悪魔は抵抗する彼女の力を吸い取った。
悪魔はただ一つ、今この場で彼女を殺すこと、滅ぼすことだけに集中していた。それが感じられた。ニッサはそれを悪魔の瞳に見た。
「貴様がどれほど望もうと」悪魔は二人の組み合わさった手とカルニの心臓を持ち上げた。「我は更に求める。そして手に入れる」
悪魔の怒りはニッサの心臓の鼓動が弱まるごとに強く燃えた。「生きたいと願うなら、次元を渡ればよかろう」
ニッサは狼狽した。視界の隅が暗くなっていた。視線をカルニの心臓へと投げかけた。衰えゆく精髄がゼンディカーの力に、彼女の手の中にある力を求めた。それとともに悪魔を押し砕く、勝てる――あとはそれを手にするだけでよかった。
それは駄目。ニッサは自身を止め、絶望の中で抑えつけた。ゼンディカーは自分に与える力を持っていない。今は、根こそぎにされて大地に触れていない今は。もしそれを引き出せば、それを吸収するだろう、花を破壊してしまうだろう、そしてゼンディカーを終わらせてしまうだろう。
自分はもはや、結果を考えずに行動するようなあのエルフではなかった。あの過ちを犯すつもりはなかった。
ならばどうする? 悪魔に屈するの?
違う。自分はそんなエルフでもない。
彼女はその間の何かだった。大昔の自分と、変わったと考えていた自分の。どちらも完全に真実ではなかった。内なる力をこれほど長く堰き止めていたのは、一つの過ちだった――彼女は強く、この悪魔を凌駕するほどに強く、そしてそれは隠すべきではない何かだった。だが統制を、注意を学ぶことは間違っていなかった。間違っていたのは決して力でも、情熱でもなかった。彼女は常に物事を行ってきた、正しい理由で、常に正しい意図をもって。だが彼女は間違いを犯してきた、自分の周囲の世界を気にかけていなかったために。より深い理解を、注意をもって行動するという意識が無かったために。
だが、今はあった。
彼女はゼンディカーから学んだ。パターンと繋がりを見て、より大局を思い描くことができた。この洞窟、面晶体、カルニの心臓の力、悪魔が吸う精髄。彼女はまたゼンディカーの全てを見ることができた、エルドラージを、他のプレインズウォーカー達を、生存者の野営を。そして多元宇宙を、無数の世界全てを。
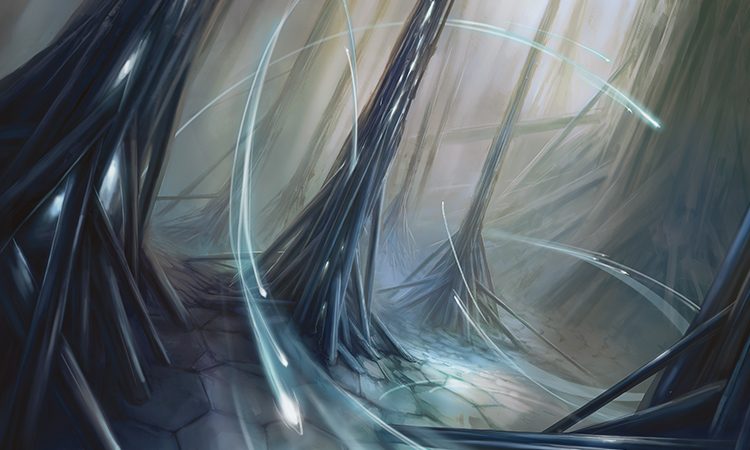
《ちらつき蛾の生息地》 アート:Sam Burley
その全てに彼女の場所があった。そこに属する力があった。今日、この時、ゼンディカーを救うために使う力が。
行おうとしている事は危険だった。あるいは彼女が行ってきた中でも最も危険な事かもしれなかった。だがそれは冒険ではなかった。何が起こるかを正確に知っていた。そして備えはできていた。
ニッサは悪魔がまだ吸い出していない、内に残った力をかき集め、そしてそれを悪魔から引き離そうとした。逆側から悪魔の掌握と、対抗して引く力を感じた。だが彼女はそれを腕に流し、指先に流し、カルニの心臓へと届かせた。
彼女の精髄が花に流れ込むと、それは生き返った。花弁が持ち上がり、葉が開き、鮮やかに輝いた。そしてついには根が成長を始めた。それらは地面へと向けて下方に伸びていった。
「何をしている?」 悪魔は彼女の精髄を引いた。その目には混乱があるのがわかった。
悪魔からは下に引かれ、自身の心央に引き上げられ、ニッサは柳の枝になったように感じた。カルニの心臓の根はほぼ地面に届こうとしていた。彼女はもう一つ、最後の波をゼンディカーの魂に送った。そして視界が暗くなり、身体の力が緩んだ。
悪魔は彼女の力を失った指から花を奪い取った。そしてニッサは膝をついた。
「この世界は我がものだ!」 彼は唸った。「この力は我がものだ」
だが、そうではなかった。
根は地面に届いていた。世界の魂は大地に帰還した。ゼンディカーは何にも属さない。地面が上方へうねり、カルニの心臓へと手を届かせるように岩の塊を飛ばした。それは花を引き寄せ、悪魔の手から離し、世界の抱擁へと包み込んだ。
「何だと!」 悪魔は膝をつき、その禍々しい爪で地面をかきむしった。だが遅すぎた。大地は既に力の心臓を封じていた。花は去った、安全に。
洞窟全体が震え始めた。ゼンディカーの力がうねりながらニッサの掌まで上がり、彼女の内の空白を埋め、残っていた彼女の精髄の最後の一滴と混じり合った。
悪魔はよろめいた。立ち続けようと壁に手を伸ばし、だが壁は弾け飛んだ。悪魔は宙に飛び上がり、岩を避けた。「何をした?」
ニッサは立ち上がり、悪魔と対峙した。「もし生き延びたいなら、今すぐに次元を渡って去りなさい」 彼女はゼンディカーとの繋がりに触れ、自身と世界の力の両方を引き出した。彼女の存在の延長を呼び出し、完全な姿を取り戻した。悪魔に向けてそれを振るうと、土と瓦礫が彼女とともに動き、大地の拳がその胸へとまっすぐに叩きつけられた。悪魔は傾きながら崩れた岩の壁まで後ずさった。
ニッサは一つの大地の砕けた破片から跳び、また次へと跳び、ゼンディカーの破片それぞれが交互に彼女の着地を受け止めてはその力を与えて放った。世界がその悪魔を押し潰す中、ニッサは立ち上がった。そして世界の魂、彼女の友もまた。
アシャヤ。
地表に戻ると、ニッサは足が柔らかく瑞々しい苔の絨毯に触れるのを感じた。彼女は脈動する生命の匂いを呼吸した。彼女の隣に、トンネルと崩れた大地の残骸から成る、聳え立つエレメンタルもまた、同じことをしていた。
ニッサは友を見上げた。アシャヤは眼下のニッサへと熱情のうねりを送った。そしてニッサも自身の精髄を送り返した。二人はひとつだった。そして二人は互いの、共有する力をもって更に強くなる。今や、その力をもってゼンディカーを救う時が来た。

目覚めし世界、アシャヤ アート:Raymond Swanland
ニッサとアシャヤは海門へと戻り、ギデオンの軍と再会するのだろう。二人は彼の鬨の声に、今一度意味をもった言葉を加えるのだろう。
「ゼンディカーのために!」
共に、二人は大陸を出発した、互いの歩調を合わせながら。
(Tr. Mayuko Wakatsuki / TSV Yohei Mori)

